2020.1.1
年頭所感:ニュートンとフックはなぜ仲が悪かったのか?
"ニュートンとフックは同時代の人であり、お互いに対立していたようだが、1/対立=双対関係にあったようだ" というのは以前のESSAY
で書いたが、あれから二人の関係が気になっていた。
 ・ニュートン 運動の法則:力=質量 × 加速度
・ニュートン 運動の法則:力=質量 × 加速度
 ・フック 変形の法則:力=バネ定数 × 変位
・フック 変形の法則:力=バネ定数 × 変位
 ・アインシュタイン少年が学校で二人の法則を学んだ時、次の様な質問をしただろうか?
・アインシュタイン少年が学校で二人の法則を学んだ時、次の様な質問をしただろうか?
アインシュタイン:
先生、フックはバネの伸びを測ったんですよね。バネを吊るす天井って頑丈でないといけないですよね。
バネがとても重かったら曲がっちゃいますよね?
先生、ニュートンの言っている物体って硬くないといけないんですか?
バネのように柔らかくて伸び縮みしたらどうなるんですか?
先生:
いいかいアルベルト、曲がったり伸び縮みしないことにするんだ。
そうしないと次へ進めない。判るかね? 勉強とはそういうものだよ。
アインシュタイン:
判んない!どんなにそれが小さくても曲がったり伸び縮みすることには変わりないでしょ。
僕は勉強は苦手だ。
家に帰ったアインシュタイン少年はその夜、ベッドの中でFig.1のような事を考えただろうか?
ニュートンもフックも自分の都合の良いように考えているんだな。じゃあ僕もそうしようっと。
バネは伸び縮みするんだから僕だってほら出来る。
運動会の徒競走でゴールのテープを切るときにできるだけ手を伸ばしてみよう。そうすれば少しだけテープを切る時刻は早くなる。
でも先生はそれをちゃんと認めてくれるかな?
Fig.1
 |
陸上競技則では100m走をはじめとする走種目は、選手の胴体がフィニッシュラインの幅のスタートラインに近い側の縁を越すことでゴールと認定される。頭・手・脚などがフィニッシュラインを越してもゴールにはならないとのこと。この競技則を見れば判るように手足の屈伸を認めていない。
○○則というものは葵の御紋のように絶対的な気がするものだが、前提を伴うものである。
二つの法則に伴う前提を記してみると、
・ニュートンの運動の法則:
力が作用する質量mの物体の伸縮は考えない→剛性k=無限大→1/k=柔性H=0
伸縮は考えない→空間の概念は持たない。
力と加速度の関係を言っているので時間の概念を持つ。
・フックの変形の法則:
力が作用する剛性kのバネ自身の質量mは考えない→質量m=0
伸縮を考えている→空間の概念を持つ。
力と変形量の関係を言っているが、変形に要する時間は問うていない→時間の概念は持たない。
以上を表1にまとめ、下のFig.2、3のように質量m、柔性Hの物体の上端を持って垂らしてみる。とても重く、あるいはとても柔らかい物体を想像してみよう。
表1
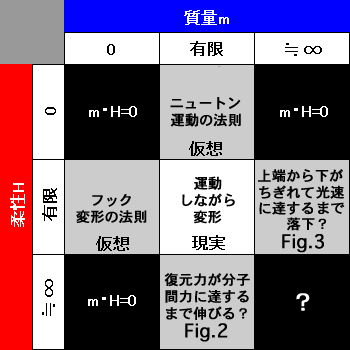
|
Fig.2
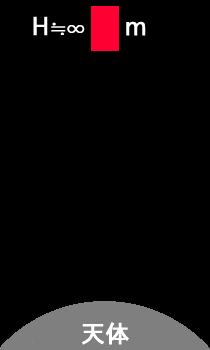 |
Fig.3
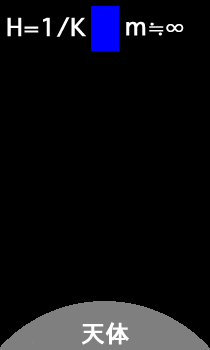 |
Fig.2 柔性H≒∞の場合、上端に近い部分ほど粗になるので霞んで見える?
Fig.3 質量m≒∞の場合、天体に接近して光速に近づくほど霞んで見える?
|
このように両法則はお互いに質量と柔性、そして時間と空間という概念を切り分けている。
ニュートンとフックはお互いに自分の法則を主張するのに質量、柔性や時間、空間の概念を無視するから仲が悪かった.....のではないだろう。
ただ、アインシュタイン少年は重さと柔らかさを切り分けることが許せなかったのではないだろうか?
○○則=ルールを教わりそれを守ることが勉強=理性なら、アインシュタインが譲れなかったものは拘り=感性と呼べばよいのだろうか?
彼の一般相対性理論= ”巨大な重力(質量)によって空間が曲がる” は感性から出発しているように思う。
今年は "前提" について考え、"感性" に戻ってみたいと思う次第である。
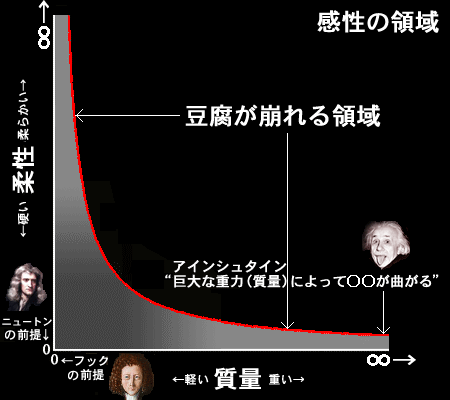
・アインシュタインは○○=空間と言ったが
・巨大な豆腐を作れば自重で崩れてしまう
・豆腐一丁でもにがりの量が少なければ柔らか過ぎて崩れてしまう
|
関連エッセイ: