
O kosmoV skhnh, o bioV parodoV
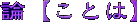
[Kritiken der Geheim-Bande]
ワルスよ、ワルスよ、余の軍団を余に返せ!
―――ガイウス・J・C・オクタウィアヌス
ゲルマニアでの圧政、そして反乱、鎮圧の軍を率いながら一人逃亡、部隊の混乱と壊滅、これを引き金とする属州兵士の任務放棄。元凶である総督ワルスに向けた「尊厳者」アウグストゥスの言葉。養父に比べると遙かに率直で、尊厳さに欠けます。しかしそれだけに、血を吐くような言葉として伝わってくるのです。
例えばマラソン競技の由来となったアテネの伝令は、母都市に到着するや「我ら勝てり!(ネニケーカメン nenikhkamen か?)」と叫んで絶命。洒脱な機転、縦横な引用は、人の耳目をそばだたせ、感嘆の声を上げさせます。そして飾らない率直さもまた、人の心を打つものです。和歌に於けるたをやめぶりとますらをぶりに対応するでしょうか。面白いのは尚武の気風に富むローマ人の方がより手弱女ぶりを好むという事です。手弱女とローマというのは似つかわしくないので、美術史用語を無視して「マニエリスム(けれん好み)」とでも呼びましょうか。
引用されていたカエサルの言葉。この論理的に畳みかけるような形式は、インド的なものを感じさせます(十二縁起等原始仏教に顕著)。あるいはこれまた朱子学の、段階を重視する態度にも通じます。とは言え、循環論法になっているところがミソなのでしょう。ギリシア文化はソフィズムの息吹です。
またハムレット的心境で発した名台詞、「賽は投げられた Jacta est alea」も、実はギリシャの俚諺を引用したものだったのです。即ち「アネリープトー・キュボス anerrifqw kuboV」。文法的に面白いのは、これは「三人称の」命令形です。かつ現在完了受動相。ぎこちない訳ですが、「賽は投げられてしまってあれ」となりますか。諺らしくすれば「投げてこそサイコロ」? 加えて「来たり、見たり、勝てり」も、初期原子論で有名なデモクリトスの箴言を思わせます。即ち「来たり、見たり、去れり hlqeV, eideV, aphlqeV 」。こちらは二人称ですね。ローマの貴顕にとって、いかにギリシア的教養が染み込んでいたかを窺わせます。一方ギリシャ人は、ラテン語を初めローマ文化にあまり興味を持たなかったようです。*タメイキ*
いずれにせよ、より後発の文明の方がけれんみが出て来るというのは、洋の東西を問わないようです。我が王朝人は漢籍を縦横に引用し、これを当然の教養としてサロン生活を送りました(今やアメリカ人になろうと必死)。ローマ文化はギリシャ語と同じ韻律を持つ叙事詩を作り、ようやく自信を付けました(ラテン語とギリシャ語は全く音韻体系が違うというのに)。四書五経の研究は北狄王朝清帝国で科学的になりました(あと南宋のように斜陽の漢人王朝)。ヨーロッパの階級制から脱出したアメリカ人は、功なり名を遂げると欧風貴族のスタイルを気取りがちです(インディアンスタイルは頭から却下)。
(中洋たる南アジアに於けるヴェーダ等の引用はどのようなものなのでしょうか。あそこら辺は文化的に混沌なので、よくわかりません。何しろ現存する文字(文学に非ず!)の半分以上は、あそこに集中していると言われる位ですから。どなたか御教示下さい。またイスラム圏に於けるコーラン等の引用は同じ流れでは論じられません。あれほどオアシス的習慣に根ざしながら、あれほど没民族的な理念は他にはないのですから。)
一方メソポタミアやエジプトに劣等感を持たず、自ら恃むところ篤いギリシャ人はずっと率直です。逸身喜一郎教授は、「ギリシャとローマの「理想像」の違いは大きい。ギリシャ人から見れば、ローマ人は、生真面目で、人間性を無視し、しかもどうかすると偽善者にも近寄れる。反対にギリシャ人は、大人の責任を知らない子供のようである」と評しています。
ああ、だがしかし偉大なるかなローマ。今や欧米の気取った文章では、ラテン語の故事成語が原語で引用されるようになったのです(ぎくぎくっ。ギリシャ語はローマ字ではないからでしょうか、原語の引用はあまり見かけません。なるほど、 It is Greek to me です)。
|
たとい地獄に堕とされようとも、
私はこのような神を絶対に尊敬することはできない。
―――ジョン・ミルトン
フランスのルターと目されるジャン・カルヴァン師の教説を聞いた、イギリスの文学者の言葉。
本来プロテスタントの教義というのは、普通の人には耐えられないドイツ的原理主義の色彩が濃厚です。何かにつけ濃い霧のように鹿爪らしく曖昧な部分を残した学説を立てるイギリス人には、嫌悪の対象以外の何者でもないでしょう。イギリス経験論とドイツ観念論の違いでしょうか。ゲルマンとアングロサクソンは人種的にも近い筈なんですが……。まあアメリカ人は、同じアングロサクソンの英国人がびっくりするぐらい割り切った「誰にでも判る」理論構築を好みますが。
(英国の経済学者ケインズ博士は、自分の学説の米国的発展形を「ハンバーガーのようだ」と評しました。アメリカ人としては、イギリス人に食べ物の事で難癖を付けられたくはないでしょうが。)
この原理性を踏まえてルター師の言葉を味わうとニヤニヤ笑いが止まりません。表情を残して消えてしまうかと思いましたよ、私は。だって成程、植える木が「林檎」なんですもの。免罪符などという(信仰の)躓きの石を売りさばいていたカトリックの向こうを張って、自らは林檎を植えまくるわけですから。これが信徒に原罪の自覚を促す目的だったら凄いですね。まさに「善人なほもつて往生を遂ぐ。況んや悪人をや」です。
もう一つ皮肉を。現代社会はエコロな社会。「植生」の概念もなく、「好きだから」という理由で特定種の植林をひたすら続ける事がどういう事か、一度省みて頂きたいものです。卑近な例では杉花粉症というのがあります。あ、ルター師にとっては、現世というのはぺんぺん草一本も生えていない不毛の荒野なのかも知れません。師の新しい、峻厳極まりない信仰からすれば「義人はいない、一人もいない」という気にもなるでしょうから。ミルトン氏など、不義の人の最たるものでしょう。そのようなところに木(信仰?)を植えるならば、植生もへったくれもありません。ギリシャに見られるような白亜の禿げ山を、日本に見られるようなたたなづく青垣に変えるべく鞠躬尽力する訳です。ルター師に限らず、そういった夙夜(しゅくや)営々たる働き、孜々汲々(ししきゅうきゅう)たる姿は、人の心を打ち行動に繋げるに充分な力となってきました。まさに「芥子種ほどの信仰心があれば、山をも動かすことができる」のです。
しかし、と加とは言います。本当に感動的なのは、宣教の義務を負っているルター師の、大向こうを唸らせる言葉と行動ではありません。むしろエピゴーネンを作るでもなく、感謝顕彰されるような事もない仕事を黙々とこなし、明日世界が滅びるとしても自宅待機命令が出ない限り今までと同じ仕事を続けるであろうお父さん方の姿だと思われてなりません。
|
より速く、より高く、より強く
―――ディドン神父
人間が前頭葉と共に想像力を発達させて以来、かの大王の望みは「人類の業病」とさえ言えるかも知れません。それでも長らく人類は自然の脅威を恐れ、これを神と称するなどして歯止めをかけてきました。また平等である筈の人間にも、能力差は厳然として実在し、より速い、高い、強い能力を持った者は、一種神の如き者として畏れられてきました。親の小言には定型句として、「平凡に生きていく事が一番なのだ」というのがある位です。
ところが中世の闇が払われ、人間の素晴らしさが礼賛されるようになると、自然や優れた能力は恐れや畏れの対象から、克服すべき目標、あけすけに言えば敵として認識されるようになったのです。これこそ近代精神の根底といえましょう。人間はあらゆる敵を克服すべき宿命を自ら背負う事となったのです。今日は昨日よりも優れた人間に、明日は更に優れた人間にと、誰にせっつかれたのでもなく(いや理性の命ずるところやも知れぬ)過労死社員のように「生きていく」事が当然視されるようになったのです。さらにため息が出るのは、「想像」力を発達させた人類は、敵を克服した直後に、より大きな敵を「創造」してしまう事です。少年向け連載漫画に特有の「敵のインフレ」は、優れて近代的な人間性をカリカチュアライズして示したものと言えましょう。
かの大王は死の床にあって「もっと強く(トン・イスキューロテロン ton iscuroteronか?)」と漏らしましたが、戦陣にあっては同じ将軍達にこう言っていた筈です。「もっと遠くへ」と。それに対して将軍達は「もう進みたくはない」と返したのです。そんな彼らが大王の死にあたって、よくも後継者について質問できたものです。しかし彼らとて武勇の誉れ高いマケドニアの武人です(なにしろマケー mach は戦闘の意味です。駄洒落)。戦いに飽いての揚言ではありますまい。現代人の解釈とは異なり、ギリシャから見た勇敢なる北狄は、「果てしない」という優れて抽象的な思考に恐れをなし、なによりもうんざりしていたのです。一方「果てしない」に真正面から組み合い、しかも行動し続けたメガロス・アレクサンドロスは、近代精神をいち早く(1800年も早く!)先取りしていた人と言えるかも知れません。私見では、本朝に於いてこの近代性に匹敵しうるのは、織田信長を待たねばなりません。
|
狂泉(きょうせん)という国があった。狂泉という泉があるを以ての名である。その水を飲んだ者は須臾(しゅゆ。たちまち)にして発狂するという。しかしながら狂泉国は、君臣各々そのところを得て交々(こもごも)幸せに暮らす鼓腹撃壌の桃源郷であった。「帝力いずくんぞ我にあらんや、百姓(ひゃくせい。庶民)あってこその帝力。百姓いずくんぞ自ら保つべけんや、帝力あってこその渡世」。国名にも拘わらず、領民は両面の見方のできる賢き人々であった。
ある日狂泉が溢れて、飲料水を汚染した。人々は皆狂気に捕らわれたが、王宮内は深い井戸から水を採っており発狂を免れた。毎朝恒例の領民への挨拶で、ただならぬ事を知った王は、名医扁鵲(へんじゃく)を呼びに使いを遣った。だが、嗚呼狂いてなお賢き哉。物事を両面から見ることのできる領民は、王の発狂を知ったのである。すわ我が君一大事と王宮へなだれ込み、王を担ぎ出して狂泉に投げ込んだ。溺れる内に王もいつしか発狂し、人々は手を取って喜び合ったと言う。狂泉は再び君臣各々そのところを得て交々幸せに暮らす桃源郷となった。
オチはありません。説話とはそういうものです。
あ、表題は英訳すると a naked toad(アネイキットード)になります。
|
君の論文はドイツ流で長すぎる。
こんなのはこのごろは流行らないから、三分の一にしなさい。
―――アーネスト・ラザフォード
学生さん、しゅーん。科学者だからといって。必ずしも論文を読みたがる訳ではないのです。量子化された電子軌道を持つ原子模型、所謂ボーアモデルを提唱したニールス・ボーアの論文は、この言葉と共に突っ返されました。お師匠様が実験的に示した原子核を持つ模型を、発展的に記述したにも拘らず、あまり喜ばれなかったようです。確かに量子状態の遷移という考え方は、現在に至るも一般的な感覚から乖離しています。でも直弟子に対するにはあんまりなお言葉です。確かにどこぞの修道院長が言ったように、「こんなに長くなかったら、もっと短かったろうに」という考えもあります。その場合、寸鉄人を刺すアフォリズムに限りなく近付いていくのは避けられません。大般若経六〇〇巻を二六二字に圧縮した般若心経が、なんやよう判らんシロモノになっているように、情報の不確定性が限りなく増大します。物理論文に、E2−E1=hνとかだけ書かれてもなあ。
(数学の場合、数式のエレガントさ自体にも価値があるので e2πi =1 とだけ書いても喜ばれるかも知れません。人文系では、元力士の輪島さんの卒業論文には手形がドカンと押してあっただけという伝説があります。ついでに般若心経ももっと短くしてみましょう。古典インド的列挙癖を削ぎ落として、「無有、無無、悉皆空、亦無空」てなところでどうでしょう。梵語で言えばもっと短く「ネーティ」。即ち「然らず」。もはや警句だか落書きだか。)
しかし画期的な論考は、発表当時非難を受けがちです。論文が長かろうが短かろうが、時が来れば必ず誰かが発掘します。本当にできの悪い論文は、時の流れるままに朽ち果てていくばかりです。却ってファナティックな檄文的論文が、反面教師として歴史(と言うかエピソード)に生き残ったりします。加とも自分の才能に見切りを付けて、キチ○イじみた文章で青史に名を残しましょうか。これこれ、逆は必ずしも真ならずじゃよ。はっ。老師!
ニールスの不思議な冒険は、幸いにも彼の存命中に良い評価を得る事ができました。学問の世界といえど、人間の集まりです。俗っぽい逸話も多いのです。我が敬愛するドイツ数学界の重鎮、エネルギッシュな偏屈爺ぃヒルベルト翁は弟子の結婚に腹を立て、就職上での嫌がらせをしました。更に子供ができたと聞くや大興奮です。「結婚しただけでもどうかしていると思っていたのに、子供までつくるときては。こんなあきれた男には、これからも一切、何もしてやらんぞ!」と。いや先生、いやがらせしてたじゃないですか。
電子計算機の発達は、科学の発達を光の速さに近付けました。そしてまた花形科学の方法を巨大産業化しました(スペースシャトル、巨大サイクロトロン等)。おかげで画期的な論考も提唱者の存命中に報われる事が多くなったのですが、同時に学会模様のエゲツナさも巨大化したのです。そんな奴らの生み出す科学には幸せ求める夢がないのだ、などと環境保護テロリストのような批判は御勘弁下さい。科学技術の使い方は、自然科学に内在してはいないのですから。全く、はなから愚かな者は、そりゃー愚かにはなりません。我々の周囲でよく観察される現象ですが。
|
砂や降る神代も聞かぬ田沼川
米くれないに水飲まふとは
白川の水の清きに住みかねて
元の濁りの田沼恋しき
―――作者不詳
はい、人任せでは革命は起きません。「私達が」いえ、「私が」権力を倒さないと、決して人民は幸せになれないのです。「乃公(だいこう。俺様)出ずんば蒼生を如何せん」は野心家の言葉ですが、蒼生もまた自ら出ずんば「真の」権利と平和を打ち立てる事はできないのです。諷刺など所詮ガス抜きに過ぎません。悪政を笑い飛ばして事足れりとするのでは、権力者の思う壺です。
しかし江戸時代、ソビエト時代の政治諷刺には迫力があります。今日の我々と異なり、当時の諷刺者には政治参加が認められていなかったからです。迂闊な物言いは手鎖遠島、あるいはシベリア送りに直結します。それを冒してなお表されるこれらの言葉には、生命と釣り合う重みがあるのです。抑圧あってこそのウィット・ユーモア、あるいは粋・洒落・エスプリとは。皮肉さに切なくなります。一方現代の(特にこの国の)諷刺たるや……。
(それならば間然する所なき専制国家ロシア帝国下でこそ諷刺が発達するはずではないでしょうか。これは貴族や知識人の愉しみだった、という所に秘密があります。ソビエト時代と異なり、ロシア帝国政府は知識人を目の敵にする原理は持っていませんでした。所詮はサロンの口遊び(くちすさび)とでも考えていたのでしょうか。貴族は貴族で曲がりなりにも政治参加者です。彼らの政治諷刺は「諷諫」以外にはあり得ません。皇帝の面前で「それとなく」批判・非難を匂わせるのです。専制君主にずけずけ言うのは、多くの場合逆効果ですから。しかしアネクドートの語源が「非公開の」である以上、御前での開陳は望むべくもないでしょう。それじゃー諷刺にならないのよ。当てこすりをしながら前漢の武帝を笑わせた東方朔は、東方のローマにはいなかったようです。参考資料:諸星大二郎の漫画)
大体現代日本の歴史教育というのは「反体制の闘志養成コース」の様相を呈していますが、多少とも自分で考える生徒、自省心を持った生徒に対しては逆効果でしょう。現代の価値観べったりの安全極まりない発言を安全な所から発表しながら、自らは反骨を気取る滑稽さ。今や(広い意味での)メディアはこの手の醜悪なる善人に占拠されています。ここに於いて反骨とは、天下の憤激を買う発言をマスメディアを通して行う以外にはあり得ません。世捨て隠遁など自己満足に過ぎません。「天下道あれば即ち見れ(あらわれ)、天下道なければ即ち隠る」などクソ食らえです。いや、これも次のように解釈しましょう。道(活動方法)がある国では表立って闘争し、道のない所では諷刺(非公然活動)で戦う、と。ところが皆さん、道があろうがなかろうが当てこすりや揚げ足取りにばかり明け暮れぐさっ。…………。すいません、何故か自分が血まみれです。
加とらしい話も書いておきましょう。アネクドートとはギリシャ語のアネクドティコスanekdotikoV即ち公刊されない、非公開のという形容詞から来ているそうです。さすがギリシャ語を公用語としていた東ローマ帝国の後継者です。どうもこれは中期以降のギリシャ語らしく、古典語では結婚していない、婚約していないという意味になります。意味単位に分綴すると an-ek-dotikoV となり、否定・分離・出た、与えたの意味になります。「嫁に出されていない」というのが原義なのか知らん。ところが語頭の否定辞を取ると、見捨てられた、裏切られたという意味になります。結婚とは若夫婦が実家から見捨てられたり裏切られたりする事なのね。ひどいなー。大和言葉の「妻問ひ」の生温さにほっとさせられます。しかし ekdotikoVに改めて否定辞を付けると、切ない話の一丁上がりです。
帝国政府や冷たい現実に、搾取され打ちのめされ続けた農奴や人民。メシアニズムの淡い期待をことごとく裏切られてきたスラブの民衆。それでもアネクドートだけは「見捨てない」「裏切らない」存在として、かの地の人々の心を支えてきたのです。
おまけ。冒頭の和歌(?)の解説です。「砂や降る」というのは伊豆大島噴火の火山灰でしょう。田沼時代は賄賂の時代。天井知らずのインフレで、浅間しや富士より高き米相場と言われました。同時に災害も多かったようで、それでこのような落首になったようです。この大老、「此虫は常は丸の内に這ひ廻る。皆人銭出せ金出せ賄賂つぶれ(マイナイツムリ)と言う」と揶揄されても、「予は天下の為尽力し、心身とも休まる暇(いとま)なし。屋敷に帰りし時、廊下に並んだ付け届けを見るのだけが楽しみじゃ」と返す確信犯です。しかしこの言葉こそ、「現代反骨」が失ったものではないでしょうか。今の政治家、とてもこの勇気はないでしょう。言ったとしても記者に突っ込まれたとたんにしどろもどろ。言い訳に終始して、例によって「妄言」として処理されるのがせいぜいです。
その現代人も憎んで止まない賄賂政治を一掃したのが白川楽翁公。清廉な政治をしたらしたで次の落首です。お上への果てしない文句は民衆の属性なのでしょうか。まあ本歌取りや駄洒落枕詞などの技巧があって、単なる愚痴ではないのがまた民衆の偉大さです。一方現代の(特にこの国の)諷刺たるや……。
取り敢えず二首並べると、両面の見方を養うことができて大ラッキー。かな。
あ、表題の主張はロシア語にするとа не "Кто=то"!(アニェクトータ)になります。無理すぎる露作文。
|
虎よ、虎よ、ぬばたまの
夜の森に燦爛と燃え。
そも如何なる不死の手、
はたは眼の造りしや、
汝が由々しき均整を。
―――アルフレッド・ベスター
闇は、不死なる者の被造物を、燦爛と燃ゆる眼を残して溶かし込んでしまいました。イギリスはチェシャー地方に赴くまでもなく、表情だけを残して消える猫(科)を見る事はできるのです。うわあっ。小窓からトイレをのぞき込むなあ。
ところで虎の均整を作り出したのが不死の「手」というのは判りやすいです。しかし不死の「眼が作る」とは? はて。確かに糸屋の娘は目で殺しますが。こちらは作り出しますからねえ、「作らせる」ですらなく。うわあっ。一ドル札の裏からこっちを見つめるなあ。
なるほど NOVUS ORDO SECLORUM(世界の新しい秩序)と書いてある位ですから、形ある虎や形無き均整を作るのなんか訳ないでしょう。不視の手は巨大市場をぎこちなく統御しておられますが、もう一方は完璧なる監視者として、あたかもサーンキャ哲学の原人、プルシャのような立場を選択したのです。ああ、賢き者の名は誉むべき哉。
(実際はプルシャはもっと控えめで「観照者」に過ぎませんが。プルシャというのはなにも、「オウム」と刻まれたバッジの事ではないのです。)
ベスター氏も西洋の方である以上、どうしても闇は後ろに引いた存在になってしまいます。闇は唯一神の最初の御業で退場する、露払いに過ぎないのです。しかし友よ、アーリア的価値観を規定したマヌ法典の歌を聞け。「このものはかつて暗黒からなっていた。それは認識されず、特徴なく、推測を越え、識別されず、あたかもいたるところ眠っているかのようであった」。
さらに、と加とは言います。闇はそのような静的なものではありません。確かにみっしりと詰まった闇は重苦しく、その中の精神を静的にする事もあります。しかし闇自身は、極めて動的で「力あるもの」なのです。現代物理学が示す原初の空間のように対生成と対消滅を繰り返す、濃密な存在の霧。澎湃たる(ほうはいたる。煮え立っている)静寂というのは東洋的に過ぎる考えでしょうか。
人が深く瞑想する時、目を閉じて「自ら」闇を創造します。これは映像という強力な情報を遮断するというだけの消極的な態度ではありません。これは自ら進んで闇に溶け込もうという積極的な行為なのです。しかも誰が教えたのでもなく、人は自然と目をつむります。ここで友よ、目を開けてなお闇を見る本邦文学者の言葉を聞け。
美と云ふものは常に生活の実際から發達するもので、暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの祖先は、いつしか陰翳のうちに美を發見し、やがては美の目的に添ふやうに陰翳を利用するに至つた。
―――志賀直哉
闇が美を作り出したのではありません。人が闇を美としたのです。闇はやはり無力だったのでしょうか。否。闇は、人に美を創造する力を与えたのです。闇は陰翳(カゲ)となる事で人と溶け込み合い、美を作り出しました。そして陰人一如となった闇はまた、美と溶け合うのです。この「美」を作り出したカゲの言霊を知れ。
カゲとは、日陰にして日影なのです。あ、ナイス機能。ATOK13 の入力支援も言っています。「日陰:日の当たらない場所。<-> 日向。日影:太陽の光。=日差し、日脚」と。近松門左衛門は虚実の皮膜で観客を感動させました。カゲもまた、光と闇の合わいを示し、淡い黄昏にえも言われぬ力を感じさせてきたのです。不夜城を作り上げた今日でも、あえて人造された薄暗い場所に呼び寄せられる人々は後を絶ちません。私自身はあの「ドロリとした」闇には馴染めないのですが。人は自ら求めた光と喧噪の直中にあって、闇と静寂を求める心をどうしても拭い去れないようです。
|
ドイツ娘はエエのう
―――ドイツ国歌
あっはっはっ。ドイツ人にもこの位の洒落っけはあるのです。ただこの歌詞は、ファラースレーベン氏が小邦分立の有様を嘆いたもので、「ドイツ人の」洒落っけと言っていいかどうかは判りません。現在のドイツでは民族主義的だという理由で、この歌詞は歌われません。確かに一番には地名が含まれており、旧約聖書並に危険です。シオニズム。一方もっぱら歌われる三番の歌詞ですが、なるほど安全。現代の価値観にべったりで、げっぷが出ます。そんなに安全策を採りたいのなら、元々「皇帝礼賛歌」だった曲も、歌詞と共に葬り去ればよいのです。かのハイドンの作った旋律は捨て難かったのでしょうか。ミーハーざますね。曲調はなんか賛美歌みたいで、ミーハーどころではないんですけど。
ただ三番の歌詞も、状況がハマると感動を呼びます。連邦議会で東ドイツの併合が承認されると、誰言うと無く議員が立ち上がり国歌斉唱。拙訳でどうぞ。
統一と権利と自由、
祖国ドイツにあれ。
されば我ら立ち行かん、
心と体を一つに結び。
統一と権利と自由、
さればこその幸福。
花咲き幸うその光輝。
花咲き匂う我が祖国。
キーワードは「統一Einigkeit」です。ファラースレーベン氏の悲願が乗り移ったかのような言霊の力。まさに「目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせしめ」る力です。ドイツ再び引き裂かるるとも、言霊の力永遠なり。
で、今や塵と帰した神聖ローマであります。よくよく注意したいのは、神聖ローマ皇帝は、長らく神聖ローマ帝国を持たなかった、という事です。自ら救い出した法王ヨハンネス十二世から「神聖なるローマ皇帝万歳!」の祝福と共に、(西)ローマ皇帝の冠を授けられたオットー大帝は、東フランク王国の君主でした。そして帝位を践んだ後も、相変わらず東フランク王国の君主だったのです。なぜならキリスト教化後のローマ帝国とは、理念上地上のキリスト教世界に他ならないからです。悪意を込めて言えば、選挙で擁立されたフランク国王は森厳極まりない「支配者」ですが、名誉称号である神聖ローマ皇帝は教会の「ガードマンの頭目」でしかありません。現在のバチカン市国も「世俗国家」である以上国防は必須の要素ですが、実効的な国軍を持たずに済んでいるのはこの辺りに秘密がありそうです。
神聖ローマ皇帝が、自前の神聖ローマ帝国を持とうとするのは、初代戴冠から 250年以上経っての事です。理念的存在でしかなかった世俗の教会は、実体を伴うドイツの地を得て初めてSacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae(ドイツ人国家の神聖なるローマ帝国)として名実共に確立するのです。皮肉なことに神聖ローマ帝国の受肉化は、法王と皇帝の関係がギスギスする中で実現しました。つまりローマ法王が世俗の君主に歩み寄る事で神聖ローマ皇帝位が生まれ、神聖皇帝が法王から離れようとする事で神聖ローマ帝国が生まれたのです。有為転変は世の習いとはいえ、諸行無常が身に染みます。その上で拝聴。神聖ローマ塵と帰すとも、ドイツの藝術は永遠なり。
マイスタージンガーのこの絶唱もタンホイザー同様、そのようにあれ! アーメンという祈りの言葉なのかも知れません。ここで改めて「芸術は長し、人生は短し Ars longa, vita brevis 」を味わうと、本当は ars longa, historia brevis なのではないかと思わずにはいられません。
|
デカンショ デカンショで半年暮らす
後の半年ゃ 寝て暮らす
―――デカンショ節
「必要な時に必要なだけ仕事をする」というのは確かに昔気質です。古代の狩猟採集時代を彷彿とさせます。古代の野蛮さを近代に引き継ぐ日本のバンカラ学生も、デカンショ節をがなり立て面目を躍如していました。バンカラを気取りながらも「デカルト・カント・ショーペンハウエル」を織り込んで(?)がなり立てるところが、「学生」の意気地(いきじ)でしょうか。♪孟子孔子を読んではみたが、酒を飲むなと書いてない。ああチャカポコゝゝゝゝゝ。
デカンショの意味を先のように解釈すると、なかなか皮肉なものを感じます。さっきから皮肉ばかりで申し訳ない。デカンショには二人のドイツ人哲学者が含まれています。ドイツと言えばプロテスタントのお国柄。マクス・ヴェーバーを引くまでもなく、プロテスタントはベルーフ(召命。天職)の概念を引っ提げて、近代資本主義を切り開いたと言われます。別項に述べた「過労死体質」の文明をうち立てた訳です。これがアメリカに渡り、「時は金なり」の金言を生み出したのは御承知の通り。デカンショ唯一のフランス人デカルトも、英語に直せば of cardsの名前の通り、四角四面の機械論を引っ提げて、時計仕掛けの世界観をうち立てました。機械時計による人間の管理に理論的裏付けが出来たのです。どいつもこいつも資本主義の手先です(いやドイツもフランスも、か)。
翻って日英同盟。ベルーフの概念は米国に渡って世俗化純化されましたが、英国ではかの名探偵の台詞の如く、余裕を感じさせるものとなっています。同じプロテスタントなのに。しかしプロテスタントと言っても英国国教会。カトリックとの折衷的色彩が強いのです。ここでも鹿爪らしくかつ曖昧な部分を残す霧の都の本領発揮です。そらピューリタンも逃げ出しまさーね。にも拘らず、英国が長らく資本主義のトップランナーたりえたのは何故でしょう。案ずるところ地方貴族が暇を持て余していた事と、食事が不味かった事が原因でしょう。いや何の根拠もありませんが。でも山田勝教授は評しています。
「貴族や地主にとっては十八世紀は退屈なほど自由な時代だったのだろう。地主たちが毎日考えることと言えば、朝食後すぐに「昼食は何にしようか」であり、昼食後は「夕食は何にしようか」ということくらいだった。
都市貴族たちも何もすることがないから、一日のほとんどの時間を酒とギャンブルに費やしていた」と。
つまりたっぷりあった時間を、浪費から生産へ向けた訳です。不景気と産業の沈滞に悩んでいたアメリカが、日本と戦端を開くや持てるポテンシャルを露わにし、資本主義の覇者になったようなものですね。
(英国の現実と建前が極端に乖離していたのが原因という気もしてきました。)
同盟相手の日本ではどうでしょう。王朝サロン文化が没落すると、武士の世がやってきました。ある程度「武士」の自己イメージが出来上がってくると、やはり後発の文明です、けれん味を求めて貴族的教養を修得しようとします。しかしそれと同時に鎌倉仏教が花開くのです。奈良仏教の学問重視、平安密教のシステマチックな修行体系に反して、道元禅師は主張します。典座(てんぞ。食事当番)を初めとする日常の作業(作務。さむ)を一心に勤める事こそが悟りであると。いかにも武人向けの、質実剛健な文化の土台を提供しました。作務と言い典座と言っても、所詮は僧堂内の話です。しかし戦場が日常だった頃の武士とって、「無我」夢中の考えは馴染みやすいものだったのです。
いったん僧堂の牆壁(しょうへき)を越えた思想は、駸々乎として広がっていきます。江戸太平の農民に答えて、和尚が言うよう。「出家や供養など、特別な事をしないと救われないと言うのは間違っている。農作業でも一心に行えば、悟りを得るのだ」と。江戸期日本にも、資本主義の手先はいたのです。
さて明治を迎えて本格的な資本主義を取り入れた日本。その前衛として養成された学生が、半年寝て暮らすというのもこれまた皮肉です。当時の学生に愛唱された「栄華の巷を低く見て」のもと、高踏とバンカラが無理なく同居していたのでしょうか。ところが敗戦後となると、皆さんファッション重視になり、学生のパッションも市民運動(ボランティア)かラグビー部による婦女暴行に向かうばかりです(西村元次官的暴論)。
|


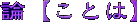
![]()
