| ベンチのある文芸 |
| 城のある町にて |
| 梶井基次郎 |
ある午後 「高いとこの眺めは、アアッ(と咳(せき)をして)また格段でごわすな」 片手に洋傘(こうもり)、片手に扇子と日本手拭を持っている。頭が奇麗(きれい)に禿(は)げていて、 カンカン帽子を冠っているのが、まるで栓(せん)をはめたように見える。――そんな老人が朗らかにそう 言い捨てたまま峻(たかし)の脇を歩いて行った。言っておいてこちらを振り向くでもなく、眼はやはり遠い 眺望(ちょうぼう)へ向けたままで、さもやれやれといったふうに石垣のはなのベンチヘ腰をかけた。―― 裾(すそ)のぼやけた、そして全体もあまりかっきりしない入道雲が水平線の上に静かに蟠(わだかま)って いる。――「ああ、そうですな」少し間誤(まご)つきながらそう答えた時の自分の声の後味がまだ喉(のど) や耳のあたりに残っているような気がされて、その時の自分と今の自分とが変にそぐわなかった。なんの拘 (こだわ)りもしらないようなその老人に対する好意が頬(ほほ)に刻まれたまま、峻(たかし)はまた先 ほどの静かな展望のなかへ吸い込まれていった。――風がすこし吹いて、午後であった。 底本:「檸檬・ある心の風景」旺文社文庫、旺文社 1972(昭和47)年12月10日初版発行 
より |
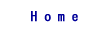 |
 |