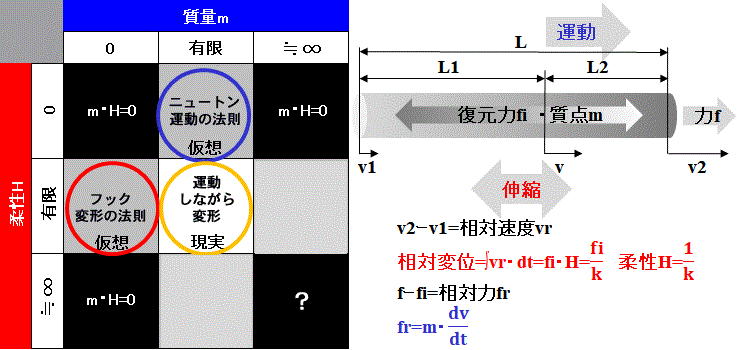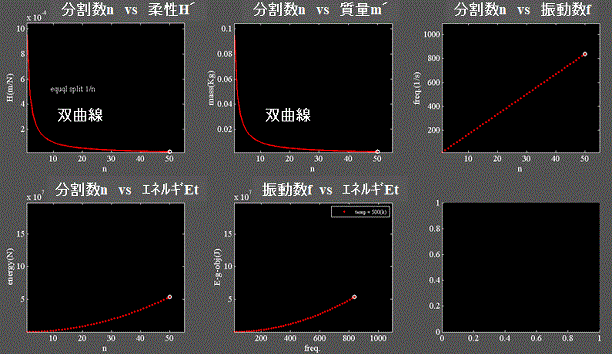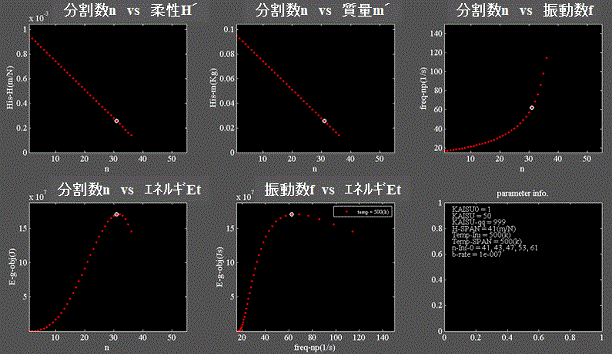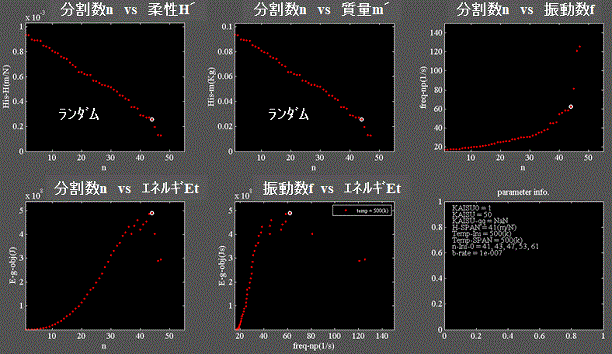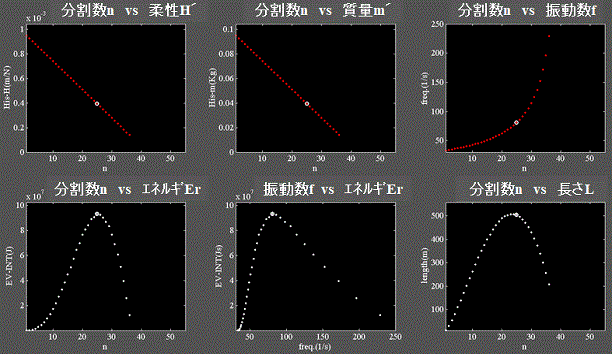溶鉱炉内の熱せられた鉄は温度の上昇に伴い、赤色から白色に遷移してゆく事が経験的に知られていた。
18世紀後半の産業革命以降、製鉄所でもこの性質を利用して光の色から鉄の温度の類推が行われ、より精確な指標が希求されるようになった。
光の波動説に基づき、スペクトル分析(音響に於ける周波数分析と同じ)を用いて溶鉱炉内から放射される光のエネルギ密度と振動数の関係を調べる手法が確立され、実験的に両者はある曲線を描く事が知られるようになった。
次いで曲線を理論的に求める研究が進み、最終的に1900年にプランクの提唱する公式に至った。
この曲線は光のエネルギは連続した値では無く、整数比を持って飛び飛びになると考えなければ説明できず、光は波動であり、同時に粒子でもあるという見方が現れた。
これは原子、陽子、中性子、電子のような物質の最小単位を扱う場合、量子的に振る舞うという見方~量子力学の萌芽でもあった。
本報ではこの曲線を便宜上、プランク曲線と呼ぶ事にする。
プランク曲線は、放射される光のエネルギの振動数スペクトル(成分)が温度が高くなるほど振動数の高い方、すなわち赤色から青色を経て白色の方向に遷移する事を示している。
光を放射するという事は物質が振動していると言う事であり、振動数と物質が蓄えているエネルギの関係が温度に因って変化すると言う事である。
彼が研究していた黒体輻射とは、閉じ込められた溶鉱炉内で鉄が放つ光を観察する場合、窓の面積が限りなく小さい場合に外部からの光の侵入を無視出来る≒真っ暗闇という意味合いでこう呼んだものである。
音で言えば外の騒音を遮断した防音室内で、お寺の鐘の温度を振って叩いた時の周波数分析に相当する。
光の代わりに物質を振動させた時のエネルギを分析すると考えれば、この曲線を導出する事が出来そうである。
力学の双対性から見ると前述の様に以下の性質がある。
・エネルギは質量m、柔性Hに比例する。式(1.1)~(1.3)
・エネルギは温度Tに比例する。式(1.4)
・振動数fは物質の質量m、柔性Hに反比例する
・物質をn連のバネとして表すとn個に分割されたバネの質量m'と柔性H'は全体の1/nとなる。
スペクトル分布は複雑な振動波形の中に、複数の振動数の正弦波形が含まれる寄与度を表していると言える。
溶鉱炉内の鉄を塊と見た場合、
・塊全体の質量mは鉄の原子1個の質量m'がアボガドロ数の整数倍=nモル個連なった複合質量と見なせる。
・塊全体の柔性Hは鉄の原子1個の柔性H'がアボガドロ数の整数倍=nモル個連なった複合柔性と見なせる。
仮にその集合は均一とは限らないとすれば、例えば原子7、17、23個と言った小塊の集合を考える事が出来る。
これは一つの大陸上に存在する複数の国家の人口密度は均一では無いことに喩えられる。
鉄の塊が均一で無いならば、個々の質量m、及び柔性Hが異なる小塊の集合という見方が出来る。
塊全体が示す物理的性質は質量mや柔性Hが異なる小塊の分布(重ね合わせ)という見方が出来る。
この概念がスペクトル分布と言える。
エネルギについても同様に、原子の小集団=小塊が持つエネルギは原子1個が持つエネルギの整数倍になる。
この見方に基づき、本報の質量m、柔性Hをもった物質のモデル=バネを例えば1/2、1/3、1/4~1/nに分割していった場合、分割数に比例して増大する固有振動数がn個得られる。
物質の振動の源となる熱エネルギは式(1.4)で与えられるが、分割数をn、分割された質量をm'とした場合、温度Tを維持する為に印加しなければならない熱エネルギは、
ここで留意すべきは、温度Tは連続値を取るが、nは整数、 質量m'、熱エネルギEtは離散値を取る少数である。
次に、本報の物質のモデル=バネでは1次元方向に伸縮するモデルであるから、現実の3次元の体積を持って伸縮する物質のエネルギを表現するには以下のようにnの3乗としなければならない。
次に、質量m'が単純に1/n=等分割ならば、nは約分されてEtはTに比例するだけで分割数nの増加に対してスペクトル分布のようなピーク値を持つ事は出来ない。 Fig.3-1参照
そこで 等分割:y = 1 / x のような双曲線の反比例関係ではなく、x軸、y軸で交差するような直線反比例の関係を与える。
本報では、以下に示すような直線を仮定した。
・x軸:分割数n、y軸:分割された柔性H'とし、nの増加に伴い柔性H'を低下させる。
ここで、等分割で無いのに整数nを掛けるのは奇異に思われるかもしれないが、熱エネルギEtは物質に印加すべきエネルギだが、それを蓄える物質の質量m' 、柔性H'は独立して任意の値を取り得るという事である。
こうする事により、分割数nと温度Tに応じて質量m' 、柔性H'が変化し、バネに蓄積されるエネルギは分割数nの増加に対してピーク値を持つことが出来る。 Fig.3-2参照
Fig.3-2は柔らかい物質のモデルを用い、環境温度50°(k)、物質温度500°(k)に於いて分割数nを1→60まで振った結果から、質量m' 、柔性H'、振動数f、エネルギEtをプロット(赤)したものである。
上段左図は分割数nと柔性H' 、上段中図は同、質量m'の反比例関係を示し、以下の式で表される。
n:分割数 = 1~60
n_Ini:分割数任意値 = 41、43、47、53 = 直線のx切片
H:物質全体の柔性 = 1.0e-3 ( mN−1 )
m:物質全体の質量 = 0.1(Kg)
H'= f(n):分割された柔性
m'= f(n):分割された質量
T:温度(k) = 500、1000、1500、2000
b_rate = 1.0e−7 温度に対する柔性の変化率(mN−1k−1 )(仮想の値である)
b = f(T)= H – b_rate・T 柔性=直線のy切片
a = f(T) = b / n_Ini 直線の傾き
x = n 直線のx座標
| H' = y = a・n =(H – b_rate・T)/ n_Ini・n 直線のy座標 |
(1.7) |
原子1個=量子=素粒子の柔性H'は人為的に決める事は出来ないが、工学の分野ではバネの設計のように課題に応じて材質(元素)、線径、長さや巻き数を決めて柔性H = 1/K K:バネ定数は任意に設定出来、その結果バネ自身の質量mも決まる。
式(1.7)(1.8)で温度Tと分割数nを振って物質の柔性H'、及び質量m' が決まるようにしたのはこれに倣ったものである。
なお、 本報ではx軸、y軸で交差するような直線反比例の関係を与えたが、双曲線のように等分割でなければどんな反比例関係でも良く、例えば乱数を用いた疑似ランダムな分割でも良い。 Fig.3-3参照
これは街中の騒音の周波数分析を例に取れば、サンプリングした音響エネルギに含まれる音源は音楽の様に人為的に整えたものでは無く、ランダムであるという事である。
次に式(1.6)のm'に式(1.7)(1.8)を代入すると、温度T 、分割数nに従って質量m'が変化する際のバネに印加すべき熱エネルギEtは、
| Et = H' / H ・m・Cp・T・n3 =((H – b_rate・T)/ H ・n_Ini)・n・m・Cp・T・n3 |
(1.9) |
H、m、p、b_rate、n_Ini、Cp は定数であり、熱エネルギEtを分割数nと温度Tの関数として表す事が出来る。
nを増加させて行くと式全体にn3が掛かっているが、( )内は減少するので途中でピーク値を持つ。 Fig.3-2下段左図
一方、物質の自由振動における振動数fは以下で表され、質量m'、柔性H'と振動数fは反比例する。*3
| f = 1 /(2π √(m'H')) |
(1.10) |
*3:E = h・ν に於ける振動数νは物質の最小単位=量子として見た時の振動数である事に注意。
m'、H'に式(1.7)(1.8)を代入すると、
| f = 1 /(2π(H – b_rate・T)/ n_Ini・n・√(m / H)) |
(1.11) |
熱エネルギEtと同じく、振動数fを分割数nと温度Tの関数として表す事が出来る。
分割数nの増加と共に分母の( )内は減少し、振動数fは増加する。 Fig.3-2上段右図
x軸:振動数f 、y軸:エネルギEtに取るとFig.3-2下段中図が得られる。
ここでエネルギの定義をあらためて以下に示す。
・エネルギEv_INT:物質=鉄塊が蓄えている速度(運動)エネルギ=式(1.1)
・エネルギEf_INT:物質=鉄塊が蓄えている力(変形)エネルギ=式(1.2)
・エネルギE_SUM_INT = Ev_INT + Ef_INT:物質=鉄塊が蓄えている総エネルギ=式(1.3)
・エネルギEt:物質=鉄塊の温度を維持する為に必要な熱エネルギ=溶鉱炉に供給すべきエネルギ=式(1.4)
・エネルギEr = Ev_INT:物質=鉄塊から放射されるエネルギ=速度(運動)エネルギ=式(1.1)
・広義には振動する空間から放射されるエネルギには電磁波と重力波がある。
・空間とは実体の有無を問わない。 例:天体は実体が有る。 天体間は実体が無い。
ここで電磁波と重力波について説明するが、力学と電磁気学の相似則により以下の相似関係にある。
・電磁波:電気のLC共振回路から発生する電場と磁場の周期的な変動に伴う実体の無い空間の歪みの伝播。
・重力波:物質の伸縮により発生する重力場とバネ場の周期的な変動に伴う実体の無い空間の歪みの伝播。
光は電磁波の一種であるが、本報のモデルは実体のある柔らかい物質の伸縮なので重力波に相当する。
実体の無い空間の歪みの伝播エネルギは外延量と呼ばれる以下のエネルギである。
・電磁波:電場の周期的な変動に因る静電エネルギ
・重力波:重力場の周期的な変動に因る速度エネルギ
なお、力学的に空間に外部から直接作用出来るのは電位差や速度差のような外延量であり、これに曝される空間内部には内包量と呼ばれる以下のエネルギが生じる。
・電磁波:磁場の周期的な変動に因る電磁エネルギ(電磁波はコイルに生じる磁束で検出される)
・重力波:バネ場の周期的な変動に因る力エネルギ(重力波は空間の歪み=変位で検出される)
これらをまとめたのが、表1である。補足資料10にも説明あり。
注:実体の有る空間=物質、実体の無い空間=量子力学や電磁気学で言われる真空を意味する。
| 空間 |
| 実体有り |
|
|
| 実体無し |
|
| 電場 |
電圧V |
静電容量C |
静電エネルギ |
アンペア
マックスウェル |
|
| 磁場 |
電流I |
インダクタンスL |
電磁エネルギ |
ファラデー
|
|
| 電磁波 マックスウェル |
|
| 量子力学 |
| 近接作用 | 万有引力(ニュートン) | クーロン力(クーロン) |
Fig.3-1~3に分割数nを振った時の柔性H'、質量m'、振動数f、供給すべき熱エネルギEtの変化を示す
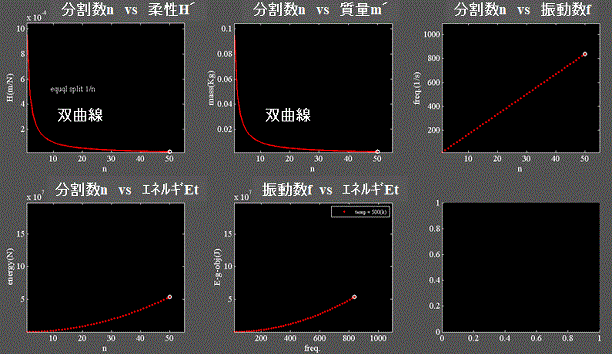
Fig.3ー1
・上段左、中:分割数nに対して質量m' 、柔性H'を等分割する場合、
・下段左、中:エネルギEtはスペクトル分布のようなピーク値を持つ事は出来ない。
・白プロットはエネルギEtがピークとなる時の座標を示す。
|
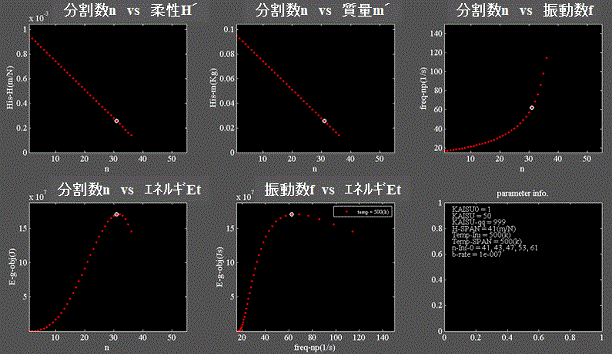
Fig.3-2
・上段左、中:分割数nに対して質量m' 、柔性H'を等分割にしない場合、
・下段左、中:エネルギEtはピーク値を持つ事が出来る。
・白プロットはエネルギEtがピークとなる時の座標を示す。
|
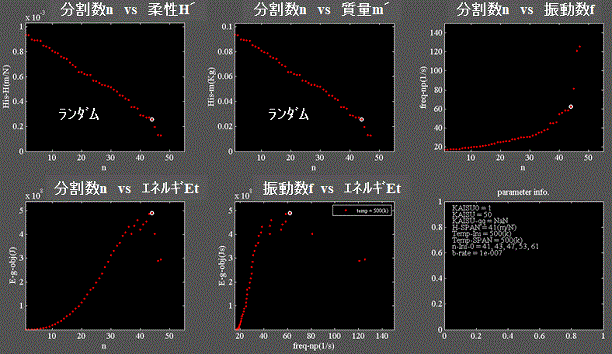
Fig.3-3
・上段左、中:分割数nに対して質量m'、柔性H'を乱数を用いて疑似ランダムに分割した例である。
・下段左、中:エネルギEtはピーク値を持つ事が出来る。
・白プロットはエネルギEtがピークとなる時の座標を示す。
|
Fig.4に分割数nを振った時の柔らかい物質のモデルから放射されるエネルギErの観測結果を示す。
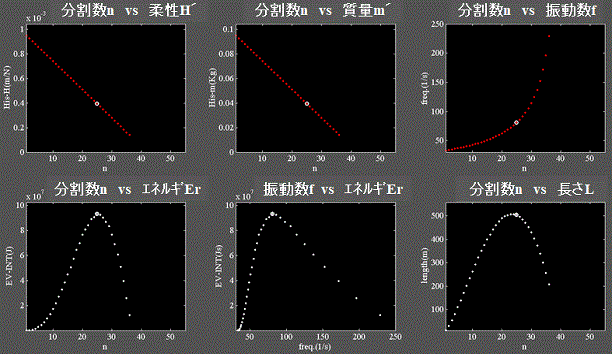
Fig.4
・上段のフォーマットはFig.3-2と同じである。
・下段左:x軸:分割数n、y軸:放射エネルギEr。
・下段中:x軸:振動数f、y軸:放射エネルギEr。この曲線(本報では便宜上曲線Aと呼ぶ)は振動する物質から放射されるエネルギと振動数の関係を表す。
・下段右:参考にx軸:振動数f、y軸:伸縮しているバネ=物質の長さL(最大値)に取ったもの。
|