|
Last update : 2000.10/09
平底船型?
|
|
平底船型?

 旧帝国海軍が軍縮条約下に建造した「吹雪」「初春」「千鳥」「最上」あたりの艦艇において、
静復元性の確保のため、水線幅を拡げて吃水を浅くとった設計が行われた...
と言われております。
本駄文はこの「平底船型」について少々考えてみよう、という趣旨で書かれております。
(「平底船型」、と言ってしまうといささか語弊がある気もいたしますが、
とりあえず呼びやすいんでこれで行きます。)
旧帝国海軍が軍縮条約下に建造した「吹雪」「初春」「千鳥」「最上」あたりの艦艇において、
静復元性の確保のため、水線幅を拡げて吃水を浅くとった設計が行われた...
と言われております。
本駄文はこの「平底船型」について少々考えてみよう、という趣旨で書かれております。
(「平底船型」、と言ってしまうといささか語弊がある気もいたしますが、
とりあえず呼びやすいんでこれで行きます。) 船体を設計するとき、静復元性の確保という面からは水線幅を大きくしてメタセンタを高くしたいのですが、
速力を下げるわけにはゆかないので船体長さを減らすことは出来ない、
よって吃水が浅くなる...というのは、
傾斜が微少である範囲ではそれなりの説得力を持っています。
船体を設計するとき、静復元性の確保という面からは水線幅を大きくしてメタセンタを高くしたいのですが、
速力を下げるわけにはゆかないので船体長さを減らすことは出来ない、
よって吃水が浅くなる...というのは、
傾斜が微少である範囲ではそれなりの説得力を持っています。 上記のような、排水量と長さが一定とされていて、
水線幅と吃水とが単純なトレードオフの関係にある状態について考えてみます。
この場合について物凄く大雑把に言うと、
「メタセンタ半径」(浮心上のメタセンタへの距離:BM)は、
水線幅の自乗に比例し、吃水に反比例します。
船体静復元性の要である「メタセンタ高さ」(重心上のメタセンタへの距離:GM)は
BMからBG(浮心上の重心への距離)を引いたものですから、
水線幅と吃水の関係は静復元性に決定的な影響を与えるわけです。
上記のような、排水量と長さが一定とされていて、
水線幅と吃水とが単純なトレードオフの関係にある状態について考えてみます。
この場合について物凄く大雑把に言うと、
「メタセンタ半径」(浮心上のメタセンタへの距離:BM)は、
水線幅の自乗に比例し、吃水に反比例します。
船体静復元性の要である「メタセンタ高さ」(重心上のメタセンタへの距離:GM)は
BMからBG(浮心上の重心への距離)を引いたものですから、
水線幅と吃水の関係は静復元性に決定的な影響を与えるわけです。 例によって分かりずらい説明ですが、要するに、
「幅を広げたくなるんやっ」ということです。
例によって分かりずらい説明ですが、要するに、
「幅を広げたくなるんやっ」ということです。 さて「平底船型」ですが、その利点としては、
さて「平底船型」ですが、その利点としては、・GM値が大きくなって静安定性を確保できる。 ・GM値が大きくなるので動揺周期が増大し、乗り心地が良く、 (特に艦艇で)砲雷の照準が行いやすくなる。 ・一般的に言って乾舷が高くなって凌波性が向上する。  ...といったあたりが考えられます。
...といったあたりが考えられます。 反対に欠点としては、
反対に欠点としては、・吃水が相対的に浅くなるため、水面上重心高さ(OG)が上昇しやすい。 ・同じく水上水中側面積比が大きくなりやすい。 ・舷端没水角が小さくなり、一般に復元力範囲は小さくなりやすい。  ...といった点が挙げられると思います。
端的に言いますと静復元性能(傾斜角が微少な範囲)が良くなっても、
動復元性能(傾斜角がより大きくなったとき)は悪化するわけで、
要するに、「実はひっくり返りやすくなるんやっ」
てとこです。
...といった点が挙げられると思います。
端的に言いますと静復元性能(傾斜角が微少な範囲)が良くなっても、
動復元性能(傾斜角がより大きくなったとき)は悪化するわけで、
要するに、「実はひっくり返りやすくなるんやっ」
てとこです。
実証?

 と、言うことで「駆逐艦 その技術的回顧」でも「海軍造船技術概要」でも「昭和造船史」でも
水線幅を広げて吃水を浅くしたことになっている我が条約期の艦艇ですが、
エンジニヤー(の見習)としては数字を出してみないことには納得が行かないわけです。
実際はどんなもんだったのでしょうか。
エンジニヤー(のなり損ない)らしく、グラフを描いてみることにします。
と、言うことで「駆逐艦 その技術的回顧」でも「海軍造船技術概要」でも「昭和造船史」でも
水線幅を広げて吃水を浅くしたことになっている我が条約期の艦艇ですが、
エンジニヤー(の見習)としては数字を出してみないことには納得が行かないわけです。
実際はどんなもんだったのでしょうか。
エンジニヤー(のなり損ない)らしく、グラフを描いてみることにします。 題材は「海風」から「橘」に至る駆逐艦を使用します。
ついでに条約型水雷艇も入れてみます。(笑)
題材は「海風」から「橘」に至る駆逐艦を使用します。
ついでに条約型水雷艇も入れてみます。(笑) 使用した値は以下の表に示す通りで、「日本海軍全艦艇史 資料篇」からとったものです。
新造計画値がほとんどだと思いますが、まぁ設計を見るためですからむしろこれで宜しいでしょう。
使用した値は以下の表に示す通りで、「日本海軍全艦艇史 資料篇」からとったものです。
新造計画値がほとんどだと思いますが、まぁ設計を見るためですからむしろこれで宜しいでしょう。 グラフを描く以上は、平底具合を示す数値が必要です。
ここでは幅吃水比ことB/dを採用しました。
なお、線図を同様のものとしたままですとBM値はB/dの3乗に比例する筈です。
グラフを描く以上は、平底具合を示す数値が必要です。
ここでは幅吃水比ことB/dを採用しました。
なお、線図を同様のものとしたままですとBM値はB/dの3乗に比例する筈です。
表の1. グラフ作成のため使用したデータ
 さて、得られた結果が以下のグラフです。
横軸が1番艦竣工年、縦軸がB/dになっています。
一見したところ、友鶴事件以降の時期でB/dが急落しているのが見て取れますが、
条約期にB/dが特別増大している様には見えません。
さて、得られた結果が以下のグラフです。
横軸が1番艦竣工年、縦軸がB/dになっています。
一見したところ、友鶴事件以降の時期でB/dが急落しているのが見て取れますが、
条約期にB/dが特別増大している様には見えません。 さては、巷間流布され続けた情報は事実ではなかったのか...?
さては、巷間流布され続けた情報は事実ではなかったのか...?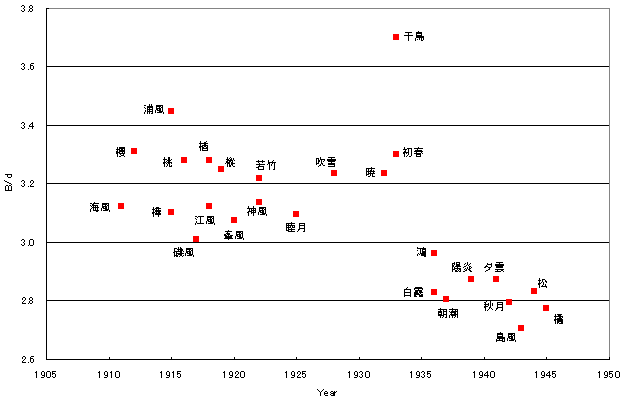 グラフ1. 日本海軍駆逐艦のB/dの変遷(その1)  こっからがエンジニヤリング・センスというものです。(謎)
こっからがエンジニヤリング・センスというものです。(謎) 「千鳥」や「鴻」が、同時期の駆逐艦よりB/dが大であることにヒントを得て、
大きさによって区別してみることにします。
ここは一等駆逐艦と二等駆逐艦で区分するのが漢の花道というものでしょうが、
調べるのが面倒くさいので1000トンより上と下で分けることにします。
(いや何、大した違いはないでしょう。)
「千鳥」や「鴻」が、同時期の駆逐艦よりB/dが大であることにヒントを得て、
大きさによって区別してみることにします。
ここは一等駆逐艦と二等駆逐艦で区分するのが漢の花道というものでしょうが、
調べるのが面倒くさいので1000トンより上と下で分けることにします。
(いや何、大した違いはないでしょう。) で、できたのが下のグラフです。1000トン以上を赤、1000トン以下を青で示しています。
で、できたのが下のグラフです。1000トン以上を赤、1000トン以下を青で示しています。 このグラフを見た瞬間、思わず笑い出してしまいました。
このグラフを見た瞬間、思わず笑い出してしまいました。
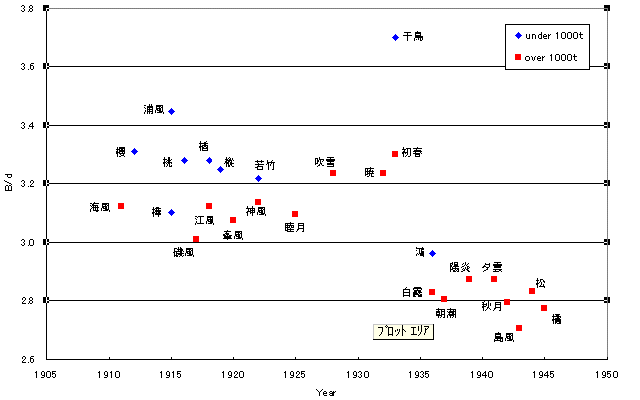 グラフ2. 日本海軍駆逐艦のB/dの変遷(その2)   このグラフから読み取れるのは、以下のような事項でしょうか。
このグラフから読み取れるのは、以下のような事項でしょうか。・一般的に言って、小型の駆逐艦ではより大型の駆逐艦よりB/dが大きい傾向がある。 ・第一次大戦の頃から、日本の大型駆逐艦のB/dは漸増傾向にある。・ この時期は日本的駆逐艦の設計が固まりつつあった時期であることと合わせて注目に値する。 ・「吹雪」より「初春」(と「千鳥」)に至るいわゆる条約期の駆逐艦では、 それ以前の時期よりも明らかにB/dが上昇している。 ・友鶴事件後にB/dは急落し、今までにない水準にまで低下している。 これは友鶴事件の反省から出た「OG重視、水上水中側面積比重視」の設計の影響であろうと思われる。 ・「千鳥」平ぺったいね...。  ...てところでしょうか。
...てところでしょうか。 何やらごちゃごちゃ書いてありますが、要旨としては、
「条約型はB/dがでかいんやっ」つーことです。
何やらごちゃごちゃ書いてありますが、要旨としては、
「条約型はB/dがでかいんやっ」つーことです。 ちなみに、同時期の重巡洋艦でも同じ現象が起こっています。
(グラフを作るのが面倒くさかったので載せません。)
「日本海軍全艦艇史 資料篇」を元にした数字では、各艦新造時(多分計画値)のB/dは、
「妙高」2.939、「高雄」2.951、「最上」3.273、「利根」2.970...となっています。
ちなみに、同時期の重巡洋艦でも同じ現象が起こっています。
(グラフを作るのが面倒くさかったので載せません。)
「日本海軍全艦艇史 資料篇」を元にした数字では、各艦新造時(多分計画値)のB/dは、
「妙高」2.939、「高雄」2.951、「最上」3.273、「利根」2.970...となっています。
結論?

 と、いうわけで日本の大型駆逐艦を見てみて、
条約型駆逐艦では幅が広く、吃水が深くなっている
らしいことがわかりました。
この理由として考えられることは、
巷説どおり静安定性の確保こそがもっとも妥当なものだと思われます。
と、いうわけで日本の大型駆逐艦を見てみて、
条約型駆逐艦では幅が広く、吃水が深くなっている
らしいことがわかりました。
この理由として考えられることは、
巷説どおり静安定性の確保こそがもっとも妥当なものだと思われます。 ここで問題になってくるのが、平底船型「理論」や、藤本「理論」ですが、
正直言って私はそれはどうでもいいことなのではないかと考えています。
当時の設計者の頭の中に「幅を広げて吃水を浅くすると良いんだ」という
何らかのセオリーがあったのではないか、とは思いますがね。
ここで問題になってくるのが、平底船型「理論」や、藤本「理論」ですが、
正直言って私はそれはどうでもいいことなのではないかと考えています。
当時の設計者の頭の中に「幅を広げて吃水を浅くすると良いんだ」という
何らかのセオリーがあったのではないか、とは思いますがね。 ま、今回は「数値を並べてみたらこういうことが起こっているよ。原因はたぶんこうだよ。」
と言うのが目的なので、この辺で。
ま、今回は「数値を並べてみたらこういうことが起こっているよ。原因はたぶんこうだよ。」
と言うのが目的なので、この辺で。 相変わらずの駄文でしたが、ここまでお読み頂き有難うございました。
相変わらずの駄文でしたが、ここまでお読み頂き有難うございました。 ご批評ご感想等を頂けますと、大変嬉しいです。
ご批評ご感想等を頂けますと、大変嬉しいです。
主要参考文献

 「日本海軍全艦艇史 資料篇」 福井静夫 編集/KKベストセラーズ
「日本海軍全艦艇史 資料篇」 福井静夫 編集/KKベストセラーズ 「昭和造船史」(1巻) 日本造船学会 編/原書房
「昭和造船史」(1巻) 日本造船学会 編/原書房 「駆逐艦 その技術的回顧」 堀元美 著/原書房
「駆逐艦 その技術的回顧」 堀元美 著/原書房 「海軍造船技術概要」 牧野茂・福井静夫 編/今日の話題社
「海軍造船技術概要」 牧野茂・福井静夫 編/今日の話題社 本文章は上記図書を参考に藤原梟介の責任において記述してあります。
本文章は上記図書を参考に藤原梟介の責任において記述してあります。 どこかしらに間違いがあることを確信しておりますので、
参考になさる際には上記文献をあたられることをお勧めします。
どこかしらに間違いがあることを確信しておりますので、
参考になさる際には上記文献をあたられることをお勧めします。 論理的な批判・批評は喜んでお受けいたします(つーか嬉しいんですが)ので、
ご遠慮なくどうぞ。
論理的な批判・批評は喜んでお受けいたします(つーか嬉しいんですが)ので、
ご遠慮なくどうぞ。 |