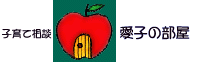

毎年、小学生を連れてキャンプに行きます。丹沢山麓、皆瀬川上流のどん詰まりです。山小屋があり、動物を飼い、後ろに山、前に川という所、『ペガススの家』と言います。絵本『ぼくはいかない』(文・柴田、絵は伊藤秀男さん。ポプラ社)の舞台になっているところです。
今年の夏も行きました。
初日のお昼は各自がお弁当を持ってきます。おにぎり、サンドウィッチ、詰め合わせ…いろいろです。食べた後は、燃えるゴミと燃えないゴミ、生ゴミに分けて処理します。燃えるゴミはドラム缶の中で燃やし、生ゴミは動物や鯉にあげられるものはエサにし、ならないものは穴を掘ってうめ、燃えないゴミは運ぶようになっています。ところが子どもは、食べ終わった空の容器や包装ゴミを手に持ったまま、立っています。分別ができないのです。
紙の箱を持ち「これ、もえる?」
アルミ箔を持ち「これは?」
と、いちいち聞きます。仕方なく分別バケツの前に座り指示しました。
何でこんなにわからないのか考えてみると、りんごの木のある横浜市はゴミを分別収集していないことに思い当たりました。それぞれの家で子どもは、日常、「燃える、燃えない、生」と、やっていないためだと、ひとりうなずいていました。
ペガススでは、お風呂も炊事も薪を使っています。庭にはたき火の炉があって、いつも煙がのぼっています。
子どもたちが喜々として遊ぶことの一つに、火遊びがあります。おとなが起こした火に、新聞紙、牛乳パック…いろいろ入れて燃えるのを喜んでいます。一つ一つを火ばさみで入れ「もえた!」「もえない」と、繰り返しています。「紙が燃える」ということ、「アルミホイルや釘を入れても燃えない」に行き着くにも時間がかかります。やがて、火の中に長い木の棒を入れ、燃えてくると火から出して、煙をたなびかせてあそんだりします。燃え方や臭いまでもが、体を通して入っていきます。
低学年は、マッチを擦って火をつけることにも興味を示します。こんな場面は日常生活にないので、大箱一箱はムダにする覚悟をします。薪に火をつけるなんてほど遠い話で、いつまでも、ティッシュペーパーを入れ続け「これ、もえる!」と、喜んでいる子もいます。「紙は燃える」という言葉や知識は十分知っているけれど、ティッシュが目の前で燃えていくことに魅せられ、「燃える」という言葉を実感し、目を輝かせます。
何回かのキャンプを繰り返していくうちに、石を火の中に入れ、火ばさみで川に運びジュウと音が出るのを発見。そのうち、バケツに水を入れてきて熱い石をいれると、水が温かくなることを見つけ楽しんでいたりします。
火を起こせるようになり「ことしは、ふろたきをしたい」と、張り切ってくる子も登場しました。
私は、「感じて身につけていくことは、本物の体験として身についていくだろう」と思っています。そして、さらに想像力や知識欲にも発展していくのではないでしょうか。
例えば、キャンプのゴミの分別にしても、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」の分別方法を種類別に具体的に教えれば、さっさとできるようになるでしょう。でも、火で遊んで、「燃える」「燃えない」を体験してわかっていくと、教えられた分別とは違ってくるのではないでしょうか。
実感を伴わずに知っていることは、「知っているけどわかっていない」ということではないでしょうか。わかっていないことからは、次を想像することはできません。
「燃える」「燃えない」という体験を通して、「なぜ、お弁当のゴミを分別するのか」は、さらに、「燃えないゴミはどうするのか」「どうして横浜市は分別しないのか」「その処理の仕方は…」と繋がっていくかもしれません。いつかは実感を根拠にした、自然保護、地球保護にまで発展することもあるでしょう。キャンプのゴミ分別と火遊びから、あれこれやってみながらわかっていくことの大事さを思いました。
泥団子でも、鬼ごっこでも、木工でも、虫の観察でも、泳ぐことでも、料理でも、楽器でも、なんでもいいのです。子どもがあれこれやりながら、実感を通して、考えたり工夫したり、想像したり、調べたりしていくこと(学校で言う総合学習とは、こういう
小学校低学年はお稽古ごとに時間を使い、中学年にもなると塾に通い詰める生活には、あーも、こーもなんて寄り道は許されません。時間をかけず、無駄な労力を使わず、最短距離で教えられ、モ知っているつもりモでいることだらけではないでしょうか。
こんな時代でもきっと子どもは、おとなが知らないだけで、あーもこーもやってみる隙間を上手に作っているかもしれません。そう、信じたいです。でも、一歩進めて、おとながそんな時間の隙間を提供できたら、提供する覚悟をしてもらえたらと思わずにはいられません。
育児にも同じ事が言えるのではないでしょうか。マニュアルを見たり専門家に相談したりして、時間をかけずにスムーズにみごとに育つ方法を願うけれど、どっこい、そううまく運んでくれないのが子ども。泣く子を抱え、あーもこーもやっていく。ワカランチンをなだめたり、すかしたり、飴で釣ったり、おこったり、叩いたりしていく。そうしながら、わが子の癖や特徴がわかっていく。わが子との付き合い方がわかっていくのではないでしょうか。
下手と言われようと、間違っていると言われようと、時間がかかろうと、実感を持って振り回されながら、『我が家らしさ』が出てくる。そうこうして、振り返ってみると、子どもを育ててきたことが、自分を知り自分らしさを作ってきたことに気づかされるでしょう。
子育ては大変でしょう、でも、きっときっと、あなたの骨を太くたくましく育てていっていると思います。
「親も子も、前を向いて急がず、寄り道をしながら、確かな歩みを」と、願います。
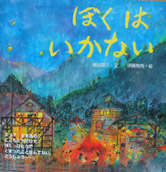 |
||
 |
||
写真/ペガススキャンプのこどもたち
 |
|