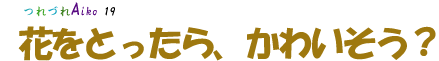 |
 |
柴田愛子 ill Takasima.N |
4、5歳児の部屋の前のプランターに、チューリップが咲いています。でも、背が高くなりすぎて、強い風に大きくゆれていました。私がはさみを持っていきチョキンと切ると、そこにいた5歳の子たちが「かわいそー」と、口々に言いました。「え?」
私に可哀想という発想がなかったので驚きました。なんだか責められたような気もして、ひっかかりました。
子どもたちがほんとにかわいそうと感じて言ったというより、反射的にでた言葉のような気もしました。
「かわいそう?」と聞くと、
「かわいそうだよ」
「どうして?」
「だって、せっかくさいたのに、きっちゃったら、かわいそうでしょ」
「きったら、かれちゃうよ」
「だって、いつか枯れるよ」と私。
「でも、きったら、はやくかれちゃうでしょ」
なるほど一理あります。負けじと弁明しているつもりはありませんが、私も食い下がります。
「あのままだと、風が強くて塀の網にぶつかって、かえってかわいそうだったよ」
「それなら、ばしょをうつしてあげたらいいんじゃないの」女の子はよく気がつきます。
「でも、こうやってちゃんと花瓶に入れて飾って、きれいだなあと思ってながめたら、かわいそうじゃないんじゃなあい?」
「でも、きられるより、さいていたかったとおもう」
だんだん、子どもたちの方が優勢?
話の視点を変えてみました。
「みんなのうち、お花飾る?」
20人のうち三分の二の子どもが手を挙げました。
「おかあさん、はなすきなの」
「いつも、かざってある」と言います。
「じゃあ、その花はかわいそうなの?」と聞きました。
「……」
「家の中に花があるとうれしい?」と聞くと、
「うん」。
お母さんが花が好きなんだとも言います。
そんな会話をした後に、もう一度聞いてみました。
「私がチューリップを切って飾ったのは、かわいそうだった?」
三分の二が「かわいそうじゃない」に変わりました。
子どもと私のずれがわかったような気がします。私は庭の花を切って飾るのは当たり前に育っています。ままごとに使うのも当然で「かわいそう」と、止められたことがありません。今でも、庭に花が咲いていれば、花屋で買わずに切って使います。ところが、子どもたちは花屋で買った花を飾っています。切って売っている花は、目の前で咲いている花とは別物なのでしょう。
つまり、庭に花が咲いていて、切って花瓶に入れるという生活体験がないということかもしれません。
公園になった柿は食べれないもの、海で見た泳いでいる魚は食べる魚とは別物、そんな感覚かもしれません。
しかし、しかし、まだ気になります、子どもたちの使う「かわいそう」が。
花を採ると「かわいそう」。アリをつぶしている子を見れば「かわいそう」。仲間に入れてあげないと「かわいそう」。理由はどうあれ泣いていれば「かわいそう」。小さい子にはやさしくしないと「かわいそう」。
「かわいそう」という言葉が安易に、自動的に出てくるような気がするのです。
本来、かわいそうという言葉は「気の毒」「見ていられない」といった、心が動かされて出てくる言葉のはず。
ところが、目にした現象に対して自動的に、心が動くまもなく口から出ているような気がするんです。いままで存在すら気がつかなかったチューリップでも、それに愛着がなくても、チューリップの気持ちにならなくても、採っている人がいれば「かわいそう」と言ってしまうというような。そして、それは正しいと疑っていない。
こんなふうに、おとなから言い聞かせられたことがパターンとなって、考えたり感じたりすることせずに、インプットされていること、多いのではないでしょうか。5歳児ともなると、それが定着しつつあるような気がします。
それは感じる心を鈍らせ、感じるままを表現することを鈍らせているようにも思います。
無意識に子どもに使っている言葉、親子でチェックしてみませんか?