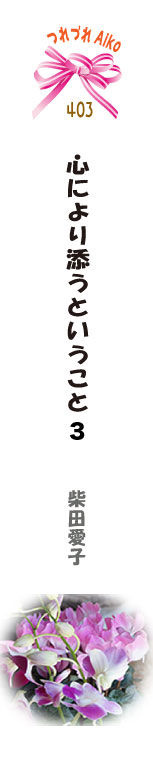
子どもの表情から察してひとこと言葉にするだけの「寄り添う」ことから始めたことですが、だんだんと子どもの表情から内面が見えてくるようになりました。見る癖がついたということかもしれません。子どもはちゃんと感じ考えていることを確信しました。
子どものやりたい気持ちに添ってみると、子どもは自ら育つ力を持っていて、自らの中に育つプログラムとスピードを持っていることを確信しました。
そんなつきあい方を続けていくうちに、なぜか子どもとの関係が "濃く" なってきたように思いました。というのは、いつの間にか子どもの名前を呼び捨てにするようになったのです 。
私自身、家族以外の人を呼び捨てにしたり、されたりした経験がありません。だのに、なぜか呼び捨てが自然と口から出てしまうのです。たぶん、子どもとの距離が近くなったのでしょう。
同時に私のことを「先生」とよばれることが気恥ずかしくなりました。それからは「あいこさん」とよんでほしいと子どもや親に言いました。
人として対等であると、子どもを知れば知るほど思うのです。
もうひとつ大事なことに気づきました。
何かあったときに寄り添ってくれる人がいることで自分を取り戻せるのだということです。
困った顔の子に「こまっちゃったね」とつぶやいて隣にいると、「うん」と言いしばらくすると動き始めるのです。いい考えが浮かんだようです。
泣いて暴れている子に「怒っているんだよね」と声をかけると、やがて暴れるのをやめて「だってね」と話し始めるのです。
子どもが心のなかで何かを感じているけれど言葉にならないときに、その感情を受け入れることで落ち着きを取り戻し、元の自分に戻れるのだと気づきました。そして、ちゃんと自分で考えられるようになるのです。
・子どもが感じてる
↓ おとなは表情から読みとったものを言葉にしてあげる。つまり、その感情そのままを
受け入れて共感する。
・感情が落ち着き、自分の気持ちを整理する
↓ 時間が必要なときです。あせって声をかけず、待ちます。
子ども自身、自分の気持ちに向き合い、考えはじめているのです。
・話しだす、もしくは行動する
自分なりに結論や方法を見いだして、気持ちにけりをつけます。
これら一連の様子を見守ることが、寄り添うことなのです。それはいっときのときもあるし、数日のときもあります。
「何かあったときに、寄り添ってくれる人がいることで自らを取り戻して、自分に向き合い、一歩前に進んでいく」と思うのです。
小さい子どもの場合は、寄り添ってほしいのは親や信頼できるおとなでしょう。思春期になると、他人でもいいし、居場所でもいいのかもしれません。さらに、おとなになるとそれは本だったり、カウンセラーだったり、宗教だったりするのかもしれません。
人は生きているのですから、なにかしらハプニングがあったり、心が荒れたり、疲れたり、悩んだりします。残念ながら、どんなにかわいそうでも、愛していても、他の人が立ち上がらせることはできないのだと思います。自らが自らに向き合って、立ち上がる以外にないのです。でも、寄り添ってくれる人がいることで立ち上がる力が生まれるのではないでしょうか。
三回にわたって「心の寄り添うこと」を書かせてもらいました。人はそれぞれですが、今、私が考えていることをまとめまてみました。ここまで実感しながら方向性を見つけてきたのですが、多くの方の刺激を受けてきたと思います。自分づくり(自分らしさ)は自分の中だけで純粋培養できるものではありません。共感や批判、反発などいろんなことを通して、培われていくものでしょう。
これから先も、今と同じように考えているかどうかはわかりませんし、今も実践できているかというとまだまだというところです。
とりあえず、今の私の基本姿勢にしたいと思ってはいます。(11月10日 記)
●今年度バックナンバーはここをクリックしてください
