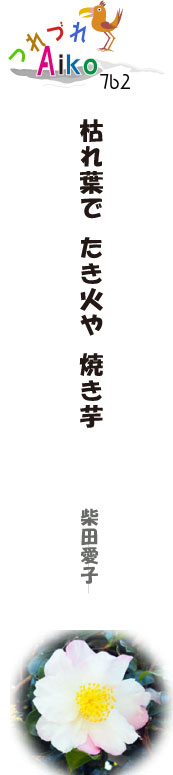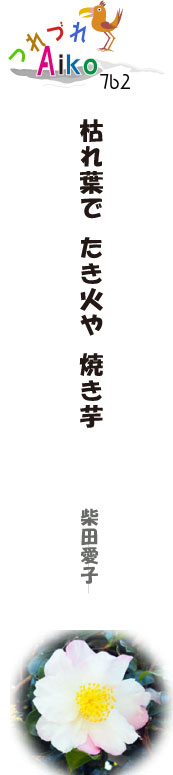庭の桜の葉が全部散って、足元が黄色くなっています。
歩くとカサコソと音が楽しい。そう、本来は枯れ葉でたき火や焼き芋をする時期です。
「おちばたき」という童謡をご存じですか? 「かきねの かきねの まがりかど・・」で始まる歌詞で、私はこの時期になると口ずさみたくなります。落ち葉を集めてたき火をして、灰を土に戻するのは子どもの頃は当たり前にしていたことです。
ところが近年、たき火は煙が臭い、洗濯物に着く、火の粉が危ないと禁止になり消防署に届けてからやるということになってしまいました。もちろん、郊外や農業地などはその範疇ではないところもあるでしょう。
りんごの木は4か所に保育の基点がありますが、どこも火はやれないのですが、唯一住宅街にある見花山はちいさなたき火(火遊び)ができます。一軒家なのですが庭があります。実はお隣の方も土いじりが好きな方だったので、お互い様でやれています。遊歩道には枯れ葉と程よい木の枝が落ちていて、子どもたちはベビーバスに集めてきてたき火をします。時には羽釜でご飯を炊き、庭でいただきます。
火を扱う機会が全くないと言っていいほどの今の暮らし、子どもたちはマッチの存在さえ知らない時代になっています。住宅が密集しているところでの火は危ないと、生活の中でも電化が進み、火の存在は避けられています。火を生活の中に見ることがなく育っていく子どもたち。
頭を悩まします。物事の原点を知らずに育っていくのはどうなんでしょう? 土とか火か水とかは、地球に生まれた人間が生きていく上で不可欠なもの。今だって昔ながらの様々な天災は変わらずに押し寄せてくるのに、人工的なものに囲まれていて、何かあったとき手も足も出ない育ちをしていくのはどうなのかと、子どもに関わる仕事をしていく者として悩みます。
りんごの木は夏には川遊びにキャンプに行きます。そこでは、薪割りや大きなたき火、お風呂沸かしなど原点に近い体験をしています。その時の子どもたちは生き生きとしています。技量がないので、目は離せないし、危なっかしいですが、やっぱり本能的にあこがれるのはこういう体験なのです。原始時代の血が騒ぐ?
こういう体験が身につくほどまでにはできなくても、させていきたいと思い至ります。なので、火遊びもチャンスをつくる方向で保育を考えていきたいと思っています。
そんな背景があって6日には4歳児が「やきやきパーティ」をしました。(前回のホームページに写真が載っています)
子どもはやたらとうちわで仰ぎます。火を燃やすには風が必要というのは、言われるからかなんとなくわかるのでしょう。あおぐと火が燃えるのは驚きで楽しくもありますしね。
ブロックで囲んだ中に紙と枯れ枝を入れ、マッチで火つけておこします。焼いて食べたいものをこちらも用意しますが、子どもたちもそれぞれ持ち寄っていました。
芋、りんごはアルミホイルに包まれて投げ込まれます。網の上にはししゃも、ウインナー、パン、ハムもあります。親が奮発してくれた、大きな鯛の干物、丸ごとのししゃも、はんぺんもあります。ひたすら食べます。あきたら砂場や周りであそび、戻ってきては焼きの繰り返し。暖かな日差しもあり、なんともいい感じでした。
私も次々いただきました。串に刺したウインナーは油がしたたり、焦げ目がついて火であぶったからこその味がします。箸もなく、焼けた魚の身を手づかみで口に運びます。群がって食べる子どもたちの姿はまさにネコのよう。アチチチと言いながら、フーフーと冷ましながら口に入れます。最後の仕上げは焼いたマシュマロ。
そこそこ満腹になり帰る時間になりました。いちにち、ただこれだけ。これだけだからいい日だったと満たされた気持ちになります。
迎えに来た親たちが「いいなぁ」とうらやましそう。そうね、おとなもこんな一日を過ごしたいですね、いえ、おとなこそこんな温かな一日が必要ですね。
もっとも帰ったら芯までいぶり臭かったです。下着までね。煙ってすごいです。
昔は馴染んだ香りでしたが、確かに今は「洗濯しなくちゃ!」と思いました。人工的ないい香りに包まれて過ごしていることを実感しました。気持ちは行ったりきたりです。(12月12日 記)
●最近のバックナンバーはここをクリックしてください。
|