毎年一回、「ハーモニーセンター」の方々が動物と一緒に来てくれます。モルモット、ウサギ、ヤギ、子どもが乗れるちいさな馬。子どもたちは年々楽しめるようになって来ました。(写真。前回の表紙にある写真も。)
ハーモニーにご縁が繋がったのは、なんと40年近くさかのぼります。りんごの木を始める頃、同時に港北ニュータウンの中で自主保育をしていました。今のりんごの木の近くです。そこに住んでいる3歳の子どもたち13人を、親の当番三人と私で保育していました。週1回から2回程度のことでした。一年間だけで、その後は近くの幼稚園に進んでいました。当番で保育に入ることもあり、親たちは全員の子の特徴を知っているばかりでなく、親同士の関係も密になっていきました。3年くらい続けたかな?
 そのときの子どものひとりが、このセンターのメンバーになっていました。その人のお兄さん(この人も自主保育の子)の子どもがりんごの木に入ったことで、関係は思い出すように繋がったわけです。私がハーモニーの方々に話しに行き、ハーモニーセンターの方々がりんごの木の子どもたちに動物を触れあわせてくれるというトレードが始まったわけです。 そのときの子どものひとりが、このセンターのメンバーになっていました。その人のお兄さん(この人も自主保育の子)の子どもがりんごの木に入ったことで、関係は思い出すように繋がったわけです。私がハーモニーの方々に話しに行き、ハーモニーセンターの方々がりんごの木の子どもたちに動物を触れあわせてくれるというトレードが始まったわけです。
15日の日曜日、今回はハーモニーセンターのボランティアをしている学生に話してほしいという要望でした。大学生がほとんどです。その会で子どもの頃過ごしてきた人、大学で動物のことをやっている人、動物が好きな人など、まさに動物が引き寄せた若者たちです。30人程度でしょうか、みなさんいい表情をしています。生き物と子どもたちのエピソードなどを話しました。
子どもたちの育ちは、なにより体験することがいちばん身になっていく。
でも、それだけではなく「見て学ぶ」ということもある。おとなのやっていることや、他の人のこと、見て学ぶことも大きい。特に初めて見ること、やることはおとなのモデルが必要なこともある。経験の少ない子どもは見てから、自分の一歩を踏み出す。動物に近づくとき、いきなり向き合う子は少ない。慎重にじっと見て、おとなの接し方をみて、やっと一歩前にという、そんな感じ。
そして、教えて育つこともある。けど、この分量は少ない。教えることが有効なのは、本人が求めていること、そのタイミングにあったときに求めている分量は吸収されていくというようなことを話しました。
集中して聞いてくれます。さらに的確な質問が返ってきます。みんなの表情がいいです。今の大学生は無表情、聞いているのか聞いていないのか、わかっているのかわからないのかつかみにくい。自分を閉ざしている人が多く、心を開いてもらえないと教えることが吸収されていかないので苦労している・・・という教授たちの声を聞きます。私自身も数は少ないですが、そういう経験をします。
そこで「みなさんも大学の授業の時はそうなるの?」と聞いてみましたら、数人が頷きました! え! 学校という組織がそうさせるのか、教える教えられるという立場の違いが不自由にするのか、人数の多さがそうさせるのか、同年代がそうさせるのか、この人たちは動物に触れあうために来ているから感性が豊かなのか? 戸惑いながらも「なーんだ、ちゃんと若者じゃない!」と、うれしかったです。「今の学生は」なんてことを言って失礼しましたという気持ちになりました。終わってからも、集まってきてしばらくおしゃべりが続きました。
学生たちの脇に実は三世代の人たちが聞いていました。それは当時自主保育をしていた親たち、その子どもといってもすでに親、その子どもたちと妻たちが来てくれたのです。同窓会状態です。三世代が耳を傾けてくれました。
「何の動物になりたいですか?」と、どの世代でも話せる話題も交えながらなんと2時間にも及びました。
その後は同窓会連中で昼食を楽しみました。
「3歳の時の、それも週2回のことを覚えているの?」と聞くと、なんと覚えていました!「新聞紙破りましたよね」って。
改めて実感しましたね「感性の記憶は長持ちする!」。当時2歳だった妹さんが母になりウン十年ぶりに会ったのに「愛子先生ちっとも変わらない!」。
それはないです、確実に年寄りになっています。
けど、覚えてくれているだけで驚きでした。私ももちろんおぼえていて、すぐにわかりました。なんだかいい一日でした。
今週末の大分市で今年の講演は終了です。今年も多くの方々にお目にかかってきました。
自分の思いを話し、耳を傾けてくれるのは、いい気分です。聞いてくれている人の表情に励まされながら話すからいいのです。そして、質問が学ばせてもらえます。思いがけないことが多いからです。とっさに頭を巡らせ、自分の考えが飛び出すのがおもしろいです。
後に感想をお送り下さるところもあります。メールで質問の追加がたり、相談になることもあります。やっぱり講演は対話なのです。話すのが好きだけではなく、話すことで育てられてきたのです。
今年も「つれづれ・・・」を読んでくださって、ありがとうございました。
よいお年をお迎え下さい。またね! (12月19日 記)
●最近のバックナンバーはここをクリックしてください。
|
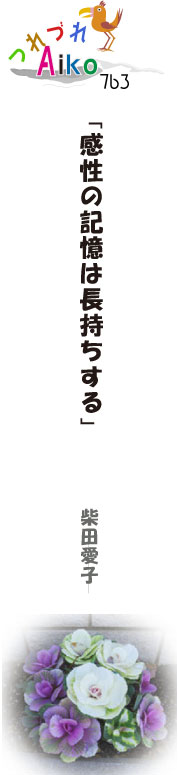
 そのときの子どものひとりが、このセンターのメンバーになっていました。その人のお兄さん(この人も自主保育の子)の子どもがりんごの木に入ったことで、関係は思い出すように繋がったわけです。私がハーモニーの方々に話しに行き、ハーモニーセンターの方々がりんごの木の子どもたちに動物を触れあわせてくれるというトレードが始まったわけです。
そのときの子どものひとりが、このセンターのメンバーになっていました。その人のお兄さん(この人も自主保育の子)の子どもがりんごの木に入ったことで、関係は思い出すように繋がったわけです。私がハーモニーの方々に話しに行き、ハーモニーセンターの方々がりんごの木の子どもたちに動物を触れあわせてくれるというトレードが始まったわけです。