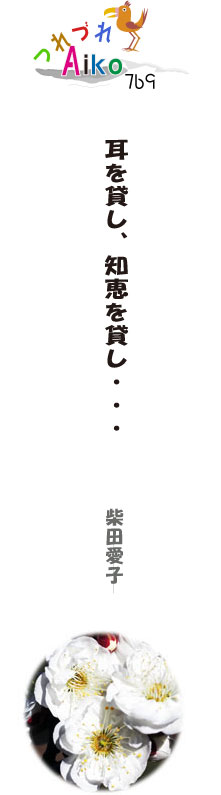一週間に一回の「坪田さんのご飯」、卒業生のお母さんが現役の母と一緒に、子どもたちのご飯を作ってくれます。今回はコーンクリームパスタでした。
ひとりの子どもが食べるときに箸でパスタ(スパゲッティー)を持ち上げって揺らしました。すると隣にいた子が立ち上がって、パスタと同じ動きをします。クネクネと。今度はパスタを持ち上げると、立ち上がって伸びます。両手を挙げて。それがおもしろくて反対側にいた子も始めます。
真ん中には箸を持ってパスタを動かす子、両脇にはその動きを真似る子。私は正面に座っていたので、おもしろいなぁと見ていました。ところが私の隣に座っている子が「たべているときはあそばない!」と大きな声でその子たちに言いました。ふと、私は困りました。おもしろいからいいかと思っていたのですが、そう言うべきはおとなの私?
いっしょにあそんでていいものか、注意するべきことなのか、見守るべきことなのか・・・・。
子育ても保育もたぶんこんなことだらけですよね?
私は子どもの気持ちに共感できる自分が好きです。だから「まあ、いいか」が多くなります。でも「早く食べちゃいなさい!」「食べながらあそばない!」「それはあそぶものではありません!」「サッサと食べてからにして!」というおとなの声が聞こえてきそうです。
そんなとき思い出す子がいます。お弁当の時間になると蓋を開け、同時に箸が立って歩き始めます。お弁当箱の区切りはお風呂やトイレ、ご飯のところはベッドになってしまいます。同じテーブルの子どももいっしょに始まります。延々とごっこあそびが展開します。そろそろという時間を見計らって「そろそろ食べないと帰りに間に合わないよ」と声をかけると、あわてて現実に戻り一気に食べ終わります。その子は小学生の時にはお話を作っていました。
イメージって自然と浮かんできちゃうんですよね。そんな豊かな子どもたちをおとなのしつけでストップさせていまうのはもったいない? とも思います。子どもの良いところを伸ばしたいとおとなは言います。これだって、いいところです。
でも、こういう子はストップかけたところで、別の時間に別のものを使って始めるだろうから食事中はやめてもらうべき? と思う気持ちもあります。
子どももいろいろ、おとなもいろいろ、だから折り合っていくしかないということでしょうか? おとなが譲れないことは子どもに譲ってもらう。子どもが譲れないときは、おとなは我慢する。そのくらい子どものあそびとおとなの価値観は違うということでもあります。
さて、先週は4,5歳児の「とことん週間」でした。自分がやりたいことを提案し、同じ気持ちの子が集まって毎日取り組んでいくのです。
子どもたちがやりたいことなので、子どもの提案、スピードで、話し合いながら進めていきます、
今年は「跳び箱」「折り紙」「縫い物」「パン作り」「ケーキ作り」「棒倒し探検」「おおアナコンダさがし」「だるまづくり」となりました。毎年、違います。
おおアナコンダとは巨大な蛇でブラジルにいるそうです。でも、毎日いそうな森や草むらをあるき、最終日には電車に乗って、いるらしき場所のやぶこぎをしながら分け入り、いたらしき洞を見つけたそうです。
だるま作りも初登場です。子どもがいろんな作り方を調べてきて、小さなものから大きなものまで、なかなか楽しいだるまたちができました。
跳び箱は跳べる子も跳べない子も、自分に挑戦です。みんな跳べるようになって成功体験。
折り紙も工作のように多様な作品ができました。
実は縫い物はひとりでした。でも、なにをどう作りたいのかイメージがはっきりしていて、ひとりでもいいと言い切り、かわいい人形を完成しました。
棒倒しは棒の赴くままに、外をひたすら歩きまわり、地域の人と声を交わしたり、お弁当食べるところを提供していただいたりしたようです。
パンとケーキは実は決めるに当たっての経緯がおもしろかったです。両方ともオーブンを使うといいます。しかし、りんごの木にはオーブンはひとつしかありません。「どっちかがあきらめれば!」と私。「綱引きするとかさ、勝った方ができるというのはどお?」というと「そういうのはいやだ」と子どもの反撃。「じゃあ、どうするの? オーブンを借りるとか、オーブンのある家にいくとか、オーブンを使わないやり方を探すとか、考えなくちゃね」と、その日はそこまで。すると、翌日、子どもたちはちゃんと考えて来ていました。ほとんどの子が「オーブンを使わない」方法を。パンはフライパンでも作れるやり方がある、炊飯器を使うのもある、ナンというのが作れると。ケーキも「クレープがある」「クレープに生クリームを重ねるケーキ」「チーズケーキ」「フライパンで作れるのもある」・・・と、子どもたちなやなかやります。この背景には親の協力があるに決まっています。子どもの困ったに耳を貸し、知恵を貸し、家でやってみた子もいたようです。親たちからも子どもから持ち込まれた相談を一緒に考えた経緯を聞きました。子どもたちが自分のやりたい気持ちを親に援助してもらい実現する。親はきっと朝送り出したあとも、子どもの今日の姿を想像していたことでしょう。
「とことん週間」は親の送迎の気持ちも、いつもと違う思いがあったことでしょう。
自ら前に進もうとしている子どもたちの姿に、惚れ惚れしてくれていたらうれしいです!(2月20日 記)
●最近のバックナンバーはここをクリックしてください。
|