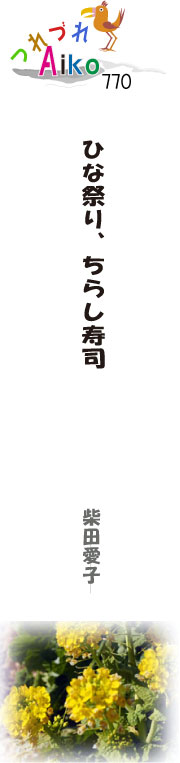前回、スパゲッティであそぶ子どもたちをおもしろいと思って見ていた私、隣で「たべているときはあそばない」と言った子どもの様子を書きました。
その後、よその保護者たちに話す機会が何回かあり、このエピソードを話してから、聞いてみました。
わが子が食べながらあそび始めたとき
①おもしろいと思う、もしくは一緒にあそんじゃう
②食べているときはあそばないと注意する
③しばらく見守って様子をみる
という三択での質問です。
①に手をあげる人はほぼいませんでした。木村泰子さん(元おおぞら小学校長)とご一緒だったとき、彼女は即まっすぐ手をあげましたけど。学童をやっている方も手が上がりました。つまり二人。ほとんどの方が②注意するでした。③は数人というところでした。別の会場では①はゼロでした。一般的におとなたち、親たちは注意するのが当たり前になっているようです。
木村泰子さんとご一緒だったのは、和歌山県橋本市の学童クラブによんでいただいたときでした。私が始めに話しました。次が木村泰子さん、その後は対談でした。私はいつものように子どものエピソードを通して、言いたいことを伝えます。会場におとなに混ざって小学校高学年の子が座って聞いていました。私が話し終わってその子の近くに行ったとき「こどものきもちがわかるんですね」と言われました。なんとうれしいことでしょう。子どもから言われたことが一層うれしかったです。
子どもの仕事を長くしていると、子どもの気持ちが親よりはわかるのかもしれません。だから食べ物のことも楽しめるのでしょう。親は子どもをきちんと育てる責任があると思うから、楽しんでいる場合ではないのでしょう。私のような人は、おとなになりきれないとも言えますが、全部おとなになってしまったらつまりません。だって、根っこは子ども時代なのですから。
さて、今回のお昼ご飯はちらし寿司でした。ひな祭りが近いのでお吸いものもつき、デザートには桜餅。手をかけて作ってくれています。もはやちらし寿司など面倒なものは作らないか、「ちらし寿司の素」のできあいを混ぜるだけになっています。ですから、滅多にない本物の味とも言えます。
このメニューを子どもたちに話す前に、ひな祭りのうたを前奏から口ずさみました。
チャチャンチャチャンチャン・・・・「灯りをつけましょぼんぼりに・・・」
当然一緒に歌い始めると思ったら、子どもたちは驚いた表情で手拍子だけ。え! りんごの木は歌をあまりうたっていないのですが、どういうわけか子どもたちはよく知っていてうたってくれたものです。数年前までは、確かに。ひな人形もないので、説明も難しかったです。
幼稚園に勤めていた40年前は<行事保育>と言われて、季節的な行事が毎月あって、歌も製作も決められ反発をしていました。日本文化の伝承は家庭でやってほしい、保育が振り回されることに憤慨していました。なので、りんごの木は行事にまつわる保育がほぼありません。けどけど、もはや家でひな祭りをやったり、鯉のぼりをあげたりは少なくなっているのでしょう。まして、歌は消えつつある・・・。もはや日本の伝統行事は保育園、幼稚園・こども園などに任されている時代?
文化とか暮らしとかが急速に変化しているのを実感します。それだけ歳とったことでもあるのでしょうけど。そういえば、晩秋のころの「かきねのかきねのまがりかど たきびだたきびだ」という歌が大好きです。でも、この光景は今の子どもたちにはまったくわからないでしょう。垣根もたき火もわからないのですから、この歌からなにかをイメージできるのでしょうか?
つい口ずさみます。でも、子どもに聞かせるのは躊躇します。
意味はわからなくてもうたい継いでいく方がいいのか、昔の古典は姿を消していくのか。カラオケでおじいちゃんやおばあちゃんがうたっていたからと、孫がそのうたを好きになるということもありますし、自然に任せるほかないかもしれませんね。なんだか長く生きている分、流れの速い文化や生活、価値観の変化に戸惑います。こんなことになるとは思わなかったという気持ちが正直あります。子どものころや若いときは今が永遠のような気持ちでしたからね。せめて自分の軸や感性が見えなくなってしまわないようにがんばることにします。 (2月27日 記)
●最近のバックナンバーはここをクリックしてください。
|