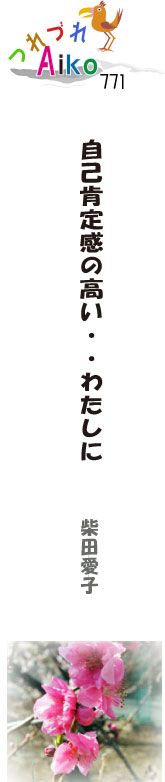二月はいろんな土地を駆け抜けてきた感があります。静岡〜山梨〜愛知〜栃木〜再度静岡〜和歌山〜福井と、いろんな方々と会い、おしゃべりに耳をすましていただき、現地の景色や食べ物を楽しませていただきました。
しかし、寄る年波で、移動が長いと家の近くの駅に着いた途端力が抜けて、這々の体で家に着く感じです。
三月は、りんごの木の<出番>です。どのクラスも年度末の会がされます。最後の親のお話し会もあり、スケジュールはりんごの木で埋め尽くされます。卒業式は20日です。
久しぶりに2,3歳児をのぞきました。なんと寒い中で出入り口は開けっ放し、いちおう暖房はついていますが、役に立っているとは思えません。大きい組もそうなのですが、りんごの木ほど寒い保育室はないのではと思うほど開けっ放し。さらに裸足で庭に出たり入ったりしているのですから、足の裏の皮はさぞや厚く丈夫になっていることでしょう。子どもは動いているから自家発電装置を持っているようなもの? 保育者は厚着でがんばっています。
たまにしか行かないのに「あいこさんだ」と言ってくれるありがたい子どもたち。へこ帯(浴衣などのときに使う帯)を髪に巻き付け、長々と引きずって歩いています。「髪なが姫かしら?」と声をかけると、すまし顔。階段を降りようとするのでヒヤッとしましたが、ちゃんと長いのを手に巻き付けて降り始めました。このあそび方はりんごの木創設当時にも見られました。あれから40年もたっているのに、子どもの発想やあそびかたは同じなのです。子どもが大きくなっていく過程には、時代の流れや、文明の発達とは関係がないのを見て、なぜかホッとします。
あちらこちらでお弁当を食べ始めています。見ていたら「たべて」とお皿を差し出してくれた子がいました。上には油粘土のうそっこ食べ物が。お気持ちを受け止めて「ありがとうございます。おいしいですねぇ」と返しました。自分は本物食べているのに・・・。
寒空の午後、庭で餅つきが始まりました。つきたてのお餅にきなこをつけて、食後とは思えない食べっぷり。そりゃあそうですよね。別腹です。
そんな子どもたちとは、まったく違うおとなの状況があります。仕事をして、子育てしている人たちが、専業主婦の方を見ると子どもに申し訳ないと後ろめたさを感じているというのです。お風呂に入れて、夕飯食べさせて、7時には寝かせると聞くと、自分は7時にさえ帰宅していなかったりする、子どもに申し訳ない気がしてるというのです。今や専業主婦が三割を切った時代に、そんなこと思っている人がいることが私にとっては驚きでした。出産後「いつから復帰する?」が当たり前の会話になっていると言うときに、少数派の人を眺めてそんな気持ちを抱くのですね。
逆に専業主婦を選んだ人は、仕事をしていないという後ろめたさを感じるというのは良く耳にします。子どもと24時間一緒というのは楽ではありません。でも、楽をしているように見られていることの後ろめたさ。 今は保育園に入ったり、こども園に入れたりで長時間預ける方が多くなったこともあって、公園も園の子どもたちがやってきます。かつて「公園デビュー」といわれていた時代よりは親子連れが少なくなっている気はします。
新聞で子育て中の母親を「子持ち様」と職場で疎んじられているという記事が載っていました。子どもに熱が出た、怪我をした、子ども同士のトラブルなどと園からの呼び出し。子どもの病気による急な休みなどで周りの人が不平をもっているという社内の現状が書かれていました。
子育て中の人が、なにかとビクビクしている気がします。
選択はひろがったのに、自分の選んだことに落ち着けていない。
保育者の話を聞いていると、親が強くなってサービスを要求する権利を持っているかのような気がしていました。園側はサービスを提供する人にみられている時代が来ているように思えていました。しかし、一連の母親たちの心情を聞いていくと、自分に弱気。
親たちは「自己肯定感の高い子に育てたい」と言います。ご自身が自己肯定感が高いと思いますか? と聞くと、手をあげる方はほんの数人です。
比較して、評価してもなにも生まれません。とりあえず、自分の選択を良しとしましょうと言いたいです。社会とくに企業のシステムをこれから変えていかなくてはいけない時期なのです。「子どもが急病です、お先に失礼します。ご迷惑おかけします」と社を出る勇気をもちましょうよ。(これほとんどが母親の役になっているのもヘンですけどね)
今までは効率よく収益を上げるために働いてきましたが、今からは効率悪くとも、人の幸せ度を上げていかなくてはいけない時期に入ったと思っています。
なにが大事? 子どもが健やかに育っていくこと、自分の人生も大事にすること。その方法は人それぞれです。とりあえず、自分が選択したことをやってみたらいいです、きつい、辛いと思ったら変更可能です。
子どもは親の選択に文句を言いません。引き受けています。親も子どもを引き受けてい自分らしく生きればいいのだと思います。(3月7日 記)
●最近のバックナンバーはここをクリックしてください。
|