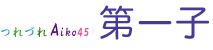

柴田 愛子
パッチワーク=福島裕美子
先日、子どもが2、3歳のお母さんたちに講演にうかがった後、参加していた一人のお母さんと話しました。その方は、今は3人の子どもの母。初めの子が2歳のときに、初めて私の講演を聴いてくださったそうです。
そのとき、私はこんな話をしたようです。
1、2歳は、まだ、動物だから、欲しいものを手でつかんで食べるのは当たり前。
本来、動物は命を繋ぐため、健康な体を維持するために、食べる。
こぼさないでとか、箸を持ってとか、最後まで座ってというのは食文化。食文化は人間によって創られた文化だから、環境によって身に付いていき、4歳以降くらいになるとできるようになる…。
ついでに姪の話もしたようです。
「自分の口に自分で入れることが大事という考えから、食事の時は、新聞紙を広げ散らかってもいいようにして、子どもは手づかみで食べてる。一度なんて、納豆出しちゃったから大変! 髪の毛までねばねば・・!」
この話のとき、この方は「そうはいったって、手づかみで食べられるのはいやだわ。4歳までは待てない、私は絶対しつけてみせる」って、思ったそうです。そして、きつく叱りながらしつけたそうです。
ところが、二人目ができ「いいか」とほっとくようになり、今、三人目は納豆ねばねばだそうです。
お話しを聞いたとき「後でできることは後にしましょう。何度言ってもできないことは、あきらめましょう」と言い続けてきているけれど、そうか、必ずしも納得して肩の力抜いてもらえる訳じゃあないんだ、ということがわかりました。本音を聞かせてくださって、大変参考になりました。
同時に、第一子と二子、三子は、同じ親でも随分違う育て方をしていることが歴然!
第一子は、年齢的に無理であろうがなかろうが、個人差なんてなんのその、自分の中のあるべき姿にまっしぐらなのかもしれません。それだけ、願いも強く、パワーもあるってことでしょう。
「何度言っても、言うことを聞いてくれないことってある?」という問いかけに、
「寝ころんでテレビを見ないでほしいのに・・・」
「鼻をほじらないで・・」と返ってきて、私はびっくりぎょうてん!
「そんなことまで言わないでよ! そんなことまで、思うようにさせようとしないでよ」と言ってしまいました。そのくらい目が離せないということかもしれません。見えるからつい言ってしまうことも多いのでしょうから。
りんごの木にきている弟を、中学生や高校生のお兄ちゃんが迎えに来る人がいます。お兄ちゃんがとってもかわいがっているのが、手に取るようにわかります。
ところが、下の子はお兄ちゃんが好きですから喜んでいますが、対等に話すばかりではなく、威張っています。かわいがってもらっている自覚なんてないと思いますね。
私のことが浮かんでいました。
私は五人兄弟の末っ子、一番上の兄とは12歳離れています。でも、私はいつも対等を求めていました。ご飯のときは「同じ子どもなんだから、おかずの大きさも同じじゃなくちゃいやだ」と主張。「おまえは小さいんだから」と、兄姉にあきれられても、食べられなくても言い張っていました。今、思い出すと恥ずかしい。
りんごの木の子を迎えに来るお兄ちゃんを見ながら、自分が客観的にはこんなに小さくて、こんなにかわいがってもらっていたのだと初めて知った気がします。そして、兄とのことをあれこれ思い出させられ、「お兄ちゃん、ありがとう」と、心から思いました。
同じ親が同じように育てても、違うから不思議と言いますが、同じ親が同じようには育てられないし、一人ひとりの家族環境はすごく違うのですね。
どちらが得とか損とかいうことでなく、違うのですよね。
(11月20日 記)
●バックナンバーもくじへ
