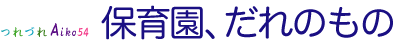

柴田 愛子
パッチワーク=福島裕美子
りんごの木に、ある“認可”保育園の保育士さんが見学に来ました。
2、3歳児の小さい組にお連れしましたら、部屋の中で3歳の男の子が、向かい合ってジャンプしていました。ジャンプをしていたというより、うれしくってうれしくって、ピョンピョン跳ねていたというほうが適切でしょう。
人間、うれしいと、どうして跳ねちゃうんでしょうね。
クイズ番組など見ていると、当たるとピョンピョンうれしそうに跳ねてます。
私は日曜日のお昼は、たいていNHKの「のど自慢」を見るのが子どもの頃からの習性になっています。上手だと鐘が鳴り響きます。カンカンカンカン、カンカンカンカンカーン! すると、飛び跳ねる飛び跳ねる、ばんざーいをしながらピョンピョンする人、泣きながら跳ねる人、舞台中を跳ね回りアナウンサーに抱きついて跳ねる人、ほんとに面白いです。
この日の子どもたちは、まさにそんな感じで跳ねていました。
見ていたその方がつぶやきました。
「うちの保育園だったら、止めなければいけない」
「え?!」と聞くと、跳ねるとうるさいから跳ねてはいけない。そればかりではなく、絨毯に座ってなくてはいけないというのです。
「絨毯で、座って保育するなんて、無理じゃないの?」と言うと、
「だから、テレビとかビデオとか・・・」
あきれて呆然としましたが、どーんと突き落とされたような気分にもなりました。
この話を他の“認可”保育園の保育士さんに話すと、
「うちもそうなのよ。私なんて新米だから怒られてばかり。保育は座ってしなければいけないの、子どもも座らせて。走ってもいけないし、紙芝居は、手の早い子は他の子と距離をあけて見せるの」
今のお母さんたちの子育てがしにくい状況を少しでも緩和するために、それと、子どもが育ちにくい家庭や地域環境の中で、つまり、公園での親たちの人間関係のために必要以上にいい子にさせようとしたり、水や泥、砂などで思う存分あそべないことや、子ども同士のかかわりが薄いことなどを考えると、本来の子どもの育ちを保障するためにも、専業主婦でも週2回くらいは保育園が預かるシステムが必要なのではないかと思っています。
ところが、肝心の保育プロの保育園が子どもの育ちを促すどころか、囲いの中で管理しているというのですから、たまりません。そう、園長が「私たちは、子どもを管理するのが仕事です」って言ったそうですから。
そういえば、ずいぶん前、ある保育士さんからの「1歳児の食事の時間に、子どもがテーブルに乗ってしまうので、テーブルの上に画鋲を上向きに置いている。こんな方法はよくないと思うのですが、先輩は、この方法でやると子どもがテーブルに乗らなくなるし、親たちからもしつけが行き届いていると評判がよいから、ということで聞いてもらえない」という手紙をもらったことがありました。
幼い子は家で、園での状況を話せませんからね、確かによくしつけられていると親は感謝しているのかもしれません。
この頃、同じような記事が新聞にも載り、この方の園だけではないのだと思いましたが、かなり騒がれましたから、さすがに今はそんなやり方の所はないと信じています。
話をもどしますと、管理の厳しい保育園は少なくなさそうです。子ども同士、けんかはさせない。叩いたりひっかいたり噛んだりなんて、とんでもない。廊下は走らない、高いところには登らない、ジャンプしない、物は投げない・・・
これ、保育者?
子どもの発達を知らないお母さんと何ら変わらないじゃないですか。
どうしてこうなっちゃうのでしょう。
「何かあったとき、困るから」という答えが出てきそう。
顔にひっかき傷でもあったら大変なことになる。怒鳴り込んでくる人だっているそうです。家でついた傷か、保育園でついた傷かわかりにくいので、登園時に子どもの身体の写真を撮るという園まであるそうです。
いずれにしても、子どもがおとなの犠牲になってると思いませんか?
本来、子どもの専門機関である保育園は、親の気持ちを受け止めながらも、「子どもってのはね、擦り傷つくりながら大きくなるのよ」とか「けんかをするほど気になる関係」とか、子どもが口で説明しないことを解説してがんばるものでしょう。
親も、大事な子ではあるけれど、他人の手なくして育てることはできないのだし、自分とは違う人に預けるメリットとして受け止めなくちゃあいけないでしょう。目先のよい子ふうになったことに目がくらんじゃいけません。
保育園は、親のためのサービスもするけど、肝心なのは子どもを心身健康に育てる手伝いをするところなんじゃないですか?
もうひとつ頭にきています。
“認可”ってなんですか?
建物や、子どもの人数と保育士の人数、日数・時間といった外枠的なことだけが認可の条件なのでしょうか。
もっと、子どもが主人公の保育園が増えるために、保育士も親たちも考えていきませんか。信頼関係の上で預け、預かるようになってほしいです。
言っておきますが、いい保育園も山ほどあるのですよ。私の知人たちの園は、どれも魅力的です。子どものことを本気で考えていく園が増えていくように、みんなでしていきましょうよ。ネ!(1月30日 記)
