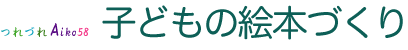

柴田愛子
絵本を作ることにしました。
二人もしたくなって、同じように作りました。
私は絵が下手です。ホントに下手です。だから、こういう場合、絵が描けなくてもいいストーリーにします。
表紙に青いボールを描きました。次のページにボールが転がっていく絵を描きました。ボールがコロコロ転がって、海に落ちてしまう。すると、落ちたボールがだんだん膨らんで、芽が出ました。
芽はどんどん伸びて、葉が伸び、とうとう大きな木になります。すると、木は空まで伸びて、虹をぽきぽき折って、飾りました。綺麗な木になったというわけで、おしまい。
思いつきで次々描いていっただけですけどね。
その間、二人はじーと考えていました。
「あら、どうしたの?」と聞くと、
「どんなはなしにしていいか、わからない」のだそうです。
私の下手な絵の作品を、得意げに見せました。
「私のはこういうのよ」
すると、さっちゃんの手が動きはじめました。○と△と□の話です。
まひちゃんは、
「あのさ、パンがころがっていくはなしにしようかな」と言います。
二人とも私のがヒントになったようです。
まひちゃんのお母さんはパンを作るのが上手で、彼女も自慢に思っているこの頃でもあります。
まひちゃんは表紙に、鉛筆でパンやさんのおじさんを描きました。そして、並んでいるパンを描きました。それから、
「このパンが、ころがっちゃったのね」と言いながら、パンを描きます。画用紙を反対に向けてパンを描き、また反対向けて、転がっていくパンを描きます。
「そうだ、このパンは、おじさんのてから、ころがっていったのね」と、おじさんの胸の部分を消しゴムで消して描き直し、パンを持たせました。1ページに、パンのころがっている姿が8個くらい描かれます。
「そうだ、おじさんはないている」と言って、おじさんの顔を消しゴムで消して、涙を描きました。
おもしろいですね。こんなふうに、話しながら絵を書き換えていくのです。
この日、午前中もお昼ごはんの後も、この続きをやりました。なにしろ、コロコロ転がったパンを、1ページに細々と10個くらい描いていくのですから、根気がいります。とうとうでき上がらずに、置いて帰りました。
ところが私は、翌日は小さい組(2、3歳児)に行ったり、外の仕事に出かけたりするものですから、なかなかいっしょにできません。その間、保育者に誘ってもらうように言いましたが、描かなかったようです。とうとう、1週間たってしまいました。
でも、その間、まひちゃんの頭から絵本づくりは離れることがなく、ストーリーを考えていたようです。一週間ぶりにあったとき、「ほんのつづきやる」と言い、彼女は、私の隣に座って、黙々と描きました、ひたすら転がっているパンを。
最後のページになったとき、女の子を描きました。
「がっこうからかえってきたら、パンがころがってきて、このこがひろったの」
「そうだ、ランドセルをしょっているこなの」
「うれしいって、わらっているくちにしなくちゃ」と、また、消しては話し、消しては話していきます。
最後に、女の子は家にパンを持って帰り、食べて、お話は終わり。それから、水性ペンで色塗りをし、絵も足されて、絵本はできあがりました。
ストーリーは奇想天外なものではありません。でき上がった本は、見事というほどのものではないかもしれません。でも、とっても楽しみ、仕上げたうれしさが彼女を満たしていたように思えます。
やり始めたことが中断しても、気持は離れなかったこと、いえ、寝かされていたことでイメージは膨らんでいたこと、話しながらそれを絵にしていくまひちゃんのやり方をみせてもらったことは、私もとっても楽しかったです。
そして、他のことでもそうですが、子どもはいっしょにやり始めたおとなと続けていきたがるのですね。跳び箱でも、縫い物でも、シールづくりでも、サッカーでも、おとなに頼るわけでもないのに、そのあそびとそのおとながセットされているみたいです。
まひちゃんと私が絵本を作っていたことに興味を持った子が「わたしもやりたいの」と、つぎつぎ声をかけてきます。しばらく、絵本づくり担当者になりそうです。また、子どもの不思議を感じます。
(2月26日 記)
