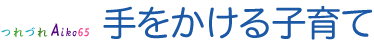柴田愛子
●フラワーアレンジ
アトリエ レ・ポンム

山のような忘れ物。シャツ、靴下、パンツ、お弁当袋・・・
「これ、だれの?」と声をかけて、持ち主がやってくると、油性ペンで名前をどんどん書いていく。
なんと、折角の日曜日の朝なのに、こんな夢で目が覚めました。
4月から始まったばかりということもあり、自分の持ち物という意識がないので、物がポンポン放り出されています。
さらに、陽気がよいと、どんどん脱ぐ。水あそびも始まって、グジュグジュになって脱ぐ。
帰る時間になると、山のような衣類の持ち主を捜すのに時間がかかるという日々が、こんな夢を見させたのでしょう。
「すべての衣類や持ち物に、名前を書いてください」という、お願いはしていません。特に、衣類に名前を書くことに抵抗がある方もいるだろうと思ってです。
でも、大勢の子どもがいますから、それぞれに、自分の持ち物が自分の手元に返ってくるために考えてほしい、と思っています。
だって、週末には大量になるのです。
持ち主が見つからない落とし物は、毎年山のようにあり、りんごの木の物にさせてもらったり、リサイクルショップに持っていったりしています。
りんごの木に着ていくシャツや靴下は、3枚に決めていた親がいました。3枚くらいだと子どもが覚えられるので、その子はちゃんと自分の物を持ち帰れていました。
4歳児の子で、毎朝リュックに入れるときに、本人に選ばせてるという親もいました。自分で選んでいるので、自分のがわかるのです。
アイロンで、名前を美しくプリントしている方も、少しはいます。第一子かな。
しかし、しかし、もらい物も多いのでしょう、親さえ自分の家のかどうかわからないという人もいますし、最悪、もらった方の名前が書かれたまま(私たちにはどこのだれかわからない)使っている人もいます。
兄や姉の名前が書かれているのはざらにありますが、まあ、書いてあるだけ本人に戻りやすいですけれど。
「物は大切に」とは、ほど遠い状況です。
ふと、布団の中で自分の小学生の頃を思い出していました。(幼稚園には行かなかったので、初めての集団生活は小学校でした)その頃は、油性ペンなんて日常的ではなかったですから、母は色の付いた糸で名前を刺繍してくれていました。
鉛筆は包丁で上部をすこしけずり、名前を書いてくれました。
教科書には、綺麗な包装紙で、表紙にカバーをかけてくれました。
シャツやパンツは、以前から、前がわかるように色の付いた糸で印を付けてくれました。母は96歳で亡くなるまで、自分のパンツに前印を縫っていました。確かに、着るときに一目瞭然で履きやすかったです。
食べるものも豊かではなかったので、少ない食材で子ども達に栄養を付けるために、かなり工夫をしてくれていたと思います。ナスのはさみ揚げやロールキャベツ、コロッケなどが好きでした。
こう考えると、小さいときに、随分手をかけてもらっていたことに気づきます。
時代が進み、経済状態も良くなり、物も豊かになり、かゆいところに手が届くような商品もたくさんあり、親が手をかけなくても子どもも暮らしやすくなりました。
しかし、今の親だって暇そうではないから、違う形で手をかけているのだろうと思いながら、4月28日の毎日新聞の一面にこんな記事があったのを思い出しました。
『「子どももっと」日本が最低』という見出しです。「少子化社会に関する国際意識調査」で子どもを持つ男女のうち「子どもを増やしたい」と答えた人は、日本は4割と最も低いそうです。ちなみにスウェーデンは8割とのこと。
日本で増やしたくない人は「子育てや教育に金がかかりすぎる」と金銭的な理由をあげたそうです。
そうか、今は子どもに手をかけるのではなく、お金をかける時代なのだと改めて思ったのです。
良いか、悪いか、恵まれているのか、いないのか、簡単に答えは出ません。
ただ、親子関係に関して言えば、お金より手をかけた方が子どもに親の愛情が伝わりやすいのではないでしょうか。
さて、5月の連休はいかがお過ごしですか?
4月から新しい環境が始まって、私、とても疲れています。いいときに連休があって、ほっとしています。
たぶん、子どもも保育者もそうだと思います。
遊園地、動物園、旅行もいいですが、イベントは気分が変わり楽しいのですが疲れるのも事実。
子どもと近くの公園でボールけり、子どもとぶらぶら散歩、時間を気にしない一日、あそびながらの長風呂、布団の上のじゃれ合いあそび、そんな、手のかけ方もあるのではないでしょうか。 (4月30日 記)