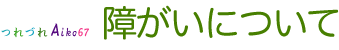柴田愛子
●フラワーアレンジ
アトリエ レ・ポンム

小さな赤ちゃんを抱いたお母さんに、声をかけられました。
「ちょっと困ったことがあるんです。実はこの子は色素のない子なんです。だから、体も髪も白いんです。そのことを私は憂えてはいません。自宅出産したんですが、出てきたときに自然と受け入れられたように思っています。ただ、よその方が『色が白いのね。どうしたの?』と声をかけてきたときに『あー、うちの子、色素がないのです』と答えると『あら、ごめんなさい』とか『聞いて悪かった』と謝られるのです。聞かれるのはいいんですが、こう言われるのが、とても辛いんです」ということでした。
赤ちゃんはまるまる太って元気そうでした。色が白いので混血の子と間違ったり、色白の子と思って近づいてきてしまう人もいるようです。
日本人は人と違うことに敏感です。島国で、村社会で暮らしがなりたってきたからでしょうか。みんな同じや、普通で目立たないことが大事にされてきたと思います。
ですから、ちょっとの違いに目が向く。そして、自分とは違うことに反応して、拒絶してしまう。
違うことだけで立ち往生してしまい、触れなければよかったと悔いたり、触れないことが『思いやり』なんて勘違いしちゃうのでしょう。
ほんとはそれが傷つけている態度であることに、気づいてもいないでしょう。
「近寄ってきた方に、色素がない子だということを平気で言えるの?」と聞きますと、
「はい」と言います。
「じゃあ、いろんな方に教えてあげて。こういう子どももいるってこと知らないから、ドギマギしてしまう。でも、あなたと出会った人は、今度、よそで同じような子どもに出会ったとき、驚かないで、自然と受け止められるのではないかしら」と言うと、
「そういえば、私も色素のない子を知っていました。だから、生まれたとき、あの子みたいなんだと思いました」
「その続きに出てくる『ごめんなさい』や『聞いて悪かった』という言葉に、あなたが傷つくのはとってもわかるけれど、世の中に免疫を広める仕事をいただいていると思って、がまんしてくれる?」と言いました。彼女は、
「わかってくれてる人がいると思ったら、がんばれます!」と、さわやかに言ってくれました。
りんごの木を卒業したダウン症のレイちゃんが、初めて学校に行くのをしぶったとき、「ダウン」とからかわれていることをお母さんは知りました。そしてお母さんは、子どもたちはダウンが何かわからないからからかうのだろうと判断し、学校の先生にお願いして授業の時間をもらい、子どもたちに説明したそうです。いじめてはいけないとか、思いやりましょうとか、手を貸してあげましょうとかいうのではなく、他の人と何が違うのか、どういう特徴があるのかという事実を、子どもたちが理解できるように説明したようです。(私は後日聞いたのですが、ホントにわかりやすい上手な説明に感心してしまったほどです)
私自身、今は、障がいを持っている人たちに会っても驚かなくなりましたし、みんな感じる心を持ち、命の重さは同じと思っています。いえ、もっと、普通に感じていると思います。けれど、そんな自分にしてもらえたのには、いろんな子に会ってきたからだと思います。
幼稚園に勤めていたときに、クラスに一人は障がい児といわれる子どもがいました。
なんといっても、「自閉的傾向」と言われた多動児の太郎ちゃんは、画期的に私を変えました。自閉症といっても、何人かに会うと、一人として同じ子はいなくて、それぞれです。
ダウン症の子どもにも多く会いましたが、これまた似た傾向はあるものの、一人ひとりの性格はずいぶん違います。
つまり、普通児でも障がい児でも、みんなそれぞれ違うということ、そして、様子や行動で一瞬ビックリして戸惑いましたが、かかわり始めると、どの子もかわいい愛しい子であることに差はありませんでした。
それぞれに癖があるように、その子の癖のようにとらえられるようにもなりました。
幼い子どもは「障がい」なんて枠をもっていませんから、あくまでも、○○ちゃんとして受け入れます。幼いときからいろんな人と触れあっていけば、当たり前として、それぞれの人格を大事にできるようになるのではないかとも思います。
21日(日)NHK教育テレビ「こころの時代」で、障がい者が演じる劇団を主宰している金満里さんという重度の障がいを持っている方が出演していました。
インタビューしていたときに「障がい者は、いつも健常者に近づかなければいけない、と努力させられます。でも、できないのです。そうすると、できない自分にふたをするより仕方なくなるのです」と話していました。
前後の話を忘れてしまったのですが、この言葉を聞いたとき、あー、みんな同じ。できそうもないことに自分の目標を置かれ、努力し続けされている。いま、子どもたちはみんな障がい児の状況にあるのではないかと思いました。
それぞれ、いろんな癖を持ちながら、共に生きていける。お互いに迷惑かけながら、手助けしながら、ありのまま生きて行ける社会になればいいなと思いますし、努力したいです。(5月22日 記)