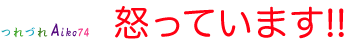柴田愛子
●フラワーアレンジ
アトリエ レ・ポンム

毎日暑いだけでも頭に来ているのに、さらにカッカする出来事がありました。
一つは、先週書いたプールの事です。
例年、小学生が夏休みになる前までと二学期が始まって一週間ほどの間、屋外の公営プールを使わせてもらっていました。幼児30人におとなが5、6人ついて行っていました。この時期はほとんど貸し切り状態です。
ここは、やっと足が着く1メートル強ほどの結構深いプールです。でも、お陰で泳げるようになる子が続出します。
親がいなく仲間と行くことで、他の子を見ながら自分に挑戦するからです。その勇気と心の葛藤には、保育者冥利に尽きるほどのドラマがあります。
ところが今年から、「1年生までは、子ども一人におとな一人の付き添いが必要」ということで、突然断られてしまったのです。
日常を共にしている保育者が、危険か安全かを判断し、覚悟と責任を持ってやっていることでしたから、がっかりどころではありません。水着を着て来た子どもたちに、急に「今日は行けない」となり、その旨を父母にも報告をしました。なんとか、回復できるように交渉を始めているところです。
そうそう、子ども一人におとな一人だったら、二人の子を持っている人は母子では行けないし、三人なら家族でも行けないと嘆いている人がいました。なんで、こんなことになるわけ!
二つめは、公園の木に網がかけられた話です。
ある子がいつも行っている公園に、とても登りやすい木があるそうです。木登りができるというのは、子どもたちにとっては輝かしいことです。もともと、人間も霊長類の動物ですから、本能的に木に登りたい要求はあるんじゃないでしょうかね。
ところが、ある日突然、その木に網がかけられたそうです。木登りを妨害するためです。
公園課に問い合わせたら、「苦情があったから」だそうです。
苦情を言った方には、それなりの事情があったようですが、それにしても、子どもに何のことわりもなく失礼なことですし、いきなり行政が処置をするのも変です。
だいたい、公園・保育園・幼稚園・学校・地域センターなどに、周囲の家からの「うるさい」という苦情は多いそうです。どっちが先にあったの?と、お聞きしたいようです。
三つめは、小学生や中学生が「(草)野球をする場所がない」と嘆いていることです
日本ではこれだけ野球が流行っているのに、子どもたちだけで野球ができるグラウンドがない。学校のグラウンドは、危ないからダメだそうです。公園はゲートボールなどの邪魔になるからダメだそうです。どこか、親がかりの少年野球にでも属さない限り楽しめないスポーツになっています。
子どもだけで群れてあそべる場所は、もうないのでしょうか。
どれもこれも、嘆かわしい。
子育て支援に、税金を使うことばかりを考えているけれど、普通のおとな一人ひとりが子どもを応援する気持なんて、さらさらない。(そういえば、プールの受付や監視をしてくれているおじいちゃん・おばあちゃん、地域の掃除をしてくれているおじいちゃん・おばあちゃんには、笑顔と温かい言葉をもらいますが、それに比べて…)。
「これからの子育ては公共の場を使いながら育てなければ、子どもが健やかに健康に育つことができない」と、常々お話ししています。だって、ベランダでビニールプールもできず、シャボン玉もできず、水あそびはお風呂場だけ? 花や虫、木登り、穴掘りの楽しさは、庭がないのなら公園しかないでしょう?
子育て広場があちらこちらにできることは喜ばしいです。でも、子どもは家と子育て広場であそびましょうと、場所が限定されるのは息苦しいです。少し前、「公園デビュー」という言葉があったように、人間関係が煮詰まるのです。
幼稚園年齢になると、園以外であそべる場所もなく、子ども同士の行き来も頻繁すぎると気兼ね、そして、遠慮なく時間をつぶせて、かつ何かが身につく場所は、お稽古事。毎日新聞にBenesse教育研究開発センターが実施した幼児の習い事に関してのアンケート集計を見ると、習い事をしているのは5歳児75.1%、6歳児85.5%とあります。教育と趣味のためばかりでなく、子どもの居場所がないから塾通いという側面もあるのではないでしょうか。
つい先日『川崎市子ども夢パーク』で講演を聴き、同じように考えている人たちから元気をもらってきたばかりなのに(第72回)…ちょっと目を世間に向けると、なんだか「世も末」という悲しい言葉が浮かんできてしまいます。
これで「子どもを産め」なんて無理!(7月18日 記)