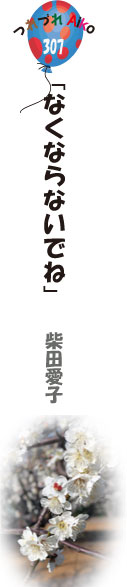20日に卒業式を終えました。
昨年のことを思い出します。 震災間もないときでした。卒業年度の子どもと親だけの参加にして、もっともシンプルな短時間の式でした。
でも、そのシンプルさが気持ちを新たにしてくれました。
今年も、狭いながらも楽しかった、いつものりんごの木の場所です。
縦割り保育ですから、にばん組(年中児)も参加しました。その親たちは立ち見参加です。
最近もときどき地震もあり、多少の不安がありましたから、始める前には避難方法の説明をしました。親は自分の靴をビニール袋に入れて持っていただき、子どもの靴はビニールシートの上に集め、まとめて持ち出せるようにしました。子どもの椅子の両脇には防災ずきんを置きました。「何事もなく、無事に終えられますように」と願いながら……。
卒業式といっても式らしからぬ式です。
一人ひとりの子どもに手書きの「修了証書」を渡し、その子だけに作った(保育者が)歌をうたうというだけです。それでも、一時間二十分もかかってしまいます。
あとは、来年度いちばん組になる子どもにカードを渡し、みんなで「りんごの木のうた」を歌って終わります。ちょうど二時間程度。子どもにはぎりぎりといったところですね。
その後、卒業児だけでいつものように遊び、親たちは茶話会でおしゃべり。
主に、日頃話すことが少ないお父さんたちにマイクを回しました。午後一時から五時くらいまででした。地震もなく無事に終えることができました。
卒業していく子どもたちは、ワクワクとドキドキだと言います。一年生になるという楽しみと心配が、気持ちの大半を占めているのです。ところが、この日、私はションボリが大半でした。楽しい一年でした。子どもたちの育ちは見事でした。さらに、二、三年も前を振り返ってしまったら、その成長の大きさに感動してしまいます。どの子も、この子も、保育者たちは大事にしてきました。愛おしく寄り添ってきました。ですから、巣立っていくのが、なんとも寂しいのです。
もちろん、「大きくなっておめでとう、小学校に行っても元気に過ごしてね」という気持ちはありますが、ワクワクまでには及びません。
子どもはいつも前を向いている、おとなはいつも振り返ってばかりいるといわれますが、ほんとにそうです。
子どもたちに、りんごの木のおとなに言いたいことを聞きました。
いちばん多かったのが「つぶさないでね」「なくならないでね」でした。これにはびっくりしました。つぶれる、なくなるなんて発想をするんですね。
一般的な幼稚園児も思うのでしょうか? 園舎・園庭もないりんごの木に経営の危うさを感じる?「がんばります」と答えました。
次は「ぼくたちをわすれないでね」でした。自分の存在をずっと覚えていてほしいという、素直な気持ちです。こんなにストレートな言葉は、おとなは使えなくなっています。
そして、「げんきでね」です。
まさに、子どもたちは今までの自分に卒業して、新しいことにワクワク、ドキドキしながら進んでいく準備ができているようでした。
「いってらっしゃい!」と、送り出しました。
私も四月に入ればワクワクドキドキになるでしょう。
もう少しは振り返って、浸っていたいです。(3月24日 記)
|