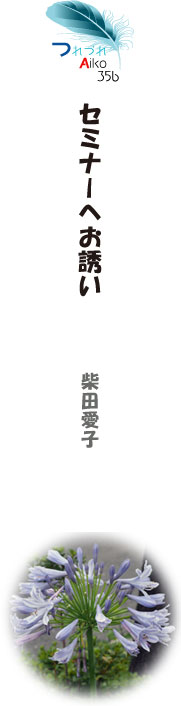
りんごの木ができて間もない頃、保育者と保育者が語り合い育ち合う会をしたいと、セミナーを始めました。
当時は、近くの保育園・幼稚園にダイレクトメールをだして、保育後に集まっていました。
20人そこそこだったのですが、徐々に人数が増えてきて、近くの幼稚園のホールをお借りするようになりました。それでも人数が増えてきて、大きいホールを借りてやってみよう! と、今の形になりました。一年に一回「りんごの木夏季セミナー」の始まりです。今年で23回目になります。
毎年、実技的なものや講演・コンサートと、バランスを考えて企画しています。
ここ数年は、みなさんの何らかの刺激になればと思い、プログラムの隙間にりんごの木の保育を感じていただくプログラムも組み込んでいます。(7月29,30日に開催。終了しました。)
今回の講演、天野秀昭さんと汐見稔幸さんの内容について紹介させてください。
子どもたちを見ていると、やんちゃな子がめっきり少なくなった気がします。
冒険や探検という言葉も聞かれなくなってしまいました。
チャンバラごっこという長年みられてきたものもなくなり、○○レンジャーの戦いごっこになりました。木登りする姿、穴を掘る姿もめったにみられません。
あそびは時代と共に少しずつ変化をするものなのでしょう。
けれど、子どもの「やってみたい」の気持ちが少し萎えてきているようにも思うのです。
「事故がないように」「迷惑かからないように」「子どもの声がうるさくないように」「ルールを守るように」と、おとなの配慮が子どもを不自由にしている気がします。
はじめは不自由を感じても、自ら抜け道を作ることができない子どもたちは、おとなに文句を言われないささやかなあそびしかしません。周囲のおとなの気持ちを察しながら過ごしているうちに、自らの気持ちに鈍感にならざるをえない子どもたち。おとなはあそびが大事と言いながら、あそべなくしているとも言えます。
そもそも、どうして、あそびが必要なのか。
ひょっとして、今からは子どもにあそびは不要な時代になるのか。
子どもがあそぶことの意味を考えてみたいと思っています。
講師にはこのテーマに最適な天野秀昭さんをお願いしました。世田谷の羽根木プレーパークをスタートに、いつも子どもたちと本音で付き合っていらしたかたです。「日本冒険遊び場づくり協会」の副代表、大正大学で教鞭もとっていらっしゃいます。
もうひとコマはりんごの木では、毎年おなじみの汐見稔幸さん(白梅学園学長)です。
いつも、時代に即したテーマを考えてお願いしています。今年は「“いい子”育ての変遷」としました。
今、親たちは心身の怪我を極端に嫌います。ほんの少し、ひっかき傷があっただけでも「これ、どうしたんですか?」と詰問されると言います。さらに、乱暴な子はうちの子に近づけないで欲しいなど、あげたらきりがないくらいに保育現場に要求してくる人が多くなっているようです。
取っ組み合いのけんかが認められている園は少ないです。
親同士であそばせているときでもそうです。ちょっと押しただけで「ダメでしょ」と言われ、おとなが嫌いなことをする子は「悪い子」「近づきたくない子」と迷惑そうなまなざし。
人は身体も心も擦り傷なくして豊かな人間には育たないと私は思っています。関わらずして、人間関係はうまれません。関わるということは傷もありです。
ふと、振り返ると、こんなに「無傷で」「いい子」を要求していた時代はないのではないかと思うのです。“いい子”のイメージは社会状況と共に変化しているのではないでしょうか?
“いい子”育てはどんなふうに変化してきたのか、そして、今後の見通しは? 汐見さんに整理していただこうと企画しました。
今、わたしたちが置かれている状況を知ることが、親たちの現実を受け止めることにもなるでしょう。
りんごの木夏季セミナーは、申し訳ないのですが託児がありません。けれど、興味がある方なら、保育者だけでなく、親御さんでも、祖父母の方でも、どなたでもいらしていただきたいと思います。
みんなで少しずつ意識をもっていきたいと願うからです。
詳しくはホームページ・セミナー案内でご覧ください。(セミナーガイドはこちらをクリックしてください)
今回はセミナーの宣伝になってしまいました。
でも、きっと、実りある会ですから! お待ちしています。(6月30日 記)
●今年度のバックナンバーはこちらをクリックしてください。
