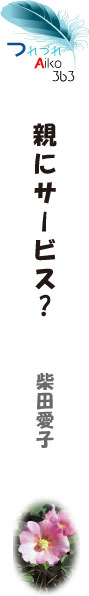
先週、ある幼稚園の保護者会によばれて、お訪ねしました。
講演前に園内をふらふらと歩かせてもらいました。
3歳児が大きな丸いたらいを囲んで、釣りをしてました。
たらいの中には水があり、子どもたちが描いた魚やタコが泳いでいました。
私が近づいてのぞくと「だめ!」「だめ!」コールです。
私はまだ何も言っていませんし、やってもいません。妨害もしていません。
だのに「だめだめ」コールは広がっていきます。
私は内心、うれしくてたまりませんでした。りんごの木も、こうなんです。
園が自分の居場所として認識された頃から、これが始まります。
さらに、子ども同士が「仲間」と思える関係になるとこうなります。
自分たちの陣地、自分たちの仲間に無断では入れません!
まして、怪しいヤツかもしれないという警戒心も働きます。
そろそろ入園説明会や見学会がはじまっていますよね。実際、たずねてきた人に「だめ!」と子どもたちが言うとヒヤッとします。
あわてて「そんなこと言わないの」とか「いやなきもちになっちゃうよ」と制したりしますが、実はこれは健康な3歳児の姿なのです。
園庭を歩いていたら、隅で子どもたちが背中を丸めてしゃがんでいます。
何かとのぞくと、泥団子作りでした。
水を混ぜた泥の部分と、白砂の場所があります。白砂はふるいにかけられてさらさら。
「ねえ。さわっていいよ」と声をかけてくれました。
白砂のバケツに手を入れると、ほんとに小麦粉のようにサラサラ。
みんな、黙々と職人のように取り込んでいますが、私がのぞくと自慢げに見せてくれます。
それはそれは見事な泥団子職人でした。
3歳児とは打って変わって、自分のやっていることに興味を持ってのぞいてくる人に、見せようとする。自慢する。それが、5歳児です。
園を見学に行ったら、ぜひ、そこが子どもの場になっているかどうかを見てください。
少子化もあって、幼稚園は親へのサービスに力を入れています。
いえ、親のことしか考えなくていいと言いきってしまう園長だっています。
「幼稚園、保育園はサービス業である」と位置づけられてもいる現状とも聞きます。
親としたら、まさか親を喜ばすことを念頭に保育をしているとは思ってもみないでしょう?
けれど、"園児獲得"は親なんです。
実は絵本だってそうです。買うのは親ですから、親が買いそうな絵本の企画は通りやすいのが事実です。
世の中、お金を払う人のご機嫌を伺うのは常かもしれません。
しかし、こと、教育に関しては子どもが主役であるべきだと、私は思っています。
特に幼児教育は人間の根源的な部分ですから、子ども自身の育ちを保障すべき保育がなされるべきです。
英語や漢字、空手や音楽、体育ローテーション(障がい物競走のように動きを決められて、ちゃんとバランス良く体力をつけていく方法)など、いわゆる"売り"をもっている園が多くなりました。
親の心配を安心に変えていく保育なので、人気も高いようです。
それなりに理念はあるでしょう。
しかし、そこに置き去りにされているのは「子どもの心の育ち」です。
感じる心、興味、やる気、試行錯誤、考える力といった子ども自身の心を動かすことに気配りがされているでしょうか?
外部からいろんなことを教えて身につけたように見えても、子ども自身の中からの要求、必然性がなければその子自身の学びにはなりません。まずは、ありのままの子どもを「よし!」と引き受けていくことから、子どもの育ちは始まります。
ありのままをよしとされた子は、ちゃんと自己主張をするようになっていきます。その子らしい本来の育ちをしていきます。
鍛えられて伸びていくものはなんでしょう?
尊重されて伸びていくものはなんでしょう?
もう一度、子どもの育ちの何を大事にしていきたいのかを考えてみてください。
親にサービスはいらない、親はがんばりなさい、とは言いません。でも、自分にはどんなサービスが必要なのか。子どもと折り合えるのはどのへんなのか、考えて見てください。
"自分の意に即したサービスをいっぱいしてもらって""楽になる"事が、子育てを楽しむ事ではありません。子どもの育ちに一喜一憂しながら自分も育つことが、子どもを産んだからこその楽しさなのではないでしょうか。
園選びは、自分に向き合ういい機会かもしれません。(9月29日 記)
●今年度のバックナンバーはこちらをクリックしてください。
