| Engineering Art=エンジニアリング・アートとは
|
ここでは舞台裏を紹介します。
・Engineering=工学とアートは二つで一つ
学校では理数系が得意な人、美術系が得意な人は居たと思われます。
ここでお話するのは物事は切り分けられるか?ということです。
数学や物理の授業を思い出してみましょう。
数学や物理に登場する○○の定理や△△の法則について疑問を持たれたことはあるでしょうか?
教科書に書いてある事をそのまま受け入れれば試験はパス出来たのではないでしょうか?
中には、”定理や法則はそうかもしれないけれど、現実はそんなに単純じゃない?” と薄々気が付く人も居るかもしれません。
工学とはそうした定理や法則に乗らない=現実的な課題を扱う学問と言えましょうか。
何かモノ作りに携わりたいと思う人は工学の勉強をされた、あるいはこれからしようと思われているのではないでしょうか?
モノ作りは現実的な課題です。
例えば料理でシチューを作るにも何回かの失敗を経てだんだん思い描いた味に近づくのではないでしょうか?
首尾よく目標の味に到達すれば、今度はそれを何度でも再現できるようにレシピを残しますね。
その時、理数系が得意な人は食材の分量や調理する際の時間や温度なども書き込むかもしれません。
工学というのは失敗しないための現実的な方法論と言えばよいでしょうか。
でも、中には分量や時間や温度など測らないでアバウトにやっても到達出来る人も居るようです。
美術が得意な人は、例えば素描=デッサンをしているときにはいちいち対象に物指しを当てて測るような事はしていないようです。
どうしてそんなにアバウトでも巧く出来るのでしょうか?
それはアバウトという言い方ではなく、目分量が正確と言ったら良いのかもしれません。
目分量とはいったい何なのでしょうか?
何を測っているのでしょうか?
数学や物理の世界では目分量という発想は無いかもしれません。一方、工学の世界では目分量は戒めています。
数学の世界では単位、例えば力なら(N)、速さなら(m/sec)というようなものは必要有りませんが、物理や工学では必須です。
工学では測るという事が必須であると言えます。
でも目分量というのはそんなに邪魔者なのでしょうか?
目分量とはこう考えてみてはどうでしょうか?
定理や法則に乗らない性質がある。
その性質はモノ作りのような現実の課題では無視する事はできない。
美術が得意な人はその性質を正確に捉える特技を持っているような気がします。
工学とアートを結びつけている性質があるようです。
その性質ゆえに工学とアートは本来切り分けることが出来ないのではないか?
それはレオナルド・ダ・ビンチも感じていたように思えます。
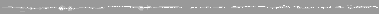
・工学とアートを結びつけている性質
それは粘性という性質です。
バネが伸縮する様を思い出してみましょう。Fig.1をご覧下さい。
振動の波を表していますが、時間が経過しても波は持続しています。
次にFig.2をご覧下さい。
波は時間の経過と供に収まって行きます。工学の世界ではこれを "減衰" していると言います。
この減衰は粘性という性質の仕業です。
粘性とは粘っこさという意味ですが、波のような周期的な変化も何か粘っこい性質に邪魔されて収まってくると思えば良いでしょう。
それは空気や液体であったり、バネの材料の中にも粘っこい性質が僅かながら含まれています。
現実の世界ではバネの振動はほっておけば何時かは収まってしまうものです。
コロナウィルスの感染者数もこのように収まって欲しいと期待していますが、世の中の成り行きもこの粘性の性質に左右されているのかもしれません。
数学や物理では収まることは考えないと言えばよいでしょうか。定理や法則は常に持続していないと困ります。
次に波の下にある図も見てみましょう。
この図は横軸にバネが伸縮する際の速度(m/s)、縦軸に力(N)の値を時間の経過順にプロットしたもので、工学の世界ではリサージュ波形と呼んでいます。
Fig.1の減衰の無い場合は楕円形ですが、Fig.2の減衰がある場合は螺旋形になっています。
工学を学び、この違いに気が付けば、Fig.2は粘性が働いているのでは?という推測が働きますが、数学ではそれは出来ません。
しかしながら、波形が閉じている〜いない=重なる〜重ならないという数学的な見方は重要かもしれません。
閉じている=遊園地のメリーゴーランドのようにぐるぐる廻っていればいずれ飽きてしまいますが、螺旋上を移動できるなら ”今どの辺?” が気になるかもしれません。これは精神的な見方かもしれません。
粘性は時間と空間を意識させてくれる働きがありそうです。
粘性を取り除いてしまえば時間と空間を忘れさせてくれるのかもしれません。
この粘性は工学の世界では(Ns/m)という単位を持っており、計測することが出来ます。
この単位が示すように粘性とは力(N)を速度(m/s)で除したもので、力と速度の比率とも言えます。
一方、美術が得意な人はそうした粘性(Ns/m)を測らなくとも、螺旋のカーブを正確に捉え、定規を使わなくともフリーハンドで描く特技を持っているようです。
橋のエンジニアでもあったダ・ビンチは洪水に耐えうる橋脚の形はどうあるべきか?を模索し、橋脚にまとわりつく渦のスケッチを残しています。
Fig.1
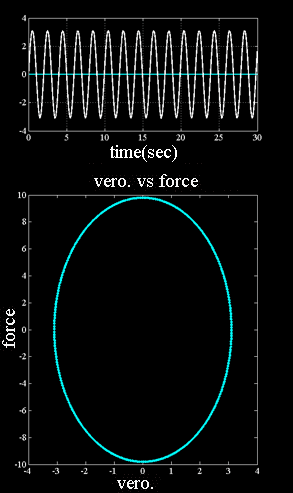 |
Fig.2
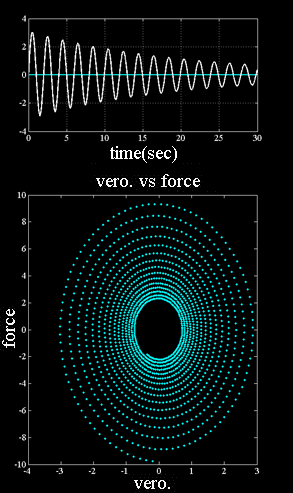 |
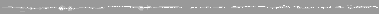
・Engineering Artの作り方
ギャラリーに展示している模様はバネの振動をリサージュ波形に表したものです。これはすべて螺旋形由来です。
波形の違いは粘性やバネの柔らかさ、伸縮させる周期やタイミングを変えたり、数値の間引き方を変えることで現れます。
こうした試行錯誤をしていると波が収まらずに大きくなる場合があります。これは共振現象と言い工学の世界では ”発散する” と言います。
コロナウィルスの爆発的感染に似ているかもしれません。つまり粘性を大きくすれば発散させずに収束させることが出来るわけです。
Fig.3をご覧下さい。一番左上にあるのがすべての値をプロットしたもので、右に進んで、7、11、13、17、23、29 と間引く数を増やして行った状態を並べています。ちなみにこの数は素数にしてあります。
右下の2例は間引き方の異なる6種類を重ね合わせたものです。この操作を繰り返せば最初の左上のカーブが復元できます。
Fig.3
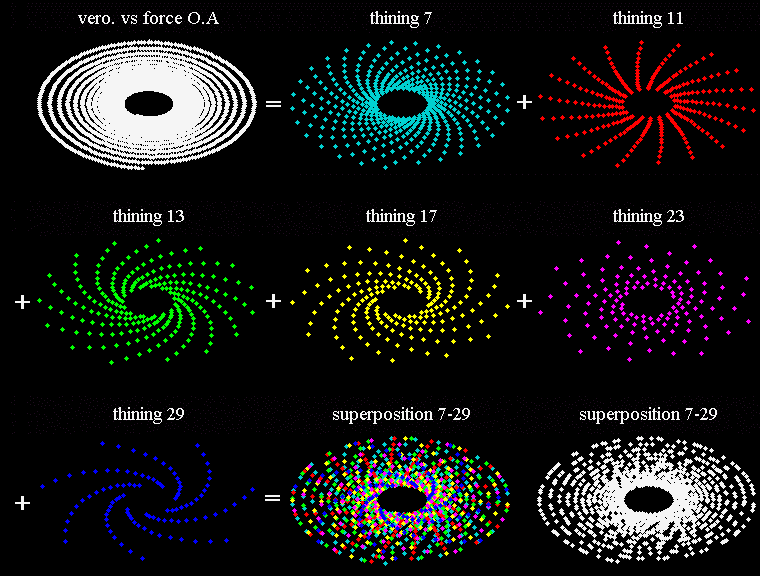 |
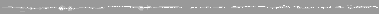
・モノの見え方は常に同じとは限らない
人為的にこしらえたものではない=自然界に見られる様々な形には黄金比が見られることが知られていますが、併せて螺旋形由来と言えるかもしれません。
ここで気が付くのは、同じ螺旋形でも間引き方が異なれば違った形に見えるということです。
5秒間に一回まばたきをしている場合と10秒間に一回の場合では違った形を認識しているのかもしれません。
これが冒頭に述べた、物事は切り分けられるか?ということです。多様性、諸行無常ということかもしれません。
あるいは、Fig.3で判るように、物事は様々な間引き方が重なった状態と捉えてもよいのかもしれません。
子供の顔には両親の特徴が重ね合わさっています。遺伝子の螺旋とはこういうモノかもしれません。
これは今話題の量子コンピューターの考え方に通じているかもしれません。
理数系が得意な人も美術系が得意な人も、今、目の前にあるモノの形を単位を伴った数値で残そうとしたり、スケッチで残そうとするかもしれません。
橋脚にまとわりつく渦のスケッチをしていたダ・ビンチも、どんどん変容している渦を見て背後に潜む性質に気が付いたのかもしれません。
鴨長明曰く、行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。
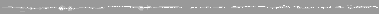
・忘れられない先人の言葉
今から38年前の1982年、私が抱えていたある違和感について相談すべくHM氏を尋ねました。
その違和感とは、”設計という仕事がなぜスタイリスト(日本語ではデザイナー)とエンジニアという職種に分業化したのか?” でした。
子供の頃は設計者なる人物が居ることはなんとなく想像していましたが、漠然としたものでした。
しかしながら高校3年の時点でデザイナーなら美術系、エンジニアなら理工系に進まねばならないという現実を理解しました。それは設計という仕事、営みが分業化されているという現実でした。
私は理工系を選択しエンジニアとして企業に採用されたのですが、自分自身デザイナーとエンジニアの切り分けがなかなか出来ない状態でした。
この違和感をHM氏に相談したところ、幸いにも理解を示してくれました。そしてHM氏の上司であるYI氏もその場に同席されており、次の様なことを話されました。
”あなたのやりたいことは良く判った。ただ、エンジニアにもデザイナーのような感性は必要だ。あなたはエンジニアの立場でそれを発揮して欲しい”
なんとなく判るのですが霧が晴れた訳ではなく、逆にとても重い宿題になってしまいました。
エンジニアとしての試行錯誤を経てそれがようやくどういう事か見え始めたのがおよそ30年後の2013年。そしてYI氏の言われた意味が判ったのが2016年でした。
その宿題はYI氏自身の宿題でもあり1982年当時、氏もようやく腑に落ち始めていたのではないか?
YI氏は工業デザイナーとして在学中から採用され、1957年に卒業されたのですが、当時の日本は工業デザインというものが廻り始めた揺籃期であり、企業側もデザイナーをどのように評価し仕事をさせるか手探り状態であったことが後から判ってきました。
一方、理工系出身のエンジニアは古くから仕事をしていたわけですが、その中に飛び込んだYI氏は、彼らとの様々な違いに直面し葛藤を抱えて居られたことも判ってきました。
私が悩んで相談した1982年当時、YI氏が到達された地点は以下ではなかったか?
・モノ作りには感性と理性がセットで必要。職種は関係無い。
・感性は理性に先んじる。
これは見方を変えると分業化の否定とも取れます。
ここでやっとダ・ビンチのやっていた事が見えてきたのです。
そして宮崎駿のアニメ ”風立ちぬ” に登場するセリフ、”サバの骨は美しい!”、”設計で大切なのはセンスだ!” がだめ押しをしてくれました。
そして今、アインシュタインが感じていたかもしれない疑問に繋がってきたところです。
・法則・学問は理性によって定まったが、人間の諸問題を解決できていない。感性も必要ではないか?。
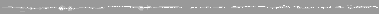
関連ページ: