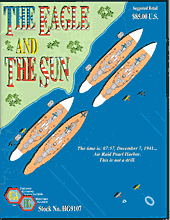
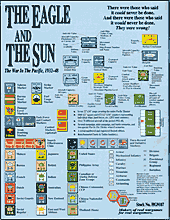
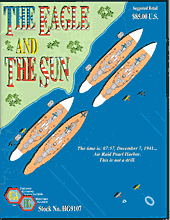 |
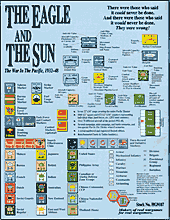 |
原形は知っている人ならSPIの幻のWar in the Pacificだとすぐにわかりますが、非常に強力にモディファイされています。1932年開戦シナリオが拡張搭載されているため、赤城と加賀には 3段空母時代、大戦初期、生き残ったときの対空火力強化型と3種類が用意されています。裏表が独立しているため計2ユニットが存在します。
印刷は非常に良好で細い線もはっきりしています。このユニットを見ていると、日本の5500t軽巡は'31になっていて古さを感じます。一気に大量に建造したため、大量に旧式化しても更新できないという泥沼状態ですね。
RPGのTravellerとエウロパシリーズで有名な会社。潰れたけどね。
GDWの初期SFゲームの2つ。2連星の星系での戦いだが、プレイした記憶も揮発するほど古いゲーム。
Travellerの世界で地球と帝国が衝突して発生する戦争を扱う。帝国はあまりに大きく、帝国側プレイヤーは一地方の長官に過ぎないため、地球と帝国の戦力差はあまり大きくない。地球側は序盤を乗り切れば勝機もある。
日本語化された物より2年ほど版が新しい英語版です。
ミニチュアで20世紀の陸上戦を行うためのルール。このセットは第二次世界大戦を扱うが、別売りのモジュールで近代戦闘や第一次世界大戦を扱うこともできる。
ユニット単位は小隊。ヘクスの対辺は250mで1ターンは15分。ほぼPanzer LeaderやBritzと同じスケールとなる。マップサイズも同じだが、光沢のある少し厚めの紙に印刷されているだけのマップは、1枚が軽いため組み合わせるのが大変でプレイし難い。Britzのようにユニット同士の火力を合わせることができないので、戦車の種類ごとの個性は表しやすい。
コマンドコントロールが厳しく、指揮官ユニットの指揮範囲内にないユニットは、移動力が半減して敵に向かって前進できないし、射撃モードにもなれない(例外:
偵察ユニットと砲兵観測ユニット)。指揮官ユニットの数は少なく、部隊が戦場を縦横に駆け回るようなことはない。
ユニット規模は小隊だが、戦術単位は大隊となり、大隊単位で士気値が設定されている。損害で士気値は減って行き、最終的には崩壊して敗走することになる。
TEAM YANKEE
同名の近未来戦争小説をFirst Battleのシステムでゲーム化したもの。当時小説にはまってしまい、いろいろ探して手に入れたが、手に入れてしまうとプレイする気がなくなった(笑)。
THE SAND OF WAR EXPANTION
THE SAND OF WARが好評だったらしく、作成された拡張キット。新たな種類のユニットとシナリオが追加された。
ユニットは標準で師団単位。独立高射砲大隊や対戦車大隊等が登場する。ユニットの種類は多く、それぞれに特別ルールが用意されている。ユニット数は多いが、基本的には単純な戦闘システムであるためプレイは不可能ではない。ただ、ルールがゆるいためヒストリカルな展開にはなりにくい。
実はGDWはこのシリーズを作るために作られた会社だったはず。以下のタイトルはすべてHJが日本語化したもの。
THE FALL OF FRANCE
1940年のドイツ軍の対フランス戦を扱う。
THEIR FINEST HOUR
ドイツ空軍対イギリス空軍の戦いを再現する。陸上ユニットや海上ユニットも豊富で、強力なドイツ空軍をうまく運用すれば、アシカ作戦を実施することも可能である。
CASE WHITE
ドイツ軍のポーランド侵攻作戦を扱うが、残念ながら未取得。
倒産したSPIの残党がAHの支援で作った会社。結局これも倒産した。
ソロプレイでガダルカナル島付近の空母戦をアメリカ軍を指揮して闘う。日本軍はさいころで決められた反応をするが、それはそれでなかなかに手ごわい。珊瑚海海戦をやったときは、発見した祥鳳に全力攻撃を指向してしまった。第一次攻撃隊は祥鳳を撃沈するが、その間に五航戦を発見してしまう。あわてて第二次攻撃隊の進路を変えさせたが時既に遅し。日本軍の攻撃でアメリカ軍の空母は二隻とも大破。第二次攻撃隊は進路を変更したため、目標への到達に失敗してしまうという踏んだり蹴ったりの結果になってしまった。結構辛い。
ソロプレイでガダルカナル島沖の夜戦を闘う。プレイヤーはアメリカ軍で、日本軍はさいころで方針を決めて行動する。
イライラ戦争などペルシャ湾岸の戦争を扱う。
マーケットガーデン作戦を扱う。
アメリカ南北戦争を扱う。指揮官ユニットが多数含まれており、昇進することもある。昇進することで優秀になるだけでなく、ぼんくらになる事もあるのが面白い。
ナポレオンのドナウキャンペーンを扱う。