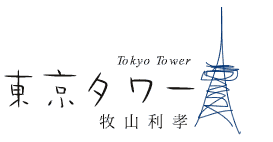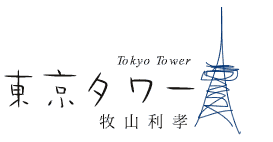東京を舞台にした男と女の短い物語。
「それはないです。彼の美意識としてそれは絶
対にありません。断言できます」
テレビを点けたらエッセイストの安藤和子さんがTVレポーターに囲まれ
ていた。どうやら夫である俳優・奥田洋二氏が浮気したらしい。相変わらず
の色男ぶりである。やれやれ夫の尻拭いというわけだ。泣き出すかな、とワ
クワク期待してしまったが、ところがどっこい、安藤さんたら全然元気。む
しろ自慢気ですらある。よしよし面白いぞ…。
(世間様、お騒がせして申し訳ございません。ほんと困った坊やなの、きつ
くお仕置きしておきますから。でもね、悪い子に見えるけど、本当はとって
もいい子なの。あんな風貌だからみんなに誤解されるけど、きのうだって、
おとといだって、二十年前だって、私の隣でスヤスヤ夢見てた可愛い男なの。
ゴメンナサイ。もういいでしょう。分かってくれなくて結構。分かってほし
くないわ)と考えたかどうかは知らないが、まあ遠からずだろう。
「しかし相手の女性は、大麻を吸わされてレイプされたと週刊誌に暴露し
たわけでしょう?」
レポーターの一人が語気を強める。
「ええ、ですから大麻とかレイプとかは絶対にありません。この件について
は主人と直接話し合いました。正直言って本当に迷惑しています」
「相手の女性はまだ十八歳ですよね?」
「奥田さんの絵のモデルでしょ?ヌードですよね?」
「彼が描く女の人はほとんどヌードですから…」
苺ジャムがパンの表面からズルッと滑り落ちた。あっ、と声を出したらく
わえてたパンを丸ごと床の上に落としてしまった。
「遅れるから先に行くわよ!」
妻は玄関で靴を履いている。
「ちょっと待ってくれよ」
聞こえなかったのだろうか。玄関のドアがバタンと閉まる音がした。ティ
ッシュペーパーを水に濡らして急いで床を拭いた。すぐに後を追ったがエレ
ベーターを一本遅らすと妻の姿はどこにも見えなかった。角を曲がるまで百
メートルはある。走ったのだろうか。
公園通りの朝は気持ちい。若者だらけの渋谷もこの時間はまだ静かだ。

|
ジァンジァンを通り過ぎて右側の小道に入る。HMVと西武百貨店の間を過
ぎると目の前においしそうなパン屋が見える。いつもならここで妻を見送り自
販機で煙草を買って我が家にUターンするのだが、きょうは見送る相手がいな
い。交差点を渡ってハチ公の頭でもなでて来ようかと思ったが流石に馬鹿馬鹿
しいのでやめた。結局、いつものように煙草を買ってそのまま家路についた。
帰りは西武百貨店の正面を通って公園通りを上るというコースをとる。通勤
のサラリーマンやOLたちと並んで歩く格好になるが、鞄も持たずぶらぶらサ
ダル履きで歩いているのは私だけだ。何となく優越感のような劣等感のような
不思議な感覚を私はここ数か月密かにたのしんでいた。
部屋に戻ると大石さんからFAXが届いていた。きのう提出したコピーの赤
字である。確認の電話を入れると「昼ごろ渋谷に寄るので飯でもどう?」と誘
われた。大石さんは広告代理店のADで、私はプロダクションのコピーライタ
ーとして彼の仕事を手伝ってきた。私がプロダクションを辞めてフリーになっ
てからも大石さんは定期的に仕事を回してくれる大切なお客様の一人だった。
コピーの修正は昼前に終わった。早めに出かけて立ち読みでもしようと思っ
ていたところに電話のベルが鳴った。長沢千鶴子だった。
「忙しいの?」
「いや、そうでもないな」
「面倒なこと頼んでゴメンネ」
「大丈夫、バッチリ泣かせてやるよ」
「笑わすんでしょう?」
「笑う人もいれば泣く人もいる、ま、そんな感じかな…」
デザイナーの長沢千鶴子から披露宴の招待状が届いたのは一か月ほど前だった。
快く二つ返事したものの「祝辞」はまだ全然できていなかった。結婚式はあさっ
ての土曜日である。まあ、せっぱつまれば何とかなるだろう。
待ち合わせたパルコの本屋に行くと大石さんは立ち読みに夢中になっていた。
7Fのレストラン街はどこも混み合っていたので北谷公園
の近くまで歩いて小さなそば屋に入った。とりあえず冷たいビールで乾杯した。
特別な意味はない、コンニチワみたいなものだ。
天ぷらそばとビールをご馳走になり、相変わらず世間話ばかりして大石さんと
は別れた。仕事の話をしないのも案外効果的な営業かもしれない。

|
いや、一概には言えないだろう、相手によるとい
うのが正解だ。少しアルコールが入るともうちょっと飲みたくなった。近く
の酒屋で缶ビールを買ってから自宅に戻り、テレビを点けると早速またビー
ルを飲み始めた。
「相手の女性は十八歳ですよね?」
「奥田さんの絵のモデルでしょ?ヌードですよね?」
どこかで見たと思ったら、朝とまったく同じシーンだ
った。
昼下がりのビール。昼下がりのワイドショー。ここ数日平和というか比較
的暇な日が続いている。自由なのか不自由なのか。何だか急に物寂しい気持
ちになった。
テレビを消してごろっとベッドに寝転がった。グラビアのエロ女にでも慰
めてもらおうと思いながら、いつの間にかぐっすりと眠ってしまった。
夢を見た。
私の三輪車が川底でひっくりかえっている。橋のたもとに突き出た大きな
岩の上で幼い私は泣いていた。小さい姉が手を差し伸べたが届かない。大きい
姉は顔面蒼白で母を呼びに走った。私はただただ大声で泣き続けた。
姉たちが悪いのだ。私は怖いと言ったのに、イヤがる私を無理やり三輪車
に乗せたのは姉たちなのだ。私が上手に乗れるところを自慢したかったのか
もしれない。近所の子供たちが見守る中を小さい姉が後ろから勢いよく三輪
車を押して走った。私は引き寄せられるように欄干の無い橋のたもとに向か
って突き進んだ。
「止めて止めて、おねえちゃん、止めて!」私は大声で叫んだのだ。嘘じゃ
ない、確かにそう叫んだのだ。しかし姉はスピードを緩めなかった。
青色の三輪車は崖を転がりながら川底へ落ちていった。私は突き出た岩の
上にストンと落ちて、お陰で奇跡的にかすり傷だけで助かった。私はいつま
でも泣いていた。電話のベルが私の泣き声を掻き消したところで目が覚めた。
急いで机の上にある受話器を取ろうとしたとき、鳴っていたのがケータイ
であることに気付いた。慌ててボタンを押すと若い女の声が飛び出した。
「もしもし、マーキーさんですか?」
誰だろう?寝ぼけていたせいかすぐに思い出せなかった。

|
「椎名です、椎名良枝ちゃんです。忘れた?」
「うわー、良枝ちゃんだあ」
驚いた。「アメリカ西海岸に行ってきます」というメールを最後に音信が
プッツンしていたのだ。何か月ぶりだろう。もう会えないと思っていた。ア
メリカ旅行は恋人に会うためだと勝手に思い込んでいたのだ。いや、恐らく
それは事実だろう。
「いまどこなの?」
「東武ホテルのすぐ近く。ねえ、ドライブしない?」
「ドライブ?」
お気に入りの青いシャツに着替えて急いで家を飛び出した。横断歩道の手
前に来たとき短いクラクションが鳴った。真新しいフレンチブルーのミニク
ーパー。フロントグラスの向こうに良枝の懐かしい笑顔が見えた。
「凄いなあ、買ったのかい?」
「えへへ、お兄ちゃんがね。ちょっと拝借してきたの」
センターメーターにバケットシート。ミニ好きにはたまらない内装だ。カ
ナリア色の丈の短いワンピースにおもちゃみたいな大きなベルト。素足に白いス
ニーカー。スポーティーというかサイケというかちょっとSFっぽい良枝のフ
ァッションにもドキドキした。バーバレラみたいだね、と言おうとしたが長
い解説になりそうなので引っ込めた。
「ドライブって、どこに行くつもりだい?」
「あなたの好きなところでいいわ」
「分からないよ」
「じゃあ私の好きなところでいい?」
最初からそう決めていたのかもしれない。ニンマリとした表情で良枝はゆ
っくりとアクセルを踏み込んだ。オルガンのような心地よい排気音が響いた。
「不思議だなあ」
「何が?」
「キミとこうしてドライブしていることさ」
「不思議?」
「ああ、とても不思議だ‥‥」
不思議な出会いだった。いや、不思議な出会いを求めていたのかもしれな
い。初めて良枝に会ったとき私は少し酔っていた。その日私は
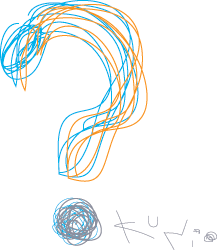
|
代理店の営業マンと一緒にいわゆる接待の酒に付
き合っていた。時計を見ると十時を少し回っていた。場所を変えてもう一軒と
いう話になったが、ツマラナイ酒にうんざりしていた私は上手にその場を逃げ
出したのだ。
六本木の夜中まで開いている書店の二階で良枝は映画のビデオを探してい
た。白いステンカラーコートにストレートのジーンズ。コートの上からでも彼
女のスタイルが抜群にいいことは一目で判った。
良枝は一本のビデオを手にするとレジに向かって歩き出した。
『女と男のいる舗道』
私の大好きな映画だった。娼婦を演じるモノクロームのアンナ・カリーナが
可憐で悲しくて美しい。
良枝は店を出た。私は駆け寄った。
「あのう…」
何度思い出しても顔から火が出るワンシーンだ。もしもその時、良枝が冷た
く無視していたら私は三日間は寝込んだだろう。
「あのう、ゴダール好きなんですか?」
しかし良枝は微笑んでくれた。あっけに取られてクスクス笑い出したのかも
しれない。どちらでもいい。私には天使の微笑みだった。
青山通りの交差点を右折してクルマは骨董通りへ入った。一体どこへ行くつ
もりだろう。六本木にでも行くのだろうか。そこでクルマからポイと放り出さ
れてサヨナラバイバイ。ジャンポール・ベルモンドなら背中から撃たれてカッ
コよく死ぬところだろう。私はどうする? 泣きながら必死にクルマを追いか
けるのか。
「誘拐されちゃうのかな?」
ワザと馬鹿馬鹿しいジョークを言ってみた。
良枝はクスクス笑い出した。
「気付かれたか。じゃあここから先は目をつぶっててもらおう」
どこかで聞いたようなアニメキャラクターの声色で良枝は応えた。
とてもいいジョークだ。抱き締めたくなった。美人が三枚目を演じるとどう
してこうエロチックなんだろう。
「ねえ、ほんとに目をつぶっててくれる?」
「えっ」

|
どうやらジョークではないらしい。一体何を企ん
でいるのだろう。でも何だかゾクゾクした。誘拐犯に言われるまま私は大人し
く目を閉じた。
「いいって言うまで開けちゃダメよ」
「眠っちゃいそうだな」
ステレオからストーンズの曲が流れてきた。何度聴いてもシビれるイントロだ。
私の好きなモノが何であるか、良枝はまるでその全てを知っているかのようだ。
あの夜、書店を出てからどこをどう歩いたのかはよく覚えていない。ドキドキ
していたのだ。気が付くと私たちは一軒のバーで飲んでいた。しきりに映画の
話をしたことは覚えている。良枝が注文したカクテルのブルーがとても綺麗だ
ったことも。きっとストーンズの話もしたのだろう。マニアックな映画論に始
まり、哲学というか文学というか負け惜しみたっぷりの女性論を堂々巡りし、
しまいには両親や親戚一同の昔話に辿り着く。酔うといつもそうらしい。私に
は見えないが妻の耳にはダイヤモンドより硬いタコが出来てるそうだ。夜中に
目を覚ますと知らない部屋だった。良枝は隣でスヤスヤと眠っていた。
「いいわよ目を開けて」
クルマがゆっくり止まった。
目の前に遊園地の入り口みたいな看板が見える。
どこの遊園地だろう? 視線を上げると東京タワーの足元に西日が眩しく反
射していた。
「私がね、東京で一番好きなところ」
良枝は踊るように入場券売り場へ走った。さっきまで誘拐犯だったのに急に子
供になったようでおかしかった。
何年ぶりだろう。そびえ立つ東京タワーを私はまじまじと見上げた。まるで
大きく脚を広げて立つ女のアソコを真下から覗いているみたいだ。
展望室からの眺めは流石に素晴らしかった。海が見える。飛行場が見える。
新宿の高層ビル、その向こうには池袋のサンシャインシティが見える。パノラ
マの展望室を私と良枝は肩を並べてゆっくりと歩いた。
「渋谷はあっちかしら」
「うん、あれがマークシティであの黄色い看板はタワーレコードかな」

|
「あなたの家は見える?」
「小さいマンションだからな。でもタワーレコードの向こうだから大体あの辺
だね」
ゴツンと物がぶつかる音がした。子供の泣き声。振り向くと三歳くらいの男
の子が床の上に転んでいた。良枝が駆け寄ろうとした時、母親らしき女が飛ん
で来て男の子を抱き上げた。
「コウちゃん、だから走っちゃダメって言ったでしょう。言うこと聞かない
とママ怒るわよ!」
もう怒ってるじゃないか。手を放すからいけないんだ。スカートをめくって
母親のお尻をひっ叩きたくなった。
「可愛いわね」
泣いてる男の子を見て良枝が囁くように言った。
「可愛いじゃなくて可哀相だよ、みんなの前で叱られてさ。ちゃんと手を繋
がないから悪いんだ」思わず声が大きくなった。
良枝の手がやさしく私の手を握った。
「ねえ、あそこのベンチに座りましょう」
夕日が眩しい。そろそろ日が沈む時間だ。そしてもうすぐ夏が終わる。
ベンチに腰掛けて良枝はぼんやり夕暮れの東京を眺めていた。何を考えてい
るのだろう。アメリカ旅行は楽しかったかい? 恋人には会えたのかい?
どうして今頃になって電話なんかしてきたんだい?どうして…。
聞けばいいことだった。でも聞くのが怖かった。どうせこれ以上近付けない
関係なら、せめてこのままの距離を楽しんでいたかった。あの夜、良枝の寝顔
を見ながら私は再び眠った。目覚めると良枝の姿はなかった。「昨夜はとても
楽しかったです。また会えたらうれしいな」というメモがテーブルの上に置か
れていた。また会えたらうれしいと言われても住所も電話番号も知らないのだ。
連絡のしようがなかった。数週間後、良枝から年賀メールが届いたときは思わ
ず飛び上がった。名刺を渡したことはすっかり忘れていたのだ。文面はごくご
く普通の律義な年賀状だったが、それが反って私の心を熱くした。

|
さっそく返事を送った。アイラブユーと書きた
かったが、結局、あけましておめでとうと書いてしまった。返事はなかった。
またメールを送った。「会いたい」と今度はストレートに誘ってみた。やは
り返事は来なかった。
惨めな気持ちになった。あの時、寝ている良枝を起こして抱き締めていれ
ばよかった。少し手を伸ばせば良枝のオッパイにだってアソコにだって触れ
たのだ。本当はそうしたかったのに、どうして我慢したのだろう。
二か月が過ぎた。良枝から突然メールが届いた。マスコミに就職が内定し
ていたがドタキャンされて大慌てだったこと。教授の紹介でなんとかコンピ
ュータ会社に就職が決まったこと。そして最後にこう記されていた。
「月末からアメリカ西海岸に行ってきます。帰ってきたら会いたいな」と。
「ねえ、百円玉持ってる?」
少し鼻に掛かったような甘い声で良枝が言った。
「缶コーヒーかい?」
「ううん、あれ見るの」
Gパンのポケットから百円玉を取り出して渡すと良枝は少女のように微笑
んで窓際に駆け寄った。
「子供みたいだな」
「子供だもん」
良枝は大きな望遠鏡をあっちこっち動かした。
「もう薄暗いからよく見えないだろう?」
聞こえなかったようだ。
良枝は夢中になって望遠鏡を覗いている。何を探しているのだろう。私ね、
結婚願望がすごく強いの。好きな人がいたけどアメリカに行っちゃった。ブ
ルーのカクテルを飲みながら良枝が囁いた声が聞こえる。結婚しようって彼
は言わなかったのかい? だって奥さんがいるんだもん。手にしてたグラス
を危うく落としそうになった。ねえ、あなただったらどうする? 完璧な言
葉を見つけようとしたら頭がグルグル回って酔い潰れてしまったのだ。望遠
鏡が一点をじっと見つめている。何を見ているのだろう。横顔がとても綺麗
だ。カナリア色のワンピースからすらりと長い脚が伸びている。大きく広げ
てくれたらもっと素敵だ。東京タワーのように。
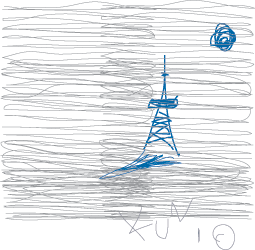
|
ページの先頭へ
© share a gift allrightsre reserved
|