
O kosmoV skhnh, o bioV parodoV
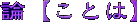
[Kritiken der Geheim-Bande]
カエサルの世は夢
神の世こそまこと
引用の域を超えるのは当然かも知れません。ポォ氏が影も形もなかった頃、既に我が朝に舶載され来たった漢籍には「胡蝶の夢」が記されていました(荘子斉物論篇)。
そして当然のように、両者の物言いは含むところが違います。荘子の場合、徹底的な相対主義、即ち固定的価値観からの自由を意識していました。一方、西洋人であるポォ氏の言は、冒頭に掲げたような意識が強いように思われます。成程西洋の知識人も、時に異教的な発想・発言をされる事があります。加との反動的な見方では、これは一種のオリエンタリズム、流行であるように見えてなりません。
最近の例:米国でベストセラーとなった「インディアンの教え」等。
闇―――私事になりますが、闇は光の欠如ではないと実感した事があります。昼間通った山道への入り口を、夜にひょいと覗き込んだら……。「あれ」は質量のある物質です、誰がなんと言おうとも。
|
磐さえとうに朽ち果てようとは・・・・・
紙と木で文明を作ってきた者の裔としては、こちらの方が染み入ります。石造りの文明は、自らの後の姿として「廃墟」を思い浮かべることができます。下手をすると「いかに堂々とした廃墟にするか」という都市造りさえ可能です。ところが紙と木の国では、死んだ都市は残りません。直ちに時間と土の下に埋もれ、諸行無常の微塵(パラマーヌ)に還元されてしまいます。廃墟は残らないのです。
我が国で「見る事のできる」廃墟はどのように古いものであろうとも実は生きている遺跡なのです。ただ様式として、死んでしまったような顔をしているだけなのです。本当に死んでいる遺跡、即ち廃墟であれば、直ちに発掘を待つ存在となり、人の目に触れる地上からは姿を消してしまうでしょう。
日本には遺跡はあっても廃墟は存在し得ないのでしょう。だからこそ、出来立ての廃墟である廃屋や廃村が、その歴史的価値の低さにも拘わらず、日本人にとって独特の感情を惹き起こすのかも知れません。
(日本の遺跡は生きているという事を端的に表すのが、伊勢神宮の式年遷宮だと思います。神宮は文献時代以降の建造物とは言え、遺跡たり得る古さです。その遺跡が廃墟とならず、遺跡として存在するには二十年ごとに生まれ変わる必要があるということです。新陳代謝する遺跡!)
石造りの遺跡は人間の存在と切り離されても、つまり廃墟となってなお、自律的に長期間存在できます。過去と栄光を蔵し続けながら。堂々としかし「ただ」そこに聳立し、目に見えぬ程ゆっくりと朽ちて行く堅固なる「存在」。エントロピー増大の法則に身を委ねながら、時間(カーラ)を容易には寄せ付けぬ不動の廃墟。彼我の遺跡の有り様の、いかに異なる事か。その「堅固」であり「不動」である廃墟にして、シェリー氏を慨嘆せしむるとは! 己の滅びた後にも自らの文明を証言すべく叡智と感性を傾けた存在。よもや朽ち果てようとは……!(加ともなんかトリップ気味です。)
神聖不可侵なる大宮(ファラオ)が見せ物になっている現状を見るに付け、私共は滅んではいけないという感を強くします。
|
人類が破滅しそうにないなら、19歳の健康な男子はポルノ嫌いではない。
(至言の対偶。意味は論理学的に同じ(同値)です。)
唾棄すべき前近代性、アニミズムの立場から一言。「かつて女は太陽だった」。女性の地位の転落は、生殖行為と性交渉の分離が致命的契機であるというのが私の信念です。従って、この至言には半分しか産道もとい賛同できません。複雑に絡み合った諸原因をばっさり捨てて、割り切った相関関係を見るならば、ポルノが広く出回っている先進国の方が、そうでない地域よりも出生率が低いのです。つまり、19歳の健康な男子がポルノ好きであっても、人類は漸減消滅しそうです。
逆方向から言えば、事務的義務的な生殖も可能だと言うことです(儒教の「孝」もこれに近い)。そういう生殖ばかりでも、種としての人類は破滅を免れます。それでも文明や文化を含んだ「人類という概念」は破滅するかも知れません。
でもね、悲しいけど、奴隷「牧場」も人類の文明なのよね。
|
一体紳士たる者に体を引き締める紳と
心を引き締める礼楽以外必要な物が在るかね
漢字もよく出来ていますが、訳語もよく出来ています。「ジェントルマン」を「紳士」と訳した幕末明治の日本人に乾杯。
紳士という熟語をちょっと考えてみましょう。
紳士の紳は、背筋を伸ばす糸(飾り帯)です。これは朝廷に参内する文武百官を象徴します。紳士の士は、士大夫などと言う熟語があるので官僚のことと思いがちですが、実は「さむらい」という訓読みの方が本来の意味に近いのです。一族血族の内、戦闘に従事しうる成人男子(壮丁)が士です。そして各家庭の夫である士を指揮する隊長が大夫という訳です。
士大夫がいかにも文民官僚のように思われるのは、中国に伝統的な文重武蔑の傾向によります。しかし源を辿れば世界にあまねく共通する「エリート=戦闘集団」の一形態であった訳です。源というと日本では戦闘集団の頭という図らざる掛詞。
緊張と余裕を合わせて示す名探偵の言葉に比べ、加とによるもじりは引き締めてばかりです。いや〜ん。抑圧と専制政治の国の人?(季語はメーデー)あるいは加とは、中国には人権意識がないという主張をしたいのでしょうか? そうではありません。
常に騎士的な雰囲気を忘れず、それを良しとするジェントルマンと、馬上で天下を取りながら、常に文弱に流れるように圧力のかかっている士大夫の違いでしょう。
文字好きの私にとって、言葉を絡めた文化論というのは、幾らでも出任せが言えて楽しいものです(泣笑)。
|
軍艦を神社に見立てる御意見には、快い衝撃を味わいました。昔から漁船には帆柱の元に神仏を安置していたという話を聞いた事があります。それからしても極めて説得力を感じます。信仰とも言える思いが船に込められているならば、艦船はただ合理的合目的に造られれば事足りるものではないと理解できるでしょう。この事は最も合理性・合目的性が求められる軍艦に於いて顕著に現れます。即ち全てを戦勝目的に向けなければならない建艦に於いて、なお譲れないものが顕わになり、形となって現れるのです。
また日本人の船に対する感覚がよく出ているのが、船に「……丸」という名を付けることでしょう(また始まったぞっ)。男女に関わらず、子供を呼ぶ時の名で船を呼ぶのです。これは現代日本人がパソコンに「ラムちゃん」とか名前を付けるのとは、だいぶ、いやちょっと違います(すいません、古くて)。
日本では古来、神様を老人か子供の姿で表してきました。エデンの園よろしく知恵を表す老人と、生命力を表す子供です。生命力を漢字を借りて「気」と称します。また日本人は穢れを嫌います。穢れは気枯れです。生命力の衰えたものは縁起が悪いのです(おおっ、神仏習合)。板子一枚下は地獄などと言われる職場である漁船の上。その船が縁起が悪いのでは堪りません。名前だけでも景気良く、ついでに神様の御加護をという心でしょう。大体金比羅さんに見られるように、海の男は縁起を担ぐ人が多いですから。以上から船に名前を付けるというのは、極めて宗教的神道的、そして日本的な儀式であると言えそうです。
(西洋魔術師にして英語教師である長尾豊(ながお・ゆたか)氏によると、「古代においては、名前こそ魔術の神髄と考えられたことも多」いそうです。洋の東西を問わず、と言ったところですか。日本は古代の尻尾が生きているわけですね。恥ずかしいと思うか誇りに思うかは、人それぞれです。)
|
Licht, mehr Licht !
―――Johan Wolfgang von Goethe
ギョオテとは、俺のことかとゲーテ言い。「オー・ウムラオト」等という、得体の知れない発音に苦しんだ明治の人の川柳です。いや発音よりも、むしろその表記に苦しんだのですね。世は疾風怒濤の言文一致。新しい文体を作り上げる、シュトルム・ウント・ドラングの時代だったのです。
大体欧米語の「オー」は口をすぼめて発音するのですが、このとき無理矢理「エー」と言うと、きれいなオーウムラオトの発音になります。しかしゲーテはフランクフルト方言を話していました。日本人風に「ゲーテ」と発音したほうが、ゲーテ自身の発音に近いのです。ですから表記も「ゲーテ」で問題ありません。
さて独文学の一大特徴というと、「発展小説」という事になるようです。ゲーテもまた「ヴィルヘルム・マイスター」という、発展小説の金字塔を打ち立てています。視点を徹底的に内面に向け、からくり時計全体がゆっくりと回るようにぎしぎしと、主人公の内面を展開させて行くのです、徹底的に。自己満足と紙一重。客商売としては失格です。
内面をしつこく見つめるドイツの文学者が、いまわの際に「外」の光を求めたのは、なかなか考えさせられます。仏教徒なら「業が深い」と言うでしょう。神と人との個人的な対面を徹底(!)させたプロテスタントのお国柄です。末期の時こそ自分の中に「神の光」を見つけてもいいと思うのですが。ドイツに付き物のユダヤ。その神秘思想に「ツィムツム」という概念があります。これもまた神が「内部へ」縮退していくというものです。それでもやっぱり結局は、「外部に」救済(すくい)を求めてしまうのでしょうねぇ、人間は。
「ただ単に、死にかけて目が弱くなっただけですよ」
口を滑らせてしまった巨人に敬意を表して、冒頭の文を格調高く飾ってみましょう。何しろヒットラーがラテン文字を広めるまでは、ドイツ文字といえばアレですから。
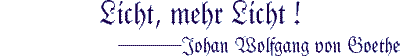
参考文献:藤田五郎「ドイツ語の新しい学び方」講談社現代新書
|
忙しいとは心が亡ぶと書く。
言葉の話にはウズウズが止められません。
確かにギリシャ語の scolh スコレーは、scholar や school の語源です。学校に行けるのも、暇なればこそですね。
しかし citizen の語源は、ラテン語 civitasであってスコレーではありません。ついでながら古代ローマの初級学校は、ludusと呼ばれていました。これは「遊び・催し物」といった意味です。有名な「パンとサーカス」のサーカスに当たりますか。いずれにせよ、暇や遊びの中から学問が生まれてくる訳ですね。
暇人と言えば、ディレッタントという言葉があります。趣味人とか好事家とかの訳もあります。元々イタリア語らしいので、こりゃまた結構。古語即ちラテン語に遡ってみましょう。
ディレッタントはイタリア語の diligareディリガーレから作られた言葉だそうです。更に diligare の元になるラテン語は diligoで、これは高く評価する、強く好む、の意味があります。なるほど好事家という訳は的を射ています。
更に一歩進んで diligo自体を分析してみましょう。これは分離を表す前綴りdis-と、集めるという動詞 ligoの合成語との事。つまりバラバラに散っている物を集める、元の場所から引き離してでも集める、という心でしょう。好事家の原初の姿はパワフルな蒐集家だったのです。そしてパワフルに知恵を集め真理を求める者こそ、ギリシャ以来の哲人即ち filosofoV フィロソフォスと呼ばれるのです。
で、学問があるもあらぬもキーウィタース。遊びをせんとやローマ人。続いて市民についてです。
civitasを更に遡ると、印欧祖語として「kei-」という音が想定されます。この学問的に再構成された意味断片は、ゲルマン神話に出てくる地名、「なんとかハイム・〜heim」にも受け継がれています。また英語の homeとも関係があります。そこで無理矢理繋げれば、ラテン語では「家庭的な人」が市民と言うことになりますか。家庭的な人をギリシャ語訳して oikonomikon zwonオイコノミコン・ゾーオン。英語に重訳すると、economic animalになってしまいます。高度成長時代のモーレツ社員は、最も「市民らしい」存在だったのね。心が亡ぶなあ(笑)。
不眠不休で立ち回り、家庭的な事(res privata, res familiaris )から大帝国即ち公の事(res publica = 英語のrepublic )を築くに至ったローマ「市民」こそ、朱子学の優等生でありましょう。まさに修身斉家治国平天下です。
言葉とは面白く、ついつい長くなってしまいます。
|
E pur si muove
あうっ。いつぞやのお手紙では仮名書きだったものが、こちらでは原語表示。やっほう。早速辞書にあたります。とは言えガリレオは自分の著作も当時の日常語で書いたくらいですから、ラテン語でもギリシャ語でもないでしょう。多分中世イタリア語です。何方言かと聞かれると答えに窮しますが。それより中世語なんてどうやって調べるのか知らん。
とか思っていたら現代イタリア語の辞書に書いてありました。さすがガリレオ偉大なるかなタロットカード二十二枚。
E pur si muove. エプール・シムォーベ。
再帰動詞とか代名動詞とか言うヤツですね。あるいは一般的事実を表す非人称文でしょうか。趣味に走って逐語解説をしてみます。
E は「そして」の意味。羅語でも仏語でも etと言います。続いて pur。これは英語のピュアと同じです。副詞的に使われて「ピュアに」とか「問答無用に」の意味。本来なら綴りも英語と同じに pureなのですが、発音上の習慣(規則ではない)、末母音脱落(トロンカメント)によって、purとなっています。辞書にはこの二単語が融合した形、eppurとして載っていました。
続いては代名詞の目的語+動詞の三人称単数現在形。「(彼は・彼女は・それは)自身を動かす」すなわち「それは動いている」と訳せます。構文としては、以前メールに書きました独語と同じです。
mir schwindelt. (それが)私にめまいさせる=私は目眩がする。
「それ」は英語で言う仮主語になります。あるいは何らかの見えざる御手を指すのか知らん。ともかくこれらの呟きでは、動作主は目的語で示されています。従って、ガリレオの言葉では、眩暈または混乱を起こしているのは老科学者自身ではなく、判事や世間(双方単数)と言うことになります。英語の moves にあたる muoveをより生かすなら、
「へへっ。……ど、動揺してやがるぜ、この審問官(モビルスーツ)」となりますか。
|
時に沈む人類の宝は、伝承なくば無
「帝都」という言葉は私の胸を締め付けます。その少なくない部分が「郷愁」によっているところを見ると、やはり反動的な加とは帝国(正確には皇国か)の住人なのでしょう。今や生きた言葉としての帝都は、東京の地下鉄会社に残るくらいです(帝都高速度交通営団)。あるいはテレビゲーム「サクラ大戦」でしょうか。
ガラスとコンクリートで世界中ひとしなみになってしまった都市は、どれほどのメガロポリスでも帝都と呼ぶには違和感があります。重厚さ、せめて落ち着きとそして「品格」がなければなりません。品格こそまさに「一日にして成らず」と言うべきものです。
いかな品格ある帝都と言えど、大きな都市にはスラムが付き物です。ピリッと締まる中心があれば、スラムですら帝都の品格を構成する部分になり得るのです。「歴」の方では皇帝の存在を重視されていましたが、それが「ピリッと締まる中心」なのかも知れません。なにしろ「只事ではない格式」なのですから。
その皇帝について寄り道してみます。皇帝が只事でない格式を持つ事は、イギリス女王だけでなく、ツァーリ(ロシア皇帝)の地位も雄弁に物語っています。奴隷(スレイブ)の語源となったスラブの田舎貴族であるモスクワ大公は、いかに羽振りがよくても自力で皇帝にはなれなかったのです。ビザンツ皇帝の姪を后とし、モンゴルのカーン位を襲って初めて皇帝を名乗ることができました。この点で、ツァーリはヴィクトリア女王と同様、西洋の最高の格式と東洋の空前の栄光を合わせ受け継いでいると言えます。ではその格式を革命とともに滅ぼした民衆とは、一体何者でしょうか。
(まあ露帝室の滅亡は身から出た錆に思えますが。あとには民衆のロマンとして「アナスタシア伝説」が残るばかりです。)
そしてフランク王家の執事、ピピン・ザ・サードを使嗾して(しそうして。けしかけて)王位を簒奪させ、その子カールを不意打ち的に皇帝に叙任したローマ法王とは一体何者なのでしょうか。
(最近ローマ法皇という表記を多く見かけます。ワープロが普及している以上、無理して法皇という変換をしているのでしょう。そんなに皇の字が使いたければ「教皇」で押し通せばいいのです。単なる誤字の裏に見え隠れする、奇麗事を言う人達のコチコチの権威主義がとても嫌です。加とみたく、「人でなしの反動です」と白状しちゃえばいいのに。)
更にはロシア帝国に対する防波堤とする為、中国皇帝の官僚であった李氏朝鮮の国王を大韓帝国皇帝に封じ、政情我に不利と見るや再び昌徳宮李王に冊立した天皇とは一体何者なのでしょうか。
(満州国皇帝も天皇による冊封と言えなくもありません。関東軍によるものとすると、それこそ軍隊の歓呼によって即位するローマ皇帝にさも似たり。)
そして、その天皇の地位を決定的に握っている「主権の存する国民の総意」とは、一体何物なのでしょうか。地縁や血縁が比較的薄い───陋習に縛られた共同体の成員ではない───自立した市民、主権を持つにふさわしい近代的国民が集まって何らかの意思が形作られている大都会に、さしたる品格が感じられないのは何故なのでしょうか。感情的になると、一つの文が長くなるのは何故なのでしょうか。
|



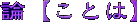
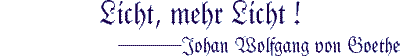
![]()

