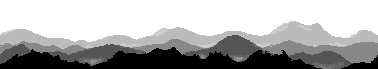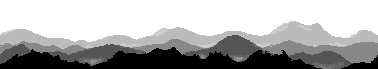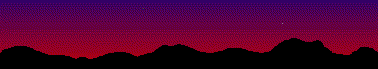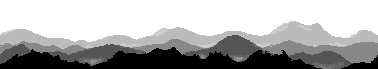
奥多摩物語/五十川晋一のサイトへようこそ!!
携帯版
-目次-
●滋味深き弦の響き
●山岳紀行音楽
●作者のことば
●多摩川とその水源
●CDのご案内
●制作過程ご紹介
●プロフィール
●エッセイ
●ご質問
●奥多摩物語 ー滋味深き弦の響きー
古代人が弓に弦(つる)を張り、弾(はじ)いたときから、おそらく人は心の琴線をゆさぶられ続けてきたのであろう。こうして始まった弦の響きへの探究は、地球のいたる所でいろいろな種類の弦楽器を生み、今日のバイオリンやギターのようにひとつの完成された楽器に成熟した。奥多摩物語はギター、マンドリン、ダルシマ等の多彩な弦楽器によるアンサンブルである。しかし、それだけではない。随所で聞き覚えのない、不思議で、そして心地よい響きに遭遇する。初めて耳にした人は、いったいこれはなんの楽器なのか?どうやって弾いているのだろうか?と思われるに違いない。 奥多摩物語の作者によれば、既存の弦楽器の響きだけではもの足りず、ある時は異種楽器を重ね、ある時は不要な響きをそぎ落とし、またある時は微細な響きを増幅するとのこと。こうした特殊な制作方法ゆえ、生演奏が不可能となり、作者は多重録音という道を選ばざるを得なかったという。多重録音はともすると空気がかよわない、却って不自然な響きに陥りやすい。しかし彼の生み出す弦の響きは、まさに琴線に触れるという言葉を実感させてくれる。そして弦楽器の経験がある方ならば、その滋味を味わうことができるに違いない。/レコーディングエンジニア:毛呂 彰
目次へ戻る
●奥多摩物語 ー山岳紀行音楽ー
日本という島国のほぼ中央に位置する秩父山地。その中の笠取山とそこを水源とする多摩川。奥多摩物語は、その流域の自然・歴史・伝説・事件等を題材にした山岳紀行音楽という。今までに山行の途中で、ファインダーを覗く写真家やスケッチブックに向かっている画家に出会う事はありましたが、奥多摩物語の作者のように山の印象を音楽で記すというのは初めてでした。 写真家なり、画家の場合は、いずれも出会ったその場でその作品の完成した姿が想像できます。しかし、奥多摩物語の作者の存在を知ったのは、笠取小屋に置かれてあったダイレクトメールだったこともあって、音楽といってもなかなかピンと来ませんでした。 ところが後日、ダイレクトメールを頼りに注文して届けられたCDを聴くと、不思議な事に山行の思い出が鮮やかに蘇ってきて、まるで絵葉書のようでした。そして作者が心底多摩川を愛していることが判りました。 CDのジャケットには1曲毎に紀行文が寄せられています。それを読むと、人に歴史ありと言うがごとく、山に歴史はあり、川に歴史はあり、 地球の歴史に連なっているのだと思わずにはいられませんでした。/登山愛好家:今野 博
目次へ戻る
●作者のことば
多摩川の河口近くに生まれ、多摩川の水を飲んで育った私にとって、その水源である奥多摩・奥秩父は母なる山々である。漠然と上流を目指して山歩きを始めたのは、私が高校を卒業した頃のことである。そしてはっきりと水源というものを意識して、更に上流を目指すようになったのが1980年頃。現在では年に数回は水源を歩いている。今まで山々を歩いていて出会った自然や人々は、私にとってはかりしれない心の糧を与えてくれた。そしてその人々から聞いたり自分で見聞きした、自然・歴史・伝説・事件等“古代から堆積してきた自然と人間の営みの痕跡”を音楽でしるすことができればと思う様になった。 「山岳写真」という呼び方はあるが、「山岳紀行音楽」という呼び方はあるだろうか? 山歩きをしていて顔なじみになった地元の人から、時々「うちで煮たんだけど、食べていかんかあ?」と山菜の煮物等を勧められることがある。その味付けは、その家で遥か昔から続いてきたであろうことを思うと、口に合う、合わないということを超越して胸に迫るものがある。自分の創る音楽もそういうふうであったらと願っている。 絵画や多色刷り版画を制作する様に音楽を制作したい。それも私の好きなアコースティック弦楽器で。これが私の永年の目標でした。1982年にマルチトラックレコーダーを手にして以来、少しずつ歩を進めてきました。まったくの自分好みに味付けした手料理のごとき代物ですが、皆様のお耳に合いますかどうか、まずは御賞味頂きたいと存じます。/五十川晋一
目次へ戻る
●多摩川とその水源
多摩川の最初の一滴は、河口である東京都大田区羽田から遡ること123.5Km、山梨県塩山市字一ノ瀬、笠取山(標高1953m)に発する。流域には、徳川時代に江戸の飲み水を供給した玉川上水の羽村取水堰、梅の郷-青梅、山岳信仰の御岳山、現在の東京の飲料水を支える奥多摩湖、奥秩父縦走の始点-雲取山等がある。奥多摩湖より上流は丹波川、最上流は一ノ瀬川と呼ばれ、渓谷は深く、美しい。水源地域は山梨県内だが水源林は東京都が管理している。戦国武将ー武田信玄にまつわる伝説も多い。
目次へ戻る
●CDのご案内
-小目次-
★「痕」
★「露頓木」
★「跡」
★「六人衆の伝説」
★「痕」:
マンドリン、バンジョー等のブルーグラス系の楽器を駆使し、弦楽器アンサンブルの新しい形を確立した作品集。民族楽器固有の音色の芳醇さを損なう事なく、生演奏では表現出来ない独特の響きを追い求めたアコースティック音楽の傑作。山を旅する喜び、寂しさ、至福感が見事に描かれている。
試聴「千の喙」(MP3 1.1MB)
試聴「緩やかな斜陽」(MP3 944KB)
CDのご注文
小目次へ戻る / 目次へ戻る
★「露頓木」:
多摩川の水源に生きる人間と生き物たちの小さな痕跡を音楽で記したい。ミクロな痕跡が地球の歴史の一ページであることを感じさせるスケールの大きさ。フルオーケストラをも凌ぐ音の厚味、ダイナミックな楽曲から郷愁漂う楽曲まで聴きごたえ十分。
試聴「お爺さんが言っていた」(MP3 1.0MB)
試聴「砂の旅」(MP3 1.1MB)
試聴「DODGE」(MP3 1.1MB)
CDのご注文
小目次へ戻る / 目次へ戻る
★「跡」:
マンドリンが軽やかにリズムを刻み、ハンマードダルシマが輝くように降り注ぐ様は新緑の木洩れ陽のよう。シンプルなアンサンブルながら繊細で芳醇な弦の響きを聴かせてくれる。古い写真アルバムを眺めているような懐かしさを覚える作品集。
試聴「唐松尾」(MP3 1.1MB)
試聴「山の息」(MP3 1.1MB)
CDのご注文
小目次へ戻る / 目次へ戻る
★「六人衆の伝説」:
戦国時代、奥秩父・多摩川の水源地域に伝わる金山を探しに集まった六人衆の伝説を題材に、作者が山行の度に感じた落武者への思いを重ねたトータルアルバム。バンジョー、マンドリン、ハンマードダルシマ等によるアコースティックアンサンブルが落武者のシチュエーションをドラマチックに描いてゆく。
試聴「神々の爪跡」(MP3 1.7MB)
試聴「羽の縁」(MP3 972KB)
CDのご注文
小目次へ戻る / 目次へ戻る
●奥多摩物語の制作過程をご紹介します
-小目次-
★アコースティック楽器で多重録音作品を!!
★どんな楽器を使うのか?
★ライブはできるか?
★奥多摩は楽曲の制作にどうかかわるのか?
★アコースティック楽器で多重録音作品を!!:
「多重録音と言うとシンセサイザ−ですか?」と聞かれることが殆どです。 ですが、奥多摩物語ではペダルスティールギターを除き、すべてアコースティック楽器を用いています。 民族楽器も含めたお気に入りの弦楽器を使ったアンサンブルをしたい・・・ これが高校卒業の頃の最初の夢でした。メンバーは集まるか?楽器は集まるか?演奏するにはスコアも書かねば・・・ それはとても困難に思えました。絵画や多色刷り版画を制作するように自分一人の手で気の済むまで作りあげられないものか?。 多重録音を行えば一人でもアンサンブルは可能です。しかしながら当時はマルチトラックレコーダーはプロ用のスタジオにしか無く、アマチュアの道具ではありませんでした。なかば諦めて数年が経過しました。そんな折、奥多摩の山歩きがきっかけで知り合った音楽家から民生用のマルチトラックレコーダーが出ている事を知らされました。これなら自分も実現できるかもしれない・・・ しかし使ってみたい楽器の全てを弾ける様になる自信はないし、ひとつひとつ基礎からやっていては一生かかっても無理か?今、振り返ってみると、構想から実現に辿りつくまでにはおよそ15年の歳月が必要でした。15年はあっと言う間でした。少しずつ楽器を集め、練習しました。しかし、あれも弾きたい、これも使ってみたい。願いは大きくなるばかりですが、やはり限度があります。 基礎練習なるものが嫌いで、弾きたい曲からいきなり始めるというのが自分の流儀でしたので、とにかく楽器が手に入るチャンスがあったら躊躇せず入手し、録音に入るときにその楽曲を仕上げるのに必要最小限な(といっても自分が納得できるまでですが)練習をするといったやり方になりました。どんな楽器も弾きたい旋律や出したい音色がはっきりしていればなんとかなるものです。こうして私にとって楽器は画材と同じようになりました。
小目次へ戻る / 目次へ戻る
★どんな楽器を使うのか?:
基本的にはギター、マンドリンが主体です。それで下地を作り、ダルシマ、筝、バンジョー、フィドル、チェロ等を加えていきます。 最初に楽器(画材)ありきではなく、音色ありきといったところです。 欲しい音色を得る為には同じ楽器や異種楽器をユニゾンで重ねたり、演奏法、録音やミキシングの工夫、例えば、ギターでも、そのなかから特定の響きだけを取り出すためにアタックの部分をカットするようなことも行います。 民族楽器は現代の楽器が洗練(蒸留)の過程で濾し取られてしまった多彩で微妙な音色を多く含んでいます。どうしても現代の楽器で得られない音色は民族楽器を頼りにします。 旋律にはパンパイプやオカリナも使います。中には楽器ではない道具や玩具もあります。
使用楽器:6&12 弦アコースティックギター、5弦バンジョー、マンドリン、ブズーキ、フィドル、チェロ、ハンマードダルシマ、マウンテンダルシマ、ペダルスティールギター、ISO式箏、ピアノ、ISO式アコーディオン、ハーモニカ、オカリナ、パンパイプ、弥生土笛、あんま笛、シンギングボウル、拍子木、キュイー、フーホー、鈴
小目次へ戻る / 目次へ戻る
★ライブはできるか?:
もうお分かりのように、残念ながらCDで聞こえるようなことを演奏会という形で再現するのは不可能なのです。途切れ途切れの演奏を何回も重ねたり繋ぎ合わせたり、音質を調整したりするからです。絵画や多色刷り版画のように音楽を制作したいと言うのはそういうことなのです。ちょうど演劇と映画の関係に似ています。 反面、ライブのような音楽としてのノリ、グルーブ感というのは望むべくもありません。ベストギグ、名演奏という言葉はいつも私の憧れです。
小目次へ戻る / 目次へ戻る
★奥多摩は楽曲の制作にどうかかわるのか?:
最初のスケッチなりモチーフは楽器をただ鳴らしているときにぽつっと出てきます。音色がモチーフになるという例が多いですね。そうなればすぐレコーダーに向かい録音を始めます。楽器を重ねたり、ミキシングをしていく過程で、奥多摩で体験した情景が思い出され、ああしようこうしてみようという次の動機となり、これが繰り返されます。山の情景や思い出に寄り添うような音楽にしていこうと思うわけです。大方まとまってくると、この曲はあの情景にしよう、あの事件にしようと標題が決まってくるわけです。
小目次へ戻る / 目次へ戻る
●五十川 晋一 プロフィール
1956年東京生まれ。音楽家。多摩川の水を飲んで育つ。高校時代にアメリカのフォーク、ブルーグラス、マウンテンミュージックに惹かれ作曲、演奏活動を開始。その後あらゆる音楽ジャンルを通して様々な弦楽器の音色に触れる。1974年以来、民族楽器を含めた弦楽アンサンブルの可能性を追求しながら作編曲、演奏、録音まで一貫作業の作品を制作。多摩川の源流である奥秩父、多摩の山歩きを趣味とし、自らの足で収集した自然、歴史、伝説、事件等を題材にした山岳紀行音楽「奥多摩物語」の制作をライフワークとする。そのかたわら、オリジナル邦楽工房"ほうきぼしに参加、邦楽器のアンサンブルも手掛ける一方、日本人の音色のルーツ探しを始める。 東洋音楽学会、日本音響学会会員

目次へ戻る

音響工房「岳響」
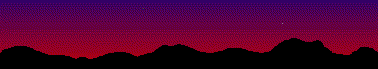 © 2008 ACOUSTIC STUDIO GAKKYO All rights reserved.
携帯版の最後です。
© 2008 ACOUSTIC STUDIO GAKKYO All rights reserved.
携帯版の最後です。