2017.7.29
人物エッセイ その6 Souther Hillman Furay考
John David Souther、1945年11月2日、北米はデトロイト生まれ。
Chris Hillman、1944年12月4日、同ロスアンジェルス生まれ。
Paul Richard Furay、1944年5月9日、同オハイオ州イエロースプリングス生まれ
かつて、Souther Hillman Furay Bandというバンドがあった。
バンド自らが名乗りを上げたというより、アサイラムレーベルを立ち上げたDavid Geffenによって招集されたという説がよく聞かれる。
70年代に入るとロックミュージックは音楽産業、ビジネスと無縁ではなくなり、成功しそうな種を探しては蒔いて水をやり、陽を当て、大輪の華が咲くことを楽しみにする。Geffenはそのひとりであったようである。彼は1969年にCS&Nを世に送り出した人物であり、この3粒の種がそれまで誰も見た事がないとんでもない華を咲かせることをほとんど確信していたようである。SHFバンドは1974年のデビューだが、メンバー夫々は知名度のあるバンドで才能を発揮したり楽曲を提供していた頃であり、Geffen本人だけでなく音楽ファンの間でも期待されていたようである。
SHFバンドはバンド名を冠したファーストアルバム*1と、Trouble in Paradiseなるセカンドアルバムをリリースして解散したのだが、ファーストアルバムは自分の愛聴版のひとつである。
この3人はそれぞれ単独で取り上げてもかなりの頁を費やす人物なのだが、3粒の石を同時に水に投げ込んだときのように、その波紋はおもしろい干渉縞が現れるような気がするので3人同時に考察してみようと思った次第である。3人に共通するキーワードはカントリー・ロックである。
JD・サウザーは5人目のイーグルスと囁かれ、グレン・フライとデュオを組んでいた経歴がある。彼の作品や共作された楽曲がイーグルスのレパートリーに多くあるのだが、恐らく、グレン・フライからもイーグルスでいっしょにやらないか?と勧められたことは想像に難く無い。ただ、サウザー本人名義のソロアルバムを聴いてみるとイーグルスの路線とは違うように思える。
サウザーがやりたかった事、彼のソロ作品から醸し出されるキーワードは、ダンディズム、ニヒリズムと言えようか。それはジャケットのポートレートの表情に色濃く現れているように思う。”Take It Easy”とは正反対の表情である。後年、映画にも出演するほどであるから、ミュージシャンであることより自分の理想とするイメージになり切る俳優の姿を見てしまう。頑にイーグルスとは一線を画すという姿勢を感じてしまうのである。
サウンド面に漂うジャジーなアレンジもそうである。1976年のセカンドアルバム、Black Rose*2の中の1曲、Doors Swing Openはあたかも映画のワンシーンを観ているかのようである。自分の想い描くシーンを忠実に精巧に描こうとするあまり、共鳴できるファンはかなり限られていたのではないだろうか?
1979年の3作目、You're Only Lonely*3はそれまでのイメージとは違ってブラックコーヒーにミルクとシュガーをたっぷり注いだかのように口当たりの優しい作品になったように思う。しかしながらジャケットのポートレートは、午後5時を過ぎて残業に入らんとする憔悴したホワイトカラーの姿である。ネクタイのヨレ具合が絶妙で、”カントリー・ロックの時代は終わったぜ" というセリフが聞こえてきそうである。
クリス・ヒルマンは自分の青写真を持って邁進するというよりは、Byrds、Flying Burrito Brothers、スティブン・スティルスのManassasを経て自身の立ち位置を一歩一歩確かめてきたように見える。
Byrds加入以前はブルーグラスのマンドリン奏者であったが、初めて手にしたエレキベース(Byrds加入時点では日本製だったとのこと)でいろいろ試行錯誤していたようである。1966年の4枚目のアルバム、Younger Than Yesterday*4の中の、So you want to be a Rock 'n' Roll StarやRenaissance Fairでは8ビートのメロディアスなベースラインを披露しており、ちょっと気になったものである。
この時期、ビートルズのPaperback WriterやTax Manもエレキベースが前面に出てくるようになり、Younger Thanをプロデュースしたゲーリー・アッシャーもこれを意識していたのかもしれない。低音を高いレベルで記録出来るようにレコードカッティングマシンが改良されたことによるもので、ポール・マッカートニーやビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンが強く望んでいたらしい。
そのアルバムではカントリーフレーバー溢れる、Time BetweenやThe Girl With No Nameを残しており、ソングライティングの面でも気になる存在であった。
ただ、”自分はこうやりたい” と言うよりは、プロデューサーやディレクターから求められるイメージに応え、あるときは期待を越えるアイデアと演奏を提供できる男、職人肌に見えたものだ。
しかしながら1987年に立ち上げたDesert Rose Bandの頃には自分の航路を確信した船長のような男に見える。Desert Rose BandはカントリーTop40でも破竹の進撃を繰り返していたが、80年代に入った頃からボーカルが一皮むけてボーカリストとしての資質に自ら目覚めたのではないだろうか?エンターテイナーとしての資質と言っても良いかもしれない。
SHFバンドの時代はその過渡期だったのではないだろうか?まだ多少青いというか、迷いがあるような、逆にそんなところがこの時代の魅力である。
2004年、彼が還暦を迎えた年にAmericana Music Associationから授与されたLifetime Achievement=功労賞は彼のそうしたキャリアにとても相応しいと思える。
リッチー・フューレイは一貫してカントリーミュージックの上澄みをすくい取ってポップな音楽を指向してきたように見える。自分が歌って良い気分、聴いている人も良い気分。そんな青写真を持っていたのかもしれない。彼の曲に共鳴するファンも多かったと思われるが、リッチー自身は”共鳴してくれるってどういうことなんだろうか?”と常に疑問符の男だったように見える。
バッファロー・スプリングフィールドを経て1969年にPOCOを立ち上げ、6枚のアルバムを発表したのだが、最後のアルバム、Crazy Eyes*5はリッチー自身の迷いがタイトルにまで現れてしまったのだろうか?バッファロー時代の盟友、スティーブン・スティルスがCS&Nで咲かせた大輪の華はリッチーの眼にはどのように映っていたのだろうか?
1980年代以降は心の拠り所としてクリスチャンとしての道を歩むようになり、牧師の資格を取って暫くは音楽活動から遠ざかっていたと聞く。
そんな迷いの中でPOCOを脱退した次のステップがSHFバンドであった。アルバム、Crazy Eyesの中のインストナンバー、Fools Goldでクリス・ヒルマンがマンドリンで客演していたので、同じカントリー畑の人間と心機一転という気持ちだったのかもしれない。冒頭のFallin' In Loveはリッチーの晴れやかな笑顔を感じるが、4曲目のBelieve Meは雲が早い勢いで次から次へと通り過ぎる、嵐の前触れのような心模様を感じる。この愛聴版の中で自分が一番気に入っている曲なのである。
さて、このような三人が集まるとどんなサウンドが産まれるのか?周囲も期待していたようだが、バンドとしての成果は少なかったように見える。バックはドラムスのジム・ゴードンを除いてManassasのメンバーをそのまま起用しているが、ペダルスティールギターやドブロを駆使するアル・パーキンスが当時のウェストコースト印を支えている。
三人はお互いの曲にボーカルハーモニーを付けているのだが、同時代のイーグルスのようなブレンド味は無い。
音楽の世界に飛び込んでほぼ10年。皆、がむしゃらに走ってきたが30歳前後といえば初めてハイスクールの同窓会に参加してみようか?そんな時期ではないだろうか?
この1974年、David Geffenも31歳である。あらためて幹事さんに感謝!。
*1:"Souther Hillman Furay Band" 1974

*2:"Black Rose" 1976
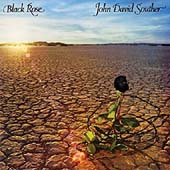
*3:"You're Only Lonely" 1979

*4:"Younger Than Yesterday" 1966

*5:"Crazy Eyes" 1973

関連エッセイ:
年頭所感:Eaglesによせて Two side to Country Rock
人物エッセイ その7 Gene Clark考
人物エッセイ その5 Gram Parsons考
人物エッセイ その3 Stephen Stills考
エッセイ目次に戻る
| 






