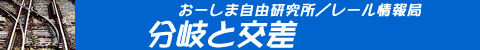
分岐器の種類 |
|---|
分岐器の種類をまとめてみました。よく見かけるものから滅多にお目にかかれないものまで知っている限りを並べてみました。「こんなのもあるよ」なんていう情報がありましたらぜひご一報ください。 |

●2方向分岐 |
|
|---|---|
よく見かける分岐器ですが,その分岐方向によってそれぞれ名前がついているんですねぇ。 |
|
片開き分岐器 |
|
|
もっともよく見かける片側が直線である分岐です。 |
両開き分岐器 |
|
|
両側に同一の角度で分岐するものです。 |
振分け分岐器 |
|
|
両開き分岐器の変形で、両側にそれぞれ異なる角度で分岐するものです。 |
内方分岐器 |
|
|
カーブの途中でその内側に向かって分岐するものです。 |
外方分岐器 |
|
|
カーブの途中でその外側に向かって分岐するものです。 |
●3方向分岐 |
|
|---|---|
これはありそうでなかなかありません。昔は連絡船の乗り場には必ずと言ってよいほどあったらしいですが、今ではよほど敷地に余裕がない限りは2方向分岐2つで代用されちゃうみたいです。 |
|
三枝分岐器 |
|
|
子供の頃読んだ図鑑で存在そのものは知っていたのですが実際に見たことはなく,長いこと探し続けた末に東急大井町線・自由が丘駅で発見しました。
すぐ手前を通る踏切から間近に見ることができる貴重なものでしたが、残念ながら現在では撤去されてしまっています。 また、有名なところではJR大宮駅がありますが、駅ビル下のためなかなかうまく見ることができません。新交通システム・ニューシャトルから一瞬見えるようですが。 敷地が確保できる地方ではあえてわざわざ三枝分岐にすることは少なく、狭い東京近郊で仕方なく導入されているケースが多いようです。JRの導入例は上記の大宮駅のみではないかと思われます。 なお,当ホームページをご覧になられた_kuni()さんからの情報ではフランス・ミュールズ鉄道博物館になんと5枝分岐があるそうです。 さらに,向山誠一さんより驚くべき画像をいただきました!アメリカで発見されたなんと三枝の鈍端ポイントです。 先日(‘24.6)、なにげなくGoogle
Mapを眺めていたところ、千葉県君津市の日本製鉄東日本製鉄所に三枝分岐器を多数発見しました。私が確認できただけでも4つあります。 いや待てよ(‘24.7)、これって日本製鉄さんだけなのか? うわーっ、神戸製鋼さんがさらに上をいってます!!神戸製鋼加古川製鉄所!!このエリア内に確認出来ただけでもなんと19箇所もあるではありませんか!!比較的狭い範囲に集中してあるのでぜひ眺めてみてください。もうここを見ちゃうと三枝分岐器なんてものは珍しくもなんともありませんな(笑)。 |
複分岐器 |
|
|
三枝分岐器と似ていますが,こちらは対称形ではなくそれぞれの分岐がずれているものです。三枝分岐器よりさらに希少ですが,仕事の出張の際に偶然,信越線・小諸駅の上田方向に確かに存在するのを見つけました。長野新幹線開通に伴い「しなの鉄道」に変わってもしばらくは残されていましたが、現在はもうありません。 こちらも_kuni()さんより,阪神電鉄神戸本線下りの尼崎駅西側に存在するとの情報をいただきました。さっそく画像をmhiroki さんよりご提供いただきましたのでご覧ください。 また,小谷松大祐様からは阪急電車宝塚線(庄内駅,宝塚駅等)や神戸線(西宮駅)に見られるとの情報をい ただきました。私もGoogle Mapの衛星画像で調べたところ、西宮車庫になんと6つ、紹介いただいた庄内駅、宝塚駅の他に塚口駅、桂駅にも各1つずつ確認できました。阪急電鉄さん、節操がありませんな(笑)。もうこうなると関西圏では珍しいものではないのかもしれません。 さらに,黒部峡谷鉄道・宇奈月駅にも存在するとの情報を桐林星河さんより画像を添えていただきました。数々の情報,ありがとうございます。 近年では京王線・笹塚駅西方に2器設置されています。 |
これらの三方向分岐器について、私がGoogle
Mapの衛星写真から確認ができたものについてマイマップにまとめてみました。 とりあえず、三枝分岐器大賞は神戸製鋼さんに、複分岐器大賞は阪急電鉄さんに贈りたいと思います(笑)。 |
|
●交差 |
||
|---|---|---|
こちらは2本の路線が交差する場合に設けられるものです。 |
||
ダイヤモンドクロッシング(1) |
|
|
|
2路線が交差する部分に使用されます。通過時にいくつものフランジウェイ(レール欠損部)を越えなくてはならず,かなりの減速を強いられるため構内や低速路線で使用されます。切替部分がないので正式にはポイントとは呼びません。 |
|
ダイヤモンドクロッシング(2) |
|
|
|
フランジウェイを減らした構造で,高速での通過に対応できるため本線どうしの交差に使用されます。こちらはポイント切替が必要です。 |
|
シングルスリップストリップ |
|
|
|
ダイヤモンドクロッシング内に渡り線を1本追加することにより交差する他路線に乗り入れることを可能にした交差分岐器です。操車場や大きな駅などで見られます。可動部分が多く,ポイント切替構造はかなり複雑なものとなります。 |
|
ダブルスリップストリップ |
|
|
|
ダイヤモンドクロッシング内に渡り線を2本追加することにより自在に路線変更ができるようにした交差分岐器です。こちらも操車場,大きな駅などで見かけられます。ポイント切替構造はもっとも複雑です。 |
|
ダブルスリップストリップ(ドイツ版) |
|
|
|
なんとまあ複雑なんでしょう。雑誌で見かけたドイツのケルンを走る電車の写真記事だったのですが,私の目は車両よりもその足もとに釘付けでした(苦笑)。通常のダブルスリップストリップより渡り線の曲率が緩和できるようですが,こんなにフランジウェイがあっては高速での通過は無理でしょう。横揺れの軽減が目的でしょうか。 |
|
|
首都圏のおすすめな見どころ |
●組み合わせ分岐 |
|
|---|---|
上記の分岐器を組み合わせたもので,これにもそれぞれ名称がつけられています。 |
|
シーサスクロッシング |
|
|
複線路線の始点駅で必ずと言ってよいほど見られるものです。向きの異なる渡り線2組と同じ働きをします。
|
渡り線 |
|
|
複線での車両の折り返し等に使用されます。この分岐器の存在が減速を強いるため,列車の高速化に伴い近年では減少傾向にあります。しかし、例えばJR中央線では御茶ノ 水駅から三鷹駅までの渡り線をすべて廃止してしまったため,事故発生時にこの間では途中折り返し運転ができないという問題も発生しています。 |
●三線軌道の分岐 |
||
|---|---|---|
三線軌道における2分岐を3例ほど挙げました。レールが1本多いためさすがに複雑な構造になります。京浜急行線・金沢文庫駅などの三線軌道始点駅周辺で見られます。「三線軌道用ダブルスリップストリップ」の構造なんていうのを考えるとワクワクしてくるのは私だけでしょうかねぇ(^_^;;。 |
||
|
|
|
|
首都圏のおすすめな見どころ |
●特殊な分岐器 |
||
|---|---|---|
特別な用途に使用する分岐器です。 |
|
|
|
|
|
|
本 線(直線方向)を進行する列車は,減速の必要なレールの切り欠け部分(フランジウェイ)がないため,高速で快適に通過できます。しかし,ブレーキ故障や オーバーランなどの緊急時にはポイントを切り替えることで列車を強制的に分岐方向に誘導します。分岐方向にはフランジウェイが用意されていないため当然脱 線の危険を伴いますが,そのまま進行して他の列車や人員を巻き込んだ大事故に発展させるよりもいいという,いわば自爆装置なのです。また,このような目的 の分岐器を脱線分岐器と呼んでいます。 |
|
|
|
|
|
近
年渡り線に代わり各所で見られるようです。主に保線車両などが一時的に使用する分岐器で,使用する際は,周囲に設けられた特殊なバーをポイント部やクロッ
シング部にかぶせることで本線レールを立体的に乗り越えさせます。乗り越え分岐器同様,本線(直線方向)には分岐器特有のレール切り欠け部分(フランジ
ウェイ)が存在しないため本線通行列車は減速の必要がありません。東急線等では分岐側レール自体に立体的加工を施したものや,ポイント切替機構を持たせた
ものといった変形版も見られます。日比谷線脱線事故で話題になった分岐器はこれです。 |
小田急電鉄・秦野駅 |
ガントレット |
|
|
|
敷地幅の狭い部分で二本の路線を重なるように敷設したもので,昔,名古屋の外濠線・本町駅構内(現在は廃線)にあったそうです。海外ではイギリスの鉄道博物館にあるようです。また,ホームページをご覧になられた遠山さんから「ポルトガルのリスボンの路面電車28番系統にあった記憶がある」との貴重な情報メー ルをいただきました。Google Mapのストリートビューでリスボンの街を必死に探したところ、ここやここに発見しました!そして、これぞガントレットの真骨頂と言える風景がこちら!まだまだあるかもしれません。 先日(‘24.6.19)、NHKの番組でリスボンの映像が映った際、キャスターの足元に変な線路があるなと思ってGoogle Mapで探してみたところ、なんとなんとケーブルカーのガントレットでした。ケーブルがセンターじゃなくてオフセットされてるのはそのためですね。リスボン恐るべし! |
|
鈍端ポイント(両フランジ車用) |
|
|
|
イタリアのトリエステ・オピチナトラムの一部区間で使用されているのがこの鈍端ポイントです。ここでは急勾配を登るために、通常の内側フランジ車輪の車両を、両フランジ車輪を使用しているケーブルカーで引き上げるという変わった運用をしているため、いずれの車輪も通過できるようにしなくてはならないことから通常の先端ポイントが使えないのだそうです。 日本ではおそらく唯一、東京大学柏キャンパスに設置された生産技術研究所千葉実験所の実験線に存在します。Googleストリートビュー画像 |
|
アプト式鉄道用分岐器 |
|
|
|
旧信越線の碓氷峠にあったことで有名なアプト式鉄道では,車両下部中央にピニオンギヤが突出しているため,交差するレール部分にこれの通り道を開けるような工夫がされています。 |
|
|
首都圏のおすすめな見どころ |
●北海道・分岐器の旅 |
|---|
北海道旅行の際にたまたま撮影したレールの数々です。初めて見た簡易分岐器数種が見どころ! |
●珍しい分岐器の数々 |
|---|
珍しい分岐器等を撮影した数々の画像をまとめてご紹介します。貴重な画像をご提供くださったみなさま,ありがとうございます。こちらへどうぞ。 |
このホームページの文・画像を無断で使用することを禁じます。(C)Y.Oshima1997