第一 神道由来之事
天地開闢の時、空中に一つの物が有った。 形は葦牙のようで、化して神と成った。 これを国常立尊という。 次に国狭槌尊が現れた。 その次に豊斟渟尊が現れた。 以上の三神は乾(陽気)のみから生じた。その次に埿土煮尊と沙土煮尊が現れた。 その次に大戸之道尊と大戸間辺尊が現れた。 その次に面足尊と惶根尊が現れた。 以上の三代六神は男女の姿は有ったが、夫婦では無かった。 その次に伊弉諾尊と伊弉冊尊が現れた。 この二神が始めて夫婦となった。 以上を天神七代という。
二神は天逆鉾を下して国の有無を探った。 その鉾の滴りが凝って嶋と成った。 今の淡路嶋である。 また、この世の主として一女三男を産んだ。 三男とは日神・月神・素盞嗚尊である。 一女とは蛭児命である。 二神は淡路嶋に幽宮を構えて住まわれた。
地神五代の最初は、伊弉諾・伊弉冊尊の太子の天照太神である。 即ち日神である。 父母神はこの子を生んで喜び、霊異の子であるとして天下を授けられた。
次は正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊。 天照太神の御子で、天照太神が弟の素盞嗚尊と誓約して生まれた。 以上の二神は天に在った。
次は天津彦彦火瓊瓊杵尊。 正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊の太子で、母は高皇産霊尊の娘の栲幡千千姫である。 日向国高千穂峯に天下り、その後は日向国宇解山に住み、天下を治めること三十一万八千五百四十二年である。 この尊の御代に、三面の鏡と三本の剣が天下った。 三面の鏡の内、一面は伊勢太神宮に在り、一面は紀伊国日前社に在り、一面は内裏に留まる、今の内侍所である。 三本の剣の内、一本は大和国布流社に在り、一本は尾張国熱田社に在り、一本は内裏に留まる、今の宝剣である。 この二つは後に内裏守護の宝と成った。
此の国を日本と名づける事は、日天子が天下って神と成った故である。
次は彦火火出見尊。 天津彦彦火瓊瓊杵尊の太子で、母は大山祇神の娘の木花開耶姫である。 天下を治めること六十三万七千八百九十二年である。 御陵は日向国高屋山に在る。
次は彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊。 彦火火出見尊の太子で、母は海童の第二の姫の豊玉姫である。 天下を治めること八十三万六千四十二年である。 御陵は日向国吾平山に在る。 以上を地神五代という。 この尊の第四の太子を神武天皇という。
伊弉諾・伊弉冊尊の一女三男の内、第一は素盞嗚尊である。 悪神なので嫡子には立てず出雲国に流された。 今の出雲大社である。
第二は日神、今の伊勢太神宮である。 伊勢国度会郡五十鈴河上に鎮座している。
第三は月神、月弓霊尊という。 今は鎮西豊後国の本満宮に垂跡している。
一女は蛭児命である。 この御子は三歳の時に楠の椌船に入れて大海に捨てられた。 この船は浪に漂って自然と龍宮に下った。 龍神がこの子を養ってその由を尋ねたところ、天神七代の伊弉諾・伊弉冊尊の御子であると言った。 龍宮に留めるべきではないので、七・八歳の時にまた楠の椌船に乗せてこの国に返した。 蛭子は龍宮に何年もいたので、第八の外海を引出物として給わった。 龍王が「我は大海を領して陸に所領が無い。外海を与えるので大海の上に住むがよい」と云ったので、蛭子は住吉の洋に留まった。 今の世に西宮と云うのがこれである。 海人は盛大に秋の祭を行い、これを恵美酒と申している。
伊勢太神宮が天下った時、第六天魔王が之を見て、この国を滅ぼそうと天下った。 太神宮は魔王に向かい、「私は三宝の名を云わず、我が身にも近づけませんので、すぐに天上にお帰り下さい」と誓ったので、魔王は天に帰った。 この約束を違えぬよう、僧は御殿の近くには参らず、社壇では経を顕には持たない。 三宝の名も正しく呼ばず、仏を「立スクミ」、経を「染紙」、僧を「髪長」、堂を「
天照太神は素盞嗚尊が天津罪を犯した事を憎み、天岩戸を閉じて隠れたので、天下はたちまち暗闇に成った。 八百万の神々は悲しんで、天照太神を誘い出す為、庭火を焚いて神楽を行った。 天照太神は御子神たちの遊びをゆかしく思い、岩戸を少し開けてご覧になると、世間は明るくなった。 大力雄神が御神を抱き留め、天岩戸に七五三(注連縄)を引き、この内に入れないようにしたので、ついに日月が天下を照らすようになった。 日月の光が当たるのも当社の恩徳である。
すべては大海の大日如来の印文より起り、内宮・外宮は両部の大日如来である。 天岩戸とは都率天であり、高天原とも云う。 真言の意では、都率天は内証の法界宮殿で、密厳浄土とも云う。 内証の都を出て日本に垂迹する。 故に内宮は胎蔵界の大日如来で、四重曼茶羅を象って囲垣・玉垣・水垣・荒垣と重々めぐらせている。 勝雄木は九本有り、胎蔵界(中台八葉院)の九尊を象る。 外宮は金剛界の大日如来あるいは阿弥陀如来である。 金剛界の五智を象って、月輪は五つ有る。 胎金の両部は陰陽を司り、陰は女、陽は男である。 八人の八女は胎蔵を象る。 五人の神楽男は金剛界の五智を象る。
また、御殿が萱葺である事も、御供が三杵ついた玄米である事も、人の煩いや国の費えを思召した故である。 勝雄木が真直ぐで、垂木が曲がらないのは、人の心を真直ぐにしようと思召した故である。 心が真直ぐで、民の煩いや国の費えを思う人は、神慮に叶う者であろう。
当神宮は自然に『梵網経』の十重戒を保っている。 人を殺すと追放されることは波羅夷罪、人を打擲・刃傷すると解官され、出仕を停止されることは軽罪と同じである。
当社における物忌は、他の社とは少し異なり、鵜羽屋(産屋)を生気として五十日の忌とする。 また、死を死気として同じく五十日の忌とする。 其の故は、死は生より来て、生は死の始めなので、生死を共に忌むべしという心である。 誠に不生不滅の毘盧遮那法身の内証を出て、愚痴顚倒の四生の群類を助けようと垂跡される本意は、生死の流転を止め、常住の仏道に入る事であり、生死を同じ忌とする。 愚苦を悲しみ、生死の悪業を造らず、賢妙なる仏道を修行し、浄土の菩提を願うべきである。
神明神道の本地を尋ねれば諸仏菩薩である。 諸仏菩薩の跡化は神明神道である。
問、何の義により諸仏菩薩は神道と顕れるのか。
答、諸仏菩薩は群生を済度するために種々の形を現し給う。 ただ無縁の慈悲であり、与物結縁の儀式である。 其の慈悲を尋ねると、『法花経』方便品には「舎利弗当知、……云何而可度」と云い、同経寿量品には「放逸着五欲、……速成就仏身」と云う。 本跡二門の仏意はこのようなものである。
非形非色の法身は、ある時は己身実仏を説き、ある時は他受用・応化身を現し、ある時は三乗・六道の形声を顕し、同塵して他身・他事を以て交わり、群生を引導される。 『法花経』寿量品には「或説己身、或説他身、或示己事、或示他事」と云う。 『法花玄義』第二には「悲生現生等是応身也。或説己身、即法身也、報身也。或説他事、即応身也」と云う。
問、報身は己身・他身に通じるのか。
答、自・他受用の分別が有る。 密教の意では、五部灌頂の中台の大日如来と申し、これを一仏とも云う。 次第に両部・三部・四種の法身が顕然とする。 顕教では、法身・自受用・他受用・応化身が己身・他身の分別である。 自性身は己身である。 自受用身は他身である。 これは勝応身と劣応身である。 和光同塵の結縁の始めは、他身・他事である。 自性・自受用の己身を隠し、等流変化の化身を現す。 雑化雑類の輩は、仏菩薩の形で利益しようとしても、罪業が深いので近付くことが出来ない。 『花厳経』教主の蓮華台上の盧遮那仏は宝玉の長者の姿で、報身は気高いので、二乗は近付くことが出来ない。 その時に如来が瓔珞細軟の上服を脱ぎ、麁弊垢膩の衣を着ることで、二乗はようやく近づく事ができるのである。
神明の和光同塵もこれと同じである。 五濁悪世の衆生は後生の果報を恐れず、今生の栄花を深く望んでいる。 眼前の事だけを信じて、後生の事は思わないので、(諸仏菩薩は)衆生の為に己身の自性の光を和らげ、他身は雑類と同塵する。 一度瑞籬・囲垣を践み、二度和光の宝殿に歩みを運べば、それを因縁として、永く三悪道に堕さず、八相成道の未来まで厚く利生するのが、神道の垂跡である。 『悲花経』には「我滅度後、於末法中、現大明神、利益衆生」と云う。 『般若経』には「為未来世濁世之時、即現大祠神形利生」と云う。 真言教主は「大日如来、為麁同類、権成冥神、心同嬰児」と云う。
問、神明を崇める事は我が朝に限るのか。
答、『観経疏』には「父王有子事、所々神求、終得事不能」と云う。 『大論』には「樹神祈子得」と見える。 漢土では、三皇五帝の往魂や七魂七星の霊廟等を始めとして、大小の神祇が多いと聞く。 我が朝はもとより神国である故に、百八十柱の神を始めとして、一万三千七百余所等はみな利益がめでたい。
問、ある人が云うには、『毘吠論』によると一度神を礼すると五百生は蛇身の報いを受けるという。 もしそうならば、神を礼すべきだろうか。
答、神道には権実が有る。 悪霊・悪鬼は物に取り憑いて人を悩ませる。 実者はすべて蛇や鬼などである。 権者の神は如来・菩薩が衆生を利益する為に和光垂跡し、八相成道の終りを論じる。 当然帰依すべきである。 ただし、実者の神といえども神として顕れているので、利益が無いわけではない。 日本は神国なので、総じて敬礼すべきである。 国の風習は凡愚であり、権実を弁別するのは難しい。 ただ神に随って敬い礼して、何の失が有るだろうか。 始めは実者だとしても、終いには権者の眷属と成るだろう。
問、大小権実の明神の本地が仏菩薩であるという事は、何を以て知ることができるのか。
答、これは不思議で、経文や論蔵には見えない。 本朝は辺州なので仏説・論判は無い。 仏菩薩は我朝に来て、明神の垂跡として人間界に応生する。 この神の託宣を以て内証とするのである。 衆生を利益されるため、日本には多くの神明が在る。 その本地が仏菩薩でないということがあろうか。
問、汚れを忌むのは方便である。 中でも女人の月水を忌むと聞くが、祭礼の時に魚鳥の類を祭供に用いる神社は多い。 皆これらは血の忌みの物であり、月水も血、魚鳥の類も血である。 然るに、女人の月水を忌み、魚鳥の類を祭供に備えるのは何故か。
答、女人の事はしばらく置き、後で説明する。 次に肉類を祭供に備える事であるが、『涅槃経』には「示肉食現、此現云、其実不食、但有執見者、如来方便不解而偏執」と云う。 『毘尼母経』には「仏言、三種浄肉食事聴、又我訪云、如来自食、彼愚癡人大罪作、長夜闇堕無利益、諸如来大会声聞等、当法非当貯事法非受取、我不浄、真肉食非説、可食善破道諍、邪念謟曲、以自活求、亦見道障」と云う。 『文殊師利経』には「仏告文殊師利、衆生以慈悲力無殺害心起、此因縁為故、肉食誡、若能害心、大慈悲一切衆生教化為、有罪科事無」と云う。
問、利益の為には仏菩薩の慈悲神力は不可思議だが、肉食をすると云っても利益すべきか。
答、この疑問はもっともである。 罪根深重の輩には利益し難い。 畜類は闇鈍で無智卑賤なので利益し難い。 『大論』には「懺悔心無、堕畜生道」と云う。 『釈義』六には「恭敬心無、驕慢瞋念心以肉食、堕畜生道」と云う。 道宣律師の『諸経要集』には「衆生以故地獄堕、年窮、劫極、更別離苦具、復畜生中堕、諸牛猪羊鶏狗魚鳥成、人為被殺、命終後返事不得、死飾殖山、禽獣無量有生死、若微善無永出免期無」と云う。 仏法の習いでは、善縁が無ければ解脱し難い。 そこで、肉食を以て微少の善縁とし、畜生の苦を救う。 垂跡は仏菩薩の化現なので、腹の内に満足して広大な善根を成す。 (畜類は)生死に沈淪せず、遂に仏果を得ることが出来る。 此の故に祭供に肉食の類を用いる。 然るに、月水を忌むのは女人の不浄を顕し、出離の心を起こす為である。 肉を祭供に備えるのは、利生の方便である。 月水を忌むのも、済度利生の方便である。
問、鹿の肉食の忌みは百日である。 他の熊・猪等よりも忌みが深いのは何故か。
答、道宣律師の『諸経要集』に引用する経には「仏言鹿我身、烏是阿難」と云う。 『首楞厳経』には「阿難白仏、一切衆生何為六道輪廻、仏阿難告、有狩師鹿殺、狩師亦鹿生、鹿亦生狩師、如此間、其罪業造輪廻事無窮」と云う。 『諸経要集』が説くように鹿を殺す罪は重く、他の肉を食うより忌みは深いのである。
問、鹿が釈尊の化身ならば、其の肉を食った人は何の罪業を得るのか。
答、『大般若経』には「菩薩摩訶薩仮使有人来、或打、或擲、或割、或截、彼有情於意無分限、彼利益示作事」と云う。 『涅槃経』には「我如往昔者、半偈為故此身棄捨、以此因縁即超越事得、三劫具足、弥勒前在、阿耨多羅三藐三菩提成」と云う。
問、諸仏菩薩の禽獣等の身に化現するのは、悉く衆生を利益する為である。 しかし其の肉を食うことは重罪であるとは、利生の道理ではない。 如何なることか。
答、諸罪の中では五逆が最も重罪である。 五逆とは、一に父を殺すこと、二に母を殺すこと、三に阿羅漢を殺すこと、四に仏身より血を出すこと、五に和合僧を破すことである。 恩深い人を殺す故に重罪である。 『涅槃経』には「提婆達多不善仍起、自仏身血出、此悪作得、堕地獄、一切苦受」と云う。
問、仏が鹿の身に化すのは何の為か。
答、道宣の釈によると、釈迦如来は鹿と成って五百の猿猴を教化した。 (その鹿は)畜生と雖も、釈尊の内証外用の功徳を具えている。 鹿を殺して肉を食うと、内証外用の功徳を損なうので、鹿の肉を食う事は深く禁じられている。
問、狐等の忌みの深さはどうなのか。
答、烏は阿難の化身である。 狐は文殊の化身である。 菩薩・声聞は仏の弟子なので、その化身を殺生するのは、仏の化身の殺生には劣る。
問、仏菩薩の内証外用は、天等も皆慈悲の願旨に随って名号を称し、別願に依り音楽形相は各別である。 故に不動・降三世明王は忿怒の形を示して、魔界を降伏する。 観音・弥勒等は柔和忍辱の体を顕して、恣に大慈大悲の利益を施す。 垂跡の中にも権現・大菩薩・大明神の違いがある。 その住所を宮と云い、社と云い、霊験処と云うのは各別である。 明神にも誦呪・誦経の法楽を奉り、権現・大菩薩にも此の法楽を捧げるのは如何なる事か。
答、権現・大菩薩・大明神はすべて仏菩薩の垂跡で、同じく法楽を受けられる。 ただ、三種の別が有り、一は権現、二は大菩薩、三は大明神である。 権者と実者は前に述べた通りである。
古記に引用された為憲の伝によると、八幡大菩薩は天平勝宝元年に豊前国宇佐宮から男山に移られた。 八幡大菩薩は元は八幡大神と申された。 宇佐宮の本地は釈迦・弥陀・観音の三尊と顕れ、男山に移られた時、行教和尚の三衣の袂に弥陀三尊と顕れた。 和尚が大乗の仏菩薩の十戒を授け、「護国土霊験威力神通大菩薩」と号して以来、大菩薩と云うのである。
問、もしそうなら、大菩薩と名づける事は八幡に限るだろう。 他の神も大菩薩と名づけるのは何故なのか。
答、観音の在す所はみな大菩薩と名づける。 神に大乗の菩薩戒を授ける故に、大菩薩と名づける。
諸仏の御住所を霊所・聖霊所と名づける。 故に垂跡の御住所を霊験所と申す。 『文句』巻一に「霊鷲山前仏後仏皆此山住。鬼神此山住。既是聖霊居所」と云う。 保胤入道の比叡山の中堂の讃明句に「霊験殊勝の地、利益深妙の所なり」と云う。 菅三品の中堂の美明句に「日本無双の霊所なり」と云う。 これら考えると、諸仏菩薩の利益めでたき所を霊験所と云う。 次に宮とは、天竺には国王の内裏精舎を堂と名づけ、王宮と名づけ、仙洞と名づける。 諸仏菩薩の御住所は堂である。 国王の内裏の名を借りて堂と名づける。 また社とは、祭祀による詞である。 神とは世間の祖宗である。 祭祀する故に、御住所を社と云う。
次に明神・権現・大菩薩の三形の各別を云うと、皆共に仏菩薩の垂跡であり、法味を捧げる事も亦同じである。 法施のめでたき事は、『金光明経』に「財施不出三界、法施法身利益、法施能断無明」と云う。 和光同塵は衆生の利益の為に現れると云う。 一切の迷いを断じ、煩悩が無い。 此れは法身を証する理である。 (明神・権現・大菩薩には)皆同じく法味を捧げる。
問、法施はそうであるが、財施に利益は有るのか。
答、『金光明経』に「財施只伏貪心」と云う。 一切衆生には煩悩が多いが、貪瞋癡の三毒を根本とし、其の中でも貪欲を上首とする。 垂跡は仏菩薩であり、衆生が皆貪欲に迷悶することを悲哀し、和光同塵の形を現す故に、財施を得て、貪欲の心を伏せるのである。
問、神明の霊所を一度践む事で、忝くも上人は三悪趣の苦を免れる事が出来るのか。
答、世間で申すには、この事は当然か。 故に太神宮には法師は入らず、宮人はこれを防ぐ。 これは三宝の中には僧宝なので、大罪を捨てるのである。 また、熊野等の社は、一度参詣すれば三世の願を成就すると申す。
問、これは不審である。 彼の御山で難行苦行し身命を顧みない行人は、貧窮孤露にして衣服は乏しく、苦を免れずに一生の願望を空しくする者が多い。 また、参詣の途中に山賊・海賊・頓死に合い、死んでしまう者も多い。 今生の望みは既に空しく、後生の頼みもまた難しい。
答、霊地を一度でも践んだ人は、必ず三悪趣の苦を免れる事が出来る。 『正法念経』には「七歩道場、永離三悪、一入伽藍、決定菩提」と云う。 道場も霊地も仏菩薩の霊地である。 仏と神は本跡は異なるが、心は同一である。 垂跡の霊地も仏菩薩の霊地も、参詣の力に依り得られる利益は同じである。 参詣の功酬により三悪道の苦を免れ、垂跡恭敬の力により菩提の果を得られる。
伊勢大神宮に僧が入らない事であるが、天神七代の末の伊弉諾・伊弉冊尊の御子は、地神五代の始めの御神の天照太神である。 今の伊勢太神宮がこれである。 御本地は大日如来である。 (大日)如来は諸仏菩薩の本師で、一切三宝の智母である。 その垂跡であるので、どうして僧を厭われるだろうか。
公任の伝によると、崇神天皇の御時に伊勢大神宮より宝剣が天皇に授けられた。 即ち、天村雲剣と云う。 その時に天皇の宣が有り、大神宮の祭主より神宮寺に衣冠束帯が下された。 この時より、(天照太神は)束帯の姿で諸神を執領し、堅く国家を鎮護される。 また、天照太神は三の鏡に御影を浮ばれる。 紀伊の日前の霊所がこれである。 伊勢太神宮は束帯の姿で鏡に浮ばれ、諸神を領し、国郡を争う為に、怖ろしげな姿で鏡に浮ばれた。 即ち、異国の軍を降伏する為である。
問、これは不審である。 仏法が王法を守り、王法が仏法を持する事は、天竺・震旦の習慣である。 日本も同様で、社内に仏法を安置し、法味・法楽を捧げ、王法を守れば、さらにめでたくなるが、如何だろうか。
答、高野の伝によると、世界は日・月・星宿の所変である。 西天月氏国は月天子の所変である。 唐土震旦は、星宿の守護する国である。 此の州を日本と名付ける事は、日天子の所変である事に依る。 此の州は元は嶋も無く、潮だけが有り、天神七代の間は天に在った。 第七代の伊弉諾・伊弉冊尊が鉾を差し下して嶋が有るかと捜り、鉾を引き上げると潮の滴りが凝って嶋と成った。 今の淡路嶋がこれである。 その後、嶋が次第に広がり、六十余州と成った。 これらの嶋が出来た後は、天より地に下って住まわれ、地神五代と云う。 この五代の始めの御神は天照太神である。 今は忝くも伊勢太神宮と申し上げる。 この御神は即ち大日如来の所変であり、皇祖である。 太神宮に僧が入らないのは、大日如来の秘密の道場である事を示している。
問、熊野や二所等の社は二世の悉地を成すと云う。 その義の無い行人は数多い、如何だろうか。
答、今生の果報は善悪高下がある。 賢愚貧富、短命長寿、利鈍智恵、非時中夭、これらは皆前世の宿習に依るものである。 『増一阿含経』には「偸盗悪業因縁、命終後、地獄中生、経二百歳、畜生報畢後、餓鬼道生、飢渇苦悩受、亦経百千歳、其罪了、人中生、三種果報得、一者貧窮衣服形不覆、二者飲食口不満、又三者悪賊為被劫奪」と云う。 『罪応地獄経』には「衆生有、自生死、有児子無事孤立、何罪至処有、仏言、尤悪付罪福不信、百鳥乱時、諸鳥子失、諸鳥敢此罪獲」「又若衆生有、孤寒、父母兄弟有事無、他為長大、何人成、何罪至処、仏言、以前世人時、諸禽獣狩、常鳥憂悩、此報得」と云う。 『大集経』には「仏言、所有衆生、現世及未来世、当深仏法衆僧可信、彼衆生人天中、常勝妙果報得受」と云う。 『花厳経』には「若一句未曽有法聞、三千世界珍宝得勝」と云う。
問、果報めでたき衆生は、今生の行業を以て、今の勝妙の果報を生じるのか。
答、『正念法経』には「一者父、二者母、三者如来、四者読法時、若此四種供養人有、無量福得、現世人為被讃嘆、未来世能菩提得」と云う。 『法花経』には「若有衆生、恭敬礼拝、観世音菩薩、福不唐捐」と云う。 『薬師経』には「求長寿得長寿、求富饒得富饒、求官位得官位、求男女得男女」と云う。 これらの文には今生の行徳を以て今生に行果を得ることを説いている。
問、その証を得ていない行人が多いが、如何だろうか。
答、天台の釈には「以信行本」と云う。 身口の行を尽くしても、意業で信じなければ、証は得られない。 信力の堅固な行人は、前世で宿善の人なので、今生の善は盛んで、証を得るだろう。 今生に不信の心が有っても、法の如く修行すれば、必ず証利が有るだろう。 その故は何かというと、仏神は信心を哀み給うからである。 参詣の時、途中の横死・横病・山賊・海賊等の事は、或いは精進中の汚穢不浄に依り、或いは無宿の懈怠、不信の科に依る。 或いは親類縁者の死気・産などの汚れに依って、途中で難が有る。 こういった例は世に多いが、これらの科は皆行人の不信に依るものであり、仏神の親疎ではない。
問、仏神の助けにより、貧を転じて福となった人は有るのか。
答、後白河院の御時に、八幡の前別当祐尊と平安京の八坂の貧女の例がある。 三年間、八幡に月詣をした功徳により、祐尊は本職に預かり、八坂の貧女は但馬国の目代藤助の妻となった。 この他、熊野・金峯山・二所・三嶋などの霊験はその例が多い。
問、権現・大菩薩・大明神の三種の内、明神に限って三熱の苦を受けると聞く。 これは何故か。
答、権現・大菩薩は三熱の苦を受けない。 何故かと云うと、垂跡の中には実者・権者が有り、仏菩薩が化現されたのは権者である。 (仏菩薩の)応化ではなく、神道の実業を以て神明の名を得たのは実者である。 仏菩薩の垂跡は苦を受けないが、実者は受けるのである。
問、仏菩薩は衆生利益の為に六道の苦を受けることが多い。 そして、身体の苦楽は本跡共に同じである。 調達は不動賓迦羅菩薩の化身だったが、五逆の罪を犯して地獄に堕ち、火炎の中に居る。 八大龍王の部類の中には仏菩薩の化現が有るが、三熱の苦が有る。 恵心の釈には「諸龍三熱苦交、昼夜無休」という。 このような部類に生れて、何故三熱の苦を受けないのか。
答、『涅槃経』巻七には「菩薩摩訶薩、憐憫一切衆生故、雖復処在阿鼻地獄、如第三禅楽」と云う。 『疏記』巻二には「霊山頂有池、名阿耨達池有、龍王其中住処、閻浮提諸龍、有三患、此池龍王、無三患、故名無熱池」と云う。 龍王は権者と云い、故に三熱の苦は無い。 則ち三熱の苦を受けるのが実者で、受けないのが権者である。 ましてや、八幡大菩薩は応神天皇である。 平野大明神は仁徳天皇である。 二所権現は天竺の国王である。 このような御神たちは三熱の苦の器ではない。
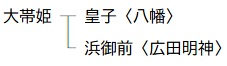
 を刻んだ図柄、外宮の御形文は
を刻んだ図柄、外宮の御形文は 形の刻文を連続模様として布置したものであった。
形の刻文を連続模様として布置したものであった。