筆者が始めて聞いた "フォーク" という言葉は小学校6先生、1967年の暮れにテレビ、ラジオに登場したフォーク・クルセイダーズであった。
そうした体験を経て、自分の中にフォーク・ソングというイメージが醸成されつつあったのだが、更に明確になったのは中学に入学した際のクラブ活動紹介であった。
その後、1960年頃にラジオで流れていた曲がキングストン・トリオやブラザース・フォアの演奏であると知ったのは、中学2年の時に母校に赴任された美術のN先生の自己紹介であった。その中にフォーク・ソング、ギター、バンジョーという単語が出て来たのである。
高校に入るとフォーク・リバイバルを通過したのは、Byrdsのリーダーであるロジャー・マッギンやボブ・ディラン、それ以前にはジョーン・バエズ、ピート・シーガー(1919〜2014)、ウディ・ガスリー(1912〜1967)という名前を知る事となった。
そんな中で少し違ったジャンルからフォーク・ミュージックを眺める機会を得たのもByrdsを通してであった。
フォーク・リバイバルと言うと必ず出て来る人物として、アラン・ローマックス(1915〜2002)が挙る。
脱輪:
アメリカのフォーク・リバイバルは洋楽情報としてすぐに日本に伝わったが、日本ではそれとは違う形で民謡を出自としたスター歌手が現れた。三橋美智也である。
フォーク・リバイバルについても誰の需要に合致していたのか?という視点では、東西冷戦やベトナム戦争を背景とする反体制、反戦や公民権運動と言った社会性のあるテーマを抱えていたところから、学生やホワイトカラーの需要に支えられていたように思える。
ところで、日本のフォーク・ソングブームも終焉に近かった1969年に赤い鳥が歌い始めた "竹田の子守唄"*1 は京都市伏見区竹田地区に伝わる民謡・子守歌と言われている。
脱輪:
アラン・ローマックスは学術的な視点でトラッド・フォークを収集していたと思われるが、多様な民族の生活の中から生まれたものが玉石混交状態であったと思われる。
脱輪:
一方、こうした限られたコードで採集されたトラッド・フォークの録音を聴いた者が、それをカバーしようとする際にコードを付け足していく例もあったと思われる。自分の解釈を入れた編曲と言えばよいだろうか?全く別の曲かと思うほどに原曲が推定できないような例も出て来る。
近年、人の曲を "カバー" するという言い方が定着したが、いろいろなニュアンスが感じられる。
そうした視点では、先述の "竹田の子守唄" や "山の教会" も同様に思われる。
そして、アニマルズのカバーはエレキギターやハモンドオルガンの伴奏から最初のフォーク・ロックではなかったかという声も聞かれる。
ロジャー・マッギンは1942年7月13日、シカゴ生まれで、"Old Town School of Folk Music" で学んでいるとのこと。ここは日本の音楽高校のような所らしい。
Byrdsはボブ・ディランの "Mr.Tambourinman" でデビュー・ヒットした訳だが、この曲はどういう受け取り方をされていたのだろうか?
2作目 "Turn! Turn! Turn!" は "A time to" で始まる聖書の一節を引用したピート・シーガーの曲だが、ブラザース・フォアの "The Green Leaves Of Summer" にも同じ用法が見られる。
ところで、Columbiaレーベル内でも "Terry Melcher" の手腕は話題になったようである。同レーベルのプロデューサー "Tom Wilson" がディランの "Like A Rolling Stone" に同様なアレンジを試み、ディランも腑に落ちていたようである。
3作目 "5th Dimension" は最初の転機であろうか。
クロスビーがボーカルを取った "Hey Joe" はジミ・ヘンドリクス初め、数多くカバーされている。版権は "Billy Roberts or Dino Valenti" となっており、"Billy Roberts" のバージョンはブルーズ寄りで禍々しい雰囲気が出ているが "Dino Valenti" のバージョンはロック寄りで疾走感がある。
ジミ・ヘンドリクスは前者、クロスビーは後者をカバーしている。
このアルバムには二つの英国のトラッド・フォークが収録されている。"Wild Mountain Thyme" と "John Riley" である。
版権は、前者はクロスビー、ヒルマン、マッギン、(マイケル)クラーク、後者は "Ricky Neff"、"Bob Gibson" となっているがいずれも18世紀辺りまで遡る古謡とのこと。
こうして見ると前2作が同時代のフォーク・ソングの発掘とすると、"5D" では現代から18世紀まで遡ったことになる。
脱輪:
同様の例はPP&Mでも見られる。1962年の彼らのデビューアルバムに収められた "Cruel War" 邦題;悲惨な戦争は、イングランドやアメリカ独立戦争起源説、南北戦争の頃には歌われていたとされるP.D.であったが、メンバーのピーター・ヤーロウとポール・ストゥーキーが歌詞とコード進行にアレンジを加えており、レーベルには彼らの作として版権が記載されている。
4作目 "Younger Than Yesterday" とは本アルバム中唯一のディラン作品 "My Back Pages" の一節だが、他は全てByrdsのメンバーによるものとなった。
ところで、プロデューサーは "Gary Usher" に変わったが、このアルバムを聴いた1971年当時はその素性は全く知らなかった。
脱輪:
5作目"Notorious Byrd Bros." は筆者にとって始めてのByrds体験だった訳だが、異色かつ問題作だったようである。
キャロル・キングはマッギンと同世代の1942年生まれで当時は "Gerry Goffin" と夫婦で職業ライターとしてポップスヒットを支えていたが、後の1971年に "Tapestry"*1 でソロデビューしている。
さて、このキャロル・キングが関わった2曲に共通するのはスタジオ・ミュージシャン、"Red Rhodes" によるペダルスティールギターの使用である。
そしてこのアルバムの異色さを醸し出しているもうひとつの仕掛けはサウンドイフェクトであろう。
更に印象的だったのは "Dolphins Smile" のイントロのポコポコサウンドである。
さて、このアルバムではクロスビーの去就に興味が行きがちで、ヒルマンの影が薄くなりがちに思える。
Columbiaレーベルはディラン、サイモン&ガーファンクル、Byrdsとフォーク系の布陣を敷いていたようだが、お互いのプロデュースに影響を及ぼし合ってフォーク・ミュージックは更に加速を続け、ブラックホールに吸い込まれて行ったのかもしれない。
デイビッド・クロスビーとすれ違いで Byrdsに加入したのが、グラム・パーソンズであった。
グラムが持ち込んだものはカントリー・ミュージックだった訳だが、メディアでは "グラムがByrdsを乗っ取った"、"マッギンは母屋を取られた" というような見方がされているようである。
ところで前作、"Notorious Byrd Bros." はスタジオアルバムとしては価値ある作品に思うが、ステージで再現不可能な作品を作り上げてしまった訳でもある。アルバムセールスだけでは食って行けないし、次のアルバム用の曲を書いている暇も無い。早急にツアーに出られる策を講じる必要に迫られていたのだろうか?
前作から僅か7ヶ月後にリリースされた6作目 "Sweethert Of The Rodeo" は革新性が殆ど無いところにリスナーもメディアも戸惑い、なんとか解釈を試みたようだ。
筆者はこのアルバムをイージーライダーでByrdsを知った翌年の夏に入手して聴いたのだが、まだByrdsを聴き込んでいなかったので、こういう音楽もやるんだなという程度であった。
"Sweethert" は今ではカントリー・ロックのパイオニアのようなニュアンスで語られているが、当時は理解不能でありながらも、その真摯さは後のフォロワーにとっては大きな示唆だったのかもしれない。
ところで、"Sweethert" ではディランの曲が冒頭とラストを飾っている。
革新性が殆ど無いと前述したが、異質な光を放っていたのはスタジオ・ミュージシャン、クラレンス・ホワイトではないだろうか?
1954年頃の "Three Little Country Boys"*1 なるブルーグラスバンドの写真があるが、ギターに抱えられながら弾いている男の子をマッギンも覚えていたのだろう。
"Sweethert Of The Rodeo" リリース後、グラム・パーソンズとクリス・ヒルマンは意気投合してByrdsを脱退、Flying Birrito Bros.を結成して "Cosmic American Music" へと旅立った訳だが、マッギンはByrdsにクラレンス・ホワイト、ドラムスはジーン・パーソンズ、ベースはジョン・ヨークを迎えた。
7作目 "Dr.Byrds And Mr.Hyde" を筆者が聴いたのはByrdsリユニオンアルバムを聴いた後、1974年の事であった。
こう考えると "Notorious" から"Sweethert" へ、サイケデリック・ロックからカントリー・ロックへ強引に繋げてしまったように思えたのである。アルバムタイトルから二重人格という事かもしれない。
さて、他の収録曲なのだが、クラレンスがBベンダーを駆使したインスト "Nashvill West" はなるほどと頷けるものの、相対的に彼のトラックのレベルが低く、よく聴こえない。マッギンの12弦のリックもトラックの分離が悪くクラレンスのリックの邪魔をしているのも惜しい。
そして8作目 "Ballad of Easy Rider" だが、マッギンも前作のプロデューサー "Bob Johnston" は懲りたのか、デビューから2作目まで手掛けた "Terry Melcher" が戻ってきた。
さて、収録された楽曲を回顧してみると、
そして9作目 "Untitled" だが、引き続き "Terry Melcher" のプロデュースが続く。
ところで、ライブ盤 "Eight Miles High" を初めて聴いた当時はインプロビゼーション=ジャズを連想してしまったのだが、今聴いてみると筆者はどこか民族音楽を連想してしまうのである。
ウィキペディアによると "Untitled" は "Gene Tryp" なるブロードウェイ・ミュージカルのために書いた素材の中から4曲が収録されているとのこと。
カバー曲はクラレンスがボーカルを取った "Littlefeet" の "Truck Stop Girl"、レド・ベリーの "Take a Whiff on Me" となっている。
"Terry Melcher" はエコーやリバーブ処理を控えて、バスドラムとベースのリズムを重ねてステレオのセンターに置く手法を取ることで泥臭い音造りをしているが、カントリー・ロックという意識はあったのだろうか?
筆者にはまだどこかにフォーク・センスが感じられる次第である。
脱輪:
そして10作目 "Byrdmaniax" だが、 "Terry Melcher" のプロデュースが続く。
そうした視点で今、回顧してみると。
オーバー・プロデュースと言われながらも筆者が印象的だったのは "Pale Blue" である。
脱輪:
脱輪その2:
脱輪その3:
そしてラスト11作目 "Farther Arong" だが、国内ではCBSソニーからリリースされた "Byrdmaniax" の直後に本国から次の新譜のニュースが伝わり、国内盤を待ち切れずに大枚¥3200を叩いて初めての輸入盤に手を出してしまった。
赤い "Columbia" レーベルの版権を見るとP.D.は無く、メンバーおよび、"Kim Fowley" との共作、そしてカバー曲が数曲収録されている。
当時、筆者はライナーズノートやメディアから後期Byrdsのような音楽がカントリー・ロックと呼ばれている事を知ったのだが、カントリー・ロックの捉え方は多様であったようである。
フォークともカントリーとも言い切れないシンガー・ソングライターとロックバンドの互恵関係がカントリー・ロックのひとつの側面であったように思われる。
さて、カントリー・ロックなる用語が聞かれなくたった後もジーン・パーソンズがコツコツと自作曲やお気に入りの曲をカバーしてソロ活動を続けて来た様子を見ると、フォーク・ミュージックに代わってルーツ・ミュージックという呼び方が出て来た理由がなんとなく判る。
脱輪:
脱輪その2:
高校2年は1972年、筆者は "Farther Arong" のおかげでブルーグラスに興味が移っていた。
そして1973年の春、再び輸入盤に手を出してしまったリユニオンアルバム。裏ジャケットのバーのカウンターに座った5人の写真は皆、どこか頼もしくなったような気がしたものである。中でも真ん中のデイビッドの表情が印象的であった。クレジットを見ると彼がプロデュースしている。
ディスクに針を落として驚いたのは奇麗に響くアコギ・アンサンブルだった。
ジーン・クラーク作の "Full Circle"、"Changing Heart" で彼はシンガー・ソングライターとなっていたことを知った。
クロスビー得意のカッティングの鋭いリズムギターが聞こえるが、初期Byrdsの音とは違う。
そのようなことで、筆者としては価値あるリユニオンアルバムに感じられた次第であった。
脱輪:


その1:'60 フォーク・リバイバルの舞台裏は?
加藤和彦、北山修、はしだのりひこのトリオである。 ”帰って来たヨッパライ”*1 で一躍有名になり、社会現象にもなった。
彼らはByrdsがデビューする1965年から活動を始めた京都の学生トリオであったが、”フォーク・ソング”というジャンルがある事を知った。
前年の1966年頃にはラジオで "P.P.M." は耳にしていたのだが、彼らの名前も音楽がそのジャンルである事も知らなかった。
従ってフォーク・ソングとは ”帰って来たヨッパライ” のような音楽と認識してしまったのである。
ただ、グループでアコースティックギターやWベース(コントラバス)を弾き、ハモリながら歌うというスタイルであるところは外れていなかったようである。
また、曲名も演奏者も知らなかったが、 "Tom Dooly" や "The Green Leaves Of Summer" は1960年頃にはラジオから流れていた。
わら半紙に手書きの謄写版で刷られたプリントの中に、"フォーク・ソング部" を見つけたのである。
担任の先生にどんなクラブなのか質問したのだが、”顧問の英語のU先生が居るから尋ねて行きなさい” とのこと。
職員室に行ってみるとU先生は女性と知ってちょっとドキっとしてしまったのだが、残念な答えが返ってきた。
”あら、去年まではあったけど休部状態なのよ”
”あなたの他に希望者が居ればなんだけど、ブームは3、4年前ね。ギターを伴奏に歌うのよ"
残念ながら筆者の他には希望者は現れなかった。
N先生は英語のU先生が言っていたブームを体験していた世代と判った次第である。
中学2年は1969年の春、"フランシーヌの場合は" なる曲で、新谷のり子がデビューした。ギターの弾き語りで、歌詞の内容から焼身自殺した女性の事を歌ったものと知った。
その曲を聴いた時にはフォーク・ソングと認識し始めていたのだが、そうした社会性のあるテーマがあることを知った。
続けてラジオからは、サイモン&ガーファンクルの "The Boxer"、夏になるとゼーガー&エバンスの"西暦2525年"が流れてきた。
どちらもデュオだが、ギターを伴奏にハモっている点でフォーク・ソングと思った。
そして年を越した1970年の早春、イージーライダー〜Byrdsの "Wasn't Born To Follow" に出会うわけである。
その後、Byrdsのレコードのライナーズノートや音楽雑誌から、Byrdsはフォーク・ソングを出自にしていること、1960年頃にアメリカではフォーク・リバイバルというブームがあったこと、それが日本にも飛び火していた事を知った次第である。
1960年頃と言えば、日本では日米安保条約で揺れていた時代であり、社会性のあるテーマを歌うという点でアメリカで起きていたフォーク・リバイバルが日本に飛び火していた事、1969年を頂点とする学生運動やフォーク集会という言葉が少しづつ繋がってきた。
純粋な音楽としての楽しみとは別の一面が見えてしまったことで、筆者はフォーク・ソングを少し距離を置いて見るようになった頃であった。
それはByrdsのラストアルバム、"Farther Arong" の中の "Farther Along" や ”Bristol Steam Convention Blues" である。
ライナーズノートによると、ブルーグラスとのことで、マンドリンや5弦バンジョーが印象的であった。
高校2年は1972年、それが切っ掛けで当時、日本公演を行った "Ralph Stanley & The Clinch Mountain Boys"*2 や "Country Gentlmen"*3 を聴くようになった。
ブルーグラスは戦後、1945年頃からブームになったまだ日の浅いジャンルであり、その素材はアパラチアン山脈周辺のトラッド・フォークが多数あることを知った。
1960年頃にはロカビリーやロックンロールに押されて下火になりかけたが、フォーク・リバイバルの影響で再びスポットライトが当った事も知るようになった。
この頃、アパラチアン周辺のトラッド・フォークと言っても、どうも社会性のあるテーマとは違うなという印象を持っていた。
しかしながら、筆者が山歩きを始めて奥多摩の山々を尋ねて地元の人の話を聞いているうちに、過疎、林業の衰退、水源林維持の難しさといった問題があることを知らされた。
街や都市に限らず、山の中にも社会性のあるテーマがあることを知ると、急にトラッド・フォークの素材に興味が湧いて来た次第である。
そしてBob Artis著、ブルーグラスを読むことで、トラッド・フォークには火事、洪水、事故、殺人事件、心中事件といったテーマが歌われていることを知るようになった。
そうすると、ウディ・ガスリー、ピート・シーガーの曲が歌われていた反戦、公民権運動と言ったようなテーマが20世紀とすると、トラッド・フォークは19世紀のテーマであったことを知った次第である。
そうしたことで、筆者にとってフォーク・ソングはさらに大きな広がりを感じるようになった。これは既に社会人となった1980年代の事であった。
*1

*2

*3





その2:フォーク・リバイバルからフォーク・ロックへ
ウィキペディアによると、彼はアメリカ議会図書館のディレクターで、全米各地のトラッド・フォークを収集、録音してきたとのこと。
多民族国家、アメリカの凄いところは、祖先の出自を徹底的に辿って保存するところであろうか。
ウディ・ガスリー、ピート・シーガーも彼が収集してきたトラッド・フォークを聴きながら、祖先は何を歌ってきたのか、自分が何を歌うべきかを知ったようである。アランもそういう彼らをサポートしていたとのこと。
日本にもアランに近似した人物として音楽学者、小泉文夫(1927〜1983)がいるが、彼は戦後、昭和の時代に活躍した世代である。
筆者が高校2年の時、彼が担当していたNHK-FMの "世界の民族音楽" は良く聴いたものである。
そのなかでもインド音楽はビートルズを始め、ローリング・ストーンズ、スコット・マッケンジー等の曲で使われていたシタールが呼び水になり、かなりの人が聴いていたようである。
日本のGS、テンプターズもストーンズのブライアン・ジョーズの影響を受けて松崎由治が弾いていた。
1950年代後半から60年代前半に掛けて、民謡で鍛えた咽と津軽三味線がレコーディング・ディレクターの眼に止まり、デビュー早々にヒットしている。
そもそも、のど自慢や民謡コンクールというものが日本にはあり、聴き手も一定の需要はあったのだが、一躍ブームとなった時期はアメリカのフォーク・リバイバルとほぼ同じ頃である。
これは戦後復興から高度成長期を前に、地方から続々と上京した若い世代の需要に支えられたものであった。
ただ、一度廃れていた訳ではないのでリバイバルとは少し違う。
そういう意味ではアパラチアン周辺に定着したアイルランド系移民の需要に支えられて発展したカントリー・ミュージックの方に似ているかもしれない。
一方、日本の民謡ブーム〜歌謡曲化の流れやアメリカのカントリー・ミュージックの隆盛は一般庶民やブルーカラーの需要に支えられていたように思える。
そしてキグストン・トリオやブラザース・フォアの登場により、次第に一般リスナーに需要は拡大して行ったようである。トラッド・フォークからモダン・フォークへの流れである。
日本の大学でもフォーク・ソング部が活況を呈し、フォークソング・コンテストのようなTV番組が生まれて行った状況は、こうしたモダン・フォークを咀嚼吸収した結果と言えよう。
また、カルメン・マキのデビュー曲 "時には母のない子のように" は、アフロ・アメリカン・スピリチュアル "Sometimes I Feel Like A Motherless Child" を基に寺山修司が作詞している。
こうした例はアラン・ローマックス、フォーク・リバイバルに倣ったものと言えるかもしれない。
また、先述の ”帰って来たヨッパライ” だが、アルコール依存症は万国共通のテーマらしく、アメリカのトラッド・フォーク "Drunkard's Hell"、 "Drunkard's Dream" の日本版と思われる。いずれも説教臭いところが良く似ている。
一方、フォーク・ソングの中にはそうした背景や知識無しに、無意識に歌っていた例もあるようである。
筆者がボーイスカウトで歌った "山の教会" は アパラチアン由来の "Old Country Church" であり、教会の賛美歌と共に渡ってきたものであることは近年になって知った次第である。
ボーイスカウトは英国のバーデン・パウェルが創設者だが、青少年育成以外にも野外活動、キャンプを体験させる事で、サバイバル能力が養われること、大人も指導力養成や社会貢献の場として参加できるなど、困難な時代にこそ希求されるものが揃っている組織と言える。
キリスト教会の青少年活動と重なる部分があり、教会を集会所として活動する例が多かったことからアメリカでも直ぐに普及した。そうした背景から活動の中でフォーク・ダンスや歌唱が日常的に行われ、自ずと讃美歌や聖歌が歌集に載る例が多かったようである。
実際にこうした歌にはトラッド・フォークが含まれており、子供の頃に刷り込まれたものは生涯消えないようである。
その中にはブルーズのようなアフロ・アメリカン系やネイティブ・アメリカン系、アジア系も含まれていたと思われる。
特にブルーズはアイルランド系のようにルーツをどんどん辿って行けるようなものとは異なり、突然変異的に現れたものと言えないだろうか?
アランが収集した録音の中ではレド・ベリー(1888〜1949)が良く知られている。
こうしたアフロ・アメリカン系は一般には音楽のジャンルとしてブルーズと呼ばれていたようである。
そうしたブルーズの素材はアメリカではなく、ヤード・バーズやエリック・クラプトンと言ったようなイギリスの若い世代によって磨きを掛けられていったようである。
ブルーズコードと言われるコード進行に沿ったギターを伴奏に、その日、その時の気分を歌ったものが、いつしか "Public Domein=詠み人知らず" となって伝承されてきたようである。
ブルーズには "3分間の暴動" と言う喩えがあるが、差別を受けたり底辺の人々の感情の発露であることが頷ける。
ジャズにおける ”ブルーノート” とは音楽理論として定義されることもあるが、感情、気分〜モーダルというように本来、定義不可能な部分はブルーズのエッセンスではないだろうか?
いわゆるブルーズ・コードは3つのコードを知っていれば良く、トラッド・フォークの中には ”モーダル” が煮詰まってきたのか、2つになったり、とうとうコード進行無し=モノコードで歌われる例も聴かれる。
道路のカーブに沿わず、ハンドルを殆ど切らずに道端の雑草を蹴散らすような強引な運転に喩えられるかもしれない。
このように僅かなコード伴奏で歌おうとすれば、基音に対して4度、5度の音を中心に歌われることになる。
この4度、5度の音はドローン=通奏音と呼ばれるように、常に鳴っている(聴こえている)状態になる。
こうした特徴は日本では数え歌のような例や、ネイティブ・アメリカンの古謡、アパラチアン周辺のいわゆるマウンテン・トラッドにも見られる。
このドローンは、メジャーにもマイナーにも聴こえることがあり、聴く者はその時の気分や歌詞の内容によっていかようにも受け取ることが出来るように思う。
アラン・ローマックスはアメリカ大陸以外ではイギリス、アイルランド、イタリア、スペイン、カリブ海地域にも収集に出掛けており、ドローンという性質は民族を問わない普遍的なものと感じていたかもしれない。
スティブン・スティルスはアパラチアン周辺のマウンテン・トラッドを思わせる "Find The Cost Of Freedom" を初め、ドローンを意識的に使ったオープン・チューニングによるギター伴奏を得意としていた。
アパラチアン周辺では4弦バンジョーに第5弦が追加されたり、アイルランドから移住後に現地で制作されるようになったマウンテンダルシマの複弦、インドのシタールの共鳴弦、琵琶、三味線のさわりも、歌の伴奏としてのドローン効果を得るための仕組みと言えるかもしれない。
シタールのシは3、タールは弦を意味し、日本の三味線、琵琶、沖縄の三線、ロシアのバラライカ等、3弦楽器は世界中に分布する。
調弦はバリエーションはあるが基本的には4度、5度となっている。これは歌の伴奏に具合が良いように自然に落ち着いたものと思われる。
1960年のジョーン・バエズ、1961年のボブ・ディランのデビューアルバムでも取り上げられ、1964年にイギリスのアニマルズがカバーしてヒットした "The House of Rising Sun" 邦題:朝陽のあたる家、はそうした例に思われる。
蒸留酒=スピリッツに自分のモードに合った果汁や炭酸を加えたカクテルに喩えられるかもしれない。
こうしたカバー曲はレコードレーベルに印刷されている作者=版権が、"P.D.=Public Domein" となっている場合も有るが、名前が記載されていれば、カクテルにも著作権があるという意味合いかもしれない。
P.D.では印税は誰にも支払われないが、そうした意味ではコードの補足は重要な意味合いがあるように思える。
原曲に敬意を表するという気持ちでも、”う〜ん、違うんじゃないの?” というケースもある。
時事問題や事件を歌ったものならば事実の伝承という意味合いが強いかもしれない。
しかしながら伝承されるべきものが歪曲されて残ったり、いつしか埋もれてしまった曲もあったかもしれない。
そう考えるとアラン・ローマックスの仕事やフォーク・リバイバルの意図はやはり "発掘" ではなっかたか?
原曲は極、限られたコードによる伴奏で歌われているので、自ずと歌っている内容〜歌詞の方に光が当る。
社会性を持ったテーマやブルーズのように心情に共感できるような曲に光を当てるという事になろうか?
旋律より歌詞となると、コードを付け足して行く作業はどう見ればよいのだろうか?
歌詞の内容によってメジャー・コードになったりマイナー・コードになったり、カウンター効果としてあえてひっくり返したりすることも考えられる。
そう考えると、フォーク・リバイバルは様々なコード進行を生み出す実験場のような役割を果たしたように思える。
デイビッド・クロスビーはCS&Nのドキュメンタリービデオの中で、フォーク・リバイバルを回顧して、"great chord change" という言い方をしていた。
ピアノのような鍵盤楽器でもコード進行は探索できるが、そうした作業はギターの方がやり易いという人も居るかもしれない。
フォーク・リバイバルに伴うギターの普及によってそうした作業はピアノを持っていなくとも誰でも経験できるようになったようである。
そのような意味でもコード進行の重要性、多様性、あるいはコード進行をフォローする形でメロディが付いて来るという事がフォーク・リバイバルを通して認識されていったように思える。
こうしたコード進行=カクテルの増殖によって、トラッド・フォークはポピュラー・ミュージックになり得る可能性がキングストン・トリオやブラザース・フォアによって示されたのではないだろうか?
1973年にアメリカのCapitolレーベルからデビューした "East"*2 は "Beautiful Morinig" で日本でも注目されたが、筆者はどこか "朝陽のあたる家" を連想するし、ここで使われているコードを引き算してゆけばマウンテン・トラッドにも聴こえる。
そしてオープン・チューニングによるアコギのストロークも聴かれる。
"East" の前身は学生フォーク・グループであった "ニュー・フロンティアーズ" であり、フォーク・リバイバルの洗礼を受けて来たことは間違い無いであろう。
この"Beautiful Morinig" は雅楽の笙、篳篥そして箏がイントロに使われており、彼ら流の日本のトラッド・フォークの解釈、カクテルと言えるかもしれない。
*1

*2





その3:ロジャー・マッギンの憶い?
ただ、Folkは民謡というより民族音楽といった意味合いではないかと思われる。アラン・ローマックスのような "発掘作業" やアメリカのFolk史について学んだり、プロ歌手のバックのような就職口の斡旋もあったと思われる。
当然ながらフォーク・シンガーとして活動し初め、"Bob Gibson" に強く影響されたと語っている。
1961年には "Limeliters"、"Chad Mitchell Trio" のバックでギター&バンジョーを伴奏しているところから、19歳でプロの道に入ったことになる。
その後、歌手、"Bobby Darin" が歌う曲の版権を管理する会社で働くことになったのを見ると、アレンジャーのような仕事を任されていたようである。
それが1963年とのこと、もれなく21歳の若者にビートルズは抗し難いインパクトを与えたようである。
直ぐに同じ様な若者、デイビッド・クロスビー、ジーン・クラークと出会う訳だが、デイビッドはフォーク・シンガー "Odetta" を、ジーンはエルビス・プレスリー、ハンク・ウィリアムズ、エバリー・ブラザーズを聴いてきており、カントリー・ミュージックに親しんできたようである。
マッギンはビートルズのような活動をしたいと望んだかどうかは判らないが、ここからはロジャー・マッギンのフィクション・インタビューである。
・
僕ら3人はアコギやバンジョーを弾いてきたけど、エレキにアレルギーはないし、時代が変われば音も変る。
・
ビートルズはロックンロールというのは判るけど、彼らの中にもキングストン・トリオやブラザース・フォアのような一面もあるでしょ。
・
彼らのレコードのレーベルに印刷されている版権を見ると、"Lennon & McCartney" になっているんで、最初はどちらの作品かは判らなかった。
でもだんだん判ってきたんだ。
・
ポール・マッカートニーは同じ1942年生まれなんだけど、彼はメロディが先にあるようだね。
・
ジョン・レノンは1940年生まれで、彼はコード進行が先にあるようだね。
・
どっちもフォーク・ソングには無いヒット性を感じたんだ。
・
デイビッドもコード進行の事を言っていたけど、彼はまだフォークのセンスに拘りがあるようだった。
・
そこへ行くとジーンはビートルズ風なコード進行を探索し始めて、ヒット性のある曲が出来そうだった。
・
僕もメロディアスなフォークというのは何か違うなと感じていた。
・
だからなんとなく3人の役割分担が見えてきたんだ。
・
僕らはボブ・ディランと同じColumbiaレーベルになったのはフォークという括りだったんだと思う。
Columbiaの中で彼の曲をアコギとエレキでやるのは一つの解だったと思うし、ビートルズじゃできないでしょ。


レコードのライナーノートに書かれた、ディランのデモテープを聴いたマッギンの表現によると、めそめそした感じだったそうで、筆者はByrdsのハーモニーはそうした感じは微塵も感じられないが、ヒット性がある曲とは思えなかった。
プロデューサー "Terry Melcher" のサウンドの狙いは判るが、歌詞は意味不明でオチがどこにも無い。
当時はドラッグ・ソングでは?という説もあったようだが、ディランのレコーディング時のバックミュージシャン、Bruce Langhorne=ブルース・ラングホーンの事を歌ったものだったと判ったのは2008年の事であった。
ブルースはアフロ・アメリカンで、普通のタンブリンではなく、本革を張った巨大なタンブリンを使っていたとのこと。すっかりディランのマジックに嵌められた感じがしたものだが、個人的な心象を書き残すと見ればフォーク・ソングなのかもしれない。
エレクトリックサウンドとディランの曲であるという理屈でフォーク・ロックに括られたような気がする。
マッギンはこの事を知っていたかどうかは判らないが、彼流の ”発掘” であったのかもしれない。
アルバムとしての選曲はトラッド・フォークには見られないコード進行を持つジーン・クラークの作品が多い。
ジーンのコード進行だが、ポップスやポール・マッカートニーの曲のように使われるコードをベースラインに沿って細分化したような=マルチコードとは違い、
まだフォークらしいシンプルさを残しているように感じる。
しかしながら、気分=モードの変化を意識したコードの組み合わせ方を探索しているようにも思える。遺伝子の塩基配列A,G,C,Tの並び方に似ているかもしれない。
先述のデイビッド・クロスビー曰く "great chord change" とはマルチコードというより配列のニュアンスが強いかもしれない。
一方、フォークらしいシンプルコードのディランの "Chimes Of Freedom" を入れているところは頷ける。同じColumbiaレーベル内でヒットの相乗効果はあったのだろうか?


この曲こそマッギンの意図したフォーク・ロックだったのではないかと思う次第である。
映画、フォレスト・ガンプの中でも登場するが、反戦集会に戦場の証言者として登場するガンプと幼なじみの彼女 "ジェニー" が偶然再会して別れるシーンは文句なく嵌っている。
その前段、
ガンプがベトナムへ出征する時に、ジェニーがディランの "Blowin' In The Wind" を歌うシーンを憶い出させる。ロバート・ゼメキス監督の演出はフォーク・ロックの意図を余すところ無く伝えているように思う。
この2作目でもジーン・クラークの曲はオリジナリティを発揮しているが、マッギンの ”発掘” はディランの "The Times There Are A Changin'" 邦題:時代は変わる、で締めが効いているように感じる。
この初期の2枚のアルバムはプロデューサー "Terry Melcher" の意図するサウンドは明快であり、同時代のディラン作品を ”発掘” することで,
もはやフォーク・リバイバルの時代では無いことを示したように思う次第である。




その4:前期Byrdsの舞台裏は? 
プロデューサーはColumbiaレーベルの西海岸担当副社長でもあった "Allen Stanton" に代わった。
タイトル曲の "5th Dimension" はマッギンの作だが、Byrdsにおいて作詞、作曲両方を手掛けているのは "Mr.Spaceman" 、"Ballad Of Easy Rider" 、"I Trust"、"Born To Rock'n'Roll" とこの曲だけである。
本作に収録された "Eight Miles High" と共にドラッグ体験、ラガ・ロック、サイケデリック・ロック、スペース・ロックなど、様々な評が音楽雑誌を賑わしていたようである。
"5D" はマッギンによるとアインシュタインの相対性理論からインスパイアされたとのこと。彼は宇宙旅行にも興味があり、一般向けの科学雑誌を読んでいたようである。
前2作はジーン・クラークとディランの比重が大きかったが、ここでマッギンらしさが出たように思う。
その時々の事件や出来事にインスパイアされたと見ればマッギン流のフォーク・ソングなのかもしれない。
トラッド・フォークには見られないコード進行だが、筆者は1962年に "Tormados" がヒットさせ、ベンチャーズやスプートニクス等にカバーされた "Telster" を連想してしまう。
バックの "Van Dyke Parks" が弾くキーボードも "Telster" で使われた初期の電子楽器、クラヴィオリンが脳裏に有ったのかもしれない。
"I See You"はクロスビーとの共作になっているが、 "What's Happning?!?!" と同じく恐らくクロスビー流のコード進行ではないか?
ドラッグ体験と評されて放送禁止にまでなった "Eight Miles High" だが、コルトレーンにインスパイアされたと評されるマッギンのリッケンバッカー12弦のリックは確かに唯一無二のサウンドではある。ボーカル部分のコード進行も違和感は無いが当時としては普通ではなく、これもクロスビーのアイデアではないか?
そして問題の歌詞であるが、腑に落ちたのはジーン・クラークのファン・サイトを見た2017年の事であった。
Byrdsのレコードのライナーズノートに依ると、ジーンは飛行機恐怖症が原因でツアーに耐え切れず "5D" リリース後に脱退したとの事であったが、彼のファン・サイトによると閉所恐怖症であったとのこと。
版権はクラーク、マッギン、クロスビーの共作になっているが、飛行機搭乗中にジーンが漏らした? "stranger than known=奇妙な感じ" がソースになっているらしい。
不貞の妻を射殺して逃走した男を歌ったもので、事件としてあったかどうかは定かではないがアパラチアン・トラッド・フォークにありそうなテーマである。そのようなところが多くのミュージシャンを惹きつけるようである。
ウィキペディアによるとこの曲はByrds結成当初からクロスビーが録音したかったものの、他のメンバーが乗り気しなかったとのこと。どこかお行儀の良いByrdsのイメージには合わない曲だったのかもしれない。
前者はロッド・スチュアートや "Tannahill Weavers"、"Iona"のようなブリティッシュ勢にもカバーされているが、コード進行はByrdsと同じところからするとマッギンの発掘の効果は大きかったようである。
後者はジョーン・バエズが1960年のデビューアルバムでカバーしているが、そのコード進行を踏襲している。
この2曲にはストリングスが被さっている。"Allen Stanton" のアイデアと思われるが、その後 "Terry Melcher" がプロデュースに戻った8作目 "Easy Rider" までストリングスが被さる例は見られない。
マッギンは作詞はするがトラッド・フォークへの興味ゆえか、作曲、コード進行にはあまり拘りが無いように伺える。このアルバム以降、作曲はクロスビー、クリス・ヒルマン、 "R.J.Hippard" や "Jacques Levy" との共作が増えてゆく。
"Wild Mountain Thyme" の版権は本来P.D.であるが、レコード・レーベルにクロスビー、ヒルマン、マッギン、(マイケル)クラークの4人の名前を記したのは以下の理由が考えられる。
・コード進行に関してクロスビー、ヒルマン、マッギンの誰かのアイデアが入っている。
・演奏アレンジに関する誰かのアイデアが入っている。
・映画やテレビで使われる場合に印税を徴収する事が出来るが、その可能性(大ヒットになる)はあまり高くなさそうである。
・仮に現れた場合、印税収入は4人の均等割りにする為の意思表示とも取れる。
日本でもヒットし、学生フォーク・グループの必修曲になっていたが、GSのスパイダースもカバーしており、井上 順のボーカルに大野 克夫のペダルスティールギターが聴かれる。


特にクリス・ヒルマンの活躍が目立ち、マッギンとの共作による"So You Want To Be A Rock'n'Roll Star" が印象的であった。
"Have You Seen Her Face" はそれまでのByrdsには見られなかったビーチ・ボーイズ風味。
カントリー・テイストだが "Time Between"、"Girl With No Name" は湿度のあるナッシュビル風味ではなく、からっとした西海岸を感じさせる。
"Thougth And Words" のベースラインは半音ずつ下降するもので、因みに、日本では富田勲による1970年のTV時代劇、柳生十兵衛のオープニングテーマがこれを用いている。
そしてこれが循環するかと思いきや、展開部でポップなコードを挿入するなど粋な印象を持ったものである。こうしたコード進行はマッギンやクロスビーには見られないもの。
加えてヒルマンの歌詞はシンプルかつ韻が小気味良くノリが良いし、ソングライターの資質があったように感じる。
デイビッド・クロスビーも "Everybody's Been Burnes" 、"Mind Gardens" で個性を発揮し出したようである。
後者はテープの逆回転を使っているが、モノ・コードによるアコギの伴奏の周りをクロスビーの節回しが自在に飛び回る様は今聴くとどこか民族音楽のように感じる。
"Renassance Fair" , "Why" はマッギン+クロスビーの共作だが、コード進行とハーモニーボーカルはクロスビーのアイデアと思われる。
"C.T.A.-102" はマッギン+R.J.Hippardの共作で、テープの早回しと逆回転を組み合わせた宇宙人の会話は笑える。これが ”帰って来たヨッパライ” にパクられたということかもしれない。
マッギンにしてみれば。このような多彩さでアルバムを作り上げるのは一人では困難だし、トラッド発掘?というコンセプトは薄くなったように見える。
あるいは加速度が付き始めて留めておくべき時代の記録というより、時代を追い越してしまいそうになったのかもしれない。
Byrds自身にとってもブラックホールに向う宇宙船のように、自分たちの航跡が見えなくなってしまうような感覚に囚われたのだろうか?
ディランの "Younger Than" を入れたのはそれを食い止める命綱=アンカーだったように思える。
それにしてもこの頃にはディランもコード進行を意識するようになっていたように伺えるのだが.....
Byrdsデビュー前の60年代前半にサーフィン・ホットロッドと言ったジャンルを陰で支えていたミュージシャン、ソングライター、プロデューサーであったということを知ったのは90年代に入ってからであった。
このアルバムは前3作とはがらっと音が変わったように感じた。それはヒルマンのベースが良く聴こえるようになった事と、鳴っている音が整理されてクリアになった事である。
1966年のビートルズのアルバム "Revolver" からポールのベースでも同様な変化が見られたのだが、これはレコードのカッティング・マシーンの改良により針飛びを誘発し易いエレクトリック・ベースを高いレベルで記録できるようになったことに因るもので、坦々とベースラインを刻むだけでないメロディアスなプレーもそれを意識したようである。
このようにベースが明瞭に聴こえるのは同時にマルチトラックによる多重録音が導入されたという事だが、ビートルズのアビーロード・スタジオでは4トラックだったそうだである。
この時期に "Gary Usher" が契約していたColumbiaスタジオでもすぐさま導入されたようだが、彼もこの扱いに気を使ったように伺える。
前作まではマッギンのリッケンバッカー12弦のピック奏法とバンジョーのフィンガーロールの組み合わせによるジングル・ジャングルサウンドと、クロスビーのコードストロークによって賑やかなサウンドであったが、本作ではギターは1本の弦による単音、あるいは2本の弦による和音リード奏法に変わってきた。"Renassance Fair"、"Thougth And Words" が好例である。
これは丁度ピアノ伴奏で左手がベースパートとすると右手の装飾音の関係に似ている。
リズムギターのコードストロークではなくとも、明瞭に聴こえるベースラインと必要最小限な装飾音があればコード進行を印象付けられ、ボーカルハーモニーの邪魔をしないという利点もあるように思える。
また、"So You Want To Be A Rock'n'Roll Star" や "Younger Than" の間奏のリードギターもピック奏法だけになっている。
それまでのバンドアンサンブルとしてのギター奏法は一発録音では不自然さはないが、多重録音でそのまま重ねると音が濁ってかつ、煩く聴こえて仕舞いがちである。こうした試行錯誤を経た結果だったのだろうか?
Byrdsはフォーク・ミュージックを出自としており、6、12弦フォーク・ギターをエレキ化してもフォークの証を残しているような印象を持っていたのだが、 "Gary Usher" のサーフィン・ホットロッドのエレキによる音造りの経験が生かされているのかもしれない。
ギターの1本の弦による単音、あるいは2本の弦による和音リード奏法だが、これを重ねに重ねた造りは1976年のイーグルスのホテル・カリフォルニアで頂点を迎えたのではないだろうか?
当時のトラック数は24まで増えて行き、アイデアはどんどん湧き出したようである。
リードギタリストのドン・フェルダーとジョー・ウォルシュは坦々とこなしたと思われるが、これをプロデュースしたマイアミはクライテリアスタジオのビル・シムジクも音が濁らないように念入りに下ごしらえをしたものと思われる。


後にクロスビーが途中で脱退する事態になっていたことを知ったのだが、彼の自叙伝にはその時の様子が生々しく語られている。ネタバレは避けたいが、最後はレコーディングスタジオの中では無かったそうである。
音楽雑誌やウィキペディアでは背景といきさつが流布しているが、ここでは本アルバムの製作過程の様子を想像してみた。
・
エンジニアのRoy Haleeです。プロデューサーのGaryに声を掛けられたんだけど、皆さんよろしく。
"Younger Than Yesterday" を聴いて思う所があってね。
僕はサウンドイフェクトのアイデアが湧いて来たんだ。
是非一緒にやらしてくれないか?
・
有り難う。僕たちもまだ何かやり残したような気がしていたんです。
・
それは良かった。僕もオーバープロデュースは望んでいないが、皆さんのアイデアとスキルは必要なんだ。
・
さあ、選曲しなきゃね。どれだけ集まるか?
・
"Younger Than" はエキサイティングだった。あんなふうに出来るなんていい経験になった。
・
"Goin' Back"(Gerry Goffin&Carole King作)を入れるのかい? トラッドのP.D.をカバーするなら判るけど、僕らと同世代の曲じゃないか。
・
いや、同世代でも共感できるなら発掘したいんだ。
・
彼らに稼がせるのかい? 僕らが発掘しなくたって朝陽はもう当っているし、もう職業ライターの時代じゃない。
"Tapestry" は時代を代表する大ヒットとなり、カーリー・サイモンやジョニ・ミッチェルのように女性シンガー・ソングライターとして認知された訳である。
フォーク・リバイバルの時代はトラッド・フォークを発掘して歌う、歌詞やコードを替えて歌う=フォーク・シンガーという見方があったようだが、次第にオリジナル曲を歌う例も出始めてきた訳である。
歌っている内容が時事性のあるものや、事件、社会に対する批判や主張、比喩が感じられればフォーク・シンガーという範疇に入れられたようである。
一方、歌詞が漠然としていたり、現実と非現実の境が曖昧だったり、詩的〜私的な内容の曲がビートルズやボブ・ディラン、Byrdsにも見られるようになって行く。
そうした状況の中で、マッギンは "Goin' Back" の中にポップスとは言い切れない、フォークのセンス、それまでの職業ライターとは違う気配を感じていたのではないだろうか?
筆者は今になると、同じコンビの作になる "Wasn't Born To Follow" もそういう気配を感じる次第である。
クロスビーもフォーク・シンガーから出発しているが、Byrdsでマッギンと共作するうちに独特で私的な内容の曲を書くようになっていった訳である。
この "Goin' Back" はキャロル・キング自身を含めて、Dusty Springfield、Diana Ross、Phil Collins等、時代を跨いで多彩なカバーが聴かれるのだが、筆者もポップスとは言い切れないような冒頭のコード進行が気に掛かっている。
筆者はこのフィーリングはクロスビーがグラハム・ナッシュとコンビを組んだ1975年リリースの2ndアルバムの冒頭の曲、"Carry Me" と通じるものを感じる次第である。
クロスビーも内心、キャロル・キングのセンスを感じ取っていたのではないだろうか?
プロデューサー "Gary Usher" のアイデアなのだろうか? 4作目 "Younger Than Yesterday" ではクリス・ヒルマンの楽曲とそれを支えるスタジオ・ミュージシャン、クラレンス・ホワイトのテレキャスターがカントリー・テイストを醸し出していたが、この2曲はそれとは少し違う。
バーのスライドによって音がベンドする様が心地よく、サイケデリックな色合いにも感じられる。
こうしたペダルスティールの使い方はクロスビーがCSN&Yの ”Deja Vu” 時代にリリースしたソロアルバム、”If I could Only Remember My name” でも聴かれるし、近年のソロアルバム、2014年の "Croz"*2、2017年の "Sky Trailes" でも聴かれる。
そんなところから、ひょっとするとクロスビーのアイデアだったのかもしれないし、"Gary" のアイデアであったにせよ、クロスビーは気に入っていたのかもしれない。
ペダルスティールはこの他 "Get To You" でも聴かれるが、この曲相はカントリーとは無縁に感じられる 。
もう一曲、"Change Is Now" は連帯を呼びかけるフォーク・ソングのように感じたが、サビの部分でカントリー調のリックが出て来るところは、初めて聴いた時には万華鏡のような感じがしたものである。
ムーグ・シンセサイザーも使用されているのだが、当時はまだ未知の音色で気が付かなかった。
”快感” と感じたのは ”フランジャー” や ”フェイザー” と呼ばれていたフェイズ・シフト=位相操作によるジェット機が通過してゆく際に体験するあの感覚である。
スタジオでサウンドイフェクトを施していった点では同時期のビートルズと比較されるようだが、Byrdsの方が大胆で筆者は ”アメリカ流” を感じさせられたものである。
この"ジェット・サウンド" だが、テープレコーダーが登場した初期に、走行しているテープの縁を指で軽く触れると同じような効果が得られることが発見され、録音エンジニアの間では "フランジング" と呼んでいたようである。
原理的には二つの同じ音を極僅かに時間差を付ける〜お互いの位相を変化させればよく、それを指ではなく2台のテープレコーダーの再生ピッチを変化させる方法が考案されたようである。
ジョン・レノンはこれをアビーロード・スタジオのエンジニアから聞かされて、自分でテープの縁に指を当てて試行錯誤していたようである。 "Back In The U.S.S.R." でもジェット機の音が被さっているが、音は揺れているものの位相がずれていく感じにはなっていない。
もうひとつ印象的だったのは "Natural Harmony" で使われたボーカルの音色操作である。今ではパラメトリック・イコライザーと呼ばれてミキシング卓に常備されているが、電話の受話器を通して聴いた様なキンキンした声や鼻をつまんでくぐもった声が時間と共に変化してゆく様である。
当時は音響フィルターを駆使していたようだが、2000年代に入ってからこうしたイフェクトを掛ける例が見られるし、60年代当時のサイケデリック・サウンドのリバイバルというニュアンスかもしれない。
エレキギターのフレット上の弦を指でランダムに叩いたような感じなのだが、マッギンかクロスビーか偶然やって録音されていた音源を使って作り出したのではないだろうか?
"Notorious" ではエンジニア、"Roy Halee" が参加しているが、"Gary" も彼の手を借りたものと思われる。
"Roy" はColumbiaレーベルのエンジニアであったが、同じレーベルだったサイモン&ガーファンクルの "Book End"、"Bridge Over Troubled Water" でも多大な貢献をしている。
Byrdsのメンバーはミキサー室に入る事を許され、作業の様子を見ていたのだろうか? マッギンはこうした事に興味があったようだが、他のメンバーはどんな反応を示していたのであろうか?
筆者が初めて聴いた当時は未だメンバーの詳細やその資質までは判らなかったのだが、今振り返ってみるとこのアルバムに選曲された11曲のうち、10曲の版権にヒルマンがクレジットされているのである。
ヒルマンはByrds結成にあたり、ブルーグラス・バンドでマンドリンを弾いていたところをベース担当として引き抜かれたのだが、前作 "Younger Than Yesterday" でマッギンやクロスビーからソングライターの資質を認められたのであろうか?楽曲が提供できるメンバーが多ければ選曲の際は難産を避けられ、報酬分配は揉め事が少ない。
マッギン、クロスビーとの共作が殆どだが、そのうちの1曲 "Natural Harmony" はヒルマンが一人で手掛けたものである。
この曲は彼のルーツであるカントリーとは無縁で、コード進行はサイケデリックな雰囲気が溢れている。こんな曲も書けるんだという思いを新たにする次第である。
レーベルに印刷されている版権は作詞・作曲が区別されていないので、どの曲がヒルマンの作曲なのか曖昧だが、例えばクロスビーらしさが出ている "Draft Morning"、"Tribal Gathering" 、"Dolphins Smile" のコード進行はもしや、ヒルマンのアイデア?
また、"Draft Morning"でバックにドローンのように鳴っているマンドリンだが、これはプロデューサー "Gary Usher"のアイデアなのか判らないが、ヒルマンが居なければ出来なかった作品であろう。
このアルバムではクロスビー作の "Triad" が選曲から外されたことは良く知られているが、これは次第に大きくなってきたヒルマンの重力という見方は如何だろうか?
*1

*2
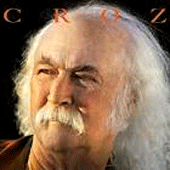




その5:ロデオの恋人のご機嫌は?
マッギンは彼がキーボードが弾けるということで採用したと言われているが、まさかムーグ・シンセサイザーをライブ演奏でやろうと考えていたのだろうか?ブリティッシュ・ロック勢ならそうしたアイデアはあったようだが、実現していればポピュラー音楽史は大きく変わっていたかもしれない。
筆者はアイルランド系移民のトラッド・フォークがルーツにあるという点、お互いにアイリッシュの家系である点でマッギンは直ぐに腑に落ちたのではないかと思われる。
アイルランド系移民を始祖にアパラチアン周辺に棲み付いた人々の中からカントリー・ミュージックが興き、マッギンの家系のようにシカゴのような都市に移り住んで行った人々の中からフォーク・リバイバルが興きたという見方も出来るように思う。
グラムはフロリダ産まれでジョージア育ちのいわゆる南部の気質と言えば良いだろうか、カントリー・ミュージックに馴染んできたようで、そうした違いも二人は腑に落ちていたように思える。
マッギンは著名なジャーナリストを両親に持ち、グラムは南部の裕福な家に育ち、音楽の道にドロップアウトする前にハーバード大学へ進んでいる点でインテリ気質が共通するように思える。
マッギンはシカゴのフォーク・ミュージックスクールでアラン・ローマックスのような学術的な視点を学んでいただろうし、グラムは "カントリー・ミュージックの本質は酒と涙と男と女にあり" と見抜いていたように思える。


前作 "Notorious" であれほど斬新な作品をリリースしたのに、拍子抜けを通り越して理解不能なアルバムに当時は聴こえたのかもしれない。
リスナーはロックの進化を期待していたのかもしれないが、出て来たのはライナーノーツのマッギンの言葉を借りれば、20〜25年くらい前の古いナンバーとのこと。
ここからマッギンの意図はやはりフォーク・リバイバル=発掘の線上にあったと言えるのかもしれない。
ただ、イージーライダーの中でも使われていた "Fraternity of Man" の曲 "Don't Bogart Me" と同じジャンルという認識を持った次第である。この曲はペダルスティールギターを用いたカントリー・ナンバーであった。
この曲は主人公達が牛が牧草を食む姿が見えるテキサス州辺りにやって来たシーンに流れ、長閑な感じにぴったりの曲だと感じたものである。
まだ中学生だった当時は何を歌っているのか判らなかったが、この歌詞が "joint=マリファナ" を廻し吸う場面であったと知ったのは学生時代である。
ウィキペディアによると "Fraternity of Man" はカントリーではなく、60年代のブルーズ・ロック、サイケデリック・ロックバンドだったとのこと。
"Steppen Wolf" がこの映画の冒頭で "Pusher =麻薬取引人" を歌った曲がロックナンバーなら、そのカウンターとしてカントリー・ミュージックで応えたものであろう。
この映画のテーマでもあるが、"マリファナを吸う様な輩は袋叩きだ!" という南部の人に向けて、彼らが好きなカントリー・ミュージックで茶化したような曲を持ってくる演出は憎いものがある。
当時は判らなかったがそうしたカウンター・カルチャーを知ることで、今では "Sweethert" はカントリー・ミュージックを真摯に演奏する姿勢であったことが理解できた。
プロデューサーの "Gary Usher" もマッギンとグラムの意図を汲んで手腕は揮わなかったのかもしれない。
ただ、残念な事はリリースされた1968年の時点ではカントリー・ミュージックには冷めた見方や、偏見があったのではないだろうか?それもマッギンとグラムは覚悟の上のプロジェクトだったように思える。
グラムはそうした当時の状況からブルーズがアフロ・アメリカンに対する差別なら、カントリー・ミュージックは白人の内なる差別と感じていたのではないだろうか? 彼は "Cosmic American Music" という言葉を残して1973年、26歳の若さでこの世を去ってしまった。
"Cosmic American Music" とは音楽から差別の消えた状態、ジョン・レノンのイマジンのような状態がいずれ来ることを予言していたように思える。
センセーションとは裏腹にセールスは失敗に終わってしまったが、現在のカントリー・ミュージックの状況を見れば予言は正しかったと思える次第である。
そして、マッギンなら発掘の意義はここにあったと確信しているのではないだろうか?
マッギンの意図を今更想像してもディランにとってはどうでも良い話かもしれないが、筆者はこの曲を聴いてペダルスティールギターの魅力を感じた次第である。
だからカントリー・ミュージックというものでもなく、BBQには美味いソースがある事を知ったのである。
そして、このアルバムの "You'll Stll On My Mind" の歌詞、”empty bottle and broken heart" からカントリー・ミュージックにはどこか酒臭さを感じたものである。
一方のフォーク・ミュージックはシラフ=ドライなニュアンスを感じてしまうのは筆者の偏見だろうか?
グラムの作品 "Hickory Wind" はサウス・キャロライナへの望郷を歌ったものであるが、1971年にリリースされたジョン・デンバーの "Country Road" はウェスト・バージニアへの望郷である。そしてどちらもペダルスティールが使われている。
しかしながら、両者は酒が入っているか否か、後悔があるか否かという違いがあるように思う。
後者はアニメ "耳を澄ませば" でも使われ、音楽の教科書にも載っている。その点、前者はそうした使われ方はまず無いのではないか?
グラムは酒とドラッグで命を落としてしまったのはなんという皮肉であろうか?
グラムの作品 "One Hundred Years From Now" ではペダルスティールの影からチョコチョコ顔を出すリックである。"James Burton" のリックに似ているが、時々ベンドするしリズムも変則だがスパイスが効いている。
昨今のYoutubeなら当時のTV出演の様子が見られるかもしれないが、筆者はまだ発掘出来ていない。
*1





その6:後期Byrdsの舞台裏は?
当時のミーティングの模様はこんな感じだったか?
・
君は子供の頃にテレビに出ていたよね。凄い子がいるなあと思ったけど、彼が今の君だとはね。是非Byrdsでいっしょにやってもらえないかい?
・
チャンスを有り難う。勉強させてもらいたいんだ。それから相談があるんだ。
僕のリックは見ての通りコケそうなところがあってね、介添えが欲しいんだ。いつも付いてきてくれるドラマーが居てね。ジーン・パーソンズというんだ。
・
クラレンスと同じフレンチのジーンです。いっしょにカントリー・ミュージックをやってきたんだ。
・
ドラムスの他には?
・
ギター、スクラッグス・スタイルの5弦バンジョー、ペダルスティール、マウスハープ等々。
クラレンスの2弦がベンドするテレキャスター見たでしょ?彼が欲しいというんで僕がこしらえたんだ。
・
そう、Byrdsにもあれが欲しいと思っていたんだ。メカにも強いんだね。
・
ところで、曲は書ける? ボーカルはどう?
・
僕はオリジナルは書かないけど、他人の曲で良いものは沢山知っている。ジーンは書くよね。
・
僕はフォークも好きでね。多少は書いた事がある。ハーモニーボーカルもOKだよ。
・
"Sweethert" は波紋は投げ掛けたけど、あれじゃ飯は食えない。次のアルバムは難しいな.....


それは1971年の時点で国内のCBSソニー盤は既に廃盤、輸入盤も見かけなかったので、最後になってしまったのである。聴いてみて廃盤になった理由が頷けた。
冒頭の "This Wheel's On Fire" は既に1968年の "The Band" のデビューアルバム "Music From The Big Pink" に収録されていたディランと "The Band" 共作のカバーだが、リバーブを効かせたこのスペースサウンドはいったい何?.....
プロデュサーが "Gary Usher"から "Bob Johnston" に代わった事を受け入れるしかなかった。
そしてエンディングの宇宙から隕石が落下して地上に衝突したようなサウンドイフェクトも謎だった。
アルバムジャケットをしげしげ眺めているうちに、なんとなくこのアルバムの意図が見えて来た次第である。
まず、タイトルの "Dr.Byrds" が当時、時代の最先端をイメージさせる電子計算機調のフォント、"Mr.Hyde" がウェスタン調のフォントになっている。
裏ジャケット*1にはコミックのように6分割のコマ割りで写真がレイアウトされており、メンバー扮する宇宙から帰還した4人の宇宙飛行士が着地したのは田舎で、宇宙服を脱ぐとジーンズに履き替えて馬に乗って現場を後にする、というストーリーになっている。
これは宇宙旅行に興味があったマッギンのアイデアだなと察した次第である。
筆者がなんとか解釈したのは以下の様なものである。
・
5作目"Notorious Byrd Bros." のエンディング "Space Odyssey" で宇宙に旅立った後、地球に帰還した続編が "Dr.Byrds" である。
・
1969年7月はアポロ11号の月面着陸のタイミングだが、当時は帰還は海に着水するのが常道であった。
・
マッギンは将来はスペース・シャトルのように安全な陸地に着陸するアイデアを持っていたのではないか?
・
当時は地球に帰還後はNASAや空軍が総出で回収、救出するという物々しさだったが、将来は帰還したら何事も無かったかのように自宅に帰宅する。カウボーイも宇宙牧場に通う。
・
もう一つの解釈は、地球に帰還したら馬の時代に逆戻りしていた。
あるいは相対性理論にインスパイアされた3作目 "5th Dimension" の続編ということなのだろうか?マッギンのインテリジェンス、恐るべし!
他のメンバーの作による楽曲はジョン・ヨークとマッギンの共作による"Candy" のみである。
"Drug Store Truck Drivin' Man"、"King Apathy III" などのフォークらしい風刺や皮肉を込めた内容はマッギンの得意とするところらしい。
そのようなところを見るとマッギンが孤軍奮闘していたようである。
*1
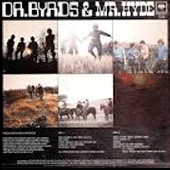


筆者も今振り返ってみるとこれは正解だったように感じる。カバー曲が多いのだが、マッギンの原点?フォーク・ミュージックのスピリッツが戻って来たよう思う。
丁度、映画イージーライダーのテーマ曲を手掛けた事もあり、マッギンはフォーク・ミュージックの身成を慎重に意識したように思われる。
ウィキペディアによると、最初はピーター・フォンダがディランに依頼し、冒頭の数行を紙ナプキンに書き留めたものの、ディランは辞退してしまい、その続きをマッギンが仕上げたとのこと。
マッギンにしてみれば絶好のチャンスと思われるが、以下は彼のフィクションインタビューである。
・
重い仕事だと思ったよ。僕らの "Wasn't Born To Follow" が使われているのは光栄なんだけど。シナリオの結末が重いし、その後に流れるテーマ曲だからね。
・
ディランの "It's Alright, Ma" がラストになる計画だったんだけど、彼がダメだって言うんだ。
ラストのテーマ曲が必要じゃないか?と、ピーターもそれをディランに依頼した。
すると今度は、ディランは "It's Alright, Ma" はこの映画に必要だが、自分には歌えないと言い出した。仕舞にテーマ曲は出来ないと言い出したんだ。
・
ピーターから "It's Alright, Ma はどうしても使いたいから替わりに歌ってくれないか?" と言われたんだ。
それでテーマ曲もディランの書き留めた数行の後を僕が補作して歌う事になったんだ。
・
この映画はロックで幕開けするけど、最後はどうやって終わるんだろう?って悩んでしまったんだ。
だってラストはボロボロじゃない。 "It's Alright, Ma" はエンディングを予感させてピッタリだと思う。
結末は南部のミシシッピ川に沿った田舎道で起きた事件だし、事故として片付けられてしまうんだろうね。
そう思ったらこれはフォーク・ソングだなって。
・
ピーターがディランに頼んだのはドンピシャだと思うけど、彼にとっては難しい仕事だったのでは?
ディランがデビュー以後に歩んできた轍を見ればこの映画のシナリオと重なってくるような気がするんだ。フォークを歌え!と詰られた気持ちだね。
・
それで最後の "Ballad of Easy Rider" が仕上がったんだけど、試写では "ディランと自分の共作" になっていたんだ。その後、ディランから電話があり、"俺の名前は消してくれ" と言うんだ。
結果そうなったんだけど、この映画は彼にとって "Easy" どころじゃなかった?
"Ballad of Easy Rider" は映画のサントラとアルバムではバージョンが異なる。前者はフォーク・ミュージックらしいシンプルなコード進行のギター伴奏とマウスハープのみで歌われるが、後者はマルチコード化されてストリングスも加わり、いかにも映画音楽の造りになっている。
"Oil in My Lamp" は教会の賛美歌由来のトラッド、"Jack Tarr the Sailor" はマッギンが英語訛りで歌う英国の古謡とのこと。
"Deportee" はウディ・ガスリー作の不法就労で送還途中に飛行機の墜落事故で亡くなったメキシコ人を歌ったもの、"Armstrong, Aldrin and Collins" はアポロ11号を扱った時事ネタ、"There Must Be Someone" は旅周りから帰ってみたら妻子が居なくなっていたというカントリー・シンガーの悲哀を歌った "Gosdin Bros.”作である。
"Jesus Is Just Alright" は "Arthur Reynolds" 作のゴスペル。 "人ががなんと言おうと気にしない、イエス様は最高さ!" というフレーズから狂信的な信者に対する冷やかしのようにも取れるところにマッギンは目を付けたのではないだろうか?
"Jesus" を "Country" に置き換えると "Sweethert Of The Rodeo" を代弁しているような気がする。
"Tulsa County Blue" は "Pamela Polland" 作のカントリー?ナンバー。
"It's All Over Now, Baby Blue" はディランが聴衆から浴びたブーイングに応えた曰く付きのナンバーである。
と言ったように、多民族国家、アメリカならではの奥行きの深さを感じる次第である。
残る、"Fido" はジョン・ヨークによるツアー中のホテルの部屋に居候した野良犬の顛末。
"Gunga Din" はジーン・パーソンズ作である。この曲は二つの事件が語られており、一つはセントラルパークで一緒に公演する予定だった "Mr.Rock'n'Roll=チャック・ベリー" が来なかった事、二つ目はジョン・ヨークがレザー・ジャケットを着ているという理由でレストランに入れなかった事である。
個人的な事件を書き留めておいたと見ればフォーク・ソングと見えるが、今流のシンガー・ソングライターの芽吹きではなかったか?
こうして見ると、筆者は1969年当時の "現代のアメリカ" を俯瞰したような作品に見えて来る。
そのように描かれた視点は映画イージーライダーとピッタリ重なっていないだろうか?
ピーター・フォンダ扮する "Captain America" とはマッギンの事でもあったのかもしれない。



Byrdsデビュー当時からのマネージャーだった "Jim Dickson" は1967年に解雇された後、"Terry" の編集助手として活動していたとの事、このアルバムでは共同プロデューサーとして名を連ねている。
ベースはジョン・ヨークからスキップ・バッティンに変り、強力なライブ・パフォーマーが揃って初のライブ+スタジオアルバムとなった訳だが、"Notorious Byrd Bros." に続いて筆者が聴いた2枚目のByrdsであった。
サウンドイフェクトを駆使したスペース・サウンドから一転してライブを体験してしまったので全く違うバンドに思えてしまったものである。
既にFMラジオの新譜紹介で聴いていたのがこのライブ盤だったが、収録時間16分強の "Eight Miles High" の途中のコーラス部分だけを聴かされていたので、ディスクに針を落としてみるとコーラスを迎える前のインプロビゼーションに聴き入ってしまった。
1970年、時代の最先端という気分だったが、クラレンスのリードギターのトリッキーさが印象的であった。
まだ彼のカントリー・リックが聴けるアルバムを聴いていなかったので、ジャズプレーヤーという印象だった。
この直後にサンタナやシカゴのようにリードギターで聴かせるバンドが一世を風靡したのだが、これらもCBSソニーレーベルだった訳で、本国の "Columbia" レーベルも力が入っていたらしい。
後にクラレンスの全貌が判ってくると、ブルーグラスに革新的なリードギター奏法を持ち込んだ彼なのだが、ジャンゴ・ラインハルトを聴いていたとのこと。あながちジャズプレーヤーは間違いではなかったようである。
スペース・ロックの次はジャズ・ロックなのかと思ってしまったが、スタジオ盤を聴いてみるとアコギも巧いギタリストが居るんだなという印象だった。
それは "Chestnut Mare" であるが、続く "Truck Stop Girl" のテレキャスターによるエンディングの図太いリックは今流に言う "レジェンド" かもしれない。
更に "Take a Whiff on Me" はマンドリンが聴こえ、ライナーズノートによるとこれも彼が弾いているとのことであった。
カントリー・ロックという用語もこのライナーズノートを通して知ったわけだが、筆者はフォーク・ミュージックに続いてカントリー・ミュージックへの玄関に立たされていたのであった。
スタジオ版 "Eight Miles High" は当時、ジョン・コルトレーンにインスパイアされた12弦エレキという評があり、クロスビーにもジャジーな面があったので、なるほどなと思っていたのだが、クロスビー流のモノ・コードはトラッド・フォーク〜民族音楽のようなニュアンスも伺える。
そうするとインド音楽にインスパイアされたラガ・ロックという当時の評も頷ける。
そもそもイントロのベースラインも4度、5度になっている。
ライブ版ではスキップ・バッティンのソロ・ベースが4度、5度で飛び回る様は "Younger Than Yesterday" のクロスビーの "Mind Gardens" の節回しを連想させる。
そしてこんな曲を演奏しても全く違和感が無いような気がする。
スティブン・スティルスの "Know You Got To Run"、 "Blind Fiddler Medley"、"Carry On" 、"Black Queen" 等である。これらはどこかアパラチアン・トラッドを感じさせる。
サンタナの "Black Magic Woman" はラテンだがこれらに共通するのはペンタトニック=5音音階という点であり、日本の民謡や演歌も同様である。
モノ・コードで4度、5度のベースラインが流れていれば日本の声明も乗ってしまう。そしてクラレンスのリードギターのトリッキーさは時折メジャーになったりマイナーになったりして、妙な快感を覚えたものである。
マッギンの脳裏には、アパラチアン・ロック、エスノ・ロックという発想はあっただろうか?
ちなみに同時期にリリースされたCSN&Yのライブアルバム "4 Way Street"*1 でも "Carry On" がインプロビゼーションによって14分強に達しているが、こちらにはそうしたニュアンスは感じられない。
"Lover of the Bayou"、"Chestnut Mare"、"All the Things"、"Just a Season" がそれだが、マッギンと精神科医でブロードウェイのプロデューサーでもあった "Jacques Levy" との共作であるところが興味深い。
ノルウェーの劇作家 "Henrik Ibsen" 作 "Peer Gynt" をモチーフにした "Gene Tryp" はカントリー・ロック・ミュージカルだったそうで、1969年頃にはカントリー・ロックという用語は認知されていたようである。
1967年のロック・ミュージカル "Hair" からはフィフス・ディメンションの "Aquarius/Let the Sunshine In=邦題:輝く星座"*2 がヒットしている事を考えると "Gene Tryp" のコンセプトは斬新だったようである。
残念ながら "Gene Tryp" の公演は実現しなかったが、およそ20年後の1992年に "Colgate" 大学の演劇科学生によって上演されたとのこと。その際、"Just a Season" は "A Romance of the Old West" と改変されているとのこと。
このカントリー・ロック・ミュージカルは "Peer Gynt" の舞台をノルウェーから19世紀のアメリカ南西部に移したとのことだが、こうしたアイデアが後のイーグルスのダルトン強盗団をモチーフにした1973年のコンセプトアルバム "Desperado"*3 に繋がっていったように思えてならない。
当時は "Chestnut Mare" のマッギンの朗読、それを支えるクラレンスのアコギや宙を駆け巡るようなテレキャスターのBベンダーから、モニュメント・バレーのような雄大な景色を連想していたのだが、こうした背景を知る事でやっと腑に落ちた次第である。
Youtubeにこの曲に相応しい映像を付けた "Chestnut Mare" が多数アップロードされている理由が判った。
このミュージカル用に用意された曲なのだが、前作までのByrdsの曲には殆ど見られなかったマルチコードを感じる。これが "Jacques Levy" 流らしい。
輪廻転生やエコロジーと言った様なテーマだったり、スキップによると"南無妙法蓮華経" を唱える "Well Come Back Home" はベトナムに出征して亡くなった高校時代の友人の為の曲とのこと。
当時、筆者はその認識は無かったが、時代が変っても後に発掘された時にその時代に何が起こり、人はどう考えていたのか?検証できるのがフォーク・ソングなのかもしれない。
後者の版権はアラン・ローマックスとなっているようにトラッド・フォーク〜ブルーズなのだが、19世紀以前からコカインの吸引が行われていた事が伺える。
*1

*2

*3

モニュメント・バレーだが、 "Untitled" のジャケットの背景に写っている。
ユタ、コロラド、アリゾナ、ニューメキシコ各州が接する "4 corners" の近くにあり、西部劇でお馴染みの場所だが、イージーライダーでもここを通過する。
そこで流れてくる "The Band" の ”The Weight” は映像にジャスト・フィットして印象的であった。
おそらくマッギンもByrdsのサウンドをイメージするジャケットのアイデアを持っていたのではないだろうか?
此処は中西部の砂漠化した原野ではあるが、ジャケットのモニュメント・バレーは雪景色に見える。砂漠でも冬には雪が降るという自然の厳しさを伝えたかったのだろうか?
筆者が初めて認識したカントリー・ロックのイメージはこのモニュメント・バレーのジャケットに因る所が大きい。



高校1年は1971年秋、過去のアルバムを揃え終わり、このアルバムからリリースを待ち望んで聴くことになったのだが、筆者が聴いた当時の印象はオープニングのピアノや女性コーラス、ホーンアンサンブルやストリングス・オーケストラがキラキラ輝いているように感じたものである。
ゴスペル調あり、ラグタイム調あり、ブルーグラスありで、今ならキャプテン・アメリカの眼で俯瞰した "Easy Rider" の続編に思えるのだが、リリースからおよそ20年後のレコード・コレクターズ誌の評によるとオーバー・プロデュースで評価が低くセールスも振るわなかったとの事。
レコーディングセッション後、メンバーがツアーで不在だった間に "Terry Melcher" が無断でアレンジを加えたとのこと、メンバーはこれに失望して "Columbia" レーベルを訴えたとのこと。
思い出されるのはサイモン&ガーファンクルの "The Sounds Of Silence" である。オリジナルはギター伴奏と二人のハーモニー・ボーカルだけだったが、ポール・サイモンがイギリスに渡って活動中にColumbiaレーベルの "Tom Wilson" によって無断でドラムス、ベース、エレキをオーバーダビングして再リリースしたことである。
当時はレーベルと専属プロデューサーの力が強く、またアレンジまで頭に思い描けるようなミュージシャンも稀だったのであろうか。恐らくByrdsのメンバーも "The Sounds Of Silence" の舞台裏は知っていたのであろう。
ウィキペディアによると "Terry Melcher" の弁が記されているのだが、以下はそれを基にしたフィクション・インタビューである。
・
セッション後のテープを聴いていたんだけど、線が弱い! それで補強しなきゃと思ったんだ。
・
今までのByrdsの曲にはどこかにマッギンが拘っていたトラッド・フォークがあると思う。
・
でも、今回のアルバム候補になった曲はモダン・フォーク、いや、ポップスの色合いが感じられたんだ。
・
ポピュラーに売れそうな要素があるってことだね。
前作のような音造りじゃないと感じてね。それでバックコーラスやオーケストラを入れたくなったんだ。
・
でもこれは間違いだった。
ポピュラーな要素とはマルチコードになって来たことではないだろうか?
トラッド・フォークのシンプルコードとは蒸留されたという意味合いかもしれない。ジンや焼酎のようなスピリッツに喩えられるだろうか。
Byrdsはデビュー前に "Beefeaters(英国製ジン)"*1 と名乗っていたそうだが、マッギンの拘りであろう。
もうひとつ、Byrdsの過去の曲を振り返ると1度、又は半音ずつ降りて行くベースラインは殆ど聴かれない。いわゆる、お洒落で口当たりが良いというニュアンスでなはい。
そう考えて見ると "Notorious Byrd Bros." でデイビッド.クロスビーがキャロル・キングの曲を入れるのに反対した事が思い出される。
彼はフォーク・リバイバルを契機に "great chord change" が出て来たことは認めるものの、その後から近年までの彼の曲を聴くとそれとは一線を画していたように思える。カクテルのようなマルチコードは肌に合わないのかもしれない。
"Byrdmaniax" の収録曲でマルチコードや下降ベースラインが出て来るのは、
"I Trust"、"Tunnel Of Love"、"Citizen Cane"、"Absolute Happiness"、"Jamaica Say You Will"、"I Wanna Grow Up to Be a Politician"、"Kathleen's Song" といったところだろうか。
最後の2曲は先述の "Gene Tryp" なるミュージカル用に書かれた曲とのことだが、共作者の "Jacques Levy" 流がここでも顕著である。
そしてスキップ&"Kim Fowley" 作品の台頭である。作詞はスキップで、作曲、コード進行は "Kim" らしい。
注目すべきはジャクソン・ブラウン作の "Jamaica Say You Will" である。彼はそれまでのフォークやカントリーには見られなかったマイナーコードを施してどこか感傷的なニュアンスを感じさせる。
"5th Dimension" のところでも述べたが、Byrdsの中でマッギンの作詞による曲は多いが、作曲=コード進行は他者による共作が殆どである。
マッギンのフォーク・ミュージックへの拘りとはコード進行より歌詞重視と言えるのかもしれない。
"Untitled" 、"Byrdmaniax" と続くと歌詞はマッギンやスキップの個性が現れているが、共作者達のコード進行によってByrdsらしさが希薄になってきたように感じる。
デビュー当時からのByrdsらしさとは、やはりジーン・クラーク、デイビッド・クロスビー、クリス・ヒルマンのコード進行に因るところが大きかったように思う。
シンプルだがトラッド・フォークには見られないコード進行で、ベースランやハーモニーボーカルが醸し出すドローンが良い。これは5作目"Notorious Byrd Bros." のクロスビー作の "Draft Morning" とほぼ同じである。
ストリングスやホーン&木管アンサンブルと相まって、陽の出の朝霧が漂う感じである。それにジーンのハーモニカが郷愁を誘う。
歌詞は旅をやめて女のもとに落ち着く男の気持ちを歌っており、8作目 "Easy Rider" のB面でジーンが歌った "There Must Be Someone" のアンサーソングと言えるかもしれない。
これは同じ時期に公開されたピーター・フォンダ監督、主演の映画 "Hired Hand=邦題;さすらいのカウボーイ" とどこかシンクロしている。
そんなところから、作詞はマッギン、コード進行はジーンだろうか?
*1

ところで "Byrdmaniax" は1971年当時に登場したばかりのSQ方式4チャンネル・オーディオシステム用の第一陣としてリリースされた為、2チャンネル用と4チャンネル用の2種類のミックスダウン・バージョンが存在する。
国内のCBSソニー盤は4チャンネル・バージョン、本国Clumbia盤はそれとは違うミックスダウンになっている。
これに気が付いたのはドイツの "Line" レーベルが1992年に復刻したCDを聴いた時で、こちらが2チャンネル・バージョンとのこと。
筆者が聴いた4チャンネル・バージョンのCD化は今の所、リリースされていない。
両者の違いは4チャンネル・バージョンはオーケストレーションが前面に出て来ているが、2チャンネル・バージョンは控えめ、あるいは故意に入れなかったような節がある。そのせいか、後者はクラレンスのアコギのベースランが良く聴こえる。クラレンス・ファンは2チャンネル・バージョンの方が嬉しいかもしれない。
なお、当時は4チャンネル・オーディオシステムは持っていなかったが、CBSソニー盤に同封されていた広告によれば、"アンディ・ウィリアムスが貴方の周りを歌って廻ります" とのことなので、オーケストレーションとByrdsのトラックが明瞭に分離して聴こえるような仕掛けだったのかもしれない。
こうなってくると "Terry Melcher" も色々なアイデアを持っていたのではないだろうか?
ただ、それをじっくりトライして納得できる仕事が出来たかどうか?興味深い疑問は残るのである。
筆者は店頭で4チャンネルを試聴できるような機会は無かったし、あったとしても "Byrdmaniax" を持参して出掛けようとまでは思っていなかった。
ストリングスやオーケストレーションを自然に纏っていたのはサイモン&ガーファンクルであろうか?
デビューアルバムの頃はフォーク・デュオと呼ぶにふさわしかったが、ポール・サイモンの生み出す曲はすでにマルチコードになっていた訳で、彼はどんな音楽を聴いて育ったのであろうか?
彼は "Scarborough Fair" は英国、 "El Condor Pasa" は南米ペルーのトラッド・フォークを発掘したし、その後、中米、南アフリカのトラッドまで素材にしてしまうところはロジャー・マッギンと同様にアラン・ローマックスの後継者と言えるのかもしれない。
アイリッシュを出自とするマッギンが英国に拘っていたのは頷けるが、サイモンが地球規模に発掘していたのはユダヤ系由来と何か関係があるのだろうか?ボブ・ディランにしてもユダヤ系というのも気になる。
いずれにしても民族のるつぼから生まれて来る多彩な音楽をColumbiaレーベルは見事に捉えた時代だったのかもしれない。
その曲で使われるコードの数が多いという意味でマルチコードという言葉を使ってきたが、音楽仲間のスラングかもしれない。
例えばベースラインがCから始まって→B→A→G→F→E→Dと降りて元のCに戻る場合、7音=7つのコードに振り分けられる。
あるいはCから半音ずつ→B→B♭→A→A♭→G→G♭→F→Eと降りて元のCに戻る場合も同様。
なお、テトラコルド、ペンタコルドと呼ばれる音楽用語は別の意味なのでご注意願う。
こうしたやり方で見てみると、
モノコード
民族音楽
Mind Gardens / Byrds
デュアルコード
民族音楽、日本の数え歌、声明
Silver Raven / Gene Clark
トリプルコード
ブルーズ、フォーク
Wasn't Born To Follow / Byrds
テトラコード
ポピュラー
Lover Of The Bayou / Byrds,
In the Year 2525 / Zager And Evans,
Heartbreaker / Grand Funk Railroad
ペンタコード
クラシック、ポピュラー
Thought And Words / Byrds,
25 or 6 to 4 / Chicago,
Stairway to Heaven / Led Zeppelin
マルチコード
クラシック、ポピュラー
A Whiter Shade of Pale / Procol Harum,
Hotel California / Eagles


ジャケットのクレジットを見るとByrdsのセルフ・プロデュース、イギリスはロンドン録音と記されていた。
ウィキペディアによると "Byrdmaniaxの失策" をフォローすべく、メンバー自身でプロデュースを決めたとのこと。L.A.の "Columbia" スタジオは空きが無かったのかもしれない。
オーケストレーションやバックコーラスがあれだけ入っていてはライブステージでの再現は財政的に大変な負担になってしまう。メンバー4人だけで演奏するにはアレンジもし直さねばならない。
メンバーの "Terry Melcher" を非難する気持ちは良く判るし、なるほど本作はオーバーダビングを控えたライブな音造りになっているのは頷ける。
Byrdsが "Columbia" レーベルと契約した際の条件は不明だが、当初から11枚のアルバムをリリースするというものだったのかもしれない。
しかしながら、セールスが芳しく無ければプロデューサーも責任を問われ、当時はレーベルに属さない独立プロデューサーも稀だったことを考えるとプロデューサー不在という事態だったのかもしれない。
"Farther Arong" はアパラチアンのゴスペル・ナンバーで、クラレンスの選曲であろう。
スキップがボーカルを取る "Bob Rafkin" 作の "Lazy Water" は彼の選曲であろう。
子供の頃に遊んだ小川のせせらぎに思いを馳せる内容でハーモニー・ボーカルが美しい。デイビッド・クロスビーが居た初期のByrdsらしいハーモニーとは違って、ブラザース・フォーに見られたようなオーソドックスなハーモニーである。
そして誰しもこのアルバムのベスト・トラックと認めるであろう、クラレンスがボーカルを取る "Larry Murray" 作の "Bugler" も彼の選曲であろう。
彼のマンドリンはブルーグラスの間奏のソロプレイとは違い、筆者はバックでドローンとして鳴っているところが気に入っていた。
これは "America's Great National Passtime" でも聴かれる。
そして何よりもジーンが弾くペダルスティール・ギターに癒されたものである。
ちなみに、"Old Blue"、"Fido" と共に、Byrdsのレパートリーにおける犬モノ3題のうちのひとつである。
アルバムのラスト "Bristol Steam Convention Blues" は、"Byrdmaniax" でも見られたブルーグラス・インストで、ジーンお得意の5弦バンジョーと、それに絡むクラレンスのリードギターの妙技が聴かれる。
ちなみに、"Steam Convention" とは毎年、英国の "Bristol" で開かれる縮尺蒸気機関車=Live Steamのショーのことで、これをホビーとしているジーンはロンドン録音と重なって参加できない無念さを曲にしたとのこと。
1971年というと細胞分裂して行った "Flying Birrito Bros." もそのように呼ばれていたが、"Birrito" や "Poco" がメンバー自作の曲を演奏していたのに対し、Byrdsはシンガー・ソングライターと呼ばれ始めた人の作品をカバーし、スポットライトを当てるという役割を担っていたように思える。
"Notorious Byrd Bros." での選曲に際し、デイビッド・クロスビーとマッギンが交わしたであろう議論以降、マッギンによる "発掘作業" は続いていたように思える。
そして筆者はメンバー3人の選曲眼には脱帽の思いである。
そうした互恵関係はリンダ・ロンシュタットやエミルー・ハリスのような女性シンガーや、カントリー・ミュージック界本家にもおよび、いくつかの名曲と共にリスナーの裾野は広がって行ったようである。
歴史を回顧すればグラム・パーソンズが生前に言っていた "Cosmic American Music" とはシンガー・ソングライター達によって実現されたのかもしれない。
反戦、反核、体制批判や連帯を呼びかけていると疲れも溜まる。たまには酒も飲むが、いつしか酒に飲まれ、これではいけないともがいていると、ふと日常の中の小さな幸福に気が付く。
そんな私的な心象や随想、遂にはスキップのように "禅の境地" や "小川のせせらぎ" に辿り着いたのは地球のバイオリズムだったのかもしれない。
そのようなバイオリズムは日本の音楽シーンも例外では無かったような気がする。
ルーツは人種ではなく私的なルーツ、子供の頃から馴染んで来た音楽・文化というニュアンスもあるようである。
ならばフォーク、カントリー、ブルーズ、ジャズ、ロック、ラテン、民謡、演歌等、なんでも良い訳である。
ルーツ・ミュージックとは "Cosmic American Music" をも越えたユニバーサルな概念に思える。
1979年のスキップ・バッティンのインタービューによると "Lazy Water" について "昔、住んで居た "Mendocino" の森に囲まれたカントリー・ライフとツアーの狭間でいつも感じていたフィーリングだった" とのこと。カントリー・ロックとはカントリー・ライフ推進ロックでもあったのだろう。
この "Mendocino" だが、太平洋に面したサンフランシスコの北にあり、自然豊かな場所らしい。
ジーン・パーソンズも近年は此処に住んでいるそうで、ジーン・クラークも1971年頃にはここで ”隠遁生活” していたとのこと。
また、"Michael Hedges" は1997年に惜しくもここで交通事故で亡くなっているそうである。
ロジャー・マッギンは若い頃 "Bob Gibson" に強く影響されたと語っていたが、ジーン・パーソンズの義父だそうである。
ジーンの今の奥さんであり、いっしょに活動している "Meridian Green" は "Bob Gibson" の娘とのこと。
ジーンの2001年リリースのソロライブアルバム "I Hope They Let Us In" で "Abliene" を歌う前に "私の義父が書いた曲です" と紹介している。
このアルバムタイトルは "Easy Rider" に収録された彼の曲 "Gunga Din" のサビの一節である。
"Easy Rider" のジャケットはジーンの父 "Lemuel Parsons"*1 がバイクに跨がった写真だったが、本作はジーン自身*2がバイクに跨がっている。
この曲や "Bugler" 等、Byrds時代の曲も収録されているが、ジーンがフォーク=ルーツ・ミュージックをこよなく愛している様が伺えるアルバムと思う。
*1 Father

*2 Son





その7:リユニオンアルバム 
同時にCSN&Yの "Deja Vu"*1 を聴いてたまげていた頃でもあった。
Byrdsとは全く異質だが、アコギを駆使したそのサウンドに耳を奪われていた。
デイビッド・クロスビーがその後どういう事になっていたのか?こういう事をやりたかったのか、とByrds脱退の理由がすぐに腑に落ちた次第である。
当時、新興レーベルだった "Asylum" からリリースされているのを見て、このリユニオンアルバムはCS&Nの影の立役者 "David Geffen" が仕掛人だと察した次第である。
デイビッドがByrdsを脱退した1967年から既に6年の歳月が流れていた訳だが、そろそろ同窓会に参加しようと思う世代になっていたという事か?
クリス・ヒルマンは "Flying Birrito Bros." を経てスティブン・スティルスのマナサスに参加したことは聞いていたが、マナサスは未だ聴いていなかった。
ジーン・クラークも "Dillard & Clark" やソロ活動をしていたことは聞いていたが、こちらも同じくご無沙汰だったのでメンバーのその後の成長振りが期待された。
しかし、Byrdsの "Byrdmaniax" や "Farther Arong" で聴かれたクラレンス・ホワイトの艶消し調のベースランとは違って、それはCSN&Yの "4 Way Street" で聴かれるのものだった。
なるほど時代は変わっていた事、CSN&Yの影響の大きさを実感した次第であった。
アコギがこんなに奇麗に響く、レコーディングやミキシングが進化していたようである。
"Wally Heider's studio lll" での録音ということを知ったのだが、後にCS&N、CSN&Yのアルバムもここで録音されたことが判り、"Columbia" スタジオとの違いを思い知らされたのであった。
アーチストの憶いがスタジオを動かし、お互いに良い環境を築き上げるという事を知ったアルバムとなった。
クリス・ヒルマンとマナサスのメンバー "Dallas Taylor" との共作による "Things Will Be Better"、同じく "Joe LaLa" との共作による "Borrowing Time" は彼らしいノリが懐かしかった。
マッギンと "Jacques Levy" 共作の "Sweet Mary" はどこか "Jack Tarr the Sailor" を思わせて英国の古謡の雰囲気があり、"Born To Rock'n'Roll" はかつての "So You Want To Be A Rock'n'Roll Star" が皮肉を込めた曲とすると、こちらはより現実を直視している点でフォーク・ミュージシャンを貫いているように思えた。
炭坑で成り立っケンタッキー州やアメリカの男の子なら誰でも憧れる消防士が出て来るあたり、マッギンは "Captain America" で在り続けているようだ。
クロスビー作 "Laughing"、"Long Live The King" ではボーカルハーモニーはかつてのByrdsではなくCSN&Y流儀になっているところにも驚かされた次第である。
ジョニ・ミッチェルの "For Free" を持ってくるところは彼女をプロデュースして世に送り出したクロスビーの意向だろうし、自らの手で "時代を変えて" しまったニール・ヤングの "Cowgirl In The Sand"、"(See The Sky) About To Rain" を入れたところは彼流の解釈をByrdsのメンバーで実現させたものなのだろう。
"Flying Birrito Bros." を経験してきたマイケル・クラークのバス・ドラムはあの時代の音になっていた。
クリス・ヒルマンのマンドリンが要所要所で顔を出したり、マッギンの5弦バンジョーも入って来るところも嬉しかった。
グレッチのセミアコースティックを使ってアンプを通さずにマイクで音を拾っているように思える。
また、アコギ・アンサンブルだが、Byrdsのメンバーのリックとは思えず、スタジオ・ミュージシャンだったのだろうか?ジャケットにはクレジットされていないので今も謎である。
いずれにしてもプロデューサー、デイビッド・クロスビーの監修が行き届いているように思えた次第である。
デイビッド・クロスビーもフォーク・リバイバルを通過し、"時代は変る" ことを実感し、自らの手で "時代をイメージし"、自分より4歳若いニールがついに "時代を追い越して" 行くのを見て来たのかもしれない。
このリユニオン・アルバムはマイケル・クラークを除く4人がそれぞれ自作曲を2曲ずつ持ち寄り、それにニール・ヤングの2曲、ジョニ・ミッチェルの1曲を合わせた11曲構成になっている。
このやり方はCSN&Yと同じである。
マッギンが "Behind The Guitar" なるトーク番組でホスト役から質問された応えによると、発案したのはクロスビーで、そもそもジーンから始まって、クロスビー〜ヒルマンとマッギンの元を離れて独立して行ったわけだが、皆それぞれ自分の道を切開いたその成果を一堂に集めて世に問うて見ないか?という主旨だったようである。
*1





筆者がByrdsを聴いていたのは1970年から73年にかけてだったが、その間にウディ・ガスリー、ピート・シーガー、ジョーン・バエズ、ボブ・ディラン、キャロル・キング、ニール・ヤング、ジャクソン・ブラウン達が通り過ぎって行った。
昨今は娘のCDを借りて来て "Ed Sheeran" や "Bon Iver" を聴いているのだが、先人の轍が微かに辿れるようである。

