筆者の推測なのだが、デビューアルバムに名乗りを上げるプロデューサーが現れなかったのではないか?
彼のカントリー指向だが、先発したByrdsを見てもリスナーの反応が芳しく無い。リッチーはByrdsとは違うシナリオを描いていたようだが、CS&N自身がデビューアルバムを自己プロデュースするのを横目で見ていたと思われる。
さて、結果としての初期のPocoのサウンドは、ByrdsやCS&Nとは明らかに違うものになった。これがジミーの初成果となった。
以前のESSAYでも記しているので参照ください。
彼はカントリー・ミュージックを聴いて育ったのだろうか?
一方、南部ではヒルビリーからの脱出を図るかのようにロカビリーが産まれ、ロックンロールになっていった事を考えればカントリー・ロックとは先祖還り?というニュアンスを受ける人もいたかもしれない。
リッチーは先発のグラムがByrdsで描いたシナリオを横目で見ながらド演歌ならぬ、ドカントリーにはしたくない、意固地にならず普段着のようなものにしたいというシナリオを描いていたように思える。
1969年と言えば映画、イージーライダーが封切られた時代であり、反体制のシンボルのようにロック・ミュージックがカー・ラジオから流れていたであろう。
さて "hoe down" は西部開拓系、ヒルビリー系、どちらだったのであろうか?
脱輪:
脱輪その2:
ところで、John Denverが "Country Road" で描いたのは ”還るべき故郷=ウェスト・バージニア” であったが、もう一つ、疲れた心を癒す自然への回帰というニュアンスも含んでいたように思える。
1972年と言えば、リッチーはコロラドの山並みを歌詞に織り込んだ "A Good Feelin' To Know" をリリースした年だが、バッファロー・スプリングフィールド時代の盟友、スティブン・スティルスは自身のバンド Manassas を立ち上げている。(Manassas は南北戦争の激戦地となったバージニア州の街とのこと、 南北戦争に拘りを持つスティブンらしい)
脱輪その3:
さて、彼はPocoでリズムギターを弾いている。バッファロー時代でも腕をくるくる回して正確なリズムを刻む姿がyoutubeでも見られる。
最初のEpicとの契約は9枚のアルバムをリリースするとのこと。
さて、結果は次の1974年リリース、7th ”Seven” を見ると曲数は8曲と少ないが、筆者は気に入った曲が多い次第。
結果として4人で結束した思いと成果は伝わってきた次第である。
その後、1978年にティモシーがEaglesに移籍するまでにセルフプロデュースの "Cantamos" をリリース、Epicとの契約満了を経てABCレーベルと契約、Mark Harmanプロデュースが続いた訳だが、ビッグヒットこそ無くともファンから見れば安定した時代だったのかもしれない。
脱輪:
彼はジム・メッシーナの後継リードギタリストとして1971年の4th "From the Inside" から参加するが、曲も書けるしリードボーカルも取れる。
ポールはウィキペディアによれば、"シカゴで育って25年過ごしたけれど南部には強く惹かれる” とのこと。
Epicレーベルが80年頃にリッチーとポールの曲を集めたベスト版をリリースしているが、二人のセンスの違いは明らかでEpicの意図は頷ける。
以下は筆者の過剰な思い入れによるポールのフィクション・インタビューである。
2020年の今でもPocoの看板は降ろしていない。
Byrdsが1968年に "Sweetheart Of The Rodeo" をリリースした時のペダルスティール奏者はLloyd GreenとJ.D.Manessで、どちらもセッションマンであった。
レコードでは多重録音でドブロ、ペダルスティール、バンジョーが聴こえてくるが、ライブステージでは大変な事になる。だがラスティはこれを手品師のようにアレンジしており、観客が眼を丸くするのを見るのが彼の喜びだったのかもしれない。
そんなラスティにリッチーが去ってから転機が訪れたようである。
前作 "Seven" までがJack Richardsonのプロデュースだが、"Seven"は4人体制になってロック色が濃くなった。
この "Cantamos"*1 はジャケットにひと工夫があり、長方形にくりぬかれた窓の中に薪ストーブのある室で歌う4人(イラスト)が見えるという仕掛けになっている。(同様のアイデアは1971年の”Graham Nash & David Crosby”*2 でも見られる。)
しかしながら "Cantamos" もセールスは低調。契約上のノルマ、最後の9作目は苦しい状況ではなかったか?
9枚のノルマを乗り切り、ABCレーベルに移籍後1976年リリースの "Rose of Cimarron" 同タイトル曲は以前のESSAYでも紹介したようにラスティ入魂の1曲であろう。
アルバム "Rose of Cimarron" は8th "Cantamos" と同様にブルーグラス系楽器の比重が高い。
ティモシー、ジョージが去り、ポールとラスティのバンドとなったアルバム ”Legend" ではポールの "Heart Of The Night” とラスティの "Crazy Love" が揃ってPoco最大のヒットとなった。
2005年リリースの再びライブ、23th "Bareback at Big Sky" のラストトラック、バッファロー時代のニール・ヤング作 "On The Way Home" が終わるとラスティのMCがおまけに入っている。
因みに、"joke" のネタの中には "Neil Young Is Not My Brother" があり、ニールの物真似も披露しているのでYoutubeでご覧頂きたい。
Poco発足オーディション時の彼の結果はランディ・マイズナーの次席だったとのこと。
これを世に知らしめたのはEpicからABCレーベルに移籍一作目 "Head over Heels" のオープニング、"Keep On Tryin'" ではないだろうか?彼はまず自宅で多重録音ですべてのパートを自分で重ねたデモテープを作ったそうで、それをPocoの3人に聴かせ、アカペラ+アコギ1本というアレンジが固まったようである。1975年リリースであるが、山下達郎も ”やられた!” と思ったのではないだろうか?
彼の楽曲はティモシー印が明瞭である。コード進行が心の変化に寄り添うような、裏切られない安心感と言えばよいだろうか?歌詞も青春時代の男女間の心理描写が多いようである。カントリーでもロック、フォークでもない、黄金の60年代のポップスに源泉があるか?あるいは日本のニューミュージックと呼ばれた楽曲と通じるところがあるように思う。
気になっているのは、7th ”Seven” に収録の1曲 "Krikkit's Song (Passing Through)" である。
僕たちの周りを蛍が舞う
ティモシーの歌詞はシチュエーションを想像させる語句を排して心理描写で聴かせるのを得意としているように思える。"離ればなれ" とは大人の別れではなく、ディズニーの世界のような "二人はお家に帰る" というニュアンスを筆者は感じてしまった。
脱輪:
彼はラスティと共に Boenzee Cryque に在籍しており、ラスティに請われてPocoに加入したとのこと。
彼の価値はやはりドラムスを叩きながら、ハーモニーボーカルのトップとしてのハイトーンであろう。
2004年リリース、22th "Keeping The Legend Alive" ではジョージが久しぶりにドラムスとハーモニーボーカルを務めている。冒頭の "Keep On Tryin'" ではだいぶ声がハスキーになったラスティがリードボーカルを取り、ポールがボトム、ジョージがトップという3声で歌い始めるが、バックコーラスが被る部分では残縁ながら2声になるのでオリジナルではジョージが勤めていたトップが聴こえない。
ジョージは "Keeping The Legend Alive" 収録後の別のライブの最中、脳卒中を起こして倒れたそうだが、ハイトーンを頑張り過ぎたのだろうか?心配していた。幸いリハビリを継続中とのことだがドラムスは復帰できていないらしく、辛い知らせである。
1989年リリースの "Legacy" は18th "Inamorata" のリリースから5年が経過していた。
それから5年は音沙汰が無かったので、これがPoco名義の最後のアルバムになったんだなと思っていたところに "Legacy" である。
さて、プロデュースだが、David Coleということで、ジム曰く、今回はお任せしたとのこと。
さて、ここで憶い出すのはラスティのことである。


その1:初期プロデュースはなぜジム・メッシーナ?
映画の世界では演じる俳優自らがプロデュースや監督を行うのはかなりの実績を積んでからのことである。
音楽業界ではレコード会社のスカウト担当がデビューさせたいミュージシャンを探し、プロデューサーに託して準備を整えると聞く。
プロデューサーも、”こんなふうにデビューさせたい” とシナリオを描けるなら仕事を受けるのではないかと思われる。
そうしたところからすると、Pocoはシナリオが描き難かったのではないだろうか?
Pocoの創設メンバーであったリッチー・フューレイはバッファロー・スプリングフィールド時代の曲、"Kind Woman" でカントリー・ミュージック指向であることは認識されていたようである。
バッファローは盟友、スティブン・スティルスやニール・ヤングが居り、2枚目のアルバムからプロデューサーが見つからず、当時レコーディングエンジニアとしてこの道に入ったばかりのジム・メッシーナにお鉢が廻されてきたそうである。(レコードジャケットにはクレジットされていない)
3人のエゴが理由と言われているが、スティブンが参加したCS&Nにしてもデビューアルバムはセルフプロデュースである。60年代末頃はこうした状況がいくつか起きていたのではないか?
当時のプロデューサーはレコードレーベル専属で、ビートルズのようにデビューはジョージ・マーティンによって”調教”されていたが、レノン&マッカートニーが次第に自分たちのシナリオを描けるようになってくるとプロデューサーの在り方が変化し始めていたように思われる。
そんな様子を米国側も感じ取り、熟練プロデューサーからは、”言う事を聞かないミュージシャン” と見られ始めたのではないか?
リッチーはPocoを立ち上げるとEpicレーベルと契約した訳だが、Epic側もプロデューサーを探したものの...という事かもしれない。
Pocoのメンバーとなったジムはレコーディングエンジニア志望だし、プロデューサーとしての初仕事としていいんじゃないか?これがEpic側との相談だったのではないだろうか?
また、プロデューサー側もレーベル専属から独立する者も現れるようになっていったようである。
当時はロックも多様化し始め、まだカントリー・ロックという概念も定まらず、リスナーも業界側も揺籃期だったのではないだろうか?




その2:リッチー・フューレイの憶い?
ただ、60年代当時の一部の熱狂的なファンを相手にしていたナッシュビルの音楽産業を冷静に見ていたように思われる。
カントリー・ミュージックと呼ばれるようになる以前は発祥がアパラチアン山脈周辺であったことから、Hillbily=ヒルビリーと呼ばれており、"田舎っぺ" というニュアンスだそうである。
アパラチアン山脈は東海岸に沿ってペンシルベニア州南部からジョージア州北部に跨がるむしろ大丘陵地帯と言った方が良いが、1840年代の飢饉によって大量のアイルランド人が移住して棲み付いた地域である。
農耕には適さないが森林資源は豊かなので樵や、ケンタッキー州のように炭坑夫として生計を立てる事が出来た。
丘陵地帯を過ぎてアラバマ、ミシシッピ、ルイジアナ州へと南下すれば製綿やミシシッピ川やメキシコ湾岸での漁業が出来た。
丘陵地帯を越えて西部への開拓は広い土地を必要とする穀倉、畜産を目的に1860年代から始まる。
色々な選択肢はあったと思うが、丘陵地帯に留まる気質というのはあったのかもしれない。
西部開拓が進み、牛で生計を立てる人々の中からはカウボーイなる職業が現れた。鉄道が全米に普及するとそれに乗って職を求めて移動する人々によってローカルなフォークソングが拡散し、カウボーイソングはウェスタン・ミュージックと呼ばれるようになった。
その後、アパラチアンのカントリーと西部のウェスタンが対を成すようにカントリー&ウェスタン=C&Wと呼ぶ時代があったが、総称してカントリーと呼ばれるようになってゆく。
カントリー歌手はいつしかカウボーイハットを被りブーツを履くようになり、カントリー・ミュージックは西部開拓というイメージが醸成されていったようである。
そこには ”ヒルビリーとは違うぜ” といったニュアンスが含まれていたのかもしれない。
リッチーはByrdsのジーン・クラーク、クリス・ヒルマンと同じ1944年生まれ、グラム・パーソンズは1946年生まれだが、この世代がカントリー・ミュージックを出自に新しいニュアンスでロックしたいと思って居たようである。
1967〜68年頃だが、筆者はクリスはどちらかと言うと西部開拓系、グラムはヒルビリー系、ジーンは孤高というニュアンスを感じるのだが、リッチーは今一つ判らない。
"カントリー・ロック・サミット" なる集いを記録した写真が残されているが*1、吹き出しを付けてそんなニュアンスのセリフを入れたくなってしまう。
(リッチーは丘陵地帯を北西に越えたオハイオ生まれ。クリスはカリフォルニア生まれ。グラムはフロリダ産まれでジョージア育ち。ジーンは丘陵地帯を西に越えたミズーリ生まれ)
デビューアルバムのタイトル曲、"Pickin' Up the Pieces" は軽く、爽やかなタッチで半世紀経った今ではカントリー・ロックのクラシックとされている。
想定していたリスナーは長距離トラッカーではなく、"カマロ" や "ムスタング" でもない、中古のピックアップの若い男女と言ったところであろうか?
ビーチボーイズのような聴かれ方かもしれない。
歌詞の内容からすると、ヒルビリーと揶揄される以前の、生活の一部としてフォークソングを楽しんだ時代を回顧しているように思われ、そうしたエッセンスを "僕らが歌うカントリー・ミュージックにある小さなマジック" と呼んでいる。
Piecesとは丁度1920年代後半から30年代にかけてカーター・ファミリー *2 がアパラチアンに住む人達に馴染み深いフォークソングを次から次へとレコード化して提供し始めた事を言っているのかもしれない。
野良仕事の合間や、夕食後の団欒にフォークソングを楽しんだというのは19世紀アパラチアンの歴史の事実としてあるようだが、全米レベルで見ると1969年の時点でそれを歌詞に織り込んでも頷けるリスナーはどれだけ居たのだろうか?
そんなことに現を抜かしつつ、選曲ボタンでニュースを選べばベトナム戦争が泥沼化していることを伝えていたようである。ワイルドに行っても帰りはくたびれるし、世相は暗い。
そんなところにPocoが流れて来たら脳天気?それとも癒し?リッチーはそんな事を思っていたのだろうか?
ビーチボーイズはピックアップにサーブボードを積んでいる。じゃあPocoは何を積む?干し草と鍬?
干し草は英語でhayだが、アルバム "From the Inside" のオープニングの彼の曲、"hoe down" とは南部のフォークダンスの種類の一つだそうで、hoe=鍬=農作業由来のダンス?これじゃあやっぱりヒルビリー?
今ではカントリー・ダンスと言えば実益から遠く離れてスマートになっているが、カウボーイハットとブーツが正装になっている。
そう言えば、カウボーイハットを被ったリッチーの写真にはお目にかかったことが無い。
"From the Inside" の中ジャケには緑濃き田舎の家のポーチの写真が配されている。此処はアパラチアンらしい。
このアルバムは唯一、R&Bのバックで活動して来たSteve Cropperのプロデュースだが、かなり南に下ったアパラチアンをイメージしているようで、ポール・コットンの楽曲と合わせてリッチー作の "Do You Feel It Too?" もかなり泥臭い仕上がりになっている。この曲は CD盤の "Pickin' Up the Pieces" に未発表テイクとして収録されているバージョンがあり、そちらはリッチーが初期に描いていた軽くてポップな仕上がりになっている。
今、こうして俯瞰してみると、"Pickin' Up the Pieces" はリッチーの所信表明だったと受け取ると、その後の楽曲はどうもチグハグさを筆者は感じてしまう。
リッチーも自分のシナリオには迷いがあったのかもしれない。
♪ 与作は木を切る hay hay hoe! hay hay hoe!
北島三郎の代表曲だが、七沢公典の作詞・作曲になるもので1977年にNHKの "あなたのメロディー" なるアマチュア作品にスポットを当てた番組で年間最優秀曲となったものである。
興味深いのは七沢氏は仕事でアメリカに居た時に感じた日本の歌の良さだそうで、もしや彼もPocoを聴いていた世代では?
"hoe down" が生まれた感覚は与作と通じるところがあるような気がする次第。
アメリカ人の中には、"hee Howoo" と嬌声を上げてそうした南部の古くさいものを蔑視する人が居る一方、それに負けずに "hee Howoo" という掛け声を挟むカントリーシンガーも見られ、これこそ文化の豊かさ、今で言うところの多様性ではないだろうか?
"俺ら東京さ行ぐだ" で "田舎っぺ" を徹底的に自虐したのは吉幾三。
"俺はぜったい!プレシリー" はヒルビリーからロカビリーに脱出を図ったカントリー・ミュージックの歴史を連想してしまう。
彼はその後、渋い演歌を自作自演=シンガーソングライターであった訳である。
先祖還りを見事に体現しているように思えるのだが、本当にやりたいことは最後にとって置き、最初からそういうシナリオを描いていたのではないか?
ウェスト・バージニアはアパラチアンの中でも美しい自然で知られ、四季は日本と良く似ている。
"From the Inside" のリリースと同じ1971年のことであった。
また翌、1972年 "Rocky Mountain High"*3 でコロラドはロッキー山脈への愛着も歌っていた。
因みにアパラチアンは広葉樹林、ロッキーは標高が高いので針葉樹林である。州都、デンバーは富士山麓の富士吉田市と姉妹都市とのこと。
スティブンは幼少期を南部や中米各地で過ごしており、多様な音楽を聴いて育ったとのこと。
バッファローやCS&N、CSN&Y時代はそうした出自は時折、垣間見えたが、Manassasでは自身の音楽的ルーツを辿るような活動を初めていた。カントリーやブルーグラスのみならず、ブルース、ラテン等、幅広くカバーしようとして2枚組のファーストアルバムになってしまった。*4
メンバーにはクリス・ヒルマンを迎え、ペダルスティールやドブロを駆使するAl Perkins、ラテン・パーカッションのJoe Lalaが多様な風味を支えている。
今の時代から見るとサザン・ミュージックの博覧会に見えなくもない。何の迷いもなくストレートな憶いをぶつけている盟友を横目で見て、リッチーは何を憶っていたのだろうか?
リッチーは1974年にPocoを脱退し、 "Souther Hillman Furay Band" に移籍するが、クリス・ヒルマンを含め、スティブンが解散したManassasの布陣がバックを固めているのは興味深い。
後にリッチーは牧師の資格を取ってクリスチャンの道へ進んだそうで、それを熱心に勧めたのはAl Perkinsと言うから人脈とは有難いものである。
牧童=カウボーイは牛を追い、牧師は迷える羊と伴に?
聖飢魔IIのデーモン小暮はライブをミサ、CDを教典と称し、布教活動を行っているそうだが、これは音楽の本質的な側面かもしれない。
アパラチアン周辺の文化を紹介するビデオで1970年代と思われる教会の礼拝の様子を見たのだが、バンドをバックに牧師が歌いながら説話を行い、牧師も参加している信者もだんだん恍惚状態となって最後は失神する様子が収められていた。信者や教会関係者も慣れたもので、失神した者をやさしく介抱していた。
一方、そうした音楽の側面を否定的に捉えて音楽を禁止するキリスト教の宗派がアパラチアンには存在することも伝えていた。
リッチーは自分の音楽や聞いてくれている人がどんな悩みを抱えているのか?憶い、迷いながら過ごしてきた日々の中で光が少しづつ見えてきたのかもしれない。
カントリー・ミュージックやブルーグラスの曲には聖書を題材にした、Sacred song なるジャンルがあるのだが、"I Saw The Light" は有名なナンバーである。
またフォーク・ソングの Pete Seeger 作で Byrds がヒットさせた "Turn! Turn! Turn!" も好例である。
アメリカの教会における音楽と言えば黒人霊歌、ゴスペルが良く知られているが、アパラチアン周辺に多いアイルランド系白人も同じようである。
アコギでリードを取る時はハーモニクスを多用したり小技を巧く使っているように感じる。レコードでも彼のリズムギターは聴こえるが、これが初期のPocoのサウンドの要かもしれない。
アルバム "A Good Feelin' To Know" のオープニング "And Settlin' Down" が良い例かもしれない。
もし、ミキシングの過程でこのリズムギターのトラックを入れなかったらどんなサウンドになっていただろうか?
リズムギターはジャラーンと弾けばギターはサステインの長い楽器であるからそれを意識的に止めるにはカッティングを行えばよい。ピックでストロークした瞬間からカッティングするまでの時間によって様々なグルーブが生まれる。
例えばデイビッド・クロスビーはこの時間が非常に短く鋭いカッティングがトレードマークになっているが、何のコードなのか判別できずむしろパーカッションの役目を担っているように思える。
これに対してリッチーは次のコードに移るまでカッティングをしないのでコード進行が良く判る反面、常に音が鳴り続けている〜うるさいという印象を筆者は持っていた。
多重録音以前の一発録音の時期は音が濁るということは殆ど起きなかったが、70年代に入り多重録音の揺籃期になるとミキシングエンジニアはこの濁りを気にし始めたようである。1975〜77年頃になるとこうした濁りは次第に排除され、音がクリアになった印象を持っていた。
ビートルズも初期はジョン・レノンがバンド・アンサンブルとしてのリズムギターを弾いているが、スタジオワークに専念し始めた1966年頃にはジョージ・マーティンは抑制しているように感じられる。僅か4チャンネルの多重録音でいろいろな音を入れたくなるのだが、音が濁らないようにする配慮だったのかもしれない。
同時期のByrdsやCS&Nでもリッチーのようなリズムギターは聴こえてこない。
このリッチーのリズムギターを新米プロデューサーでもあった3歳年下のジミーはどう思っていたのだろうか?
*1
1970年頃と思われる、Dillard & Clark、Flying Burrito Bros.、Poco、Byrdsのキーパーソンが一同に会す。
出典:Jon Corneal Facebookより
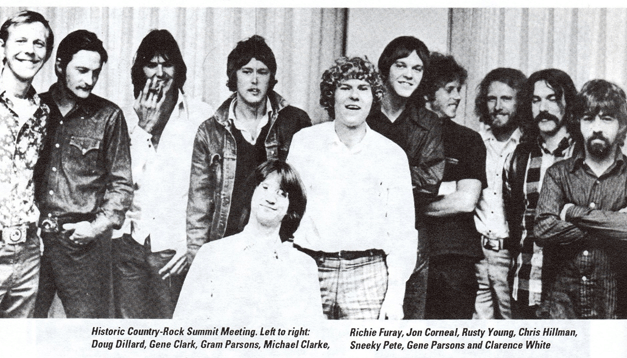
*2

*3

*4
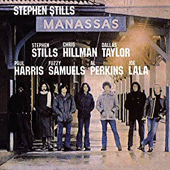




その3:4人時代の舞台裏は?
しかしながら、6th "Crazy Eyes" をリリース後、リッチーは脱退してしまう。
例えばビートルズ以前なら、"Bill Haley & The Comets" のようにリーダーの名を冠したものが一般的であった。
周囲は " Richie Furay & The Poco" という見方をしていたのだろうか?リーダーを失ったバンドの行く末は?音楽雑誌ならそのような書き方をしたかもしれない。
一方、CS&Nのようにリーダーを決めない行き方も出て来た時代であった。
彼はアサイラムレーベルのDavid Geffenの呼びかけに応じて "Souther Hillman Furay Band" に参加することになった訳だが、メジャーリーグの選手が新進球団に移籍するような感じなのだろうか?
残された4人のメンバーの会議の模様はこんな感じだったか?
・
Epicとの契約ではあと3枚。リッチー、ポール、ティモシーの3人で曲を分担してきたけど、2人はキツい。
・
アルバムの曲数を減らすのは簡単だけどインストを長々やる時代じゃないね。
・
ラスティのインストは助かるけど、何か曲書けない?
・
ライブでもバックコーラスは3声だったけど今度は2声でもしかたないね。ラスティも一緒にハモれない?
・
カントリー・ロックって言われているけど、食っていけるんだろうか?
・
ラスティが居るからサウンドは維持できるかもしれないが、リッチーが抜けてもカントリー・ロックかい?
・
Desperado(Eagles)のコンセプトとサウンドは共感できるけど、反応はイマイチだったね。
・
カントリーは嫌いじゃないけど僕らは Nitty Gritty Dirt Band のように掘り下げちゃいない。
・
ジムが居た頃もそうだったけど、僕らはシンガーソングライターの合宿ってとこだね。
・
リッチーのボーカルのキーは高かったからティモシーもジョージも良くついていったよね。
・
"A Good Feelin' To Know" の出だしは音外してしまったけど、リッチーやプロデューサーのJackからはNGが出なかった。心残りなんだ。
・
"A Good Feelin' To Know" から3作続いたJack Richardsonのプロデュースはここで音が変ったように感じる。
・
前作まではリードギターやリードボーカルに短めのディレーを掛けてライブな雰囲気が感じられたり、リッチーのリズムギターが賑やかであったのに比べ、鳴っている楽器の音が整理されてクリアになった。
・
替わって、"Driving Wheel"、"Angel" ではアコギはリズムギターではなくアルペジオにしてサステインを抑え、ドブロのようなほかのアコギの邪魔をしなくなっている。このおかげでリバーブを深く掛けたペダルスティールの効果が引き立っているように感じられる。
・
"Krikkit's Song"、"You've Got Your Reason" のストリングスはいわゆるバラードに被さる柔らかいトーンではなく、前者はどこかR&Bを、後者は映画音楽を思わせて自己主張が感じられる。
・
ストリングスはアレンジャーや奏者へのギャラも馬鹿にならず、財政的に楽とは思えない中で先行投資したか?
・
ハーモニーボーカルの美しさ。
・
ポールのリードボーカルが一皮むけた。
・
ジムが "Rocky Moutain Breakdown" で端正なマンドリンで客演してくれたのも嬉しい。
・
カントリー・ロックに拘らないハードな選曲は同時期のEaglesのアルバム "On The Border" と似ている。
ところで、"A Good Feelin' To Know" をリリースした年に"Take It Easy" でデビューしたEaglesだが、先述のように1st、そして2ndアルバム "Desperado" はGlyn Johnsのプロデュースによるカントリー・ロック仕立てだったわけである。
しかしながら、3rdの "On The Border" の途中からプロデューサーはBill Szymczykに交代している。
Szymczykはペダル・スティールやバンジョーは残しつつ、当時の勢いに乗っていたエレキ・ギターアンサンブルに重点を置いたハードな音作りをしている。
これはメンバーのグレン・フライの意向だったそうだが、アルバム制作途中でプロデューサーが交代する事態は只事ではない。
カントリー・ロックだけでは食って行けないという懸念は同じだったのかもしれない。
9th "Head over Heels" から 12th "Indian Summer" までの時代は、Pocoに限らず転機となるいくつかの伏線があったように思う。
・
1975〜77年にかけてマルチトラック録音〜ミックスダウンの扱いが洗練され、音がクリアになった。
・
音が濁らないように重ねる前に各トラックで処理(ダイエット)しておくやり方が定着した。
・
リズムギターの意味合いに変化が見られ、コードストロークによる音は控えめになり、気持ち良くバックで鳴っているという使い方になった。
・
楽曲の雰囲気を左右するコード進行はリズムギターが無くともベースラインでもその役割が担えることが認識されていったようである。
・
ライブな音に定評があったThe Bandも "Northern Lights - Southern Cross" はこの例に洩れず。
・
ウェストコーストから南下、メキシコを抜けてカリブ海、ラテン、レゲエ風味の楽曲が出て来た。
"Shittin On A Fence" 、"I'll Be Back Again" 等
・
これは1969年の映画、"明日に向って撃て" の主人公、ブッチ・キャシディとサンダンス・キッドが辿った逃亡ルートに一致しているのは興味深い。
・
これはヒットチャートを賑わしていたロギンス&メッシーナのアレンジが影響していたかもしれない。
"Sailin' The Wind" 、"Vahevala" 等
・
アルバムジャケットに海岸や帆船が登場するようになる。*1*2*3
・
EaglesやCS&Nはフロリダ、マイアミビーチのレコーディングスタジオ "Criteria Studios" を利用し始めた。
・
やはり1969年の映画、"イージーライダー" の主人公、ビリーが終盤に吐いたセリフ、"これで俺たちもフロリダで引退だ!" とは無縁ではないように思える。
・
Jimmy Buffettのようにミシシッピーからカントリー・ミュージック発祥のアパラチアンに北上、ディープサウスに戻ってフロリダに南下する潮流も伺えた。
・
ミュージックシティ=LAの存在感が問われ、Eaglesの "Hotel California" がジャッジを下した。
・
ファンが社会人となる年齢を越え、AORなる用語が囁かれ始めた。
北アメリカのハリケーンはメキシコ湾岸に沿って進み、南部に大きな被害をもたらすが、メキシコ半島とフロリダ半島は中米から北米に向う移民の要所でもあり、文化のクロスロードとも言える。
The Bandの曲 "Arcadian Driftwood" はカナダからディープサウスへ移動したフランス系カナダ人を流木に喩えたものと言われているが、文化は大移動するようである。
桑田圭祐が標榜したサザン・オールスターズとはハリケーンが去って湾岸を漂い、とうとう茅ヶ崎まで流れ着いた流木を拾い集めたものだったか?
*1

*2

*3





その4:ポール・コットンの憶い?
このアルバムはジムがColumbiaレーベルの専属プロデューサーとなり、替わってR&Bのバックで活動して来たSteve Cropperがプロデュースしたことでガラリとサウンドが変った。録音もメンフィスで行われている。
カントリー・ロックという発想はウェスト・コースト発であり、カリフォルニアで育ったジムがプロデュースした3枚のアルバムもそうした色合いだったように思う。
一方、Steve Cropperはカントリー・ミュージック発祥の南部を意識したように伺える。サザン・ロックという用語はまだ囁かれていなかったかもしれない。
ポールは南部はアラバマ生まれのシカゴ育ちで、そのリードギターのスタイルはジムの軽快なピッキングとは正反対に重量級の機関車を思わせ、ビブラートに情感を込める。
3rd "Deliverin'" で聴かれるようにジムとラスティのペダルスティールやドブロとの掛け合いは機関銃のようにスリリングだが、ラスティとポールの掛け合いはまた違った趣きである。
ラスティはセッションマンだったので相手に合わせることが出来たようだが、ペダルスティールで美しいハーモニクス・ピッキングを披露するようになったのはポールの少ない音数とビブラートに呼応したものではなかったか?
歌詞の中にジョージア、ダラス、ニューオーリンズと言ったディープサウスの地名やミシシッピー河口一帯をさすbayouという語句が出て来ることから頷ける。
更には13th "Legend" では中米のカリブ海はバルバドスまで足を伸ばしているようにアメリカ南部を越えてコロンブスが歩んで来た道のりを辿っているようにも思える。
そうしたアプローチは西海岸のサンフランシスコから登場したC.C.R.やDoobie Brothers、カナダ人の眼でアメリカを俯瞰したThe Bandでも見られたが、彼らが外から南部を見ていたのに対し、ポールは生まれが南部ということで情がすこし違うようである。
例えば、Allman Brothers Bandはサザン・ロックと言われているが、どちらかと言うとディープサウスから少し外れてアイリッシュが多いアパラチアン文化圏にあるように思える。
それに比べるとポールはアフロ・アメリカンに足を踏み入れているように思える。アフロ・アメリカンと言ってもディープサウスのブルースやジャズではない、R&Bの匂い?いわゆるデトロイト=モータウンサウンドと言えばよいだろうか?デトロイト周辺には自動車産業を支える部品工場が点在しており、シカゴも例外ではない。工業都市の労働力を担って都会で暮らすアフロ・アメリカン文化ということかもしれない。
ポールの曲は起伏のあるコード進行と言えばよいだろうか? 60年代の職業作曲家のセオリーのように、四季の移ろいに似た気分の変化を与えてくれる。
"Bad Weather" 、"Early Times" 、"Faith In The Family" 、"Angel" 、"You've Got Your Reason" と言ったところだが、4人時代になった最初のアルバム "Seven" で花が咲き出したように思う。
ヒットとなった"Heart Of The Night” は切なさが漂う一品である。確かにこれはR&Bかもしれない。
Pocoの歴史を通して彼のインストは僅か1曲だが、17thアルバム "Ghost Town" のラスト "High Sierra" は唸るようにディストーションを効かせた豪快なリードギターでドラマチックに展開する。
"Sierra" とはスペイン語で山の意味だが、西海岸のシェラネバダ山脈を描いたものだろう。ディープサウス周辺は遠くから眺めることが出来る山というものが無く、南部の人から見ると山はひとつの憧れなのかもしれない。
彼の曲は初めて聴いた時にはそれほど印象に残らないが後になってじわじわ効いて来る。決して悪酔いはしない。
・
Pocoに入ったのはラスティがペダルスティールを教えていたChicagoのピーター・セテラの紹介なんだけれど、ラスティはセッションマンだから安心して頼れると思ったんだ。
・
それまでに居たillinois Speed PressやChicagoはColumbiaレーベルで、Epicレーベルと共にCBS傘下だったからお互いの動向は知っていた。
・
ジムがPocoでやっていくためのノウハウを教えてくれたけれど、彼のリックとは全然違うんで心配だった。
・
"From the Inside" ではillinois時代の曲、"Bad Weather" をやったけど、ラスティのペダルスティールが入ると全然違った感じになった。
・
自作曲を3曲やらせてもらったけれど今までのPocoと違って泥臭いかな?
・
この頃のボーカルは今聴くと恥ずかしい。"A Good Feelin' To Know" に収録の "Ride The Counry" ではプロデューサーのJackが初めてコーラス処理をしてくれたんだけどファルセットで歌ったんでイマイチかな? 自分の声に自信が無いのが判っちゃう。
・
僕もカントリーは好きだけど、アパラチアンの樵じゃなくてカウボーイ。ウェスタン、テキサス。ディープサウスの西隣りだね。EaglesやN.R.P.S.*1なんかもそうじゃない?サボテンが出て来るでしょ。
・
ABCレーベル時代の未発表ライブ音源、21th "The Last Roundup"*2 このタイトルは新しいもの。"Roundup" とはカウボーイの用語で放牧していた牛達を追い立てて集合させる作業のこと。カウボーイから足を洗って都会へ出て働くとか、年老いたカウボーイのこれが最後の仕事という感じ。
・
Epic時代のベスト版の "Forgotten Trail"*3 もそんなイメージ。カウボーイ用語のtrailとは、牛を街で売るために牧場から何日も掛けて行く長旅のこと。昔は此処を長い牛の行列が通って行ったものさ。
・
”Seven” のジャケットデザインはPocoのマネージャだったJohn Hartmanの兄弟で俳優、コメディアン、グラフィックデザイナーでもあるPhil Hartmanに馬の蹄鉄を描いてもらった。Pocoのトレードマークになった。
・
"Legend" でも頼んだら今度は疾駆する素敵な馬を描いてくれた。これは今でもラスティが使い続けている。
・
2002年にリリースした "Running Horse" はPocoの遥かなtrailを回顧してPhil Hartmanへの感謝を込めたアンサーアルバムになった。(Philは1998年に亡くなっている)
・
4人の時代はいろいろな意味で大変だったけれど、おかげで自分達の航路がだんだん見えて来た。それで "Living In The Band" を書いたんだ。♪ 始まりは、コロラドから二人、テキサス、ネブラスカ、そしてオハイオ。そう、ランディ・マイズナーを含む最初のメンバーを紹介したんだ。
・
ティモシーがEaglesに移籍する気配は感じていた。ランディの替わりが出来るのは彼しかいない。Eaglesはある部分でPocoと良く似ているし。
・
だからEaglesが生き延びる事が出来るんだったらPocoの役割は終わったねって。
・
そう感じたからラスティと "Cotton & Young Band" にしようと話し合ったんだ。知らないうちに彼は自作曲を貯めていたんだ。これで僕も楽になる!
・
でもABCレーベルは、知名度を活かして "Poco" で行けって!
・
13th "Legend" からは僕の "Heart Of The Night” とラスティの"Crazy Love" がヒットしてゴールドディスクを頂いたが、"Living In The Band" で書いた "winning hand" が本当になった。
・
Phil Kenzieのサックスはどう? サックスは6th "Crazy Eyes" の "Magnolia" や11th "Rose of Cimarron" の”Starin' At The Sky” で入れたことがあるけど、今度はSanford Orshoffのプロデュース。
・
サックスとペダルスティールが絡んで、これはいけるブレンドだと思ったよ。
*1

*2
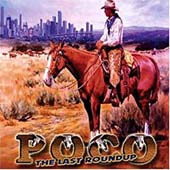
*3 




その5:ラスティ・ヤングの憶い?
バッファロー・スプリングフィールド時代にセッションマンとしてリッチーの "Kind Woman" でペダルスティールを弾いた時、ラスティは今の未来を予測していただろうか?
半世紀後の今思うに、ラスティはPocoの骨格だったのかもしれない。発掘された背骨の化石を輪切りにしてみたら金太郎飴のようにラスティのとぼけた顔が出て来た?
その後に登場したFlyig Burrito Bros.にはSneaky Peteが、N.R.P.S.にはJerry Garcia、Buddy Cageが、Pure Plairie LeaguにはJohn David Callがバンドメンバーに収まっていた。あるいは、Byrdsの後期メンバーであったGene ParsonsやEaglesのDon Felder、Doobie Bros.のJeff Baxterもペダルスティールを操っていた。
当時のカントリー・ロックではお馴染みの楽器だったが、そうした動向をラスティも横目で睨んでいたと思われる。成功しそうなバンドなら今のうちにポストを確保しておきたい?
そうした眼で見てみるとPocoデビューの1969年の時点でペダルスティールギタリストを擁していたのはFlyig Burrito Bros.であり、どちらがブレークするか?ラスティも気が気では無かったのではないだろうか?
当時のSneaky Peteのペダルスティールのトーンは低音を抑えた軽い感じで、ロック寄りを意識してディストーションを効かせたサイケデリックなトーンも披露していた。
対してラスティはナッシュビルのオーソドックスなトーンでカントリー・ミュージックに必要なリックは全て揃えた手堅さを感じた。Poco名義ではないペダルスティール奏者として残された音源を聴くとジャジーなリックも披露しており、セッションマンとして食って行く為にどんな音楽でも対応できるように鍛錬していたようである。
そしてレズリースピーカーを通してハモンドオルガンのような音を出したり、"Sweet Lovin'" ではイフェクターを通してパイプオルガン、”Indian Summer” では断面が真円のバーを六角形にして琵琶のさわりと同じ仕掛けでシタールを模した音も出すなどアイデアマンらしい。
また、ペダルだけでなくラップスティールやドブロと言ったスライドギターにも長けているし、5弦バンジョーやマンドリンも操る多芸さであった。
デビューアルバム以来、”Grand Jumction”、"Fools Gold"、"Rocky Moutain Breakdown"、"Sagebrush Serenade" 、"SlowPoke、Feudin'" と言ったブルーグラススタイルのインストナンバーは他のバンドには無いPocoの魅力になっていたと思う。
ポールがリードギターを弾いている間や1拍の空白を作って楽器を持ち替える訳だが、できるだけ姿勢を変えずタイムラグが無いように楽器を配置し、バンジョーは抱えるのではなくスタンドに固定してピッキングしたりする。最も失敗のリスクが高いのはスライドギター系の楽器とバンジョーを切り替える時のバーさばきである。バーは転がり易いのでしっかり所定の位置に置かねばならないが、バーを取り上げる際もガンマンのような早業が必要である。
Youtubeのライブステージ映像を見ると、ノーミスでキマッた時にはバーを放り上げて空中でキャッチし、観客にとぼけた顔を見せるのが彼の瞬間芸になっている。
こうして見ると、初期のビートルズのようにPocoはレコードとステージの音に差を感じさせない高いライブパフォーマンスが真骨頂だったのかもしれない。
リッチーもそうした百人力のラスティに大きな期待を寄せていたのではないだろうか?
それまではインストナンバー専門だったが、シンガーソングライターのスイッチが入ったのはいつだったのか?
手始めにインストに歌詞を添えた曲を提供するようになったのは "Rocky Moutain Breakdown" からだが、8th "Cantamos" の "Sagebrush Serenade" と続き "High And Dry"、“All The Way" で初めてインストでない楽曲を提供し始める。
前者はバッファロー・スプリングフィールド時代のスティブン・スティルス作の"Bluebird" を思わせるナンバーで、後者はコード進行に起伏があり、アルバムのラストらしく高揚感が盛り上がってゆく。どちらもアコギを前面に押し出している。
Byrdsがフォークの河をエレキで遡ろうとしたとすると、バッファローはロックの海にアコギで漕ぎ出そうとした様なところがあった。時折、PocoもそのDNAを受け継いでいるような印象を受けるのはリッチーやジム由来と感じていたのだが、あるいはラスティの仕業だったのかもしれない。
一方、Eaglesもブルーグラス色を押し出した前作 "Desperado" が低調だった反動でロック色の濃い "On The Border" をリリースしたが、ここから生まれたシングルヒットはペダルスティールを用いたバラード "The Best Of My Love" であったのは皮肉である。
"Seven"からはチャートを賑わすヒットは生まれず、Epicレーベルは8作目のプロデューサーを手配出来なかったのかもしれない。この "Cantamos" はPocoのセルフプロデュースとなっている。
4人は開き直ってやりたい事をやっておくしか無いと思ったか?蓋を開けてみればブルーグラス色が戻り、それを期待していたファンは歓迎したかもしれない。筆者もそのひとりなのだがラスティ色が出たように思う。
イラストはポールがアコギ、ラスティがドブロを弾いて、ポール、ティモシー、ジョージがハモっている。薪ストーブはカントリー、ブルーグラス発祥のアパラチアン山中を思わせる。あるいはコロラドのロッキーかもしれない。どこかいい雰囲気でアルバムの中身を予告しているような気がしたものである。
これはもしやラスティのアイデアではなかったか?
しかしながら、このジャケットはコストが掛りそうで、当時の財政状況ではEpicは渋ったのではないだろうか?80年代にCDで再販された際にはこの仕掛けは無くなりイラストが消えていたのである。
真相は判らないが、ラスティは1965年頃、音楽活動と平行してコロラド大学でビジネスを学んでいるとのこと。何処からか資金を工面して現れた、とぼけた顔のラスティを想像してしまうのである。
結果はMark Harmanのプロデュースだがライブアルバムとなった。恐らく編集作業のエンジニアとして仕上げたものと思われる。それでもラスティの大活躍によるライブパフォーマンスの高さは1stライブアルバム "Deliverin'"に劣らないと思う次第。(リリースはABCレーベル移籍後の "Head over Heels" の後になった)
なお、"Deliverin'" はステージ直近の音を届けたいというジムの狙いか?、マルチトラックによる編集は程々にしているようだが、こちらは楽器の分離と残響に気を使って編集しているように伺える。大きなホールの中程で聴いたかの様な音になっている。
12弦エレキのイントロに始まり、ドブロ、マンドリンが被さり、エンディングはストリングスが遠い山並みを望むように押し寄せる。最後は5弦バンジョーがフェードアウトしてゆく様は、伝説の女アウトローの肖像を描いた油絵を思わせる。
エミルー・ハリスが1981年に同じタイトルのアルバム*3をリリースしたように彼女の心を動かしたようである。今ではカントリー・ミュージックのスタンダードナンバーと認知されている。
2004年リリースのライブ、22th "Keeping The Legend Alive" に収録されているバージョンはコード進行に一部手を入れており、筆者はこちらの方が心模様の陰影が深いように感じる次第。ラスティもどちらが良いか迷っていたのではないだろうか?
この曲のキーはリッチーのように高く無く、アルバムではポールとティモシーが交互にリードボーカルを取り、ジョージと3人でハーモニーを付けている。ラスティはライブでは手品師に徹する為にリードボーカルは取らなかったのかもしれない。
ロギンス&メッシーナでバックを務めるアル・ガースのフィドルが加わり、一時的にPocoのメンバーになっていた。
ラスティがPoco参加前にコロラド州はデンバーをベースに活動していた Boenzee Cryque なるサイケデリック・ロックグループには1971年に前衛ブルーグラス、New Grass Revival を立ち上げる Sam Bush が居り、その頃からラスティの頭の中にはブルーグラス・ロックなるシナリオが描かれていたのかもしれない。
Pocoデビューの1969年にブルーグラスからカントリー・ロックに転身したミズーリ出身の Dillards や、1970年頃からブルーグラス系楽器をロックに持ち込んだ Nitty Gritty Dirt Band の動向を見ると、若いブルーグラッサーはアコースティック楽器を武器にロックで生計を立てることを模索していたように思える。
アパラチアンを水脈とするブルーグラスはケンタッキー生まれのマンドリン奏者、Bill Monroe & The Blue Grass Boysから来ているが、Earl Scruggsが5弦バンジョーを花型楽器に押し上げたことで若い弟子が全米で繁殖した経緯がある。(日本も例外では無かった)
そして1967年の映画、”俺たちに明日は無い” で彼の "Foggy Mountain Breakdown" がサントラに使われたことがラスティ達の背中を押したのかもしれない。
ブルーグラスで5弦バンジョーを操る者は殆どがScruggsスタイルであり、ラスティも例外ではない。Scruggs自身、"ロックやったら破門" とは言わず、若いロックミュージシャンとのジャムセッションを試みていたことは歴史的に大きな意味合いがあったように思う次第である。
12弦アコギによるイントロは手品を見せられているように鮮やかで、カントリー・ミュージックのツボを押さえながらこのように美しいイントロは聴いた事が無かった。
"Hotel California" も12弦アコギで始まるが、2004年リリースのライブ、22th "Keeping The Legend Alive" では "Crazy Love" を歌う前のラスティのMCが良く判らない。"ドン・ヘンリーみたいって言わないでね" と言っているように聴こえるのだが.....
3パートのハーモニーボーカルも"hee Howoo" と嬌声を上げていた輩を黙らせるに充分な出来映えに思う。
これを含めてラスティは全9曲中5曲を手掛けているが、ポールに負けず劣らず佳曲揃いである。Pocoという看板を掲げてはいるが、一切の重しが外れてエネルギーが溢れ出したのかもしれない。
EpicやABCレーベルの時代では見られなかったが、この頃になるとアルバムジャケットの写真にはカウボーイハットを被ったラスティが登場する。
彼はリッチーに誘われた時から密かにこうした機会が来る時に備えてコツコツ磨きを掛けていたのかもしれない。
"Rabbit joke" と題した小咄といったら良いだろうか?ファンにせがまれて披露したようで、お馴染みだったらしい。お客様を楽しませる芸人魂が彼の真骨頂なのかもしれない。
*1

*2
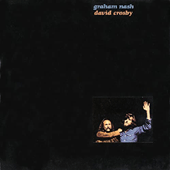
*3





その6:ティモシー・シュミットの憶い?
・ベースを弾きながらリードボーカルが取れる
・ハーモニーボーカルが出来る
・楽曲が提供出来る。
この3つがリッチーとジムが決めた条件だったと思われる。
この条件に適う人材を見渡してみるとポール・マッカートニー、ブライアン・ウィルソン、ピーター・セテラが挙る。あまり多く無いところを見るとリッチーとジムが思い描いていたシナリオが見えて来る。
ハモルという作業はお互いに和音を揃える事だが、右脳が旋律を見張りながら同時に、左脳が和音がズレていないかを見張る場合と、相手が正確であると信じて和音がズレているかどうかは問わず、自分のパートの旋律に集中すれば右脳だけで済む場合がある。
前者は相手の音が互いに良く聞き取れるようなスタジオ向きであり、後者は聞き取り難い大ホールや野外ステージ、最近で言えば遠隔者同士がオンラインで合奏するような場合に向いている。
しかしながら、後者は誰かが音程を外し始めたら最後、修正が効かない。
演奏家には両方対応出来る人と前者が苦手な人が居るようで、ポール・マッカートニーは両方出来るようである。
ボーカルは出来るが、同時にベースが弾けない人の中にはベースラインが外れていないか?まで左脳が面倒見切れないようで、そう言う人は押さえるフレットを間違えなければ良い。すなわち、ボーカルは右脳と左脳に任せ、ベースは身体が覚えていれば良い=練習次第でなんとかなるものである。
ポール・マッカートニーやランディ、ティモシーの脳はどうなっているか判らないが、いずれにしても生まれながらに出来ることではなく、経験と鍛錬は積んでいるものと思われる。
ビートルズはジョン、ポール、ジョージ、Byrdsはマッギン、クロスビー、クラークのようにハモれるメンバーは3人居たが、数小節で3声になる部分もあるが、基本は2声であった。ドラムスのリンゴやベースのクリス・ヒルマンもハモリに参加してくれれば...だが適わなかったようである。後輩のリッチー達は、"僕らは3声でキメよう!"と思っていた様子である。
これはCS&Nを立ち上げたバッファロー・スプリングフィールド時代の盟友、スティブン・スティルスも同じ思いだったに違いない。
蓋を開けてみると、CS&Nは終止3声で通すアレンジに対し、Pocoはドラムスのジョージを加えて4人がハモれたので、ソロボーカル+3声バックコーラス、または2声デュエット+2声バックコーラスというアレンジが可能であった。リッチーはキーが高いこともあるが、CS&Nより意識的にキーを高くしていたように思う。
ランディとティモシーに共通するのは高いキーに対応できるところで、リッチーを主旋律にしてアッパー、トップを重ねている。
ただ、声質が違っていてランディが遠くまで良く通る金属的なトーン、いわゆる八百屋声に対して、ティモシーはニュートラルな甘いトーン、男性、女性ボーカルを問わず相性が良さそうである。
ランディはデビューを待たず脱退。後のEaglesではトップに収まったのに対し、後任のティモシーはアッパーに収まった。トップはジョージ・グランサムである。
ティモシーは1978年からランディの後任にとしてEaglesに移籍するが、Eaglesもここでより甘くメローなハーモニーボーカルになったように思う。
Pocoのハーモニーボーカルは周囲からも注目されていたようで、ティモシーには頻繁に客演の声が掛っている*1。彼がPoco以外でハーモニーボーカルに参加し始めるのは、1976年のクリス・ヒルマンの1stソロアルバム "Sllippin'Away"*2 ではないかと思われる。
彼の声質はソロボーカルではティモシーと判るが、ハモれば浮き上がらない、濁らないところが好まれているように思う。
オフコースの小田和正もキーが高い1人だが、Pocoをしっかりマークしていたようである。
この年、Eaglesは "One Of These Nights" でファルセット(裏声)によるウルトラハイトーンを披露し、"Take It To The Limit" でもランディが熱唱していた時代である。Bee Geesも兄弟3声によるファルセットハーモニーに移行し、AORな季節が巡ってきたようである。このティモシーのデモテープが芽吹きだったのではないか?
ティモシーのPoco最後のアルバムとなった1977年 "Indian Summer" のラストトラック、組曲 "The Dance" は圧巻で、筆者には花火大会のフィナーレに聴こえた次第である。
Pocoでの最初の楽曲は参加直後の "Keep On Believin'" で、リッチーとの共作になるポップなもの。
続く4thアルバムのタイトル曲になった "From The Inside" はそれほど暗さは感じさせないが、基本的にはマイナーコードで、最後はメジャーで平穏に落ち着く。Eaglesに移籍後にヒットした "I Can't Tell You Why" のルーツかもしれない。(このヒットは日本の有線放送で始まり、本国が追従したとのこと)
間奏のラスティのペダルスティールもカントリー?と思せるが、早くもAORな雰囲気が漂っていないだろうか?この曲と同じトーンを "I Can See Everything" 。"Find Out In Time" にも感じる次第である。
だから星明かりも届かない渓谷にじっとしていられる
月明かりも届かない
.....
.....
でも、僕たち、離ればなれになるんだから
蛍=firefly、渓谷=hollow、月明かり=moonlight だが、"firefly" 、"hollow" からは清廉な水の豊かな場所=此処はアパラチアンを暗示しているように思える。
もし "moonlight" ではなく "moonshine" と来れば間違い無くアパラチアン山中であろう。この3語はアパラチアンゆかりのキーワードだからである。(moonshine =密造酒の隠語で、禁酒法時代に人目に付かない山中で月明かりの中で造っていたとの事。この後に続く "right" と韻を踏みたかったのであろう)
そして曲名の"Krikkit's"=コオロギは歌詞にはついに出て来ず、蛍なのである。あるいは "僕たち" をコオロギに喩えたのだろうか?
北米ではコオロギは広く棲息しているようだが、蛍は湿度の低い中西部では見られないのではないか?ティモシーは曲を聴いて行くうちに二人の居場所が絞りこまれてゆくような仕掛けを用意したのかもしれない。
こうした細やかな感性ゆえに、女性ファンが多かったのではないだろうか?
"Krikkit's Song" とは、”コオロギの歌” だが、日本人だけが虫の音を愛でるという訳ではないようである。
コオロギをネタにした楽曲はこちらを参照ください。
コオロギは歌う?
虫の音は音楽?
米国人にとって虫の音は?
カエルの歌
*1

*2
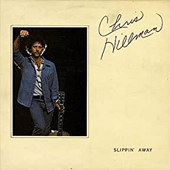




その7:ジョージ・グランサムの憶い?
ウィキペディアにはあまり多くのページが割かれていない。リンゴがそうであったようにドラマーはどうしても過小評価されがちである。
音の性質として周波数が高くなると倍音成分が人が聴こえる範囲を超えてゆくので音声の特徴が薄くなっていく。誰の声か判別しづらいという感じである。
しかしながら、1st "Pickin' Up the Pieces" の "Calico Lady" のリードボーカルはリッチーでもジムの声でもないところから、これがジョージの声らしい。
12th "Indian Summer" のラストトラック、"The Dance" のソウル調 "Never Gonna Stop" のリードボーカルもジョージと思われる。
21th "The Last Roundup" の中でも歌われるが、ライブならではのアドレナリンが出まくったのか、どこまで高い声が出るかご覧有れ!と言わんばかりのウルトラハイトーンが聴こえる。
Eaglesのドン・ヘンリーも叩きながらリードボーカルもハーモニーボーカルもこなしているが、大量の空気とエネルギーを消費するらしい。両人ともアスリート並みのトレーニングをしていたかもしれない。
ドンはテキサス出身、ジョージはオクラホマ産まれでコロラドで活動していたが、コロラドは標高1000m付近なので肺活機能は鍛えられていたのであろうか?
興味深いのはスタジオ録音のオリジナルよりキーが半音上がっている事である。晩年になるとライブではキーを落とすミュージシャンは多いのだが、どうしたのだろうか?
このライブではリッチーも参加し "A Good Feelin' To Know" を歌ってくれたのだが、こちらはキーを半音落としているのと対照的である。
リッチーのキーが高かったことで3声を重ねると、トップが務まる人材は限られていたのではないかと思われる。ジョージが居なかったらPocoのハーモニーボーカルは凡庸なものになっていたかもしれない。




その8:リユニオンアルバム
"Inamorata" の時期はドラムスは打ち込みの時代に入っているがスティーブ・チャップマンは失職していない様子。しかしながら、17th "Ghost Town" に比べると音の粒は揃えられ、残響処理は深くなり、ジョージが叩いてもこのような音になっていたかもしれない。Pocoよお前もか?と思ったものだが、こうした音造りは賛否両論、カンカンガクガクしたことも今は昔になってしまった。
"Inamorata" のプロデュースはポールとラスティに加えてJoe Chiccarelliが務めている。Chiccarelliは綴りからしてジムと同じくイタリア系と思われる。
北米のプロデューサーやレコーディングエンジニア、アレンジャーにはイタリア系が多いようだが、どんな音になっているのか興味津々であった。
蓋を開けてみたら、もうこれはPocoでなくなってしまったという印象であった。13th "Legend" 以降は実質コットン&ヤングバンドだったが、再びプロデューサーが覇権を取り戻したように感じた次第である。
Chiccarelliはポールとラスティに、”ドラムスは打ち込みをやってみるかい?” と尋ねたかもしれない。スティーブ・チャップマンも内心、気を揉んでいたかもしれない。
そんな情景を想像してしまうとリリースを喜ぶ気持ちが萎みかけてしまったことを憶い出す。
それでもポールのリードギターは情感が溢れているし、”Save A Corner Of Your Heart” を聴いたときには、ラスティってこんな曲も書けるんだと驚いたものである。
そして、ここではランディとジムを除くかつてのメンバーがハーモニーボーカルで参加してくれており、Pocoのリユニオンアルバムという雰囲気をなんとなく感じていた次第である。
ラジオのFENから "Call It Love" が聴こえて来たのは1989年の秋のことであった。
黄金のコード進行はヒットしそうだけど、誰?と思っていると、なんとなくどこかで聴いたようなボーカル、これってラスティ?と頭がどんどん回想し始め、曲がエンディングに近づき、ジョッキーの声が被ってきて "Poco" と告げてくれた。
嬉しいという気持ちと同時に突然やってきた今時の音造りに耳が追いつかなかった。
早速、週末は渋谷のタワーレコードに走った。当時はCDへの過渡期でまだアナログ版である。
中ジャケの写真にランディを含むデビュー直前の5人が勢揃いしていたが*1、ポールとティモシーが見えない。そういうことだったのか?!
皆、いいおじさんになって、こういうふうに歳を重ねたいものだなと思わせてくれた。
リッチーはオープニング曲、"When It All Begin" で昔を語り出し、ジムは "What Do People Know" のエンディングのアコギで懐かしいリックを繰り出し、ランディはEagles時代の "Take It To The Limit" を憶い出させる "Nothin' To Hide" を聴かせてくれるし、素敵な同窓会に思えた。
この時、あらためて認識したのはラスティのボーカルもキーが高かったということである。
そしてジムの曲、"Follow Your Dream" には本当に背中を押された次第である。
Bob SegerやRichard Marxを手掛けた手腕でPocoをやったらどうなるか?という興味深い組み合わせである。
80年代後半は録音からミキシング〜マスタリングまでデジタルで通貫し始めた頃で、アナログ時代では出来なかった事が可能になり音のクリアさは申し分無い。
筆者が "Legacy" で強く印象に残ったのはシンセサイザーの扱いである。
既存の楽器からは生み出せない音はそれだけプロデューサーが頭に描くイメージが要求される。
例えば高層ビルの谷間や山間に漂う霞、天空の天の川を連想させるような音が使われるようになった。カントリーだからペダルスティールというような理性ではなく、感性由来の発想が思わぬ雰囲気を醸し出したりする。
例えば、ランディの "Nothin' To Hide" である。背後に薄らと煙がたなびくようなシンセサウンドが配されている。旋律を奏でるのではなくサウンドイフェクトという感じである。この曲だけは作者のRichard Marxがプロデュースしているところも興味深い。"Take It To The Limit" のストリングスを配した70年代の王道はクラシックになってしまったと感じた次第。
また、音を重ねていけば濁ってくるのは色彩と同じで、そうした濁りを抑える作業はデジタルミキシングで勘に頼らず精度良く出来るようになった。
ジムが "お任せした" というのは、当時やりたくても出来なかった事を今出来るのなら見ておきたいという気持ちではなかったか?
煙がたなびくようなサウンドイフェクトは10th "Live" の中の "Angel" で聴き覚えがある。ペダルスティールにイフェクターを通して作り出したようである。
7th "Seven" に収録されているオリジナルではドブロの背後にリバーブを深く掛けたペダルスティールが被さるのだが、この時既にラスティの頭の中には
そういうイメージがあったのではないか?
ラスティはセッションマン、シンガーソングライターに留まらない、プロデューサー、サウンドクリエイターの一面があったように思う次第である。
2020年の現在でもPocoの看板を降ろさない気力の源泉はラスティから滾々と涌き続けているのかもしれない。
*1





筆者が初めて聴いたPocoは "Poco" と "Legend" だったのだが、冒頭で述べたように後者はカントリー臭は殆ど感じなかった。こういうのをサザン・ロックというのかな?と思ったものである。
1979年当時、レコード屋に並んでいる国内版ジャケットの帯にはカントリー・ロックという文字は見られなくなり、代わってサザン・ロックという文字をどこかで眼にしたからであろう。
ラスティがPoco立ち上げ以来駆使してきたペダルスティールやドブロ、5弦バンジョー、マンドリン等はカントリー・ロックのアイコンになっていたし、ウェスト・コーストらしいサウンドだと感じていた。
しかしながら今思うに、そうした楽器はやはりアパラチアンを水脈とする南部ゆかりの楽器だった訳である。
ラスティはコロラドで育っているが、ずっと思い描いて来たのはやはり南部であり、ポールも同じだったのではないだろうか?
もはやヒルビリーという言葉も聞かれなくなり、2020年の今の時点ではそうした土着のニュアンスから脱皮したような印象をサザン・ロックという言葉に感じる次第である。
サザンとはカントリー・ミュージックやブルーグラスという範疇ではなく、R&B、ブルース、ゴスペル、ケイジャン、ラテンまで含まれる、すなわち、アイリッシュ、アフロ、フレンチ、スパニッシュが織り成す多様な文化圏なのかもしれない。


関連エッセイ:
年頭所感:Eaglesによせて Two side to Country Rock
楽曲エッセイ:Kind Woman/Hot Burrito #1 演歌二題
楽曲エッセイ:Take It Easy/A Good Feelin' To Know 明暗は別れた?
楽曲エッセイ:Bitter Creek/Eagles、Rose Of Cimarron/Poco 薔薇よ銃を取れ!
楽曲エッセイ:Poco/Paul Cotton 鉄道3部作
楽曲エッセイ:Glorybound/Poco 娘達が男達を高揚させる
人物エッセイ その2 Jimmy Messina考
ハーモニーボーカル回顧録 Phillip Everlyに捧ぐ
1969年という節目 ジム・メッシーナのこと

